
2025年5月~8月
[5月の雑記/6月の雑記/7月の雑記]
[一覧に戻る]
[今まで日々雑記で採り上げた読了本の一覧(その1/その2/その3)]

| 2025年8月30日(土) 移転先の施設も、いつか行ってみたいと思っています |
8月の最終更新になりましたので、今回もいつものように、Top写真 を変更しました。今年の5月に続く「近代化建築」シリーズ第2弾、ということになるでしょうか。まぁ、このまま第3弾以降も続けていくかどうかは、現時点では全く未定なのですけれども。今回の建物は、わりと最近まで美術館の別館として使用されていたもので、都内にある美術館・博物館の1つです。東京都内、しかも23区内にある古い建物は結構空襲で燃えてしまっていたりするのですけれども、ここは幸いなことに戦災を逃れることができた、のかな?美術館になる前にそもそもここが何の為に建てられたものなのかを考えると、空襲の対象とならなかったのは分からなくもないのですが、それと同じ理由で、(今現在の頭で考えれば)ここだったら空襲の対象になるのも「脅し」としてはアリだったのかもとも。とはいえ、当時は今ほどのピンポイント攻撃の手段は無かったのだから、空襲の攻撃対象にはならなかったわけですね。誘導弾とか、ドローン爆弾とか、そういうのはありませんでしたから。
なお、この写真は、ここがまだ現役の展示施設だった頃に、とある企画展を観に行った際にとったもので、今からだと、およそ10年弱も前のことになります。当時の私は実は仕事をしながら夜と土日に専門職大学院に通って講義を受けて単位を得つつ論文を書いていた時期で、朝イチの講義が終わって午後の講義までの間に時間が空いたから気になっていた展覧会を観に行った時か、あるいは、入学式典&懇親会が行われる日の式典開始前に立ち寄った時か、どちらかで撮影したものだったはず。駅からはちょっとばかり歩かないといけないのですが、それはむしろ程よい散歩になると言えなくもないでしょう。
東京で美術館・博物館というと、どうしても上野の一連のものとか、六本木の国立新美術館とか、そういうところが有名ですけれども、実は、そうではない、全国的にはそこまでメジャーではない施設でも、良い展示をしていたり、建物が一見の価値があるものだったりというのが結構あったりします。ちょっとした東京観光旅行でそういうところに寄るのは難しいかもしれませんけれども、例えば港区白金台の東京都庭園美術館とか、結構お勧めですよ。今回の写真のところも個人的にはお勧めだったのですが、今はここは展示には使われていないので……。
知念実希人の『天久鷹央の推理ファイル 鏡面のエリクサー』(実業之日本社 実業之日本社文庫)の粗筋は、「鷹央の天敵にして、天医会総合病院の院長、天久大鷲。彼が手術を執刀した都議会議員が『このままでは自分は殺される!』と大鷲を告発し、警察に助けを求めた。まさかの状況に混乱する小鳥遊たちだったが、やがて事態は殺人事件へと発展し、病院の存続がかかる最悪の事態に。果たして、鷹央は叔父の容疑を晴らし、病院に平穏を取り戻せるのか。現役医師が描く本格医療ミステリー!」というもの。怪しい代替医療の詐欺問題を扱ったところにはそこまでの新鮮さは無いのですけれども、今回の注目点は、やはりなんといっても天久大鷲と主人公のタカタカコンビとの関係性の変化にあるでしょう。特に、258ページから260ページに記載された、大鷲のモノローグは、全部で約360ページある本作の中で、最重要箇所だと思います。知らぬは本人達ばかりという感じでどんどん外堀が埋まっていっている感がありますが、いやぁ、いいですねぇ、こういうの。お約束な流れではありますけれども、ラブコメ好き、ロマンスもの好きの血が騒ぎます。
二月公の『声優ラジオのウラオモテ #13 夕陽とやすみは道を選びたい?』(KADOKAWA 電撃文庫)の粗筋は「『カラメル・プロモーションに移籍しませんか?』 『主役』への拘りが強くなったものの、もらえるのは悪役のオファーばかり。悩む由美子が次に共演するのは、超新星後輩声優の綿菓子モコ! 『わたし、キャストは純粋な実力で決まるとは思ってないですよ』 新人なのに主役の作品を持っている彼女。ただそれは、演技がすごいからじゃなくて、事務所のプッシュのおかげらしくて?そんなときに声をかけてきたのは、モコのマネージャーの南雲で――。夢を追うからこそ悩み迷う、青春声優ストーリー、第13弾!」というもの。前巻で1つ大きな区切りがあって、それで次はどう来るのかと思っていたら、安易に新キャラを登場させてきたのか、と思いつつ読んでみたのですが……ほほう、こう来ましたか。こういうキャラであるならば、ここで新たに登場させる意味は確かにあるでしょう。声優のアイドル売りについて私は特にそれが悪いとは思っていませんけれども、軸足はあくまで「声優」にあることは忘れて欲しくないとは思っているので、今回の展開はなかなか面白く読ませてもらいました。これで、次の第14巻はどういう流れにするのか。ちょっと楽しみかも。
あちこちで高評価を得ていること、特に古河絶水の『かくて謀反の冬は去り』シリーズ(小学館 ガガガ文庫)や、最近読みはじめた樽見京一郎の『オルクセン王国史 野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか』シリーズ(一二三書房 Saga Forest)が好きだという人にはお勧めであるという、ちょっとそう言われたら無視はできないなという情報から、これは読んでみる必要があると思った、本条謙太郎の『汝、暗君を愛せよ』(DRECOM DRE NOVELS)を読了。裏表紙の粗筋は「お飾り社長としての人生に嫌気がさして自ら命を絶った『ぼく』は、異世界の若き王の中へと転生する。しかし彼の王国は巨額の赤字財政と列強の干渉に悩まされ、国内には革命の気配すら漂い始めていた。 政治的影響力を無視できない妃候補の令嬢たちと、自分よりも明らかに有能な重臣たちに取り巻かれ、無力な異世界人たる彼にできることはあまりに少ない。だが、何とか“上手くやらなければ” 生き残れない。『ぼくの名は、暗愚な君主の1人として残るだろう。永遠に』 それでもなお、彼は玉座に在り続ける。かつて “投げ捨てた” 役割を今度こそ全うするために。」というもので、異世界転生モノの1つではあるのですが、転生先で無暗矢鱈な無双をするわけではないのが本作のミソですね。転生時に何らかの能力を身に着けたわけでもなく、こちらの世界で得た知識をフル活用して成果を得ていくのでもなく、自分が何もできない「暗君」であるということを前提として、少しでもいい方向に国を導かんとする。一方、国内にも国外にも不穏な動きがあって、それが物語と主人公の先行きに陰を落としています。作品によっては、こういうことも全て最終的には良い方向に解決していくんだろうなと楽観的に思えるのですが、本作の場合は破滅、破綻、破壊が待っている可能性も否定できなさそうで、それが不安でもあり。何のかんの言っても、やっぱり「そしてみんな幸せに暮らしました」的な大団円が好きなんですよね、私も。ただ、そんな安直でリアリティーの無いハッピーエンドなどあり得ない、というような空気を強く感じさせるこういう作品も、決して嫌いではありません。特に本作の場合は、そういう空気感こそが魅力の1つになっているとも言えそうですし。ここから先も引き続き書籍版で刊行し続けてほしい、面白い作品でした。
版元を一迅社から早川書房に移行すると同時に主人公の性別を変更した作品の続編、宮沢伊織の『ウは宇宙ヤバイのウ!2 天の光はすべて詐欺』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)を購入。「高校生・久遠空々梨は、星間諜報組織〈偵察局〉のエージェント。従姉妹の非数値无香は、空々梨の探査船〈ヌルポイント〉だった。何やかんやで地球の危機を救った2人だが、うっかり高度18000mの空中でヒッチハイカーを撥ねてしまう。慌てているところに突如地球の惑星意思が出現し、『人類は絶滅させます』と宣言する。さらに幼馴染の加羅玉ちよが攫われて――!?超兵器と陰謀だらけのハチャメチャ百合SF第2巻!」というのが粗筋で、今回もひたすらドタバタが繰り広げられるバカSFを楽しめる作品になっています。世相を反映させたところに若干の生々しさがあって、そこで個人的には笑いきれないところもあったりしたのですが、しかし総じて楽しい1冊となっていました。このままシリーズが更に続いてくれると、いいなぁ。
TVアニメ化が発表された、荒川弘の『黄泉のツガイ』第10巻(スクウェア・エニックス ガンガンコミックス)。物語としてはかなり大きな転換点になる1冊だと思いますが、個人的に本作に覚えている今一つ乗り切れない感じは、今回もまだ払拭されないまま。盛り上がっていない……わけではないし、つまらないと思っているわけでもないのですけれども、何だか波長が合わないというか、はまらないんですよね。荒川弘作品が合わないというわけではないのは、彼女の他作品は好きだという事実があるから。だから、いつかどこかのタイミングで本作も、しっくりくるときが来るだろうと信じて読み続けています。ここ数巻で段々と面白くなってきている印象もあるから、その期待は外れないだろうと思っているのですが。
堂々の最終巻となった、高江洲弥の『先生、今月どうですか』第7巻(KADOKAWA HARTA COMIX)。本作の場合は連載開始当初(第1巻の冒頭)からラストシーンが確定していたわけですから、ある意味で予定調和な終わり方ではあるわけですが、こういう作品には相応しい終わり方で、しっかりと面白く読ませてもらいました。何のかんの言っても結局みんな、こういうシンプルな恋物語は好きですよね。次回作がどのようなものになるのかは分かりませんけれど、今作と同じように丁寧に物語を紡いでくれるようなものであれば、それは買ってみてもいいかも。そう思えるくらい、面白い作品ですし、雰囲気のある絵柄でした。
前巻で作者の前作である『サマータイム・レンダ』(集英社 ジャンプコミックス 全13巻+外伝1巻)と同一世界の物語であることが明らかになった、田中靖規の『ゴーストフィクサーズ』第5巻(同社 同コミックス)。話の流れ的には訓練~実践という感じで変化はあるのですけれど、実際に読んでいると、少々一本調子で単調に感じられるのがやや問題かなと感じました。何気ない日常を1回挟むだけでも、ここは随分と違うのではと思うのですが。話のテンポが単調で、ちょっとばかり退屈になりだしているのが否めないので、それは惜しいなぁと思うのです。







| 2025年8月23日(土) can't live without MUSIC(その2) |
前回は、小学校進学までに私が受動的に聴いてきた音楽がどういうものであったか、というようなことを書きました。今回はその後を書いていくわけですが、ただ、小学生になったくらいで、急に自分で欲しいLPを買うようになったりはしません、というか、ごくわずかな小遣いしかもらっていないのに、LPなんて買えません。だからこの段階ではまだ、そんなに能動的に音楽を聴きだしたということも無かったりします。ただ、それまでと明らかに異なる要素もいくつかあって、それは、小学校でできた友達の家に遊びに行くようになったこと、そして、そこで友達の親の好きな音楽をなにげなく聴かされたりするようになったことです。そこで知ったのが、さだまさし。シリアスな曲よりはコミカルな曲が当時は印象に残っていて、それは例えば「雨やどり」というあたり。多分、その時に「精霊流し」や「無縁坂」といったグレープ時代の曲なんかは聴いているはずなのですが、この時点ではそこまで記憶には残っていません。だから、当時の私の中では、さだまさし=コミックシンガーというイメージだったことになりますね。それは間違いではないけれど、あくまでも さだまさし の一面に過ぎないというのは、もちろん今は分かっていますけれど。
さらに、小学校中学年くらいの時に、我が家で音楽番組「ザ・ベストテン」の視聴が解禁されたのも、大きな変化です。それまでは母の方針で、教育的にあまり良くない(と、彼女が考えている)歌謡曲については、禁止とまでは行かないまでも、聴くことはあまり推奨されていませんでした。父は下町育ちの庶民でしたが、彼女は基本、クリスチャンのお嬢様育ちでしたしね。この解禁は上の姉が強く母に働きかけた結果で、ヒットチャート番組を見ていないと学校でクラスの話題に取り残される、ということがその主張の軸になっていました。それが真実だったのかどうかは知りませんが、彼女の粘り強い交渉が功を奏し、結果的にそれから我が家では週に1回、「ザ・ベストテン」を観ることは認められるようになりました。松田聖子とか中森明菜、近藤真彦や田原俊彦といった面々がデビューしていく頃、かな……?そこで当時のアイドルソングが刷り込まれたわけですね。同時に、チャートに上がってきていた演歌も、このタイミングで親近感をもって接するようになっています。
一方で、好きなアニメの主題歌というのも、当時から私が好んだものの1つでした。そんなわけで、私が初めて自分で購入したLPは、『銀河鉄道999』のヒット曲集(歌モノを集めたアルバム)でした。何年生の時が記憶が曖昧ですが、収録曲に映画『さよなら銀河鉄道999』の「SAYONARA」や「LOVE LIGHT」があったから、1981年か1982年かと思われます。毎月の小遣いは、まだまだLPの代金にはとても及ばない額しかもらっていなかったので、これは、お年玉で買ったはず。当時の私のお年玉は、LPレコードを1枚買うと、それだけでほとんど無くなってしまうくらいの総額だったはずなので、これは、かなりの冒険でした。とはいえ、TVシリーズのOPとED、最初の映画の時の ゴダイゴ の主題歌と挿入歌は好きでしたから、少なくとも4曲は自分の趣味に合うものが収録されているということで、そこまでギャンブル的な購入では無かったのですけれども。
『さよなら銀河鉄道999』の2曲はアメリカのマリー・マクレガー(Mary MacGregor )が歌っていましたが、それを除けばここまで基本的に邦楽を聴いてきていた私にとって、次に大きな変化をもたらしたのが、このタイミングで単館でのリバイバル上映が行われた The Beatles 主演の『A Hard Day’s Night(ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!)』を、母の弟である叔父と観に行ったことです。これ、どういう経緯で行くことになったのか記憶に無いのですが、叔父から誘われたのだったかな……?実際にスクリーンで観るまで、とりたてて The Beatles に興味があったわけではないですし、私から「これを観てみたい」というようなことを言ったわけではないのは、確実です。この叔父とは色々あって現在は接点がほぼ皆無になっているのですが、この点については大いに感謝しなければならないと思います。ともあれ、ここで私に洋楽との接点ができたわけですね。
前作の1年後の夏休みを描く、「ランサム・サーガ」の2作目、アーサー・ランサムの『ツバメの谷』上下巻(岩波書房 岩波少年文庫)を読了。主人公であるウォーカー家の4兄妹は、前作で仲良くなったブラケット家の2名(アマゾン海賊)と今年も無人島であるヤマネコ島でキャンプ生活することを夢見ていたのですが、ブラケット家の事情と、自分たちにおとずれたアクシデントのせいで、それが難しくなります。で、この2作目ではそんな彼らがムーアの中の谷でキャンプをする様を主に描いているのですが、第1作目との共通点を入れつつ、目先を変えてきたという点で、既視感少なめに楽しむことができました。何より、キャラクターが魅力的ですからね、このシリーズは。「カンチェンジュンガ」という響きを久し振りに目にして思わずネット検索してしまったり、コンビーフが食べたくなって買ってきてしまったりしたのですけれど、どうしてそういうことになるのかは、是非、これを読んで確認してみてください。
想定外に面白かったという感想をネットで見て、その記述内容が気になったことから発売日には購入を見送っていたのを急遽購入した、大武栄一の『ニュー忍者ロード』上巻(小学館 ガガガ文庫)。「群馬県の高校1年生・連城大弥は、一度も日の目を見たことのない不遇な忍術+現代戦闘術の当代。近ごろ県内で古の剣豪を名乗る謎の者たちが暴れているという噂を聴いていた。大弥がある日街で出会ったのは、高校の生徒会長であり柔道世界一の美少女・姫氏原すみれと、彼女に従い立つ男、天下に雷名轟かせる剣聖・上泉伊勢守信綱。信綱が語るすみれの『運命』に激しい憤りを覚えた大弥は、誰にも理解されない戦いを決意。行く道に立ちはだかるのは、柳生一族とその統領・柳生連也巌包、新選組一番隊隊長・沖田総司、そして!」というのがその粗筋ですが、前橋や沼田を舞台にして復活した剣豪と今の時代まで連綿と伝わってきた無名の忍術継承者が戦うというアクションエンタメ小説で、もちろん総合評価は下巻を読んでみないといけないわけですけれども、この上巻の時点で既にかなり面白い物語となっていました。惜しむらくは、著者による推敲の痕跡かあるいは校閲後の修正ミスか、単純な誤字脱字が主に序盤に目立っていたこと。そこで読むテンポが崩されるというか、ちょっとした引っかかりを感じることで読み進めがいちいち止まってしまうことになっていたのはあまりにもったいなく、内容的にはどうということのないミスではあるだけに、こういうのはきちんと潰しておいてほしいなと思った次第。とりあえず早急に下巻を読み始めます。
予定通りに無事にシリーズ化された澱介エイド の『ファム・ファタールを召し上がれ』第2巻(小学館 ガガガ文庫)。「『ああ~~! ガキ共の性癖ぐちゃぐちゃに踏み躙るの楽し~~~~!』 "傾国の悪女” ニカ・サタニック・パルフェスタは魔界で自由を謳歌していた。種族間交流の一環として小学校の先生になったニカは、自慢の色香で子供たちを次々と骨抜きにしていく。やがてニカは魔王を含めた城中の魔族を支配し、魔王城を自分のための楽園に改造してしまうだろう。そんなスケベで邪悪な奸計の前に立ちはだかるのは、かつての敵と……運命の許嫁!? 『惚れたら破滅』とばれたら破滅!エロスで全てを支配するコメディファンタジー第二弾。」というのが今回の粗筋です。はぐれ者、除け者たちの救済、彼等彼女等が居場所を見つけていくというのがテーマの作品なんだろうなという本作、ジャンル的には少しエッチなラブコメということになるのでしょうが、何気にバトル部分も充実していて、今回も楽しく読ませてもらいました。イラストに石破ラブラブ天驚券みたいなポーズのものがあるのは、まぁご愛敬。これは、長期シリーズになってほしい作品かも。
第44回日本SF大賞、第54回星雲賞(日本長編部門)などの華々しい受賞歴を持つ、長谷敏司の『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)。かなり高い評判をあちこちで目にしていた本作の公式の粗筋は、「伝説の舞踏家である父の存在を追って、身体表現の最前線を志向するコンテンポラリーダンサーの護堂恒明は、不慮の事故によって右足を失い、AI制御の義肢を身につけることになる。絶望のなか、義肢を通して自らの肉体を掘り下げる恒明は、やがて友人の谷口が主宰するダンスカンパニーに参加し、人のダンスとロボットのダンスとを分ける人間性の手続き(プロトコル)を表現しようとする。だが、待ち受けていたのは新たな地獄だった――」というもの。2022年に単行本版が発売され、その時から注目はしていたのですが、この粗筋に微妙に魅力を感じなかったので読むのを後回しにして文庫化を待っていたという経緯があるのですが……。実際に読んでみると、いや、これはなかなか凄い作品ですね。クラシックバレエは重力からの解放を、コンテンポラリーダンスは重力そのものの表現をするものだ、というようなニュアンスのことを以前どこかで目にした記憶がありますが(曽田正人のマンガ『昴』だったかもしれません。だとすれば、さらにどこかにその出典があるのでしょう)、なるほど、身体性と人間性と自己表現とAIと介護と人の尊厳とヤングケアラーとを真正面から語った本作がコンテンポラリーダンスを題材にしたのは、正しい選択でした。実際に父が現在進行形でアルツハイマーの症状を強めている身としては読んでいてキツい部分も多々ありましたが、それだけに、かなり深く考えさせられて刺激的でした。AIと介護という題材を扱ったSF小説ということだと、この文庫版に解説を書いている人間六度の『烙印の名はヒト』(早川書房)という、こちらはかなりエンターテインメントに振ったスタイルの傑作がありますが、このテーマに対する両者のアプローチは全く異なっていて、そこも結構興味深いところがありました。個人的な見解ですけれども、この両作品を共に読み込むことが、このテーマを自らの内に受け入れて思考していく為にはいいかもしれません。
新しい学校のリーダーズのベスト盤『新しい学校のすゝめ』は、結成10周年を記念してリリースされたものとのこと。最近よくある商売スタイルとして「ベスト盤」といいながらも若干の新曲が収録されていたりするわけですが、そういうやり方はいかがなものかと個人的に思うのと、そこまでして新曲を手元にしたいとも感じていなかったので、このベストは買わなくてもいいかなと当初は考えていました。ただ、彼女等にはこれからも頑張ってほしいし、ご祝儀みたいなものとすれば、まぁいいかなということで、結局こうして購入することに。他のミュージシャンのCDを買う時に合わせて買ったという流れで、そこまで積極的にというわけではなかったものの、こうして改めて主要楽曲を聴いてみると、実際、良いベスト盤ではあるんですよね。興味はあるのだけれどこれまで彼女等の音源を買ったことが無いという人には、入門として最適な商品かもしれません。
唐突に「奏」が聴きたくなって、ネット上のPV等で聴いて済ませても良かったものの、どうせならば音源を手に入れようと、スキマスイッチのベスト盤『POPMAN'S WORLD』を購入。個人的な見解としてスキマスイッチといえばこの曲と「全力少年」だよな、という頭で再生してみた2枚組ですが、想定していた以上に良い感じです。そういう曲が多そうという先入観に加えてベスト盤だから余計にミディアムバラードがメインになっているだろうというイメージがあったのですけれども、そうとばかりも言い切れない、アップテンポな曲も結構ありましたし、なにより、どれもメロディーラインが良くて、なかなかの良曲ばかりなのがいいですね。ここから更にオリジナルアルバムまで揃えることはこれを聴いた限りでの感想としては多分無いのですけれども、このベスト盤を購入したことについては後悔していない……どころか、ナイス判断だと自分自身を褒めたいくらいです。
デビュー15周年で少しづつデジタルリリースしていた曲をまとめたミニアルバムが、CDとしては4年振りのリリースとなる、中島愛の『invitation』。これまでの活動でゆかりのある制作陣とともに作った5曲にインスト2曲の全7曲で、派手さは無いのですがじっくりと聴ける悪くない内容となっています。総収録時間が30分にやや満たないくらいの短さですが、コンパクトにまとめた雰囲気モノのミニアルバムという感じで、なかなかの佳作と言っていいでしょう。事務所を移籍してからの今の活動ペースで、フルアルバムが出る日がいつ来るのか、来ないのか分かりませんけれども、彼女のこれからの音楽活動の動向も、チェックはし続けておくべきかな、というところ。








| 2025年8月16日(土) 暑中雑感 |
夏は暑いのが当たり前で、暑くない夏なんて夏じゃないということもできますが、とはいえ、最近の夏は暑くなりすぎです。クーラーが毎日ずっとガンガンに効かせるのは大前提で、電気代がどうなってしまうのかが怖いですが、そうしなければ熱中症になるかもしれない、場合により命も危ないかもしれない、となっては、電気代の事はひとまず横に置くしかありません。個人事務所の事業主になってからは、職員時代以上に、まとまった休みが取りにくくなっているのですが、本当は少しくらいの連休を確保して、どこかに旅行したりしたいのが本音だったりします。まぁ、ただ、こんなに暑いのが常態化していると、真夏の時期は旅行を避けるべきだというようなことも、言えなくは無いのかもしれませんけれど。避暑地とか、涼しいところへの旅行なら、そうでもないのかな……?ただ、避暑地の代表格であるような軽井沢(異論は受け止めます)は瀟洒な別荘地の中に入ってしまえばまだしも、町中は非常に暑いですからね、最近の夏は。
ところで、暑い時に熱い食べ物・飲み物を摂取して汗をかく、ということが健康上も良いという話があります。これの科学的根拠は、熱いものを食べると胃腸の働きが活発化し体調が改善すること、熱さでかいた汗は蒸発をする時に体表から熱を奪っていくので体温が下がることが見込まれること、等が挙げられています。後者は、気化熱ですから、打ち水と同じ理屈ということになります。逆に冷たいものは胃腸を弱めて消化吸収が悪くなり、食欲減退と夏バテに至る可能性があるから、熱いからといって冷たいものばかりを食べるのは避けた方がいい、となるわけです(実行に移せるかどうかは、この際、横に置いておきます)。とはいえ、過ぎたるは及ばざるがごとし。あんまりにも高温多湿な、「直ちに生命の危険があるから不要不急の外出は控えるように」とアナウンスされてしまうような日に、直射日光下でフラフラになった状態であれば、熱い食べ物はむしろ熱中症を推進してしまうからアウトで、そういう時は早急に日陰で風通しが良くて涼しいところに行って、冷たい飲み物などで体を冷やすべきです。
街歩き、散歩が好きな私は、かなり以前に真夏の京都で1日中歩き回ったことがあって、その時は定期的にペットボトル飲料を買って飲んでいたので熱中症にはなりませんでしたが、大量の汗はかいたし、どれだけ水分をとってもトイレに行きたくならなかった(つまり、全て汗として出て行った)しで、真夏の水分補給の重要性を痛感したことがあります。それでもあの頃は今よりもまだ気温は低くて、その状況で20代の健康男性がああだったわけですから、もう同じことはできないかなというふうに思っていますし、他人には絶対に推奨はしません。凄い楽しかったですけども。とりあえず、涼しくなった頃に休みをどうにかして、どこかに旅行して街歩きなどしてみたいなと思いつつ、以上、とりとめのない、2025年夏の雑感でした。
2022年に単行本で刊行されたものが昨年の7月に文庫落ちされて発売になっていたのに今になって気づいた、青柳碧人の『ナゾトキ・ジパング SAKURA』(小学館 小学館文庫)。ロサンゼルスからの留学生(セレブの息子)が探偵役、森見登美彦の腐れ大学生的な主人公がワトソン役で綴られるミステリーで、起きる事件はかなりハードな本作の粗筋は、「精南大学に通う秀次は、絶望的な成績ながら寮での人望は厚い三年生(二回目)だ、事情により、春からLA出身の留学生ケビンと同室になった。桜満開の三月、旧学生会館で死体が発見された。第一発見者となった後輩の疑いを晴らすことはできるのか――。『ミョーデス』日本の文化が大好きで洞察力にすぐれたケビンと、巻き込まれがちな秀次が、探偵コンビに!? SAKURA! FUJISAN! CHA! SUKIYAKI! KYOTO! 日本の名所名物をめぐって起こる数々の事件の謎を解く、キャッチーなミステリ。」というもの。明記はされていませんが、主人公の住む学生寮は池袋当たりらしいので、おそらく立教大学辺りをモデルとして念頭に置いているのでしょう。桜の花、富士山への山岳信仰と富士塚、茶室、すき焼き、京都と、インバウンドでも人気の、いわゆる「日本的な」観光資源を題材にして描かれる物語は、殺人事件等の殺伐とした事件を扱いつつも、秀次とケビンのコンビ、そして秀次の幼なじみである理沙の3人のキャラ設定が良いのと、会話の掛け合いが楽しいので、あまりシリアスになることなく読むことができます。さらにキャラでいうと、かつてロス市警に派遣されていた時にケビンとの接点があったという、警視庁の田中刑事が、いくらなんでも現実にこんな警察官はいないだろうという、一種ライトノベルかマンガ的な言動をするのも、本作の軽めの読み心地には大いに貢献しているでしょう。リアリティーは無いかもしれませんが、いかにも青柳作品らしいキャラで、私は結構好きです。
おそらく大学生編がTVアニメとして放送開始となったことに合わせて刊行された、鴨志田一の『青春ブタ野郎はビーチクイーンの夢を見ない+』(KADOKAWA 電撃文庫)。「その日は峰ヶ原高校の体育祭。咲太はいつも通り、かえでに起こされ学校に向かう。理央や佑真と同じ青組で応援を決め込むも、憂鬱な相談が舞い込んで……。『玉入れのメンバーに欠員が出たから、咲太が出てくれ』 任されたのは、急に姿を消した同級生にしてビーチバレーのジュニア選手でもある大津美凪の代役。朋絵と玉入れをしたり、のどかと借り物競争に出たりして、ようやく訪れた麻衣とのお弁当タイム。 ところが、その途中立ち寄ったあるところで美凪の姿を発見し――!? 書き下ろし『トロピカルサマー』も収録する『青ブタ』初の短編集をお届け!」という粗筋の今回、「青ブタ」シリーズ本編は昨年完結していますが、そのサブエピソード的な番外編として表題の中編「青春ブタ野郎はビーチクイーンの夢を見ない」の他、「青春ブタ野郎はホワイトクリスマスの夢を見る」と「青春ブタ野郎はトロピカルサマーの夢を見ない」の2つの短編を収録しています。いわゆる円盤特典、劇場版の特典に書き下ろしを加えた形らしいのですが、こういう形で特典小説を1冊の文庫にまとめるというのには(アニメ版の円盤を揃えたり劇場版を観に行ったりした人等からの)批判もあるものの、個人的には新しくファンになった人にもそれ等の作品を読める機会を提供するという点で、むしろ肯定的に捉えています。
知念実希人の『天久鷹央の推理ファイル 呪いのシンプトム』(実業之日本社 実業之日本社文庫)は、3つの短編を1つの長編としてリンクさせるという、まぁ、こういうたぐいの作品には良くあるタイプの1冊。その裏表紙の粗筋は「水神。化け猫。消える銃弾。『呪い』の正体は? 水神の祟り。化け猫の憑依。頭蓋骨から消えた銃弾。まるで『呪い』が引き起こしたかのような数々の謎を前にして、天才医師・天久鷹央が下した『診断』とは!? ……そして推理の結果、小鳥遊の恩師が死んだ事件を『正解のない問題』と言い放ち、自ら手を引くと語った真意は?二重三重に仕掛けられた伏線と驚きの展開、その結末や如何に! 現役医師が描く、本格医療ミステリー!」というものですが、内容的には、ここまで煽りまくっている程では無かった、かも……?それはともかくとして、本作については、ラストのちょっとビターな結末がなかなか良かったです。もしかしたらそろそろネタ切れなのか、と思わせるようなところがあったのは、シリーズの今後というところでは、アレでしたけれども。
シリーズ2冊目にして完結篇……というか、最初から上下巻的な構想だったのだろうなという、中西鼎の『宮澤くんのあまりにも愚かな恋』(KADOKAWA 電撃文庫)。「ビッチなカノジョのアイツを、裏切ったのは俺でした――。 瑠音(るいん)と正式に付き合うことになった矢先、果南(かなん)と肉体関係を持ってしまった。俺と果南の関係に怪しいものを感じ取った瑠音は、しかしまだ何も問い詰められずにいた。あれから一週間。その間になんとか問題を解決するつもりだった。果南とは親友同士に戻り、瑠音とは裏表のない恋人に戻る。そのつもりだったのに。 「言ったでしょ、親友……。私はバレちゃった方が君を独り占めできて嬉しいんだよ?」 あざとくも破滅的な果南の企みの前に、事態はただただ悪くなり続ける。そして――『さよなら、ワタ』」というのが裏表紙の粗筋なのですが、いやぁ、第1作にも増してドロドロでインモラルです。この生々しさこそが、本作で作者の描きたかったことなのでしょうけれど、これを出すとは電撃文庫も随分と冒険をしていますね。とはいえ、最近はラノベレーベルの読者層も以前よりもずっと高年齢化しつつあるのでしょうし、こういう性的描写も普通に出てきて、インモラルなところもある作品も増えてきている感はあります。本作については、終わり方がちょっと弱くて、もっとエゲつないラストでもいいのにとは思いましたが、まぁ、これはこれで本作のシチュエーションの中では一番常識的な、一番穏やかな終わり方なのかもしれません。劇薬になり切れていないのが、やや惜しい感はありますが。
岩原裕二の『クレバデス 魔獣の王と赤子と屍の勇者』第9巻(KADOKAWA MFコミックス アライブ+シリーズ)は、いよいよ第2部のクライマックスか、という流れ。北の魔獣王ヴォーデインの行動の目的が明らかになりましたが、それが成されたとして、そのことがどういう事態を生み出していくのかは、まだ不明のまま。何となく予想できることはありますが、まぁ、しょせん私程度が予想していることですから、当たる保証はありません。物語は相変わらず面白さをキープしていますし、ここからの展開も、非常に楽しみです。
少年の抱く「年上のお姉さんへの憧れ」のじれったさやもどかしさを堪能できる、小川麻衣子の『波のしじまのホリゾント』第4巻(小学館 ゲッサン少年サンデーコミックススペシャル)。この第4巻では、ヒロインである年上のお姉さんの元彼氏、主人公の兄が帰郷。当然それで何も起きないわけがなく……という展開が描かれています。とりあえず、今回は兄弟がお互いに同じステージに立って相手と戦うということを確認し合った段階ですね。つまり、(兄は再び大学のある沖縄に戻りましたが)今後は今回のこれを受けての話が始まるわけで、それがここまでと比べどのような変化を生み出していくことになるのか、来年春発売予定だという第5巻が、待ち遠しくてたまりません。
遂に物語が明応の政変にまでに至った、ゆうきまさみ の『新九郎、奔る!』第20巻(小学館 BIG SPIRITS COMICS SPECIAL)。京都で足利将軍家のお家騒動が起きている中、新九郎も堀越公方の足利茶々丸を攻めて伊豆の地を奪うべく、味方勢力の拡大をしつつ機会をうかがっている状態です。歴史の大きな転換点、下克上の時代がすぐ目の前にやってきていて、となると、前巻の感想の時にも書きましたが、本作もいよいよクライマックスでラストが近いということになるのでしょうか……。本当に面白い作品ですのでできれば、新九郎が亡くなるまでを丁寧に描いていって欲しいのですけれど。


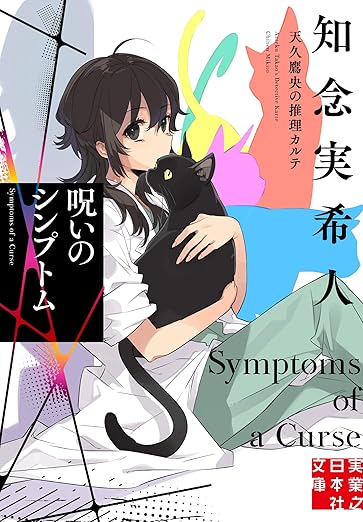




| 2025年8月9日(土) can't live without MUSIC(その1) |
今年の3月から5月にかけて、全6回で私というオタクがどのように製造されてきたのかという、言ってみれば履歴書的なエントリーを書きました。それは、「オタク」であることに引け目を感じない時代に対する私の気持ち等を書いてみようかなということをスタートにして、50代を迎えたところで一度、人生のこれまでを振り返ってみようかなという企画だったわけですけれど、主にアニメ、コミック、ラノベ等をどう愛しつつ人生が展開してきたかを簡単にまとめたそのエントリーを書いていて、次は音楽に焦点を合わせて、どの時期に、どういう音楽に接してきたかを書くのもいいかもな、と思うようになっていました。既に「るーつおぶまいみゅーじっく」でざっくりとは書いているのですけれど、ここらでもう一度、ちょっと別の形で書いてみようかな、ということです。正直、この「雑記」をお読みの皆様にとっては「そんなのは、どうでもいいくだらないこと」であるのは承知しているのですが、まぁ、そこはそもそもこの「ぱんたれい」の運営自体が私の自己満足でもあったりするので、その一環だとしてスルーしていただけると……。全部で何回になるかは分かりませんが、あまりダラダラと続いたりしないように、なるべく簡単にまとめていきたいと思います。
さて、私と音楽、ということで、今回はその導入部分、原初の体験というか、物心ついた幼少期に私がどんな音楽を好んで聴いていたかということを書きます。とはいえ、これはまぁそんなに面白い話はなくて、当時の私がよく聴いていたのは普通に童謡や唱歌でした。ちょうど家に、そういったものをセレクトしたLPが、確か4~5枚あって、それを幾度となく繰り返し聞いていた感じです。あとは、母がクリスチャンで、讃美歌のLPも2枚くらいあったので、それもたまに聴いていたかな。それで私がキリスト教徒になったかというと、母も別に信仰の強要はしてこなかったし洗礼を受けたりもしていないしで、そんなことは全く無いのですけれども。それでも今でも一部の賛美歌については何となく歌えたりもするのだから、無意識的な刷り込みは多少なりとあるのかもしれません。それで何か得や損をするということはありませんけれど。この讃美歌の辺りはもしかしたら若干特殊かもしれませんが、原体験が童謡・唱歌というのは、普通に考えて、そんなに珍しいことではないですよね。
で、それ以外のジャンルでの幼少の記憶となると、これは、父が集めていたLPということになります。彼はクラシック好き、ピアニストのウラジミール・ホロヴィッツ好きでしたから、その辺のLPはそれなりの量がありました。ここで「それ等を聴きまくっていくことで私の音楽生活の下地ができた」というようなことを書ければ、非常に模範的かつ教育的なのでしょう。が、そうでもないんですよね、実際は。一応書いておくと、父のクラシックLPを聴いていなかったわけではありません。また、その影響を受けていないこともありません。クラシックマニアである大学時代の友人に比べれば恥ずかしいくらいの少数とはいえ、私も自分でクラシック系のCDを買ったりしますし。もっとも幼少時となると、クラシックについては積極的に自分から再生したというよりは、父が聴いているのを私も受動的に聴いていただけ、というところですが。加えて、出版社勤務の父の生活は時間が不規則で私のそれとはズレていましたので、そういう機会は、そこまで多くは無かったと思います。一方で、小学校に上がる前の段階で私の音楽的嗜好の根本に刷り込まれることになったのは、父が集めていた、クラシック以外のLPでした。実は彼は、デビュー時からの 中島みゆき ファンだったのです。小学校入学前だと、アルバムでいうと3枚目の『あ・り・が・と・う』』が出た辺りかな。こちらは父が不在の時でも個人的に聴いたりしていたのですが、当時からの私のお気に入り楽曲は、「ひとり遊び」「歌をあなたに」「雨が空を捨てる日は」「彼女の生き方」「流浪の詩」「真っすぐな線」「遍路」「店の名はライフ」「サーチライト」というようなラインナップ。わりと、ブルースだったりカントリーだったりのテイストの強い曲が好きでした(というか、今でもこれ等の曲は好きです)。
この辺りが、私の音楽的好みの根っこ、将来に渡って影響を及ぼしていく、基本を形成したものとなります。
書店で見かけて購入したまま積読になっていた、小森収の『明智卿死体検分』(東京創元社 創元推理文庫)を読了しました。これは買っておかなければ、と私の背中を押した本作の裏表紙の粗筋は、次のようなものです。「被害者は、四阿に充満する雪に埋もれて凍死していた。この異常な状況は、間違いなく魔術によるものだ。魔術を行使して人を殺めるとその証が術者の相貌に顕れるが、事件関係者にその気配はない。ではこの殺人は誰がなぜ、どうやって為し遂げたのか?――謎に挑むのは権刑部卿・明智小壱郎光秀と陰陽師・安倍天晴。魔術が発達した世界で起きる不可能犯罪を描くシリーズ第一弾。」。科学では無く魔術(陰陽術)が発達した架空の現代日本を舞台にした、歴史改変SF特殊設定ミステリーです。作者のあとがきや大森望の解説によれば、これはランドル・ギャレットの「ダーシー卿」シリーズへのオマージュというか、同作と同じ世界を舞台にした作品なのだということです。ということは、同シリーズを読み込んでいる方が楽しめるタイプの作品であるのはおそらく間違いないところ、残念ながら、私は未読……。その他、マニアと呼ばれるようなミステリー好きであれば思わず笑ってしまうような小ネタも満載らしいのですが、それも私には(一部を除いて)察することができませんでした。ただ、そういう本作が、いわば「内輪ウケ」なだけの作品になっているのかといえばそういうことはなくて、架空世界のミステリーとして普通に面白く読ませてもらいました。ボリューム的にはちょっと物足りなさもあるのですが、物語としても過不足なく綺麗にまとまっていると思います。そして、本としての薄さをカバーする為に、この世界の本能寺の変を描く短編「天正十年六月一日の陰陽師たち」が同時収録されているのですけれども、これも、なかなか面白かった。なるほど、ここから、織田・徳川・羽柴が交代で日本を統治する天下三分の計に繋がっていくというわけですね。本作には続編も出ていて、実はそれも購入済みですので、早々にそちらも読むことにします。
主人公が家族と和解する流れを描いた前巻に続く、燦々SUNの『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』第10巻(KADOKAWA スニーカー文庫)。今回は「『俺は、自分が誇れる自分になるために、周防政近に戻る』 周防家当主の座に懸ける覚悟と、選挙戦への揺るがぬ決意。互いに本音をぶつけ合い、政近と有希はついに仲直りを果たす。(いや……これ、本当に誰? 別人? な、わけないわよね?)一方アーリャさんは、妹モードの雪に猛烈に振り回されながらも、兄妹が背負ってきた過去に寄り添い真実を受け入れる。そんな中、独り何かを思いつめたような様子の綾乃。彼女の前に、無邪気な悪意を忍ばせた乃々亜が急接近してきて……!?『本当は目障りなんでしょ? 九条アリサが』ロシアンJKとの青春ラブコメ、策謀が渦巻く第10巻!」という粗筋で、大筋は、主人公が家の事、有希と兄妹であることを近しい友人に明かすことと、乃々亜の悪意がいよいよ周知のものとなったということでしょうか。エピソードがこれ単体で完結しておらず次の第11巻に続く形になっているのは人気の出ている長期シリーズですから良しとして、問題は、これで次巻の発売がいつになるのか、ということです。今回の第9巻から第10巻までのスパンよりも早く出てくれればいいのですが。
先々週の第1巻に続き、樽見京一郎の『オルクセン王国史 野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか』第2巻(一二三書房 Saga Forest)を読了。第1巻も非常に地味な、兵站というかシステムを語っていくような内容になっていましたが、第2巻のこちらもかなり地味だった、その粗筋は「故郷を追われたダークエルフのディネルース・アンダリエルは、卑劣な白エルフへの復讐心を胸に、仲間たちと共に魔種族統一国家オルクセンに身を寄せた。『ならば戦争だ。ひとつ始めようじゃないか』エルフィンドに宣戦布告したオルクセンの賢王グスタフ・ファルケンハインが、勝利のために繰り出す前代未聞の『奇策』とは――?」というもの。つまるところ、エルフィンドへの侵攻自体は既に決定事項として存在しているわけですが、戦争というのは簡単に始められるものではない。単なる侵略ではないという大義名分と、慎重かつ十分な準備が必要になる。……というわけで、今回は1冊を丸々使ってオルクセンが開戦に向けて様々な準備をしていく、その過程を描いています。ミリタリー系に大きくウェイトを割いている作品だという事前情報は得ていましたが、ここまで丁寧にこういう部分を描いてきますか。「そこに至る」までをここまで丁寧にやっていくというのは、例えば笹本祐一の最近の作品なんかもそういう傾向がありましたが、こういうのはなかなか受けないこともあるものの、どうやら本作については多くの読者を獲得した模様。私も結構楽しく読ませてもらいました。面白かったです。
岬鷺宮の書いた作品は追いかけようと思っているので一応昨年10月の発売日に購入しましたが、映画のノベライズですし映画そのものもあまりピンと来なかったので、こちらも内容的にもどうなのかなと思って、なかなか手を伸ばしていなかった『ふれる。Spin-off Wanna t(ouch) you』(KADOKAWA 電撃文庫)を読了。「同じ島育ちの幼馴染、秋と諒と優太。東京で共同生活を始めた3人は20歳になった現在でも親友同士。それも不思議な生き物『ふれる』が持つテレパシーにも似た力で、趣味も性格もバラバラな彼らを結び付けていたからだ。お互いの身体に触れることで、心の声が聴こえてくる――。誰にも知られていない三人だけの秘密。しかし『ふれる』に隠されたもう一つの力が徐々に明らかになるにつれ、3人の友情は揺れ動いていく――。『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』『心が叫びたがってるんだ。』『空の青さを知る人よ』スタッフが贈る長編アニメーション。キャラクター達を掘り下げる、電撃文庫オリジナルの短編集が登場!」というのが裏表紙の粗筋で、まぁ、それ以上でもそれ以下でも無い、という感じ、かなぁ。面白くないわけではないけれど、何か新しい発見だったり意外性のあるエピソードだったりがあるわけではなく、視点を細かく分散しつつ映画のストーリーをなぞった(だけ)という印象です。申し訳ないけれど、どうせスピンオフ短編を出すのであれば、もっと本編のストーリーと絡んでこないようなところでアレコレと書いてもらう方が、個人的には好きです。
X(旧 Twitter)で本人が日本語で投稿しているのを見て、そこから公開されている動画を何本か見ていたら何だかすっかり気に入ってしまったアメリカのスカ・エモパンクバンド、MILLINGSTON の1stアルバムである『MILLINGSTON』と、ミニアルバム『BEATDOWN GENERATION』、『WELCOME HOME』の2枚を購入。楽曲が若干ワンパターンでマンネリ気味なところがあるのは否定できませんけれど、ホーンも入ったアレンジは無条件に陽気で気持ちが湧きたつエモさで、なかなか格好良いのです。当然、邦盤などは出ていないのですが、名古屋の大須にあるショップが即時に輸入したものを通販で扱っていたので、有難く買わせていただきました。彼等は楽曲の動画を積極的に Youtube にアップしているので、興味のある人は是非、それを見てみてください。CD(あるいはLP)を買えるかどうかは、タイミング次第かもしれませんけれど……。
プログレ熱と大人買い欲求が暴走して、そういえば PINK FLOYD のアルバムは未所有のものがまだまだあるなと、『a saucerful of secrets』、『MORE』、『UMMAGUMMA』、『OBSCURED BY CLOUDS』、『the final cut』、『A MOMENTARY LAPSE OF REASON』と『A MOMENTARY LAPSE OF REASON(REMIXED & UPDATE)』、『The Division Bell』そして『THE ENDLESS RIVER』の9枚を購入。今年新たにリリースされる海外ミュージシャンの新譜よりは少し安い紙ジャケ版を買っているとはいえ、これだけまとめ購入するとそれなりの代金を支払うことになることも受けて冒頭では一応「暴走」とは書きましたが、まぁ実際のところ今回の一機買いについて一切の後悔はしていないので、「暴走」という表現は妥当では無いかもしれません。今回買った中には、これは良いな、というものもあれば、申し訳ないけれども個人的にはイマイチというようなものもあったのですが、総じて満足度は高かったですし、内なるコレクター魂は歓喜にむせび泣くほど大満足したので、問題はありません。
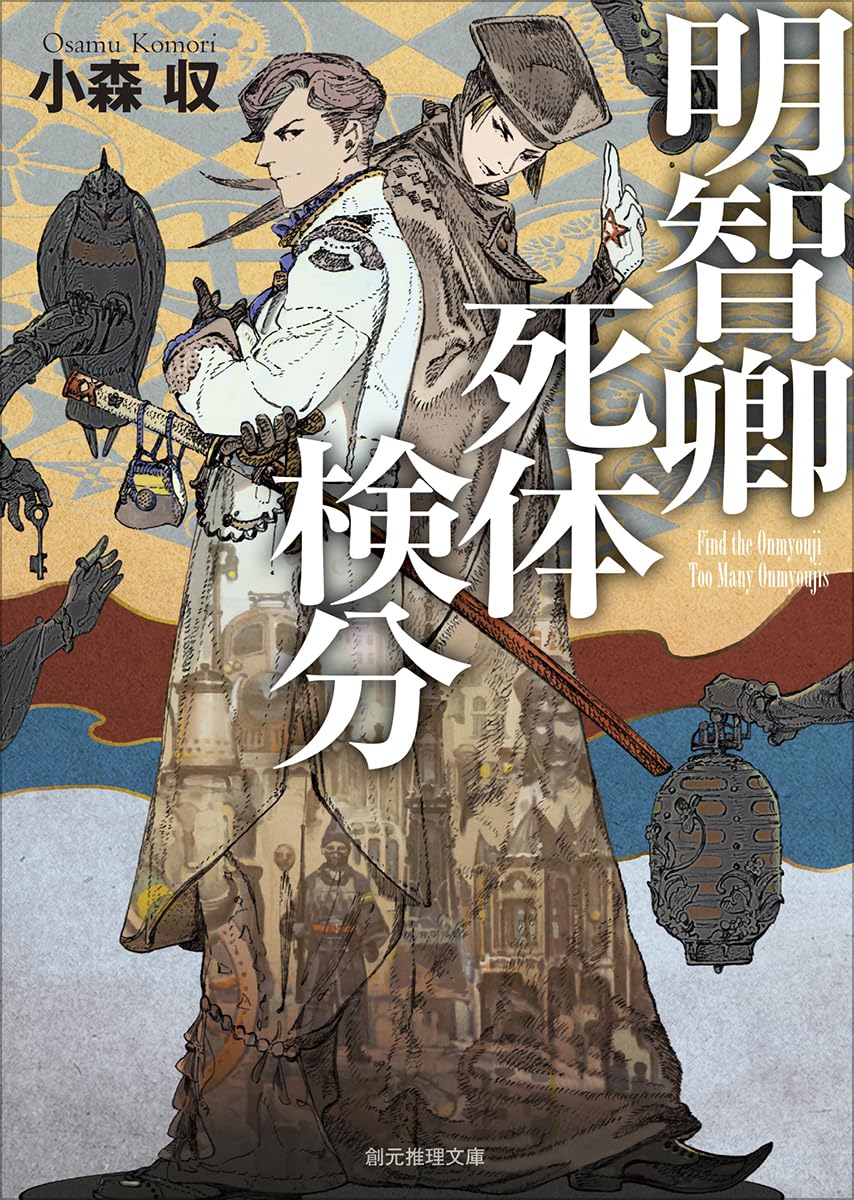
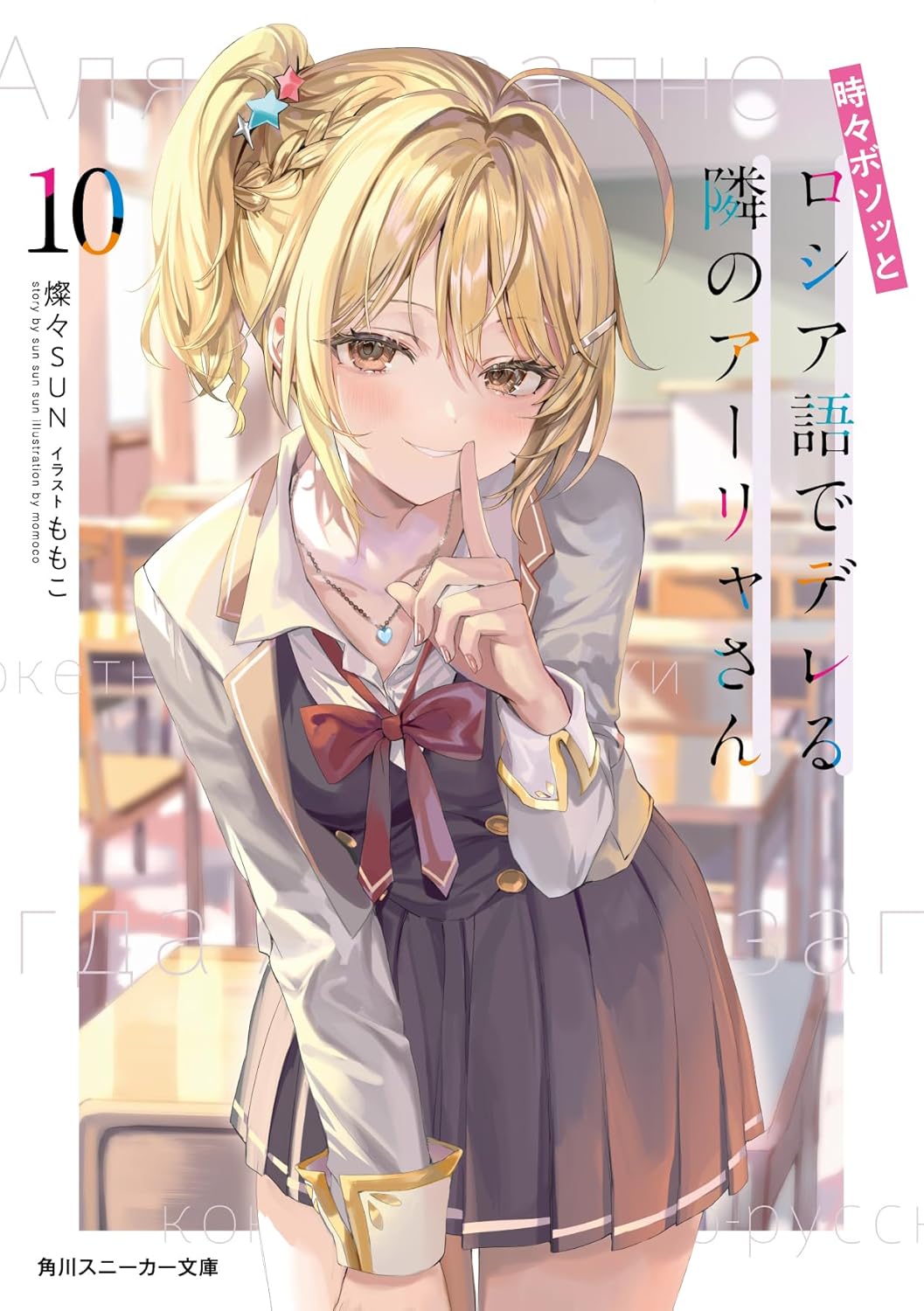














| 2025年8月2日(土) ポガチャル、ミラン、ポガチャル、リポヴィッツ |
2025年のツール・ド・フランスは、今年も最終日を迎え、先週日曜日に全21ステージの日程を終了しました。落車は自転車ロードレースという競技では避けて通れないところのあるアクシデントで、その転び方によっては大怪我をするし、命を失ってしまった選手もいるのですけれども、世界最大の大会にして注目度も高いツール・ド・フランスでは出場してくる選手もチームも気合の入り方が違うこともあり、他のレースに比べて落車が多い印象があります。これはちゃんと集計などをした数値を裏付けとして書いていることではなくて、私が抱いているイメージだけの話なので、間違っていたら申し訳ありません。ただ、今年の大会においても、結構深刻な落車が発生して、それで有力選手が複数、途中で大会を去ることになったりもしたのも事実です。本当は、そういうアクシデントが一切なくて、全選手が(体調不良等の場合は致し方ないとして)負傷リタイアすることなく無事に最終日まで走り切ってくれればいいのですが。
今年の大会だと、開始早々の落車で、個人TTその他での活躍が期待されたイネオス・グレナディアーズのフィリッポ・ガンナがリタイアしたことや、中間スプリントで他の選手と接触して落車しリタイアを余儀なくされたアルペシン・ドゥクーニンクのヤスペル・フィリプセン等を始めとして複数の選手が落車でレースを去りました。それ以外だと、これは落車のせいとは言えませんが、私が応援していた選手だと、総合優勝候補の1人として、個人TTステージでは圧倒的な勝利を見せたりもしたスーダル・クイックステップのレムコ・エヴェネプールが、実はツール開始前から骨折していたという肋骨のダメージを堪え切れずにリタイアしたり、ステージ勝利を挙げた後もポイント賞を争っていたアルペシンのマチュー・ファンデルプールが肺炎を発症してレースを去ったりと、やむを得ないところもあるとはいえ、まさか、と思ってしまうようなことも色々とありました。それがレース、勝負の世界ではありますけれど、こういうのは観ていて辛いですね。
そんな今大会で総合優勝を果たしたのは、昨年勝者で今回も優勝候補筆頭に名前を挙げられていた、UAEチームレミレーツ・XRGのタデイ・ポガチャル。安定した強さを全てのステージで発揮して、まさしく横綱相撲とでも言うべき走りで、これでツール・ド・フランスは通算4勝目です。ポガチャルの強さは実際凄いレベルに達していて、それはもちろん彼(とチーム)のたゆまない努力の結果なのですけれども、しかし、ここまで当然のように勝たれてしまうと、総合争いとしては面白くないのも、否定できない事実です。怪物級の選手が圧倒的強さを見せつけるのも面白さが無いわけではありませんが、やはりライバルとの激しい争い、勝ったり負けたりという展開の方が、視聴している側は興奮させられます。今回総合2位に入ったチーム ヴィスマ・リース ア バイクのヨナス・ヴィンゲゴーは、かつてポガチャルを圧倒してツールを制覇した年もありましたが、2024年イツリア・バスク・カントリーでの落車大負傷から復帰した昨年も今年も、ポガチャルに比べると微妙に格が落ちる感じになってしまっています。ヴィンゲゴーも他の選手と比べると異次元の強さを今でも誇っているのですが、ポガチャルは更にその上を行っている感じです。
で、そのポガチャルは、山頂ゴールステージでの圧巻の走りもあって、山岳賞も手中にしています。これは、山岳賞の配点を変えるか、あるいは開幕時点から明確にこれを目標としてひたすらクレバーに細かくポイントを積み上げるような選手がいないと、ポガチャルが出走する限り彼には勝てないということになりかねないかも。昨年のリチャル・カラパス(EFエデュケーション・イージーポスト)のように、総合争いができるレベルの選手がここにフォーカスするくらいの方が、山岳賞獲得には確実性が高い気もします。もちろん、そもそものコース設定がどうなのかということも、大きく関係してくるとはいえ。
ポイント賞は、ライバルが途中でどんどんリタイアしてレースを去っていく中、ステージを獲る等もしつつポイントを確保していった、リドル・トレックのジョナタン・ミラン。3週間の最期の辺りは疲労困憊で体力的にも精神的にもかなり限界に近いところにあるようにも見えましたが、それでもチームメイトに支えられながら何とかパリまで完走し、この栄誉を手にしています。最近の山岳勝負多めのグラン・ツールだと、そこでポイントを稼げないピュアスプリンターは平坦ステージでのステージ優勝はともかくとして、総合でのポイント賞争いには絡めないことになりそうですよね。となれば、平坦ステージと山岳ステージとのポイント差をもっと大きくするとか、中間スプリントポイントの設定ヶ所を再考するとか、そういう対処が必要になる、のか?
2000年1月1日以降に生まれた選手が対象となるヤングライダー賞は、総合でも3位に入った、レッドブル・ボーラ・ハンスグローエのフロリアン・リポヴィッツ。まぁ、3位とは言っても1位のポガチャルはもちろん、2位のヴィンゲゴーからもかなりのタイム差を開けられているのですが。リポヴィッツは自転車ロードレースの前にはバイアスロンをやっていたという24歳。上にいるトップ選手がとんでもない実力者揃いなので、どこまで勝利を挙げていけるかは分かりませんけれども、今後に期待できる若手であることは間違いありません。
以上、各賞の獲得者を振り返ってみました。ポガチャルはこれでツール・ド・フランス総合4勝目なので、もし来年も優勝すればいよいよ歴代最多勝の5勝クラブへ仲間入りということになります。それをヴィンゲゴーやエヴェネプールが阻止することが出来るのか、それとも新たなるポガチャルが彗星のように現れるのか。そこに興味が出るところですが、2025年の自転車ロードレースとしては、グラン・ツールもブエルタ・ア・エスパーニャも残っていますし、ワンデイレースもまだまだ残っていますから、妄想をたぎらせるのはやめにしておきましょう。
「ランサム・サーガ」と言われる全12作24巻の児童文学シリーズの第1作、アーサー・ランサムの『ツバメ号とアマゾン号』上下巻(岩波書房 岩波少年文庫)を久し振りに再読しました。児童文庫の裏表紙へ印刷されたものだからそんなに長くは無いのですけれど、上巻の公式粗筋を引用してみると、「ウォーカー家の3人きょうだいは、小さな帆船ツバメ号をあやつり、子どもたちだけで無人島ですごします。湖の探検、アマゾン海賊との対決……自然のなかで遊ぶ楽しさいっぱいの冒険物語。シリーズ第1巻。」というものになります。つまり少年少女が夏休みに経験するちょっとした冒険の様子を描いた作品なわけですけれども、舞台となっているのはイングランドの湖水地方で、ウィンダミア湖がモデルだと言われています。作者自身の経験が色濃く反映されているシリーズであり、現地にはゆかりの地も色々とあるのだとか。
ところで、湖水地方といえばビアトリクス・ポターの「ピーターラビット」シリーズという印象が一般的に強いと思いますけれど、個人的には、「ランサム・サーガ」の舞台、というイメージが一番大きいです。というのも、私が初めてこの作品を読んだのが確か小学校低学年の頃で、その段階では(さすがに存在自体は知っていましたが)「ピーターラビット」に関する知識はほぼ皆無と言っていい状態でした。つまり、「湖水地帯」に係るイギリスの作品という事で最初に刷り込まれたのが、この『ツバメ号とアマゾン号』だったというわけです。最初に読んだものの方が印象付けられるというのは、そりゃあそうでしょうという、特段珍しくなければ変でもない、ごく普通のことですよね。実はそれからも「ランサム・サーガ」は何度も読み返しをしていたものの、「ピーターラビット」については今まで一度もきちんと読んでみたことが無いという……。当時の「ランサム・サーガ」はハードカバーの『アーサー・ランサム全集』になっていたのですが、今回の岩波少年文庫版は、それを2010年から2016年にかけて新訳で刊行したというもの(その当初発売日にきちんと全巻を揃えつつも、すぐに読まずに積読放置していたのは、まぁ、いつもの私のパターンです)。児童文学として非常に評価の高い、人気のあるシリーズで、多分30年振りくらいに読んだのですが、やはり非常に面白かったです。古臭い部分は多々あるのですけれども、子どもたちの夏休みのキラキラした時間がページの端々から零れ出てきていて、良いのですよ、このシリーズ。このまま、最終巻まで少しづつゆっくりと再読を続けていきます。
川岸殴魚の『シスターと触手3 邪眼の聖女と不適切な魔女』(小学館 ガガガ文庫)は、全3巻となったシリーズの完結巻。「正教会の襲撃により拉致されてしまったシスター・ソフィア。邪教の仲間たちと共に救出に臨むシオンだったが、その前に立ちはだかったのは大聖女・ルシアと “勇者のなれの果て”。このままでは邪教壊滅のピンチ、シスターを救い出すことが出来る唯一の方法は……シオンの右手に宿る触手を覚醒させることのみ。『だったらヤるしかねぇ!』村人、仲間、王女、最後は大聖女まで、剥いて、剥いて、剥きまくる! 世界の真実が剥き出しになったとき、ついに真の女神が目を醒まして!? インモラル・ファンタジー、世界創世の最終章!!」というのが粗筋で、やや駆け足な流れになってしまっている感はありますが、しかし物語としてはきっちりとした盛り上がりを見せて綺麗にまとめてくれています。作者自身があとがきで「いやー、変な話だな」とコメントしていますけれども、その「変」で個性的な作品を出してくれるところが、ガガガ文庫の好きなところです。読み込んでいくとテーマもかなり深いですし、触手プレイの印象が強すぎるところはありますけれども、実はかなり真面目な話ですよ、これ。
白鳥士郎の『りゅうおうのおしごと!』第20巻(SBクリエイティブ GA文庫)は、本編の最終巻ということもあってか、590ページ超というかなりの分厚さを誇る1冊。当然、厚ければそれだけで面白いとか優れているとかいったことになるわけではありませんが、シリーズ開始から10年、常に熱い物語を届けてくれていたシリーズの最終巻ともなれば、「今回も」と期待しないわけには行きません。ちなみに、この第20巻については、これまで電子版でしかリリースされていなかった番外編、第15.5巻『りゅうおうのおしごと! ~髪を切った理由~』、第16.5巻『りゅうおうのおしごと! ~あねでしのおしごと!~』、第17.5巻『りゅうおうのおしごと! ~天ちゃんのおしごと!~』の3冊を1冊の文庫にまとめたものが同梱されている特装版が発売されており、こちらはこちらで同様の厚さがある為、合わせると普通の文庫であれば5冊くらいになってしまうかもしれないようなボリュームになっています(なお、当然私は特装版の方を購入しています)。
そんな今回の粗筋は「『私は絶対に認めたくありません』 プロ編入試験の是非を問う臨時棋士総会が開催され、あいの前に最強の試験官が名乗りを上げた。一方その頃、竜王防衛戦のため海を渡った八一に『谷間の世代』と呼ばれた伏兵たちが襲いかかる! 『始めようか? 居飛車と振り飛車の最終戦争を……!』 将棋二大戦法がその存続を懸けて激突する時、棋士たちもまた己の存在意義を求めて泥臭く足掻く。序盤、中盤、終盤どこを読んでも熱い対局の連続! 全ての駒たちが躍動する本編最終巻!!『九頭竜八一……先生。わたしをまた――――に、してくれますか?』空前絶後の将棋ラノベ、遂に終局。」というもので、基本的には収まるところに収まった終わり方といえるでしょう。内容もいつも通り楽しめて読めましたし。ただ、ここまで来たシリーズの、しかも最終巻なのですから、もっと熱く盛り上がる感じでも良かったのになぁという微妙な不満は残ります。その為、満点を付けられるかと問われるとやや微妙なのですが、しかし、シリーズ全体として考えれば、かなり良質のコメディーラノベだったと思います。現時点で、本編終了後の、主人公の結婚を描くスピンオフが出ることは確定しているとのことで、それを以て本作は完全完結ということになるのでしょう。多分、グランドフィナーレのカーテンコールに相応しい、賑やかで楽しいものを読ませてくれることでしょう。
シリーズ17冊目となる知念実希人の『天久鷹央の推理ファイル 猛毒のプリズン』(実業之日本社 実業之日本社文庫)の粗筋は、「容疑者は、天久鷹央!?天才医師、絶体絶命の窮地。 長野県の山奥に聳え立つ洋館、九頭龍邸に招かれた天久鷹央。そこで彼女を待っていたのは、計算機工学の天才、九頭龍零心朗からの『最後の依頼』だった。だが、捜査を開始して間もなく、とある『殺人』が起き、事態は混迷を極めていく。浮かび上がる容疑者たちと、連鎖する事件。そして最後に嫌疑がかかったのは、まさかの……? 現役医師が描く本格医療ミステリー、書き下ろし長編!」というもの。なる程、今度はクローズドサークル、しかも山奥の洋館モノですか。いかにも本格ミステリー的な設定で、このシリーズがどのような謎解きを提示してくるか、期待しながら読ませていただきました。やや無理のある展開も無きにしも非ずというところではありましたが、面白かったです。前巻が国家規模の事件を扱うものだっただけに、変に物語のインフレ化が起きてしまってはシリーズそのものの寿命を縮めることになりかねないと懸念をしていましたが、それはひとまず、杞憂に終わったと思ってよさそう。長く続いているシリーズですから少々マンネリ化しているところもありますが、それも含めて楽しく読ませていただきました。
一色まこと の『もうひとつのピアノの森 整う、音』第1巻(講談社 モーニングKC)は、名作『ピアノの森』(同社 同コミックス 全26巻)のクライマックスであるショパン国際ピアノコンクールで同作の主人公である一ノ瀬海と共にファイナリストになった向井智を新たなる主人公として、一流の調律師を目指す彼の苦労と悩みを描く作品。この第1巻の段階ではまだまだ話は始まったばかりで、ここからどうなっていくのかは分かりませんが(最終的にどうなるのかは、前作のラストで明示されていますけれど)、とりあえず出だしとしてはなかなかいい感じでしたし、今後も期待大でしょう。
発売は5月なのですが、ついつい積読にしてしまっていた冬目景の『百木田家の古書暮らし』第6巻(集英社 ヤングジャンプコミックス GJ)を読了。神保町の古書店を継いだ次女をメインにした3姉妹の物語は、この巻で完結です。一応、それぞれの恋愛模様にも決着がついた……のかな。なかなか面白い作品を描いていながら、ラストがちょっと微妙というか、曖昧に終わりがちなのが冬目景ですが、本作もその傾向から解放されてはいない感がありますね。まぁ、そんな中ではわりときっちり収まっているようにも思えるのですけれども。とはいえ、ここから更に何を描くかというと、これ以上は物語にとって蛇足になるだけでしょうから、本作についてはここで終わりというのが適切とも言えそう。
第1部の頃の破壊力はまだ戻ってきていない感があるものの、ようやく面白くなってきた、藤本タツキの『チェンソーマン』第21巻(集英社 ジャンプコミックス)。物語の着地点をどこに設定しているのかも、少しは見えてきたかな……。混沌としていた中に、ようやく筋道が出てきたというか。混沌は混沌として、それはそれで必ずしも嫌いでは無いのですけれど、本作の場合は第1部とのギャップで、(あくまで私個人としては、ですが)読んでいるこちらが困惑する感じになってしまっていました。ですので、こうやって物語が整理されてきてくれた方が、すっきりできます。








| 2025年7月26日(土) 銀座のランドマーク |
7月最後の更新ですので、恒例どおりに Top画像 を更新しました。こういう時に私はしばしば、今回使った画像の撮影場所についてはわざわざ説明せずとも一目瞭然だ、というようなことを書きますけれども、今回については、そんないつもよりも更に、どこの写真なのかが説明不要なのではないでしょうか。対象となっている建物も有名ですし、場所も有名。「日本一地価が高い」交差点である銀座四丁目です。構図的にも、あまりにもベタなので、それが故に Top画像 として使うのをむしろ躊躇われてしまうくらいだったのですが、雲一つない空の青さがあんまり綺麗だったので、まぁこういうありきたりな画像もそれはそれで悪くはないか、と、ちょっとばかり開き直ってみました。
なお、「日本一地価が高い」のはここですが、ではその逆に「日本一地価が安い」のはどこなのか。2025年の公示地価ランキングをざっと見た感じだと、北海道紋別郡滝上町、ですかね……。地図で場所を確認することはできますが、北海道は札幌や函館ですら現時点でまだ行ったことがありませんし、ましてや紋別の方ともなると、そこがどのような感じの場所なのかイメージも湧いてきません。北海道にもあちこち、一度行ってみたい場所はあるのですが、今のところその機会が無くて、津軽海峡の向こうには渡ったことが無いのです。まぁ、言ったことが無くて、一度行ってみたいと思っている都道府県は、実は北海道だけではないのですが。もう少し仕事に時間的な余裕が出てきたら、ふらっとあちこち行ってみたいものです。
ところで、ここでは「地価」とくくってしまっていますが、実は土地に値段を付す時には、そのやり方は1つではなく、具体的には主だったもので「実勢価格」、「公示地価」、「基準地価」、「固定資産税評価額」及び「路線価」という5つの種類があります。以下、それぞれを大まかに説明すると……「実勢価格」は実際に売買が成立している価格、一般の地取引の指標その他として使用されることを目的に国土交通省が毎年1月1日時点の価格として合評するのが「公示地価」、各都道府県が発表して「公示地価」を補完するのが「基準地価」、固定資産税の課税対象となる価格として各自治体が「公示地価」の概ね7割くらいになるように3年に1度決めているのが「固定資産税評価額」、贈与税や相続税の課税価格を算出する為に国税庁が(主に都市部について)「公示地価」の8割程度になるように決めているのが「路線価」、ですね。これは本当にざっくりとした説明なので、詳しく知りたい人は、是非ご自分であれこれと調べてみてください。
第173回直木賞の候補作となったのを見て、3月の発売日に購入しつつも何だかんだで積読にしたままでまだ読んでいなかった逢坂冬馬の『ブレイクショットの軌跡』(早川書房)を急ぎ読了。「底が抜けた社会の地獄で、あなたの夢は何ですか? 自動車期間工の本田昴は、Twitterの140字だけが社会とのつながりだった2年11ヶ月の寮生活を終えようとしていた。最終日、同僚がSUVブレイクショットのボルトをひとつ車体の内部に落とすのを目撃する。見過ごせば明日からは自由の身だが、さて……。以降、マネーゲームの狂騒、偽装修理に戸惑う板金工、悪徳不動産会社の陥穽、そしてSNSの混沌と『アフリカのホワイトハウス』――移り変わっていくブレイクショットの所有者を通して、現代日本社会の諸相と複雑なドラマが展開されていく。人間の多様性と不可解さをテーマに、8つの物語の『軌跡』を奇跡のような構成力で描き切った、『同志少女よ、敵を撃て』を超える最高傑作。」というのが公式の粗筋で、570ページにも及ぶなかなかの分厚さを誇る力作です。本作については原稿段階で早川書房の担当編集者が絶賛をしていて、私としてはそれで逆にちょっと構えてしまっていたところがありました。ハードルを上げるだけ上げているような前振りを見ると、むしろ疑わしく感じてしまうことって、ありますよね。
まぁそれはさておき、実際に読んでみた『ブレイクショットの軌跡』の感想です。色々な要素をてんこ盛りにしてそれを複合的に組み立てていく構成はかなり情熱を注いで作り上げたのが伝わりますし、今の日本社会について筆者が抱いている問題意識を、群像劇という形で、あくまでエンターテインメントの枠の中で作り上げた力量は素晴らしいです。また、これはデビュー作の時からそうでしたが、逢坂冬馬の文章はかなり読みやすいので、ページ数は確かにあるものの、余計なストレス等を感じることなく読み進めていけるのも、いいですよね。エンタメとしてはラストのところで更なる盛り上がりがあればとは感じましたが、そこはリアリティーとの兼ね合いでの落としどころがありますし、逢坂冬馬としてはそちらの方向をやりたいわけでもないのだろうなとも思えます。あと、LGBTQの要素は必要なかった気もしますけれども……ここはまぁ、それぞれの好みの問題でしょう。善良さと誠実さが全てを解決していくというような楽観主義的視線は、現実世界では成立しえないものかもしれませんけれども、フィクションでそれを描くことには大いに意味があるのではないでしょうか。綺麗にまとまり過ぎているラストも、希望を描こうという姿勢であったのだろうと解釈できますし、総じて、なる程確かにこれは良作だと言えます。
以前から読んでみたいと思っていた、樽見京一郎の『オルクセン王国史 野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか』第1巻(一二三書房 Saga Forest)にようやく手を出しました。「仲間と共にエルフたちの国(エルフェンド)を追われたダークエルフのディネルースは、満身創痍で倒れていたところを隣国の王グスタフに救われる。グスタフは魔種族統一国家オルクセンを統べるオークの王。ディネルースは自分たちを迫害した同法の白エルフ族に復讐すべく、グスタフに助力を乞い、オルクセンの民となるが――」というのがその粗筋。オークは何故いつもエルフや女騎士を襲うのか。もちろんそれは、(敢えてごく単純化した言い方をすれば)書き手や読み手の側がそういう物語構造を好んで創作し二次創作などもしてきたから、いつの間にかそれが「お約束」と化したということになるのでしょうが、フィクション内の設定として、オークがエルフを滅ぼさんとする理由を追求した作品であるということが、あとがきに書かれています。そのうえで、兵站部分にクローズアップしてストーリーを構築したと。それもあってか、第1巻のこの段階ではかなり地味なテイストになっています。ただこの作品の場合は、「むしろそれがいい」と言うべきで、その様な描写の積み重ねが面白さに繋がっているので、地味なことはマイナス要素とはなっていません。これは、第2巻以降も読まなければなりませんね。
理不尽な孫の手の『無職転生 ~蛇足編~』第3巻(KADOKAWA MFブックス)は、「小説家になろう!」版で封印された、アルスとアイシャの物語。「ビヘイリル王国での決戦の末、勝利したルーデウス・グレイラット。彼と彼を取り巻く人々のその後を描く物語集『蛇足編』。シリーズ第三巻は、家族も最も大きな危機がルーデウスと彼の息子アルスの両視点で描かれる特別編『ジョブレス・レッドカーペット』を収録。甲龍歴四九九年。ルーデウスの死後十八年が経過したある日、アルスは父の残した『ルーデウスの書』のうち未発見であった幻の二十九巻を入手する。そこに書かれていたのは若きアルスの暴走と父ルーデウスの過ちの記録だった。取り返しのつかない失敗の後も、人生は続く――。その先に何を思い、何を為すのか……。人生やり直し型転生ファンタジー、本編のその後を紡ぐ物語、シリーズ第三弾!」というのが裏表紙の粗筋です。私たちの今現在持っている常識とか倫理観からすると少しばかりインモラルなのですけれども、そこも含めて、ルーデウスと彼の家族の物語として、非常に面白く読ませていただきました。やはり面白い作品です、『無職転生』は。
何で今、と思われるかもしれませんが、ともかくも急に聴きたくなってしまったので映画『もののけ姫』のサントラCDを購入。安定の久石譲、安定のジブリサントラであり、ここに特にコメント等は必要ありませんよね。収録されている楽曲も、主だったものは皆さん良くご存じでしょうし。少々ワンパターンでマンネリぎみなところはありますけれど、それでも元々のモノが素晴らしいから案外と飽きがこないというのも、言うまでもないことです。まぁ個人的な久石サントラのベストは、実はジブリでは無くて、安彦良和監督作品の『アリオン』なのですけれど、それはそれ。ジブリに限定すると、原風景としての『風の谷のナウシカ』か、純粋に楽曲が好きな『天空の城ラピュタ』か、どちらか、かな……?今回入手した『もののけ姫』も良いものですし、音楽的なこと、技術的なことで言えば、『ナウシカ』や『ラピュタ』の頃に比べればレベルアップしているのでしょうけれど。
普段はスラッシュメタルやデスメタル系は聴かないのですが、昨年のパリ五輪の開会式の映像を何となく久し振りに見たらちょっと興味が出たので、GOJIRA が2021年に発売したアルバム『FORTITUDE』を買ってみました。それで早速聴いてみたのですけれども、ここで奏でられている音楽が私の好みにとってド真ん中のストライクかというと、確かにそこからは外れているのですが、これはこれで悪くないですね。楽曲や演奏のクオリティーも高いし、素直に格好良いなと思いました。例えば10代~20代の頃の私だったらこの音楽スタイルは受け入れられなかった可能性が高いことを考えれば、それから様々なものに触れ、聴いてきたことで好み等が(主にそれまでよりも拡大していく形で)変わってきたんだなぁということを強く実感させられました。とはいえ、これ以降、GOJIRA の他のアルバムもしくは同ジャンルの別ミュージシャンのアルバムも買ってみるかどうかと問われると、それはまだ未定です。そこまでジャンルに嵌れるかどうかは、このアルバムをここからどれだけ聴き込んでいくか、気に入っていくか次第、かな。
今年の6月頭にリリースされた ano の2ndアルバム『BONE BORN BOMB』は、1stとはちょっと印象の変わった1枚。具体的には、1stの『猫猫吐吐』がポップさの部分の押しが強かった感があったのに対し、こちらはロックテイストの印象が強いというところでしょうか。もちろんこれはあくまでそういうイメージという話であって、実際丁寧に比較して聴くとそこまでではない、どちらもポップさもロック風味も普通にある、というご指摘もあるでしょうが……。アルバムとしてどちらが好きか、ということであれば、今回の 2nd の方がより私の好みに合致すると言えます。収録楽曲にもう少しバラエティー性があるともっといいけれど、今は表現者として自分の路線を確立させようとしている過程である、としたならば、こうして固め打ちのようなアルバムになるのは、それはそれでアリかも。まぁ、私が勝手に妄想しているだけですが。
昨年の後半くらいから私の中では密かにプログレッシブロック強化期間が展開されていたのですが、その流れで、金属恵比須のアルバム、ミニアルバム、ベストアルバム、ライブアルバムを合計で8枚、発表順に『箱男』『ハリガネムシ』『阿修羅のごとく』『武田家滅亡』『黒い福音』『虚無回廊』『邪神覚醒 ~プログレ・ベスト~』『邪神〈ライヴ〉覚醒』と一気に大人買いしました。とはいえ、これで彼らの音源が全部揃ったというわけではなくて、流通しているモノが無かったりなんだりで手に入っていないものもあるのですけれども、まぁ、それはそれです。金属恵比須は1996年結成だからキャリアも30年程とかなり長いのですが、プログレは日本ではメジャーではないのもあってか、ここまでリリースされてきたアルバムもそこまで多くは無いし、おかげでまずまず手元にできたのかな、というところです。それが良いことなのか悪いことなのかというと、やや微妙でもありますけれども。そんなわけで、彼等のキャリアを一気通貫に堪能するような形になった今回の大人買いですが、うん、やっぱり格好良いですね、これ。彼らが徹底してプログレを追求してきたこと、楽曲が良くて演奏技術も非常に優れていることが、一聴してすぐにひしひしと伝わってきます。「プログレ」とひとことで言っても、そのスタイルにはそれぞれの個性があるわけですが、これ私の好物なタイプです。














| 2025年7月19日(土) 「置き配」標準化??? |
少し前に、国土交通省が宅配便に関し、通販サイトなどの配達業務や私的な利用について、いわゆる「置き配」を標準仕様とすることを検討しているというニュースがありました。コロナ禍以降のネット通販取扱量の増加に加え、労働人口の減少等による深刻なドライバー不足に働き方改革が追い打ちを掛けていような中で、初回配達時の受取人の不在等による荷物の再配達率も高いという現状であることがその背景で、運送事業者への負担を減らさなければいけないという認識から、そういう方針を掲げているのでしょうけれども……。お題目としてはそれでいいとしても、その解決手段として「置き配」の標準化というのは、いかがなものでしょう。これが実際に現実化すると、今でさえあちこちで言われている「置き配」関係トラブルが一気に噴出して大問題と化す可能性が大きいですよね。具体的には、盗難、消失、破損、誤配などのトラブルです。
配達されたとされている品物が存在しない場合、破損していた場合、誰がその損害の責任を負うのか。配達の任についていたドライバーか、配送業者か、それとも販売事業者か、あるいは(最悪なことに)誰も責任を取らないのか。この話題の時に、「だったら同じ商品を再度発送しなおせばいいだろう」という声も出てくるのですが、同じ商品の存在しないようなものだったらどうするのでしょう。これは、ワンオフでそもそも1つしか生産されていないようなアイテムに限ったことではなく、複数生産されていてもそれぞれ微妙に出来上がりに差があるような「縫いぐるみ」のような商品とか、数量限定でもう手に入らないとか、初回限定で特別な特典が付いているものとか、(プレミア的価値の有無を問わず)今では製造されていないレアな中古品とか、そういったものが挙げられます。同じように「返金をすればいいだろう」という声については、誕生日その他の何かの記念日に合わせて発注した商品とか、旅行などのイベントの前に入手しておきたくて購入した商品とか、そういった、そのタイミングで手にしていなければ意味が無かったものについて、「置き配」トラブルで購入者の手元への配達が成されなかったことで生じる逸失利益、損害について、賠償する側がそういったものの存在を認めるのか、その逸失利益・損害の金額はどのように算定するのか、という問題もあります。こういったあれこれがしっかりとクリアーになった後でなければ、「置き配」の標準化には、私はとてもではないけれど賛同することはできません。
で、反対するだけでは能が無いので……私なりに配達関係の環境改善を考えるなら、まず、現状のコンビニ受取の拡充が1つ考えられます。ただこれ、対象となるコンビニチェーンが少し限定されているのと、そもそもコンビニが近くに無いような人はどうするのかという問題があります。例えば私の住居のそばにはセブンイレブンがありますが、ローソンやファミリーマート、ミニストップ等はありません。ヤマト運輸の配送センターも、歩いていけるようなところでは無いです。これはせめて、全てのコンビニチェーンと、それに加えて郵便局や農協等も受取場所に指定できるようにしないことには、標準仕様とはできないでしょう。それに、そこまでやってもなお、それ等の店舗等が近くにない人というのはいますしね。「コンビニ受取があるだろう」と簡単に言う人は、都会の基準でモノを考えている可能性があります。次に宅配BOX受取ですが、それがあるような集合住宅ばかりではないし、あったとしても数が限られているところも多いと聞くし、設置場所の有無とその広さの問題等々もあるでしょう。設置場所については仮に確保できるとしても、費用のことを考えれば、これを推進するなら何らかの助成金を設ける必要もありそうです。つまり、コンビニ受取も宅配BOX受取も、部分的な解決策にしかならず、標準仕様とするのは難しいと思います。
となると、残るのは発注時もしくは発送時の受取日時指定です。全ての通販サイトでここの入力を必須にして、かつ、当初指定時に不在だった場合は追加で送料が発生する旨を明記し徴収する。追加料金をどのように徴収するのか、ということもありますが、これが一番現実的な対策だと私は思っています。Web上の通販ページの修正、システム構築については、一定額以上の支出があった場合に、例えば中小企業投資促進税制のソフトウェア規定に準じるような形で税制優遇を付ける。これも色々と問題のあるやり方ですが、とりあえず現状でやれる対策としては、一番無理がなさそうな気がします。まぁ、これは今ちょっと考えてみただけのことなので、最終的な結論を出すにはもっとしっかりと調べたうえで、じっくりと考えなければならないのですが。
第2部の3冊目、シリーズとしては9冊目になる紺野天龍の『あやかしの仇討ち 幽世の薬剤師』(新潮社 新潮文庫nex)の粗筋は、「父の仇を討ちたい――。悲願成就のため、破鬼の巫女・御巫綺翠のもとへ弟子入りを望む青年剣士・物部総十郎。偶然に彼と知り合った空洞淵霧瑚は、総十郎の病を心配しつつも彼の稽古を見守るが、そんな中、極楽街では謎の剣士に襲われる人が次々と現れる……。綺翠とともに祓い屋を担う釈迦堂悟の師弟関係を描く中篇を含む二篇を収録。現役薬剤師が描く、異界×和風ファンタジー!」というもの。今回は恋愛ネタを基本した2エピソード(まぁ、前半の方は「広義の」恋愛という感じですけれども)で統一したという感じで、わりと私にツボな内容だったこともあって、かなり楽しく読ませてもらいました。こういうピュアさって、いいですよね。第2部になってからタイトルに通算巻数が記載されなくなった問題については、やはりどうかと思いますけれど。
この、「タイトルにシリーズ巻数が無い問題」は、本作に限らず最近あちこちで目にしますが、これはアレですかね、長期シリーズになって巻数が2桁を超えてくると、新作が書店に置いてあった場合にそれを手に取りにくいから、巻数を表示しないことでさも単独の作品であるかのように見せた上で、シリーズ作品であることを知らないことに付け込んで中途の巻から買わせようとしているのか、と疑いたくもなりますね。まぁ、それで新規読者が増えるのであれば、否定すべき悪だとはあながち言い切れないのかもしれませんけれど。作品そのものに面白さがあれば、そこから遡ってシリーズを揃えようという気になってくれる可能性もありますし。個人的には好きじゃないやり口ですが、出版社的には正当化できる手法と言えるのかもしれません。
知念実希人の『天久鷹央の推理ファイル 絶対零度のテロル』(実業之日本社 実業之日本社文庫)の粗筋は「九月の熱帯者、小鳥遊優と鴻ノ池舞が当直を務める救急外来に搬送されてきた身元不明の男性。その死因は『凍死』だった。摩訶不思議な状況を前に司法解剖の必要性を説く医師達だったが、刑事の反応は芳しくなく……。捜査機関の協力が得られない中、天久鷹央は独力で遺体の正体に迫るが、それは日本全土を揺るがす大事件の序章に過ぎなかった。シリーズ最大規模の凶悪犯罪の真相は!」というもの。この粗筋にあるように、今回はこれまでのシリーズに無かったくらいに大きな事件が題材になっていて、物語としてのダイナミクスはかなりのものがあって面白かったのですが、こういう題材をこのシリーズに使うという事については、個人的にはあまり歓迎したくない感があります。その理由ですが、あまり大きな事件は何となくシリーズに合わないような気もするのが一点、こういう方向に舵を切ると扱われる事件にインフレが発生して、次の巻はもっと大きな事件を、そのまた次の巻はさらに大きな事件を、というように求められる規模が膨らみ続けた挙句、そんなものは書けない、となってシリーズの寿命を縮めてしまいがちだというのがもう一点です。余計なお世話、要らない心配かもしれませんが、それがちょっと気になった1作でした。
藤井太洋の『まるで渡り鳥のように 藤井太洋SF短編集』(東京創元社 創元日本SF叢書)は、2015年から2024年の間に彼が日本、中国、韓国、アメリカで発表してきた11の短編を集めた1冊。公式の作品紹介は「宇宙で生物の『渡り』を研究する日本人と、春節に地球へと帰省する習慣を持つ華人のパートナー。それぞれの選択を描いた表題作ほか、薩摩藩に雇われ江戸総攻撃に臨む屍兵遣いの数奇な人生を綴る『従者トム』、大国による侵略の危機に晒される国境近くの難民キャンプで感染症対策に挑むエンジニアの闘い『距離の嘘』、軌道作業ステーションに就職した奄美の巫女(ユタ)が遭遇する宇宙的脅威『祖母の龍』など、国内外で発表した十一編を収録。各編に書き下ろしの著者解題を付す。 テクノロジーと人類への希望を描く傑作SF短編集」というものであり、収録作の幾つかは既読で、「従者トム」と「晴れあがる銀河」については、それぞれのリンク先に簡単な感想を掲載済みです。とはいえ、様々なアンソロジーを全てフォローしていくのも難しいし、海外媒体での発表作はなかなか手を出せるものでは無いしで、かなりの部分、今回のこの短編集が初読になります。広く活躍されている好きな作家で、こういう短編集が出てくれるというのは、嬉しいこと。
さて、前置きはともかくとして、内容について。収録されている作品はどれもかなりガチでハードなSFなのですが、現代社会の問題を反映させたものが多いのが特徴なのかなというのは、ちょっと感じたところです。それは藤井太洋という作家の創作スタンスがそういう方向性なんだろうなというのも、これまで読んできた彼の作品の内容を思うと想像できるわけですが(ご本人から「それは勘違いだ」と言われてしまうかもしれませんけれど)、基本的にどれも前向きなテイストなので、読後感もかなり良いものとなっています。ここにあるような硬質さを好まない人もいらっしゃるとは思いますが、クオリティーの高い面白い短編が多いので、これは是非、読んでおくべき1冊だと思います。個人的には、表題作の「まるで渡り鳥のように」と「距離の嘘」、「海を流れる川の光」、「読書家アリス」、「祖母の龍」がお気に入り。
三河ごーすと の『義妹生活』第14巻(KADOKAWA MF文庫J)は、高校時代の終わり(友人との卒業旅行)と大学生活の始まりを描く1冊。その粗筋は「親友たちとの卒業旅行。趣味も価値観も異なる4人がアイデアを持ち寄ったことで、新しい経験をし、未知の物に触れ、悠太と沙季の見える世界が拡がっていく。旅行や大学生活、プロと呼ばれる大人との会話を経て、二人は思い知る。日本の渋谷。通っていた高校――そんな限られた狭い場所にいるだけでは見えないものがたくさんあるのだと。自分の人生をより良いものにするために。二人の関係をより良いものにするために。沙季は、ある決断をくだす――。卒業旅行、テーマパーク、お笑い、水族館、大学生活開始、インターンシップ、子づくりの相談。自立の時を迎える “兄妹” が距離を越えた証を求め合う恋愛生活小説、第14弾。」というもので、何と言うことも無い日常を淡々と丁寧に描いていく本作にしてはイベント感のある内容となっていますが、テイストがそれで変わるわけでもないところに、本作らしさが溢れているな、と。2人が大学に進学したことで新たなる友人キャラクターも登場してきて、今後彼ら、彼女らとどのように絡んでいくのかが、楽しみといったところでしょうか。今回ラストの、アレもありますし……次の第15巻は、何気に少し注目かも。
いよいよセントルイスの地でのコンテストが始まる、石塚真一の『BLUE GIANT MOMENTUM』第5巻(小学館 ビッグ コミックス スペシャル)。裏表紙には「6年ぶりにテナーサックス奏者を対象に開催される超名門ジャズコンペ会場に足を踏み入れる大…!!世界中から集まった若手テナーマン13名はそれぞれ強い個性と覚悟を兼ね備えた猛者たち…!!決勝に残れるのは僅か3名。険しい条件下で大の演奏はッ!?」とあり、エクスクラメーションマーク(!)を使い過ぎではないかと感じてしまうものの、内容的には今巻はこれが全て。今回は1次予選部分が描かれて、当然主人公である大はここは通過して決勝に進むわけですけれど、大以外の参加者についても(全員ではありませんが)その背景等が短いながらもしっかりと描かれていて、物語に厚みを出しています。やはりコンクールであれば、ライバルとなる奏者に、主人公とは異なるタイプの、そして豊かな才能のあるメンバーを揃えるべきですよね。連載では追わずにコミックスで読んでいるので決勝の結果はまだ知りませんが、物語的にはここで勝たなければ話にならないので大が優勝するとして、そのシチュエーションをどこまで説得力ある感じに描けるか、次の第7巻も楽しみです。
アニメ第2期も絶賛放送中の、龍幸伸の『ダンダダン』第20巻(集英社 ジャンプコミックス)。裏で暗躍するサンジェルマン伯爵の思惑はまだ不明ですが、画も相変わらず綺麗ですし、作者が良い感じにノリノリになって描いていることが推測されて、読んでいてニヤニヤしてきてしまいます。とはいえ、大枠のストーリーにあまり進展がない状態が続いているので、そこはそろそろ少し動きが出て欲しいところ。アクション等が格好良いのと構図やコマ割りの迫力で普通に楽しめてしまいますが……。
今回も圧倒的に熱かった、つるまいかだ の『メダリスト』第13巻(講談社 アフタヌーンKC)。色々なキャラクターの過去がぐるんぐるんと頭の中を回って、この感情をどう処理したものかなかなか困ってしまうことに。これだけ連載が続いてくるとどこかで中だるみというか、弛緩したところが出てきてもおかしくないのですけれども、本作は相変わらずのハイテンションで、かつ、圧倒的な熱量を維持したまま突っ走っています。一時期登場キャラが一気に増えた際に、これはこのまま何となくストーリーが散漫になっていってグダるパターンなのではと懸念したのが嘘のようですが、結局、あの時に登場したライバル達の中で今でも物語に絡んできているのがどれだけいるのか、と考えると……。この、小さい頃は才能を期待されつつもその後は名前を聞かなくなるという流れ、考えてみると非常にリアルな気がします。スポーツに限ったことではないでしょうが、才能で勝負する世界って、そういうシビアなところがありますよね。







| 2025年7月12日(土) 段々と絶滅危惧種になりつつあるのかも |
わざわざ改まって言うまでも無く皆さんご存じのことと思いますが、私は読書好きです。で、小さい頃から馴染んでいたのが紙の本だからということもあってか、電子書籍には魅力を感じず、基本、どんな本でも紙で購入することを方針としていたりもします。なので、電子オンリーでの販売とか、部数が減っているのか書店で新刊が手に入りにくくなっていたりとか、そういう状況にはそれなりに思うところもあるのですが……これは、紙の高騰とか、それ以外の諸経費も値上がっているとか、そういう外的な要因もあるでしょうし、私のように「紙」にこだわる人も減ってきているのかなという(個人的には)ちょっと寂しくなる風潮もあってのことかなと思うと、致し方ないところもあるのかという諦念に囚われたりもします。
ところで、紙の本がそんなに売れないということは、欲しい本を書店で手に入れにくくなったことだけでなく、本の単価の上昇にも結び付いているのではないかとも考えられます。ちょっと前なら400円程度で買えた文庫が900円くらいするとか、同じく400円台だったコミックスが700円台後半になっているとか、印象としてはおおむね1.5倍~2倍くらいの値段になっているという感覚です。もちろん前述の外的要因、そもそもの原価が上がっているということは無視できないわけですが、発行部数が少なくなれば1冊当たりの単価が上がるのは昔からある話です。そうなると、もともと数が減少傾向にある「紙の書籍」愛好家の1人当たり購入書籍数が(予算の都合で)減ることが想定されるから、ますます販売総数が減少し(本当は紙の方が好きなものの、電子の方が安いから紙では本を買わないことにするという人も増えるでしょうし)、それを受けて値段がまた上がる、もしくは紙での出版が行われなくなる、という方向になることも容易に予想されます。そういう負のスパイラルが生じるのは、個人的には勘弁してほしいなぁというところ。
ちなみに、文学青年だったウチの父が学生時代に買っていた文庫本は1冊100円程度でしたから、経過年数と値上げ幅でグラフを作った場合に、値段だけで考えれば近年急激に上昇しているとまでは言えない(もちろん、価格は毎年見直されていたりしたわけではなく、一定年数ごとに値上げが行われる階段状のグラフになるはずですが)かもしれません。ですが、昨今政治的な争点にもなっている食料品価格と同様、本の値段の上がり具合も個々の消費者(買い手)の収入の上がり具合と比例していないのは、大きな問題です。これって、文化保護・文化振興のお題目の下に補助金を投入すればいいという話でもないですよね。むしろそれは、税金の無駄遣いに該当すると思えます。とはいえ、町の書店の倒産も留まるところを知らない感じですし、書籍流通の形式の見直しとか、紙の本を読む習慣をどう復活させるかとか、課題は多いです。私個人だけの事ならば、現時点で所有している書籍を再度読み返しているだけでも、ここからの人生で困ることはなさそうなのですけれど、それはそれ、これはこれです。まだまだ読みたい新作、これからも追っていきたい作家も多いですし、紙の本にも町の書店にも、無くなってほしくはないと強く思います。
今年になってから少しずつ読み進めている知念実希人の「天久鷹央の推理ファイル」シリーズ、今回紹介する『天久鷹央の推理ファイル 羅針盤の殺意』(実業之日本社 実業之日本社文庫)の粗筋は「『頼んだよ……鷹央君』師を殺したのは、誰だ? 御子神氷魚。帝都大学の元主任教授で、現在は総合病院の院長を務める彼女は、天久鷹央の学生時代の師だった。同じ個性を持つ氷魚に導かれ、診断医の道を志した鷹央。天才医師が唯一『先生』と呼ぶ存在は、しかし不治の病に冒されており、最後には不可解な死を遂げる。謎めいた言葉を遺した師の真意を知るため、鷹央は捜査を開始するが……。姉弟の絆を描く、本格医療ミステリー!」というもの。動機とか犯人が誰かとかは分かりませんでしたが、トリックに関しては、レベルの浅いミステリー読者の私にも今回はわりと分かりやすかったかもしれません。とはいえ、本シリーズについてはトリックで読ませるタイプのものだとは私は思っていなくてキャラクター小説に近いという認識であり、いつものメンバーが賑やかに動き回っていればそれで楽しめるので問題はありません。
人間六度の『推しはまだ生きているか』(集英社)は、文芸誌『小説すばる』に2022年末から2024年頭にかけて掲載された5編を収めた短編集。「宇宙船内の超サステナブル都市で生きるリンネの前に現れた、自殺した親友・マドカを名乗るマシン。マドカの遺体を “循環” させないため、二人は危険な旅に出る。『サステナート314』 荒廃した東京で過酷なシェルター暮らしを送るアミパン。唯一の『推し』が消えた日、彼女は凸ることを決意した。『推しはまだ生きているか』…他全5話。」という帯の紹介文からも分かるように、これはSF作品、それもかなりシリアスなポストアプカリプスものを集めた作品集と言ってもいいような内容になっています(唯一、4本目の「君のための淘汰」は少し違いますが)。明るい未来を描くようなものにならない、未来がロクなことになっていないことが全ての作品で前提となっているところが、彼の作風なのかな、と一瞬思いかけたのですが、考えてみれば今の時代に無邪気に「明るい未来像」を描くことも難しいかもしれないとなれば、人間六度に限らず、真摯に題材に向かい合っていたならば必然的に人類にとって酷な未来が来た作品になっていくのかもしれません。そして、全く絶望に包まれた、陰々滅々たるラストというのではなく、どれも絶望的な世界においても強く生きている人間を描いているところに、作家としての人間六度の良心が感じられます。これは、彼が急性リンパ性白血病からのサバイバーであり、一次は死も意識しながら念願の作家になったという経歴の持ち主だということも関係しているかもしれませんね。私の勝手な想像なので、ご本人がここを読んだら「そんなわけがあるか」と言われてしまうかもしれませんが。シビアな内容がメインとも言えるので、メンタルが最低にある時に読むことは推奨いたしませんが、知的刺激もあって、これは良い短編集でした。
シリーズ4冊目となる伏見七尾の『獄門撫子此処ニ在リ4 狐の窓から君を見る』(小学館 ガガガ文庫)の粗筋は、「まどろみから目覚め……迷い込んだ異界の街で撫子たちが出会ったのは、『はざま』を探る案内屋ドラセナと、吹雪の如く荒れ狂う獄卒カシャリ。奇妙な二人ろの縁をきっかけに、撫子とアマナの心はすれ違い始める。新たな友人との交友で自らの世界を広げていく撫子と、少しずつ遠ざかろうとするアマナ。そんな二人の絆を試すように、獄卒と九尾の忘却された因縁が、京都を異形の祭に染め――『あなたと見る景色、わたしは好き』『君と同じ景色を見ていたらと、心から思うよ』うつくしくもおそろしい少女鬼譚、繰り返す縁の第四巻。」というもの。内容的には、色々あって撫子とアマナの絆がさらに深まるエピソードで、その過程でこれまで明らかになっていなかった設定が色々と開示されるという感じ。正しくシリーズものの流れに乗って展開させていると思いますが、発生する事件が第2巻の焼き直しになっているところが若干見られたのが、やや残念でした。発展形というか、アレを踏まえての今回、という造りにはなっているのですけれども、
2018年の4月に発売になっていたのをすっかり見落としてしまっていた美奈川護の『星降プラネタリウム』(KAOKAWA 角川文庫)。公式の粗筋は、「施設運営部プラネタリウム事業課天文係――それは、5月上旬に新入社員研修を終えた渡久地昴が告げられた配属先だった。希望とは違う部署で働くことになった昴は、先輩である望月にプラネタリウムのコンソールボックスへ案内された。上映が始まると、指先一つで宇宙を操り、観客に星の解説をする仕事を目の当たりにする。「人は何のために星を見るのでしょうか」その答えを知るために、故郷を捨てた己と向き合っていく。」となっています。要するに美奈川護お得意のお仕事小説であり、新社会人の成長モノであり、そして魂の救済的な要素もあるという、鉄板的な構成の作品だと言えます。それだけに、Amazonのレビューでは構成のマンネリ気味なことを心配するコメントもあって、それには私も賛成するところだったりします。更に本作はちょっと盛り込み過ぎなところが無きにしもあらずであり、そのため、中途半端というか、消化不良気味で終わってしまっている要素もあったりするのは、結構なマイナス要素。基本的には面白い作品なのですが、美奈川護ならもっとやれるだろうというか、求めているレベルからすると物足りないというのが、正直な感想です。悪い作品では無いのですけれど。
これで物語が完結する最終巻となる、まきぶろ原作、白梅ナズナ作画の『悪役令嬢の中の人 ~断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします~』第6巻(一迅社 comic LAKE)。描くべきものを描き、因果応報の顛末、復讐譚をすっきりとする結末へと導いた、いいラストでした。エピローグ部分の余韻も非常に良かったですし、これは非常に優れたコミカライズです。まきぶろ さんは、味のある絵柄で細かいところまで手を抜かずに丁寧に描く人でありつつ決して「画が上手い」とは言い切れないところはありますが、しかし「マンガが上手い」のは間違いなく、その「上手さ」がいかんなく発揮されたのが本作であると言えると思います。全6巻というボリュームも手ごろですし、アニメ化も決まったらしいということもあるから絶版にもならないでしょうから、今からでも普通に入手しやすいので、未読の方は、是非、このタイミングでこの傑作を一気読みしてみてください(グロテスクな画が苦手な人は、ちょっと合わないかもしれませんけれど)。最高に面白いですから。
アニメ『ONE PIECE』の劇場版でゲストヒロインであるウタの歌声を担当した Ado が、作中の歌楽曲をまとめたミニアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』を購入。そういえば買っていなかったなと思ったのが購入の動機であり、それ以外に何かがあるわけではありません。映画も観に行ってないですしね。つまりコレクションとしての完成度を重視して、見所有のものを買ったというだけのことなのですが……案外に良いですね、これ。歌い上げる系の曲もあって、何気にデビューからずっと Ado はもっとそういうタイプの曲をやればいいのにと思っていた私にすれば、まさにこれを求めていた、と膝を打った次第です。
音楽活動20周年を記念した、廃盤となっていた同人時代のミニアルバムのリアレンジ復刻盤である新譜の発売を契機に、やなぎなぎ の未所有だったアルバム等のうち、今回リリースされた新譜の『Encore』の他、『memorandum』、『エメラロタイプ』、『Branch』、『ホワイトキューブ』の5枚を購入。ミニアルバムで品切れになっていることにより今からでは購入できなくなっているものもありましたが、まぁ、一応、それを除いた一通りがこれで私の手元に揃ったことになる、のかな……?自作曲もそうでない曲も含めて、しっかりと自分の世界を作っているのが彼女のいいところですよね。以前、ある程度のアルバムを買って何となく満足してしまっていましたが、改めてこうしてそれ以降に発売になったものを揃えて聴いてみると、そのことを実感します。自分の世界を確立しているミュージシャンにありがちな、ある種のマンネリさからの脱却までは出来ていない感こそありますが、総じてクオリティーも高く、「ああ、買ってよかったな」と思った次第です。











| 2025年7月5日(土) 違う、そうじゃない |
ちょっと前は東京都議会、そして次は参議院と、選挙が続きます。選挙カーが五月蠅いとか、通勤時間の駅前での演説が邪魔くさいとか、そういうのは(選挙カーについてはもっとやりようがあるかとは思っていますが)ともかくとして、ポストに投函されたり街頭で配っていたりするチラシを見ていて、幾つか、これは言わせていただきたい、ということがあります。こんなところで政治の話はちょっと……というのは思わないでもありませんが、さすがにどこかに書き散らしてガス抜きをしないと、致命的な場所で口走ったりしてしまいそうなのがマズいので、お目汚しでしょうが、ここで吐き出すことをお許しください。
選挙に限らず、こういう一定の候補者から誰かを選択・支持しようという時に、その基準をどこに求めるか。これは人によって異なるでしょうし、余程のことでもなければ、どれが正しいとか間違っているとか、そういう話にはなりません。そのうえで私としては、私の思う基準で誰を選ぶかを決めるわけですけれども、その時にはまず、大前提として選択対象となる方々の能力を重視したいと思っています。もちろん、私自身の望むこと、考えていることと逆の方向で能力が高い場合にはアレなのですけれども、いわゆる「無能な味方」の危険性を考えれば、人が良くても能力が無い人に票を投じるのはちょっとね、となります(人柄だったり熱意だったりという要素も決して無視してはいけないし、無視してはいないのですけれど)。そして当然、その人がどのような主張を持っていて、何を為そうとしているのかが、その次に問うべきポイントになります。
先日の都議会選と一部の市長選の情報を見ていて気になったのが、この点。誰かを特定して批判をしたいわけではないので個人名は出しませんけれど、こう、特に女性候補において、演説においても配っているチラシにおいても、「都議会に女性議員を」とか「〇〇市初の女性市長を」というようなことばかりを訴えていて、それ以外の何らかの具体的な政策は皆無と言ってもいいレベルでした。私個人の感覚では確かに女性議員や首長の数はもっと増えてもいいとは思いますけれど、だからといって女性採用・登用の定数を設けるクオータ制度には批判的な立場を取っています。実力不足・能力不足で地位を得るのは結局は良いことでにはならないから、というのがその主たる理由ですが……。上記の候補者については、そういう選挙活動、売り方でやっているということは、つまり、「私の最大の売りは “女性であること” であり、実のところ、それ以外には大したアピールポイントは無いし、訴えたい政策も無いのです」と言っているも同じだと解釈できてしまうのですけれど、本当にそれでいいんですかね?私としては、そういう候補には投票したくないのですが。
おそらく直接本人にそれを聞いたら、「そんなことはありません」という答えが返ってくるのでしょうけど、表面に見えている活動状況は、性差で優遇されたり差別されたりを否定的に訴えているであろう候補者が、むしろ性差を理由に自分を選べと言っているという、自己矛盾めいた姿だけです。こういう戦略で仮に当選したとして、もしそれで少しでも失敗をしようものならば、「それみたことか」という大合唱が始まるのは目に見えているわけですよ。本来の実力がどうこうとか、掲げている政策の正当性とか素晴らしさとか、そういうのは一切関係なく、ちょっとした言い間違いとか、大したことのない些細な瑕疵が出ただけで、「だから女性は……」的な反応が出てくるような状況になってしまうというのが最悪なパターンで、それって結局、ジェンダー格差をむしろ深めていることになっていますよね。だから、「女性であること」を売りにしたりしないで、もっと人物本位・政策本位で、かつ熱意の感じられる形で選挙活動はしてほしいのです。それで、この人は能力がありそうだな、(内容に共感を覚えられることが前提ですが)訴えていることを実現させるべく頑張ってくれそうだなと感じられたら、私も一票を投じます。
地方選挙、国政選挙、男女を問わず、私が支持したくなるかどうかはともかくとしても、しっかりとした政策を掲げて、優秀さを感じさせてくれる、きちんとした候補が増えていくことを願ってやみません。そうしないと、現状の諸々の問題を変えていくような候補を選びたいと私が思っていたとしても、選択肢ができてこないんですよ、残念ながら。
著作をゆっくりと読み進めている作家の1人である、斜線堂有紀。そちらの方向のものも多いみたいだから、少し陰鬱な作品も一度読んでみようかと思って『恋に至る病』(KADOKAWA メディアワークス文庫)を読了しました。「やがて150人以上の被害者を出し、日本中を震撼させる自殺教唆ゲーム『青い蝶(ブルーモルフォ)』。その主催者は誰からも好かれる女子高生・寄河景だった。善良だったはずの彼女がいかにして化物へと姿を変えたのか――幼なじみの少年・宮嶺は、運命を狂わせた "最初の殺人” を回想し始める。『世界が君を赦さなくても、僕だけは君の味方だから』変わりゆく彼女に気づきながら、愛する事をやめられなかった彼が辿り着く地獄とは? 斜線堂有紀が、暴走する愛と連鎖する悲劇を描く衝撃作!」というのがその粗筋なのですが、まぁ、読んでいて気が滅入るタイプの物語であることは、間違いありません。詳しく書こうとするとネタバレになってしまうし、私の思うところを語るとこれから読む人の本作に対する解釈にバイアスをかけてしまうことにもなりかねないので、何を書くかは難しいのですが……取り合えず言えるのは、おそらく本作の読者には、終幕に主人公への救済を見出す人と、そうでない人がいるだろうなということ。そして、ヒロインであり多くの人を死に至らしめる「化物」になったヒロインについて、悪意の所在がどこになるのかとか、彼女の意図はどこにあったのかとか、主人公の事を本当はどのように思っていたのかなど、善意的にも悪意的にも解釈が可能で、そういう意味で、かなり読み応えがあったということでしょうか。個人的なことをいえば、こういうタイプの作品は、嫌いでは無いです。ただ、メンタルが若干疲れている時に読むものでは無かったかも。こういうのは、元気な時に読むべきですよね。
加筆して【完全版】として再刊行されたものは一通り読み終わり、いよいよ新たに刊行されだしたところに突入した知念実希人の『天久鷹央の推理ファイル 吸血鬼の原罪』(実業之日本社 実業之日本社文庫)。といっても、新版としての【完全版】発売が始まってから既に2年近くが経過し、もう結構な巻数のエピソードが発売になっているので、「新たに刊行」というのも何だか違う気もしてならないのですけれど。ともあれ、そんな今回のエピソードの粗筋は「二つの傷跡。抜かれた血液。犯人は……吸血鬼? 東久留米市の公園。荒川の河川敷。そして、東京湾の沿岸。三つの場所で相次いで見つかった遺体。被害者はいずれも首すじに二つの傷跡があり、ほぼすべての血液が抜き取られていた……。まるで『吸血鬼』が起こしたかのような連続殺人。捜査一課の桜井公康から内々に相談を受けた天才医師・天久鷹央は、事件解明に動き出す。現役医師による本格医療ミステリー、書き下ろし長編!」となっていて、これはつまり、吸血鬼の仕業によるものとしか思えない死体が発見された場合に、医療ミステリーとしてそれをどのように科学的に説明し、合理的な謎解きを行っていくのかを楽しめる内容だと言うこともできるでしょう。まぁ、そこについては個人的には「そういう感じかな」というところだったのですが、このエピソードのポイントは、教育実習生制度のダークサイドにスポットライトを当てたところにあるかもしれません。もっとも、今現在の同制度は、本作中で描かれたものから改正が加えられていて、主に職場が合わなかったり倒産したりした場合の転職関係に結構な違いがあるのですが……まぁ、それはそれ。制度の理想と現実の格差、発生しているトラブル等は今でもまだまだ大きな問題となっているわけで、こういう作品を通じて、多くの人がそこに対して何らかの関心を抱いてくれるようになるのであれば、それはいいことだなと、私としては思うのです。
2024年3月に第18回小学館ライトノベル大賞で優秀賞を獲ったデビュー作の『嫉妬探偵の蛇谷さん』シリーズ(小学館 ガガガ文庫 第2巻まで発売中)の野中春樹が、その翌4月に第18回講談社ラノベ文庫新人賞を獲った作品、『探偵気取りと不機嫌な青春』(講談社 講談社ラノベ文庫)が先月発売されたので、とりあえず買って読んでみました。「身勝手な探偵気取りの行為で、高校生の朝河探は一年前、相手の逆恨みから妹に大怪我を負わせた。以来、朝河は他印の問題に関与することに抵抗感を抱いていた。しかしある日、同級生の青山景が万引きの疑いをかけられる。朝河は青山の何もかもに諦め切った表情に突き動かされて、青山にかけられた冤罪を晴らす。何かと朝河に話しかけてくるようになった青山と関わるうちに、二人の距離は近づき、朝河は青山の過去と母親との確執に行き着く。青山の母が犯した罪の真相に協力して辿り着き、さらに関係性が前進したその直後、朝河の過去が朝河自身に襲い掛かる――!?事件が新たな事件を呼び覚ます学園青春ミステリー。ここに開幕!!」となっていて、こう言っては何ですが、米澤穂信の「小市民」シリーズの要素を焼き直している感が強いです。もちろんそれについてはオマージュ、本歌取りという言い方もできますが、ちょっとこの作品ならではのオリジナリティーがそこまで強く感じられないので、そういう点で今一つ評価しづらいかなぁ、というところ。面白いか面白くないかだけで言うならば、普通に楽しんで読める作品なのは間違いないのですけれど、上位互換として 小鳩常悟郎 と 小佐内ゆき の顔がチラついてしまうんですよ。
年に1回の新刊発売、石塚千尋の『ふらいんぐうぃっち』第14巻(講談社 講談社コミックス 週刊少年マガジン)を購入。梅雨入り前の時期に発売となっていながら表紙イラストが思いっきり秋の紅葉で季節感無視なのはアレですが、内容的には今回も普通に面白かった。「とっちゃり」勝負とその結末には、ちょっと笑わせてもらいましたし、やはり良い作品だなぁということを改めて実感した次第。続きはまた来年になってしまうのですが、期待しつつ気長に待たせていただくことにします。
今月からTVアニメも放送される岩原裕二の『クレバデス 魔獣の王と赤子と屍の勇者』第8巻(KADOKAWA MFコミックス アライブ+シリーズ)、第5巻から始まった神学校編(正式名称ではありません)も次第にクライマックスになってきました。東西南北四方の魔獣王がいよいよ一ヶ所に集結しそうで、魔獣王ヴォーデインの目的も判明していますし、複数の勢力が動き出している感もあって、話がどんどん盛り上がってきています。ヴォーデインの狙いも単純な話では無いでしょうし、もしかしたら更なる裏もあるかもしれないと思えば、物語はまだまだ続きそうです。となれば、連載が打ち切りになどならずに完結まで続くよう、TVアニメ版にも、一定の成功となってほしいものです。
大体2ヶ月に1冊のペースで刊行されている、野上武志の『はるかリセット』第21巻(秋田書店 チャンピオンREDコミックス)を購入。今回も面白いエピソードが多かったのですが、そういえば私が最後に帽子を被ったのはいつだっただろう、と、ふと思いました。まさか小学校の赤白帽まで遡ったりはしないはずですが、中学や高校の制服には学帽は無かったし、大学に入ったり社会人になってからだと、帽子を被っていたという記憶が、まずまず存在しないんですよね。熱中症の予防にも寒さ対策にも、帽子というのは非常に優秀なツールであるというのは、『はるかリセット』に教えてもらうまでも無く知っていたけれども、こう、帽子を頭に置くという行為がそこまで好きでなかったりするもので……。
夢路行の『あの山越えて 日・日・天のたより』第10巻(秋田書店 A.L.C.DX)を購入。タイトルを変えての仕切り直しシリーズも、2桁に乗りました。基本的にのんびりまったりとした時間の流れている大石家にも毎年変化というのは訪れているわけで、この第10巻でも、あんなことやこんなことが起こったりしています。そのうえで、それでもやはり、のんびりまったり、というのがこの作品の持ち味ですよね。今回も、良い感じに楽しませてもらいました。夢路行がこういう作品で長期連載をするとは、まさかむかしは思いもしなかったものですが、こうしてずっとコミックスを追いかけて読み続けていると、しみじみと面白い作品だと実感することもしばしばですし、改まって考えてみれば、作風的に、確かにこの路線は合っているなぁと。







| 2025年6月28日(土) The Castle |
今回が2025年6月最後の更新。つまり、1年の半分が経過することになるわけですけれども、感覚的にはそんなに時間が経ったというようには思えなくて、気が付いたら半年が過ぎ去ってしまっていたことになります。何だかいつもそんなことを言っているようにも思えますが、ということは、逆に今の感覚の方が通常な速度感であって、以前がむしろ時間を間延びして感じている状態だったのかもしれませんね。と、まあ、それはそれとして、月の最終更新ですから、いつものように今回で Top写真 を変更しています。今回の写真については、非常に分かりやすい構図となっていますし、特にここで解説をするようなことは無いかと思います。これがどこの城なのかとか、そういうのは、また来月に Top写真 を更新した際に、「あーかいぶ」に書く予定ですが、有名な城ですから、言われなくても分かるという人も多いでしょう。
Top写真 に城の、というか天守閣の写真を使ったのは、2022年の6月に続いてこれが2回目。このまま天守閣シリーズというような形で色々な天守閣を使っていくのも面白いなと思ったりもするのですが、それをやるには、まず画像を撮影に行かなければならないというネックがあります。とはいえ、実際、それは私にとってかなり魅力的なことに思えるので、真剣に検討する価値はありそうです。ベタといえばベタですが、まずは12の現存天守からというのがオーソドックスでしょうか。ここで問題になるのは、天守閣撮影旅行の時間をどのように確保するのかということです。どうせ行くのであれば天守閣だけ撮影してさっさと帰るというのではなく、近隣の観光もして、温泉などに入ってから帰りたいですし、2泊3日くらいで考えたいですよね。仕事の段取り、やり繰りを何とかしてその休みを確保できるか否かは、要は私の覚悟というか、やる気の問題ですけれど。
ところで、城といえば真っ先に連想されるのは、やはり分かりやすい天守閣でしょう。しかし、城はそればかりではありません。個人的には、山田果苗のマンガ『東京城址女子高生』(KADOKAWA HARTA COMIX 全4巻)を読んでからというもの興味を感じている中世の城跡なんかも見にいきたいところです。それだと、都内・東京近郊で日帰りできるところに、色々ありますしね。Top写真 に使えるようなものが撮影できるかということは、さておき。
八咫烏シリーズ9冊目、阿部智里の『烏の緑羽』(文藝春秋 文春文庫)を読了。「八咫烏の一族が住まう世界『山内』。正式に即位した弟の奈月彦を支える長束は、自らの護衛をつとめる路近を信じることができない。なぜ彼は自分に忠誠を誓ったのか? 答えを求め、ひとりの男のもとを訪れるが――あの政変の裏で、長束とその配下たちが見ていたものとは。深い因縁と山打の行く末がからみあう!」というのが今回の粗筋で、要するに第2部になってからの新展開をより重層的に語っていこうという趣向のエピソードということになるのでしょうか。このキャラはこういう人物なのか、という気付きはありますが、物語としてはあまり進展は無いかも。刊行ペースもそこまで早くはないというのもあって、話の大筋を忘れてしまいがちになってしまうのが、このシリーズを読んでいる時の問題といえば問題かもしれません。さすがに、毎回ここまでを全て読み返すなんてことをしている余裕はないですし。
ホラーテイストの強い、彩坂美月の『double ~彼岸荘の殺人~』(文藝春秋 文春文庫)を読了。「少女の頃に念動力で世間を騒がせて以来引きこもるようになった紗良を、幼馴染のひなたは見守ってきた。しかし紗良の噂を聞きつけた富豪から『幽霊屋敷』の謎を解き明かして欲しいとの依頼が入る。屋敷にはテレパス、サイコメトリストら超能力者が呼び寄せられていた。惨劇が二人を待ち受ける。書き下ろしホラーミステリ。」というのが裏表紙の粗筋で、要するに、過去に何人もの死人が出ている曰く付きの「呪われた館」に集められた超能力者たちが事件に巻き込まれるという筋立てなわけです。彩坂美月といえば青春小説、という(そう評されることについて本人が嬉しいかどうかはともかくとして)基本的な判断基準があるわけなのですけれども、それに即して考えると、今回のこれは、そこまで「青春小説」というわけではないものの、少女2人の関係性を描いているという意味では、一応、そういう要素が無いわけでもない作品、ということになるでしょうか。
ミステリーに超能力者というのは、変な話、わりとどういうシチュエーションでも「超能力だから」で強引に突破できてしまいそうな分、あまり相性は良くない気がします。そこで、例えば能力の発動に一定の制約をかけるとか、状況的に例えば三竦みみたいな配置になっていてうかつに能力を使えなくなっているとか、そういう縛りを加えることが対策の1つとしてしばしば考えられるわけですけれども、本作の場合は、そういうところにあまり気を遣わずに書かれている感がありました。一応、超能力者「ならでは」の部分とか、個々が有している超能力が物語の展開に貢献するシーン等もあったのですが、残念ながら、「集められた超能力者たち」という設定を有効に活用できていたかと問われると、正直微妙かもしれません。そこがいかにも勿体ないとは思ったのですが、作品そのものは結構面白く、「紗良とひなたの物語」として、大いに楽しませてもらいました。
個人的に待望の発売となった、ニテーロンの『転生程度で胸の穴は埋まらない』第2巻(KADOKAWA 電撃文庫)。何しろ前巻がかなり面白かったので、続巻にも絶対に出て欲しいと思っていましたし、いざ発売が決まったとなったら、実際に読める日が凄く楽しみで、とはいえタイミング的に発売日すぐとは行かずに若干経ってからの読了紹介とはなってしまったのですが……。そんな本作の粗筋は「白い孤独は、渇望を隠す赤い少女と再会する。 『私、偶には寝ているコノエさまを起こしたいです』 シルメニアの一件が終わり、テルネリカと穏やかな日々を送るコノエ。彼女によって胸の穴は埋まったかと思われたが……。『あなた、いつも必死で真面目よね。全部を警戒している感じ』そう指摘してきたのは、彼の学舎時代を知る超越者(アデクト)の同期メルミナ。『……さっきのエルフの娘と随分仲がいいのね?』やけにコノエに “重い” 視線を向ける彼女と共に向かうのは、魔物救う汚染地の掃討。だが仕事の最中、自らの渇望をひた隠す彼女もまた、大きな欠落があることが分かり……。持たざる彼らの渇望を描く、本格異世界転生譚第2弾!」というのが裏表紙の粗筋ですが、なる程、こういう方向性でやってくるわけですか。内容的に水準以上のものであればという前提の上で言うならば、このパターンを繰り返すことでしばらく巻数を重ねることは可能ですけれど、それはあまり好きではないし、私は本作の「主人公の人間性回復の物語」としての側面に魅力を感じているので、この第2巻ではそこが微妙に薄れているのがちょっと残念でした。メルミナと関わったことで変わった部分もあるというのは分かるのですけれど、ならばそこをもうちょっと描写的に厚くしてくれた方が、個人的には好みです。とはいえ、ラノベ的な作法・文法で言えば、今回のこの第2巻のやり方で正解かもしれないのですが。
大きなエピソードというよりは、今後に向けてキャラの堀下げをしようという巻なのかなと思えた、日向夏の『薬屋のひとりごと』第16巻(イマジカインフォス ヒーロー文庫)。「皇帝の手術を無事に終えてから半月、季節も冬へと近づいていた。術後の治療を上級医官に替わってもらったおかげで、猫猫の日常は忙しくも平常運転へと戻っていた。そんなある日、老医官に届いた文を読んだ妤の顔色が変わった。『怖いことになるかもしれない』。その文には水膨れができた患者が増えてていると書かれていたのだ。嫌な予感がする猫猫だったが、その心配は当たってしまった。『疱瘡の発生』。感染力、致死率が高く、顔や身体に痕が残りやすく恐れられている流行病だ。特効薬はなく、猫猫でも今から見つけることは不可能だろう。感染が広まれば村一つが閉鎖することもあるという。そんな絶望的な状況に一筋の光を放ったのは――。」というのが粗筋で、一応、基本ラインとしては「疱瘡の流行」という大ネタがあるのですが、敢えてなのかどうなのか、そこにはあまり重きをおかない感じでこの巻は書かれています。まぁ、次の第17巻で改めてそこをやる可能性も否定はできないところではありますけれど……。ラブな要素もしっかりと盛り込まれていて、その点では大満足というところ。小蘭まわりのところにちょっと不穏さが漂っているのは、心配ですけれど。
FLYING KIDS の35周年記念アルバム『希望のシッポ』を購入したのですが、これ、実に素晴らしい出来ですね。ファンクとはかくあるべしと言わんばかりの、陽気で底抜けにポジティブ、ノリノリで繰り広げられるサウンドは、今の流行からは外れているかもしれませんけれども、こういう音楽からしか吸収できない栄養分というのは、確かに存在します。ちょっと難しい感じのファンクミュージックも嫌いではありませんけれども、やっぱりファンクっていえば、今作のような音楽ですよね。あくまで個人的なイメージの問題ですけれど。こうなると、ライブにも行ってみたくなるところです。仕事に追われていて時間がなかなか無いのがネックとはいえ。
これまでにリリースした3枚のガンダム曲カバーアルバムが好評で、シリーズとしては完結していることがアナウンスされていつつも、「でも4枚目も出るんでしょう?」的なファンの声が絶えなかったという、森口博子 。そんな要望を完全に無視してしまうのも心苦しいということか、ならばガンダム楽曲をオーケストラアレンジで歌ってみましょうという企画盤、『GUNDAM SONG COVER -ORCHESTRA-』がリリースされました。まぁ、どうしたって原曲と比較する気持ちが無くならないのがこういう企画の常ですが、でも今回のこれはかなり良い出来。もともとの曲がいいことは言うまでもなく、オケの厚いサウンドと、そこに森口博子の優れたボーカルが乗るのですから、まあ、それは間違いなく一定レベル以上のものが提示されるというものですよね。意外性のある楽曲、意外性のあるアレンジこそ無かったですが、手堅いつくりの、好盤と言えるでしょう。
人間は、ストレスが溜まると「大人買い」をしたくなってしまうもの。もちろん財布に相談をして断念をすることだって普通にありますが、何かの間違いでそこで(心理的な)障壁が崩れてGoサインが出てしまうと、もうブレーキは効きません。今回紹介する緑黄色社会が、まさにそのパターンになりました。流れとしては、上で第16巻の感想を書いた作品『薬屋のひとりごと』のアニメ版第1期のOPだった「花になって」を聴いているうちにバンドのその他の曲にも凄く興味が出てきて、ちょっとこれは音源を手に入れていようかなと徐々に思うようになったという感じです。そんな中で仕事関係で最近わりと負荷が高くかかってきて蓄積されたイライラが限界に達してきたのをきっかけに、ならば最近気になっている緑黄色社会がここまでに発表してきたアルバムやミニアルバムで、今現在購入できるところをずらっと一応一通り買ってしまえと決めた次第です。具体的に今回購入したアイテムの名前を挙げるならば『緑黄色社会』、『溢れた水の行方』、『SINGALONG』、『Actor』、『pink blue』、『Channel U』の6枚になります。サブスクで聴けばいいのではないかと思う人もいらっしゃるかもしれませんけれども、やっぱり手元に実際に手触れるブツ、マテリアルとしての音源が欲しいという気持ちは、程度の差はもちろんあるとしても、自分で稼げるようになったオタク・マニアであれば、「そういうことは普通にあるよね」と納得していただけるのではないかと思います。
さて、それで緑黄色社会なのですが、このグループのことを最初に知った段階では、「緑黄色野菜」をもじったと思わしきバンド名から、コミックバンド系なのかなと思ってしまっていました。その後にネットでいくつくかの曲を聴いてからも、想像していたものとは少し違うけれども、私の好み的には今一つ刺激の足りないポップバンドかなと感じたので、これまでは音源を手に入れようという意識があまり働いていませんでした。そんな中、リリースされたのが「花になって」です。同曲を聴いたことがある人であれば分かっていただけるかと思いますが、これが実に良い曲なんですよね。メロディーラインも歌詞もアレンジも、私の好みのツボにはまりまくりました。で、その時点で配信のデータは購入していたのですけれど、そうなると他の曲も色々と聴いてみたい。ネットにアップされているようなもの以外の曲も聴いて、バンドの全体像を知りたくなるわけです。そうして今回、晴れてまとめ聴きをしたわけですが……。最高潮に気に入るとまでは行かなかったものの、これは、なかなかのものですね。特に現時点での最新アルバム『Channel U』は、「花になって」が収録されているからというだけでなく、普通に秀逸な1枚です。個人的には楽曲のバラエティー性がもっとある方が好きですけれども、これはこれでバンドとしての個性がまとまっていると解釈できますし、業界関係者にも評価が高いというのも頷ける内容でした。












| 2025年6月21日(土) You Know? |
違和感のある言い回しとしてしばしば挙げられてきた、飲食店でのオーダー確認時などの「~でよろしかったでしょうか」という言い方とか、自己紹介的なシーンで言われる「私って〇〇じゃないですか」という発言ですが、気が付けばいつの間にやらすっかりと巷間に定着していますよね。そうなってしまうと、物心ついたころからこれを「定型文」として接している、いってみれば「ネイティブ」な人が増えて、むしろここに違和感を覚えるのは年寄りの証明、「老害」とまでは言わないまでも、時代の変化には取り残されているオールドタイプ扱いされても、ある意味、致し方ないように思います。ただまぁ、私はその「オールドタイプ」側に属している人間ですので、さも相手が既に承認していたり認知していたりするのが前提のように言われてしまうと、「俺はそんなことは承知していないぞ」と、ついつい胸の中で毒づいてしまったりするのです。
オーダーの方はマニュアルがそうなっている可能性もあるからともかくとして、自己紹介の方は……うがった見方をしてしまうならば、そういう言い方をしている人というのは自分が思っていることは相手も肯定してくれるのが当然と思っていると言えなくもないわけですけれども、さすがに皆が皆そこまで傲慢・傲岸不遜であるということはないでしょう。とはいえ、それ以外にも、承認欲求に飢えていることの表れの1つなのか、それとも人の目を通して自分を規定しようとしている自信の無さのあらわれなのか、それとも最終判断を相手にゆだねて自己の責任を回避する他責志向なのか、そういう感じに、悪く考えようと思えばいくらでも悪意のある解釈ができるのも、また事実。そういう解釈の成り立ち得る話だからこそ、上記のように、私が天邪鬼ぎみに毒づくということも、生じたりしてしまうわけですね。
まぁ、実際のところはどうかというと、何らかの1つの理由で説明ができるような単純明快なことではなくて、様々な要素が複合的に関係して、それでそういう言い方が一般に定着してきているという感じなのかもしれません。つまり、色々という人もいるけれど、単に言葉が時代につれて変化してそれまでとは違う言い回しが定着しただけというのが本当のところだったりするのでしょう。捻りも何もないつまらない話ですけれども、案外そういうのが真実だったりしますよね。ただ、それはそれとして、そういう言い方をされた時に私が違和感を感じるというのは、それも一方の真実です。そういうところがオールドタイプのオールドタイプたる所以でしょうけど。
シリーズ13冊目、知念実希人の『天久鷹央の推理ファイル 生命の略奪者【完全版】』(実業之日本社 実業之日本社文庫)を読了。今回は臓器移植とミイラと死者復活ということで、「強奪された『心臓』誰が、何の目的で? 臓器移植。不幸にも命を失った人間の善意が別の患者を助ける、命のリレー。そんな死者の崇高な遺志を踏みにじる。『連続臓器強奪事件』が発生する。心臓を運ぶコーディネーターへの襲撃を皮切りに、次々と奪われる命の灯。その被害は天医会総合病院にも及び……。声明を略奪する犯人の正体は? 現役医師が描く本格医療ミステリー!書き下ろし掌編『生命の摂食者』収録。」という粗筋になっています。ワンパターンと言えばこれ以上ないくらいのワンパターンさが表に噴出してきているシリーズですが、それが酷く目立つわけではありません。今の私のように第1巻から順番に一気に読み進めているようなことをやっていると気になるけれど、既存のエピソードは全部読了していて、新刊が出たら読むというスタンスになっていると気にならないという可能性もありますしね。良く言うと、シリーズとしての円熟味を増した読み心地があり、キャラが生き生きと魅力的で面白く、また、自分もドナー登録とか脳死での臓器提供意思表示とか、そういうことをしないと駄目かな、というような気分にもなる佳作、ということになるでしょうか。
「東京創元社×カクヨム 学園ミステリ大賞」の優秀賞受賞作だという、下村智恵理の『天網恢恢アルケミー 前崎中央高校科学部の事件ファイル』(東京創元社 創元推理文庫)を読了。「高校2年の春、群馬の進学校に転入した安井良はある日の放課後、着崩した制服に白衣姿の金髪ギャルと遭遇する。彼女は何と化学室で牛タンを焼いていた!?この強烈な出会いから良は、、彼女の属する科学部の面々と共に、図書室の呪いの忌書、黄泉からの手紙、トンネルの悪霊と3つの事件に巻き込まれていく――。『東京創元社×カクヨム 学園ミステリ大賞』優秀賞の傑作ミステリ」というのが、裏表紙の粗筋です。賞の名称や粗筋にも書いてあるように、要するに創元推理文庫が積極的に出版している「学園ミステリ―」の1つになるわけですが、現実の世知辛さというか、シビアなところを飾らずに書いているところに好印象を覚えます。地方都市あるある的な人間関係、出身中学校で地縁を確認して「利害関係とか敵対関係とか、共通の知人とかがいるかを探るための、コミュニケーションの初手にうってつけの質問」として「オメーどこ中だよ」という問いかけが効果を発しているという記述とか、個人的なツボにはまるところも多々あって、面白く読ませてもらいました。都市伝説や七不思議的な謎を化学で解析して解明する本作、謎の解明に至るまでの化学的検証の描写がしっかりとしているのと、あちこちに何気に社会な描写があること、科学部関係や主人公廻りのキャラが良い感じなこと等、わりと魅力もありましたから、続編が出たら買ってみようかと思います。なお、読み始めていきなり最初のエピソードが「Project#33」となっているので、これはかなり長大なシリーズの一部分なのかと思わされたりもしたのですが、これは「科学部としての33番目の案件」という意味合いでそうなっているという位置づけだから、これより前に32本のエピソードがある、というわけではなさそうです。「33」という数字に作者の何らかのこだわりがあるかどうかは、分かりませんが。舞台となった「前崎中央高校」のモデルは……群馬県立前橋高校かな?
半年ぐらい積読で寝かせてしまっていたのですが、第2部の2冊目として、昨年11月末に発売となった、紺野天龍の『堕天の誘惑 幽世の薬剤師』(新潮社 新潮文庫nex)を読了。「嘘だ――。その光景を前にして、薬師・空洞淵霧瑚は目を疑った。想い人であり、破鬼の巫女でもある御巫綺翠が、見知らぬ男と二人きりで買い物をしている。しかも、空洞淵にも見せない笑顔を浮かべて。共に世界を救い、愛を誓った綺翠が、まさか……。だが、謎の男との出会いは、新たな事件の始まりでもあった。曰く『天使』が現れた、と。現役薬剤師が描く異界×和風ファンタジー!」というのが粗筋で、新シリーズの序盤として、まずは通常イベントがあって、その解決、という流れの物語となっています。今回はわりと謎解きが予想しやすかった感がありましたが、内容的には安定して面白かったと言っていいでしょう。色々といつも通りだったので、どうせならばもうちょっと捻りがあっても良かったのでは、という気にはなりましたが、悪くないです。積読にしていた間に次の巻も出てしまっているので、そちらもなるべく早く読みたいと思います。
藤津亮太の『富野由悠季論』(筑摩書房)は、『機動戦士ガンダム』や『伝説巨神イデオン』といった作品で知られるアニメ監督、富野由悠季の「アニメ監督」としての部分、その「演出の技」と「戯作者」としての意識というところにフォーカスして、彼の手掛けた作品を年代順に振り返りつつ分析し、評論し、本文だけで460ページ程の論文にまとめあげた、著者渾身の1冊。「『オタク』な私の製造工程」と題した一連の文章の最初の方にも書いたように、私がこの「雑記」やブログの「別館」でこんな風に、読んだ本や聴いた音楽や観たアニメについてアレコレと書くような人間になったこと、そもそもアニメが好きになったこと、SFやファンタジー等の創作物を好むことの「根っこ」の部分には、富野監督と彼の監督作品の存在が拭い難い大きな影響を及ぼしているわけで、そんな私が、これを読まないわけがないのです。富野ファンであれば必読と言っていいでしょう。こういう書籍が普通に一般書籍として出るようになっていることに感謝しつつ、著者には、これを第1段として、さらに深く「富野由悠季」を掘り下げた本を出してもらいたいとも思うのでした。
新たなる“少女”が登場する、大武政夫の『J⇔M』第5巻(KADOKAWA HARTA COMIX)。前巻も「こうきたか」感がありましたけれども、そこから更に、こういう流れですか。大武政夫、最高潮に乗ってきていますね。『ヒナまつり』でいうと、アンズが出てきた時の感覚に近いでしょうか。同作を知らない人にはパッとイメージしにくいかもしれませんけれども。作風に幅があまりないのが個性でもあり欠点でもある大武政夫ですが、現状はどれも面白いからとりあえず大きな問題にはなっているとは思っていません。
こちらもノリノリになってきた、市東亮子の『やじきた異世界道中記』第3巻(秋田書店 PRINCESS COMICS)。一発ネタ的に始まった感もあった作品でしたけれども、内容も面白いし、先がどうなっていくのか大いに気になる良作になってきたと思います。しかし、これ、この感じだと全10巻以上にはなりそうですね。それが嫌かというとそんなことはなくて、むしろ大歓迎なのですが。あとは、編集部が好きなだけ連載を続けさせてくれるか否か、か。
発売を見落としていた、田中靖規の『ゴーストフィクサーズ』第4巻(集英社 ジャンプコミックス)を購入。霊能伝奇バトルものとして王道を進んでいる感のある本作、この第4巻で前作『サマータイム・レンダ』(同社 同コミックス 全13巻+外伝1巻)と物語がリンクしてきて、「おお、そう来たか」とニヤニヤとさせていただきました。そして作品の軸となるストーリーも明らかになってきて、本作がどういう作品で、何を描こうとしてきたのかが段々と分かってきた感じです。面白くなってきました。
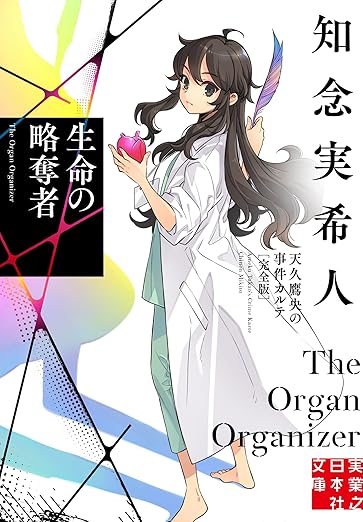
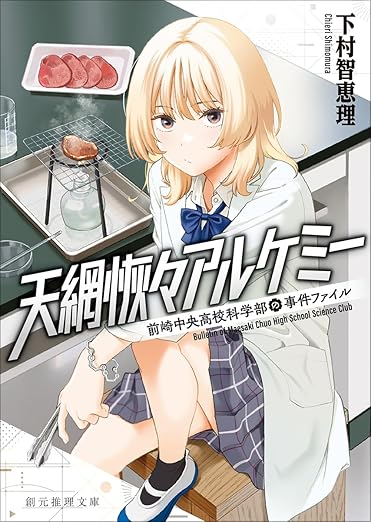

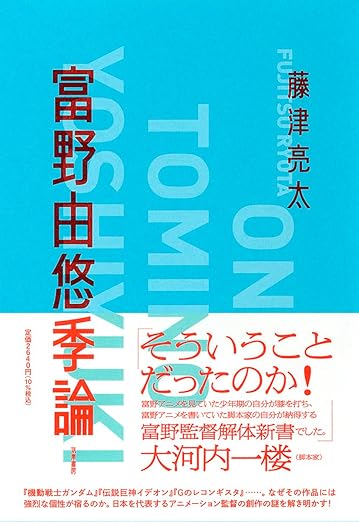


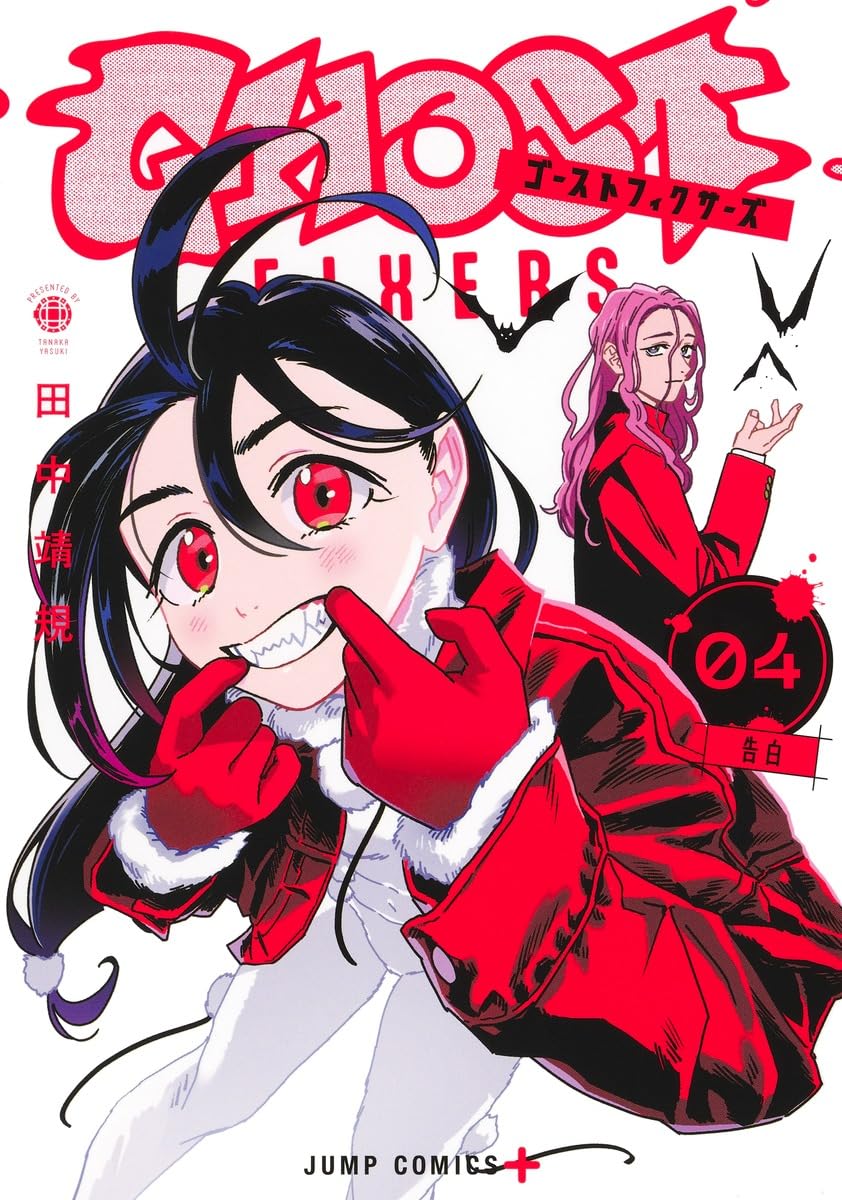
| 2025年6月14日(土) 自負と、ときどき無力感 |
ちょっとお見苦しいかもしれませんが、今回の「雑記」では、自戒も込めて愚痴を零させていただこうかと思います。ご存じの方もいらっしゃるでしょうが、私は某国家試験を取得し、その分野のプロ・専門家として法的知識、専門知識を顧客に提供し、書類等を作成し、顧問料をいただいております。当然ですが、そういう仕事をしていると、顧客から、専門分野及びそこに少しでも関わりのあるようなところについて様々な質問を受けることになります。専門性故に一般の方は判断しかねるものの私の業務的にはメジャーな話だから即答できるようなものもあれば、朧げに記憶はしているけれどもきちんとした回答をするには条文その他の再確認をしなければならないものもあり、更には専門外だから一から色々と調べまくらなければ答えられないようなもの(この場合は、あくまで専門外だから「これが正解だ」「絶対に正しい」とは言い切れないこと、確実性を求めるのであればその分野の専門家にも相談・確認をしてほしいこと、を念押しします)まであります。このうち、特に後者2つはどうしても調べ物が伴う以上は結構な手間がかかって大変なのですが、しかしそれは私の職業に課せられている社会的な義務でもありますから、夜遅くまで作業して寝不足になりながらも、顧客の期待に応え社会貢献をすべく、前向きに頑張ってやってきています。
ところで、私が扱っているもの、私の資格の専門性は、法律に係るものとなっています(なお、弁護士ではありません)。ですから、顧客の要望や意図がどうであれ、最終的には「法律の規定・解釈はこうなっている」ということに立脚した回答をすることになります。グレーゾーンについても、裁判事例を調べて、過去の判例を分析したうえで、リスクの高い、あやうい手段は選ばないように進言・指導・助言をすることになります。こちらもしっかりとした詳細な確認作業をして理論的な回答を提示するのですが、その内容が顧客の意にそぐわないものであれば、そこを不満に思うのは、人間である以上は仕方がありません。それで煙たがられたり嫌われたりしたくないからといって、回答を捻じ曲げて「黒」を「白」と説明することは、その場は良くても結局は相手に不利益を与えることになるので、絶対にやってはいけないことです。長い目で見れば、その方が顧客にとってプラスになると信じてやっていますが……。
時に、私の説明に不服を覚えた顧客から、「あの後にネットで調べたらこう書いてあった」「だからあなたの説明はおかしい」といったようなことを言われることがあります。確かに今の時代、ネットは非常に身近に存在している検索ツールであり、ちょっとした調べ物もすぐにチェックできるような便利さがあるから、自分の分からないことや不安なことをネットで調べてみるというのは、かなり有効であり有意義であることを私も否定はしません。私自身も、そういうネットのメリットを最大限活用して仕事をしていますしね。ただ、あちこちで多くの人が指摘しているように、ネットにある情報は「玉石混淆」です。内容的に完全に法令に遵守した大いに参考にできるものもあれば、書き手の欲望や思い込みばかりが押し出されていて適法性や合理性を無視した感情的なものまで、本当に色々な情報が、ネットには溢れています。『攻殻機動隊』の草薙素子少佐ではありませんけれども、良くも悪くも「ネットの海は広大」なのです。で、怪しげな情報を基に私に反論や異論を言ってこられても、こちらもプロとしてしっかりと調べたうえで説明を申し上げている以上は、私としてはそれを否定することしかできないわけで、お互い不快な気持ちになって疲れ果てるだけで実りの無い時間にしかなりません。
顧客が独自に調べること、それ自体はむしろ歓迎すべきことであると私は思っています。ただ、その場合は同時に、その調べた先・参照先は、きちんと判決や法律・通達等を根拠に挙げて検証しているものなのかどうか、変な政治的・思想的なデバイスをかけずに対象となる事象を分析しているもなのかどうかは、大いに気にしていただきたいとも思っているところだったりするのです。自らの主義主張、イデオロギーにとって都合のいい解釈を無理やり導き出しているケース、そもそも何の検証もしていない希望的・楽観的見解の陳列を自己の判断の根拠にするのは非常にまずいです。これは少々偏見が入っているかもしれませんが、尖った内容の政治的な思想が背景にあることがうかがえるようなものには、特に、絶対に参考にしてはいけない誤った見解が多いという印象があります。自分の得たい情報に飛びつきがちなのは人間の性かもしれませんが……。検索で得られる情報の内容に肯定的か否定的か、どちらのスタンスを取るのも自由ですし、それぞれに意義があるとは思いますけれども、「現行制度はこうなっている」という正確な認識をスタート地点にしないと、道を間違えて迷うだけですし、有意義な議論は導き出せないだけでなく、それを安易に信用してしまうと大怪我をすることにもなりかねない非常に危険な行為だという認識は、常に根柢に抱いていなければならないと思います。
なお、自らの恥をさらすと、実はこれは顧客だけの問題ではなく、私の仕事を手伝ってもらっている職員にもそういうことをやらかす人間がいるのが、大いなる困りどころだったりしています。過去、職員時代には私自身も経験があるので、それで強く叱責するようなことは、当然、やらないのですが、専門性の高い職業に就いていて、その専門性に係る質問を受けた時などは、もっと慎重に、法的・制度的根拠を確認してから回答する習慣を身に着けてスキルアップをしていって欲しいと、そう願っています。
ネット炎上、本人特定、一方的な正義感による決めつけ、といったようなものが扱われている、浅倉秋成の『俺ではない炎上』(双葉書房 双葉文庫)を読了。「外回り中の営業部長・山縣泰介が帰社すると、社内の様子が変だった。どうやら泰介が『女子大生殺害犯』であるとされて、すでに実名、写真付きでネットに素性が晒され、炎上しているらしい。まったくの濡れ衣だが、Twitter で犯行を自慢するアカウントは実に巧妙で、見れば見るほど泰介のものとしか思えず、誰一人として無実を信じてくれない。会社も、友人も、家族でさえも……。ほんの数時間にして日本中の人間が敵になり、誰も彼もに追いかけられる中、泰介は必死の逃亡を続ける。」というのが裏表紙の粗筋です。ここまでのものでは無いにしても、類似の、というか、根っこを同じくするような問題は現実世界でわりと頻度も高く起きるようになってしまっているのではないか、ということは、私程度のネット利用者であっても自分が目にしてきていることから思っていることなので、今の時代に書かれるべくして書かれたものだなと思って、実は文庫化を心待ちにしていた作品だったりします。そのくせ、文庫が出た昨年6月から実際に読んでこの「雑記」で紹介するまでに9ヶ月くらい経ってしまっているのは……まぁ、いつものことなのでスルーしていただけるとありがたいです。
で、『俺ではない炎上』なのですが、シンプルに言ってしまえば「SNSのなりすましで殺人事件の犯人であると疑われ、追い込まれた会社員が、無実であることを証明する物語」ということになります。これだけでもきちんと描けばすごく面白くなりそうな題材ですが、そこは「伏線の狙撃手」とも呼ばれる朝倉秋成なので、この主軸にさらに一捻り、二捻りを加えた物語を作り出しています。そこから浮かび上がってくるのは、単にネットリテラシーを持とうとか、承認欲求等に背中を押されて刺激的で曖昧な情報を拡散することの危険性とか、独善的だったり思い込みが強かったりする正義感の危険性とか、そういうことだけではなく、人は多面性を持っていることの再確認とか、例え気心の知れている黙っていても心で通じ合っていると思っているような近しい関係性であってもしっかりと言葉と態度でコミュニンケーションをとることの大事さとか、そういう昔からある、ある意味で古典的なテーマです。なお、この場合の「古典的」というのを否定的に捉えていただきたくはなくて、逆に、普遍的で古びないものだと私は思っていて、今この時代「ならでは」の題材にそういうものをきっちりと絡めてきて、定番の「家族の再生」ネタも扱ってくる、そして娯楽作品、サスペンス要素を忘れずに読者を楽しませてくれるところも、本当に上手い小説家だなと改めて思った次第です。
アニメ第2期制作も発表された、雨森たきび の『負けヒロインが多すぎる!』第8巻(小学館 ガガガ文庫)の破壊力が、凄かった……。「『いまだけは私を――私だけを推してくれませんか』 生徒会選挙の季節。会長に立候補した天愛星さんは、なんと推薦人に俺を指名した。ただでさえ文芸部部長という重責があるのに、俺にそんな余裕はない。やんわり断るのだけれど、天愛星さんはいつにもまして頑なで……。あの手この手で迫られ、なし崩しに俺は生徒会選挙に巻き込まれていく。そんなとき、対抗馬の推薦人に八奈見がなったと聞いて――『正々堂々とやろうよ、温水くん』あなたは押さずにいられるか? 遅咲きヒロイン、馬剃天愛星ここにあり!!」というのが今回の粗筋なのですけれども、もう、ここに書いてあることが全てです。この第8巻は、とにもかくにも天愛星の為に存在していると言ってもいいでしょう。そして、まさしく “遅れてきたヒロイン” 的な存在感を彼女が発する中で、温水の周囲の負けヒロイン達にも動きが。ラブコメとして展開的にグッと舵を切ってきた今巻を受けて、物語は次の第9巻以降に大きく動き出しそうです。
支倉凍砂の『新説 狼と香辛料 狼と羊皮紙』第12巻(KADOKAWA 電撃文庫)を読了。今回のサブタイトルは「羊たちの宴(上)」となっていて、粗筋は「コルを殉教者に仕立て上げようとした異端審問官ローシェと選帝侯たちの非道な計画は、空から駆け付けたディアナの協力により砕かれた。無傷の生還という偉業は、帝国内に薄明の枢機卿の名声をますます轟かせ、コルを一目見ようとウーバンは謁見を願う者たちで溢れかえることに。そして、多忙な兄を支えるミューリの下にも真面目で頑固なコルを説得してほしいと陳情が集まり……。そんな中、薄明の枢機卿の暗殺計画が再び持ち上がって!?上下巻でお送りする、堅狼の娘と若き羊皮紙が世界を変える運命の前夜祭!」というもの。いよいよ公会議の開催へ、ということで、今回はその直前の、改革派側の動きのまとめと、旧体制側が陰謀を巡らせ始めている気配をところを描いています。とはいえ、今回はタイトルにもあるようにあくまで前後編の前編なので、このエピソードがどういうことになるのかは、後編を読んでみなければ分からないのですけれども。このシリーズ、展開がかなりゆっくりしている感はあるものの、基本的にどの巻も面白いですし、後編も非常に楽しみです。
第1巻が出てから第2巻までとほぼ同様のスパンで出版された、仏ょも の『極東救世主伝説 3 少年、世界の敵と相対す。 ―軍学校襲撃編―』(KADOKAWA カドカワBOOKS)。「魔物の襲撃を受けた都市を救い、極東ロシアの英雄となった川上啓太。帰国した彼を待っていたのは、壊滅的な被害を受けた国防軍と、軍学校での学園祭だった。学園祭ではAクラス全員による魔装機体での模擬戦が行われることになるものの、啓太が搭乗するのは自身の愛機ではなく量産型の御影に。さらにある任務が与えられて――?クラスメイトたちが刃を交える中、ついに英雄は人類の宿敵と対峙する――!」というのが、今回の粗筋です。話の流れとしては定番なところをなぞっていっているという印象が今まで以上に強く、そろそろ何か本作「ならでは」なところがもう少し欲しいなと感じではありますが、押さえるべきところをしっかりと押さえているのは間違いなく、エンターテインメントなロボットものとして面白い作品となっています。だからこそ、読んでいるこちらとしても欲が出て、もう1つ、2つ、何かを求めてしまうわけですが。類似の先行作品に並び、超えるものになれるかどうか、そろそろその勝負所にきているのかもしれませんけれど、最悪それが叶わなかったとしても、現段階で十分面白いんだからそれでいいという考え方も、あるでしょう。いずれにしても、ここまで楽しめる作品なのだから、このまま第4巻以降も継続して発売してくれることを願っています。
STING の最新ライブ盤『3.0 LIVE』は、彼が新たに組んだトリオ編成のバンドで行ったライブの模様を収録したというもの。STING でトリオ編成ということになると、まず何をおいても THE POLICE が連想されるわけですが、STING の側も当然そういう反応は分かっていたのでしょう。また、トリオでやるからには、という自身の思いもあったのかもしれませんが、このライブでは、THE POLICE 時代の楽曲も結構やっているというのが、1つの特徴となっています。私が購入したのは全17曲2枚組のデラックスバージョンの方ですが、中には STING として初めてのライブ・バージョンとなるものも4曲あるのだとか。歌詞カードにMCの訳まで載っているのは少し珍しいかもしれませんが、その内容はともかくとして、それくらいのところまできっちりと記録としようというのが、この2枚組だということでいいんですよね、つまり。
デビュー当時のサウンドはもの凄く好きだったものの、最近はそうでもないかなという感もあるので購入も発売日からかなり遅れてしまった、椎名林檎のアルバム『放生会』。多分、彼女の求め目指す音楽性は、デビュー当時はあまり表現できていなくて、外部の助けを借りながら模索を続けていて、それが次第に自らとしてしっかりとアウトプットできるようになってきたのだろうなと思います。つまり、それが故に私個人の音楽的な好みとは段々と乖離してきてしまったということなのですが、まぁ、これは世の中に良くあることで、誰が悪いというようなことでもないから、仕方がない。実際、今の(「完成された」とまで言っていいかどうかは、現在について椎名林檎自身がどう思っているかによりますが)音楽性、今の楽曲はかなり広い層の支持を受けているわけですから、一般論としては、これで正解、間違いないということになると思います。私がひねくれ者なだけで。それでも、男性ボーカリストとの共演企画として当て書きで曲を作ったという前作『三毒史』を受けて、今度は女性ボーカリストとの共演企画として当て書きして製作されたアルバムというところに興味を抱いて結局、この『放生会』については購入を決めたわけです。で、実際に聴いてみると、うん、やっぱり結構良いんですよね、椎名林檎。好みのド真ん中からは外れてしまって、それが(勝手な言い分なのは承知していますが)私にとってかなり残念だったから、積極的に買おうという意思が薄れてしまっているだけで。
アニメ『進撃の巨人』で使われた「僕の戦争」の音源が欲しくなったので、神聖かまってちゃん の2つ目のベストアルバム『聖なる交差点』を購入。彼等の新譜をしばらく買っていなかったということもあって、ベスト盤ではありますが、未所有の楽曲が多かったのも、これを買おうと思った動機の大きな1つです。収録曲を聴いていて私は、彼等のサウンドにアングラ感は今でも強く漂っていますが、その濃度は昔よりは薄くなってきている、かもしれないなと感じました。とはいえ、思い返すとデビューの頃から彼等の曲にはポップさが存在していたので、これはまぁ、正当的な進化と言うこともできるのかもしれません。それに、ポップでキャッチーになってきたことが悪いわけではありませんし、実際、最近の曲もかなり良いものがありましたし。買い漏らしているアルバムも揃えなければならないかな、と思うくらいには。なお、もう1つのベストアルバム『ベストかまってちゃん』も大分前に購入しているのですが……「聴く」に掲載するのを忘れていました。こちらは「Os-宇宙人」の為に買っていたと言ってしまっても良くて(シングル盤はもともと所有しているのですが)、買ってそれで満足して、「ぱんたれい」への掲載をしないまま終わってしまっていました。
「望郷じょんがら」が聴きたくてたまらくなったので、細川たかし のベスト盤『2020イヨマンテの夜』を購入。ここに収録されているのはニューアレンジ版なのですけれども、もともとそちらの方の音源が欲しかったので、問題なしです。それに、どうせならば 細川たかし の歌う「イヨマンテの夜」も聴いてみたいというのもあったので、数あるベスト盤から、これを選びました。「イヨマンテの夜」といえば伊藤久男で、そちらのベスト盤は既に入手済みでもあるのですが、いかんせん、録音が古いのでどうしても音質はイマイチ。それでも曲の力強さと確かな歌唱力で圧巻の1曲なのですけれど、ではそれを民謡をベースにした超絶的な歌唱力を誇る 細川たかし が歌うとどうなるのか。これは、興味が出ますよね。細川たかし といえば私が重大で音楽番組を見ている時にヒットしていた「北酒場」や「矢切の渡し」等も良い曲で、当然それもこのベスト盤には入っています。1トラック目に「望郷じょんがら」で2トラック目に「2020イヨマンテの夜」と、初っ端から飛ばしまくっている構成で、その分、後半にかけて失速した感が出ないでもないのが惜しいところですが、なかなか良いベスト盤でした。









| 2025年6月7日(土) サイモン・イェーツ、ピーダスン、フォルトゥナート、デルトロ |
自転車ロードレース、2025年のグラン・ツール第1弾となるジロ・デ・イタリアが先週日曜日に全21ステージの日程を終えてローマにゴールいたしました。普段のレースの感想はブログの「別館」に譲ってこの「雑記」では書かないようにしていますが、毎年、グラン・ツールだけは別格扱いとして各賞の結果と簡単な感想を掲載することにしています。ジロは毎年5月の開催で山岳などでは雪が残っていたり、悪天候になると寒さが選手を襲ったりという過酷さを誇っていますが(というか、グラン・ツールはどれも過酷なレースですが)、今回のジロも、優勝候補が何人も雨でぬれた路面や無舗装のグラベル区間での落車等で途中でリタイアを余儀なくされたりするなど、いつも通りの厳しい展開となりました。
総合優勝は、最終日直前の第20ステージ山頂ゴールで、総合3位のポジションからのアタックを成功させ、そのまま1分半近いタイム差をひっくり返し、そのまま逆に大きなタイム差を付けるという大逆転劇を見せつけた、チーム ヴィスマ・リース ア バイク のサイモン・イェーツ。奇しくも、この日の勝負どころとなったフィネストレ峠は、2018年のジロ第19ステージで、それまでにステージ3勝を挙げて総合首位を走っていたのに、クリス・フルームとそれをアシストするイネオスの猛攻にやられて首位から陥落してしまった、サイモンにとっては因縁の場所。つまり7年振りのリベンジ、忘れ物の回収であり、ゴール後に感極まって涙を流す彼の姿は、とても感動的でした。サイモンはその2018年にブエルタ・ア・エスパーニャでの総合優勝を成し遂げているので、後は、ツール・ド・フランスを勝てばグラン・ツール全勝となるわけですけれども、ヴィスマには絶対的エースのヨナス・ヴィンゲゴーがいるので……移籍でもしないと挑戦はできないかも。サイモンがその道を選ぶかどうかは、分かりませんけれど。
ところで、この第20ステージでは、サイモンに取り残された当時総合1位のUAEチームエミレーツのイサーク・デルトロと、EFエデュケーション・イージーポストのリチャル・カラパスが互いの牽制から勝負を捨てた感じになってしまうなど、普通はそうはならないだろうという信じられない光景もありました。デルトロが終始、登りで爆発的なアタックをする能力を持つカラパスを意識していて、サイモンを追うことに協力的では無かったから、カラパスの側も自分だけが力を使ってサイモンを追いたくは無いし死なば諸共とばかりに牽制に入ったのかな、とは思います。それは理解できなくはないものの、ただ、その結果がサイモンによる総合首位奪還。デルトロもカラパスも勝負に真剣だったからとはいえ、モヤモヤするものを感じるのは否定できません。とはいえ、それもこれも、サイモンの思い切った攻めがあったればこそなので、勝者については率直に称えたいと思います。デルトロとカラパスには、何を考えていたのか、ちょっと問いただしたい気もしますが。
ポイント賞は、ステージで4勝を挙げるなど大活躍だった、リドル・トレックのマッズ・ピーダスン。これはもう、強かったとしか言えません。スプリントの絡まないところではチームメイトを懸命にアシストしていた点も尊敬できますし、ここまで「嫌いなわけではないけれども、そこまで好きなわけでもない」という扱いだったピーダスンの株が、私の中で一気に上昇した大会だったと言っていいかもしれません。
山岳賞は、XDS・アスタナ チーム のロレンツォ・フォルティナートが、総合勢が睨み合う中、山岳ステージで何度か逃げに乗って山頂のポイントを荒稼ぎし、2位以下に圧倒的な差を付けて獲得しています。アスタナはプロツアー残留争いで、今期はUCIポイントの獲得にかなり動き回っていましたが、このジロでも活躍して何と山岳賞では2位もアスタナの選手となっています。アスタナというチームについては、これまではあまり積極的に応援をして筺あなかったものの、昨年のツールでマーク・カヴェンディッシュにステージ通算35勝を飾らせるべくチーム全体が全力でサポートをして見せた辺りからちょっと印象も変わってきていたました。今大会のフォルティナートの走りが、それをさらに後押しした感があります。おそらくプロツアーへの残留には成功するでしょうから、来年はビッグレースでの勝利を積極的に狙うアスタナの姿も見たいものです。
新人賞は、展開もあって第9ステージでステージ2位に入り総合首位に立ってから、ずっとその座を維持し続けながらも、前述のように第20ステージであえなく栄誉を失うことになった イサーク・デルトロが、これだけは死守。デルトロはまだ21歳ですから、これも経験だということはできるでしょう。ただ、再びこのようなチャンスを手にする日が来るか分からないのが勝負の世界ですので、後々、あの時にカラパスと変に張り合わないでサイモンを追っていれば、と、生涯後悔し続けることにならなければいいのですけれど。とりあえず、カラパスとデルトロの間には、拭いきれない深い遺恨が残りましたね。
浅葉なつ の『どうかこの声が、あなたに届きますように』(文藝春秋 文春文庫)は、ラジオのパーソナリティーを主人公にした作品。「とある事情から地下アイドルを辞め、マスクを手放せなくなっていた奈々子は、ある日ラジオ局のディレクター黒木から、番食いアシスタントにスカウトされる。初日の生放送は後に『伝説の十秒回』と呼ばれる神回となるが――。絶望を抱える中学生、子どものいない夫婦、切実な日々を生きるリスナーに、奈々子の声は響くだろうか。」というのがその粗筋。元アイドルで今はスーパーのパン屋で働いている小松奈々子を軸に、様々な人々の人生が彼女がパーソナリティーをすることになったラジオを通じて救われていくというような筋立てはベタですが、それだけに丁寧に描けばそれだけで読者の心に浸みるような作品になりやすそうです。つまり、安易な感動ものにしようと思えば、ある程度の実力のある作者であればいくらでもやりようがある、ということも言えそうです。それで「こうすれば泣けるんでしょ?」というような作り手側の作為があまりにあけすけに見えてくるようだと興醒めも限りないのですが、その辺り、本作は奈々子自身の身の上も絡めて、人の心の救済とか、成長譚というようなところに上手く、作為的な嫌らしさ無しに落とし込めていると感じました。
これは、題材がラジオ、というところも良かったのかもしれません。私はそんなに熱心なリスナーではなかったし、ハガキの投稿もほぼやっていないのですが、それでも受験生などの深夜の友としてラジオが一般的であった時代を生きてきたので、こういうストーリーにも一定の共感を覚えるからか、なかなか面白く読ませてもらいました。本作に限らず、ここ数年、ラジオを題材にした小説を何本か読んできている気がしますが、それはおそらく、かつて十代の頃等にラジオ放送に親しんできた書き手がそういう作品を発表するようになってきているのかなと、ふと思いました。今この文章を書いていてそんなことが頭をよぎった、という程度のことなので、本当にそうなのかどうかは分かりませんけれども。
お、これも続きが出たか、と思ったのが、岡崎マサムネの『異世界リーマン、勇者パーティーに入る』第2巻(小学館 ガガガ文庫)。「無事魔族を追い払うことに成功した、アレクたち勇者一行。けれど、魔王は日に日に力を増大させているようだ。王様からの情報で、魔王討伐のためには伝説の装備が必要だと分かったのだが、なぜかその伝説の装備がレースの優勝賞品に!? 賞品を手に入れるため、営業車のハンドルを握るのはゴールド免許持ちのハヤシ。はたしてハヤシは、強者達を抜き去り優勝することが出来るのか!? さらには、魔王四天王や新たな仲間、ハヤシを気に掛ける女性も現れて……。勇者一行+営業ハヤシの、異世界コメディー第二弾!」というという粗筋から一目瞭然、異世界転生モノの若干の亜流作品ということになります。題材とか展開に新鮮味はなく、むしろどこかで何度も見ているぞという食傷感すらあるようなところすらありますが、勇者一行とハヤシとの関係性が何となく良い感じで、結構好きなんですよね、コレ。新キャラ等も登場していますし、このまま第3巻、第4巻として続いていって欲しいところですが、それにはもうちょっと「本作ならでは」な新鮮味が欲しいかも。つまらなくは、無いのですけれども。
バレンタインとその後のホワイトデー、そして三年生への進級直前のクラスの様子を描く、佐伯さん の『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』第11巻(SBクリエイティブ GA文庫)。「『周くんの格好いい所ずっと見たくて我慢してましたもん』 告白された周への不安を拭い、バレンタインデーの夜は甘い時間を過ごした周と真昼。ホワイトデーのお返しでついにアルバイト先へ真昼を招待した周は、嬉しそうな恋人の姿を見て真昼と出会い世界が変わったことを実感する。二年生も終わりが近付くなか、穏やかで愛おしい日常を送る二人は、重ねた日々を思いながらあたたかな陽だまりに包まれるのだった……。可愛らしい隣人との、甘く焦れったい恋の物語。」というのが粗筋で、まぁ、要するに、いつもの感じでいつもの風景が繰り広げられる、安定していて安心できる1冊です。それは別の表現を使えばマンネリとも言いますが、そこが本作の楽しみどころなわけですから、特に問題はありません。最後にちょっと不穏な要素が出てきましたが、いつもまったりしているだけでも仕方がないから、たまにはアクセントも必要だよねという程度のものだろうと勝手に予想しています。その答え合わせができる次の第12巻を、楽しみに待たせていただきましょう。
シリーズ12冊目は、オンラインサロンを舞台に、不老不死を巡る謎を解く内容の、知念実希人の『天久鷹央の推理ファイル 久遠の檻【完全版】』(実業之日本社 実業之日本社文庫)を読了。「美しく可憐な少女は、『不老不死』のアイドル? 楯石希津奈。十五年以上前にアイドルとして活動していた少女が、当時とまったく同じ外見で現れた。患者の姿に驚いた精神科部長の墨田淳子は、統括診断部の天久鷹央に診察を依頼する。だが、その矢先、父親によって希津奈に連れ去られてしまい……。ミイラ化した遺体。自殺からの復活。不当不死は実在するのか?現役医師が描く医療ミステリー!書き下ろし掌編『天国への道』収録。」というのが裏表紙の粗筋で、作中で触れられていますが、オンラインサロンも宗教のようなものだと考えれば(そして本作に登場するオンラインサロンは限りなく宗教に近いものとなっています)、新興宗教がらみの事件はこれで3回目になるでしょうか。主人公たちとの対立構造を作りやすく、また、普通であればさすがに理不尽に過ぎたり道理が通らないようなことも、信仰心や宗教的熱狂を理由にすれば「ああ、そういうことってあるかもなぁ」と納得できてしまうという利点はありますが、ちょっと、同じパターンを使いすぎなのではないか、という気もしないでもありません。エピソードとしては面白かったので、そんなに大きな不満とか懸念とかいうわけではないのですけれども。
城平京原作/片瀬茶柴コミカライズの『虚構推理』第23巻(講談社 講談社コミックス 月刊少年マガジン)は、エピソード「まるで昔話のような」の完結までとなる第3話~第7話と、次のエピソードに入る前の単発エピソード「木製だから大丈夫」が収録されています。かなりシビアでハードめな内容となった「まるで昔話のような」はシリーズの中でもかなりお気に入りのエピソードとなりました。異類婚姻譚が、そんなにスッキリとしたものになるわけがない、というのは、それはそうだよな、と。そして「木製だから大丈夫」には、アレの最新バージョンが登場します。3回で終わるんじゃなかったのかと突っ込みを入れつつ、かなり笑わせてもらいました。六花さんのポンコツ化に歯止めがかかりませんが、それがむしろ良いですよね。
古書店を舞台にしたコミックの2冊目、児島青の『本なら売るほど』第2巻(KADOKAWA HARTA COMIX)を読了。このジャンルはどんなエピソードを描くのかに定番の流れがある……というか、わりとワンパターンになりがちですし、そこから本作も抜け出せているわけでは無いのですけれども、私が本をネタにした作品に弱いというところを差し引いても、本作は結構面白くできているのではないかと思っています。特定の作品を題材にして、その魅力を語る方向性ではなく、古書店に関わることになる人、やってくる客について描くヒューマンドラマ的な方向性の作品で、ブレイクするいはもう1つ2つ何か必要かなとも思うものの、個人的には、何だか結構好きなのです。
白浜鴎の『とんがり帽子のアトリエ』第14巻(講談社 モーニンングKC)も読了。この巻でも、銀夜祭編は終わっていません。作者にとってはテーマ的に重要なところを描こうとしているのだろうなというのは察せられますし、画は相変わらず良いのですけれども、ストーリーが、ちょっとなぁ……という感じになりつつあるのが、少々残念です。いい加減、この銀夜祭に関するエピソードは終わらせて、次に移行した方がいいのではないかと思うのですけれど。しかし実際には、まだまだ数巻は銀夜祭が続きそうで、となると、このままコミックスを買い続けるかどうかが迷われる感じになってきてしまうんですよね。
山口つばさ の『ブルーピリオド』第17巻(講談社 アフタヌーンKC)を読了。プロの作家を目指すことを決めた八虎、高校時代の美術部仲間との再会、そして憧れの存在であった森先輩との会話という感じで、内容的に非常に濃い1冊だと言えるでしょう。現段階では自身の「作家性」を模索して足掻いている八虎ですけれども、美術部仲間+森先輩とやることになったグループ展で一皮剥けて成長をしたりするのでしょうか。一時の停滞から再び「面白さ」を取り戻している本作、今回も楽しませていただきました。








| 2025年5月31日(土) 都内の初詣ランキング9位、でしたっけ? |
今回は5月の最終更新日になりますので、恒例に則り、Top写真 を更新しました。この「ぱんたれい」では毎年1月については Top写真 に寺社仏閣で撮影したものを使う、というのを(開設当時からでこそないのですが)マイルールとしていて、例えば今年の1月もそれを踏襲して久能山東照宮の写真を使ったりしています。一方で私は寺社仏閣巡りも好きなので、どこかに出かけたり旅行に行ったりした際に、ちょっと良さげな神社や寺があれば立ち寄って写真を撮影したりしているものですから、実は結構前から「1月用」にストックしている画像が毎年どんどん溜まっていって、消費が追い付かない状態にもなっているのが現状です。正直、このままだと私が「ぱんたれい」を管理し続けている間、つまり私が健康で生きている間(もしくは、こういうサイトを運営することに飽きたり、限界を感じたりするまでの間)には、到底その全てを Top写真 に使うことはできないことは、確定事実であると断定できます。
もちろん、それはそれで、別に構わないのではないかということも考えとしては普通に成り立つのですが、しかし、折角の写真だから、まぁ、可能であれば「ぱんたれい」の Topページを飾る画像として使いたいという気持ちも、また確かに存在しているわけです。他人からしたら、どれも大同小異で写真として特に優れているということもない、どうでもいいものなのかもしれませんけれども、撮影をした本人としては、思い出補正も込みで、やはりそれなりに思い入れもありますし。で、そうであるのならば、どうすべきか。これはもう、明確ですよね。1月以外にも、寺社仏閣の写真を使ってしまえばいいのです。そのうえで、マイルールはマイルールとして維持していきたい気持ちもありますから、来年以降も1月には寺社仏閣の写真を使う。これで、問題は解消されます。
今回は、そんなわけで、6月ではありますけれども寺社仏閣の写真を使ってみました。さすがに毎月寺社仏閣なのはどうかと思うので、来月は違うモノを使う予定ですが、ひとまず試験的に。ここに私が何を使おうとも誰も気になどしないのは分かっていますが、一応、自分自身にとっての座りの良さ・悪さというのは、あるので。私の中でしっくりくるようであれば、今後は、こうやって半年に1回くらいの感じで寺社仏閣で撮った写真を使うことにするかもしれません。マイルールといえるような形にはしないで、気が向いたら選ぶという感じになるでしょうが。
ちょっと期待していたアニメ化が、謎に第1巻を飛ばして第2巻から物語を始めていたり、細部の描写に問題があったりで、せっかく面白い原作を生かし切れていない感があって何だかなぁと思っている、菊石まれほ の『ユア・フォルマⅦ 電索官エチカと枢軸の軋轢』(KADOKAWA 電撃文庫)。前巻から刊行スパンが開いたのは、おそらくアニメ化に際してのアレコレがあったが為だろうと推測されるわけですが、ならばせめてアニメはしっかり作ってほしかったなぁ。作画の微妙さは、TVシリーズですし、この際よしとしておいても。ともあれ、そんな中で発売された久し振りの新刊の粗筋は、「『エチカ。あなたが私に抱いているのは、特別な「愛情」ですか?』 RFモデルのシステムコードが全世界に公開され、ハロルドの廃棄処分が決定。追い打ちを掛けるように、エチカまでが謂れのない職権濫用罪で逮捕される。全てを覆す一手など見つからないと希望を失いかけていた最中、エチカはシュロッサー局長の隠蔽行為をはじめとする『同盟』の綻びに気がつき――。 『同盟』の軋轢、レクシー博士の裏切り、エチカの父、チカサトの存在。欠けていたピースが一つの答えへと収束する中で、最後に目に映る『機憶』とは――。」というもの。正直、ちょっと都合よく話が進み過ぎているのではないかという、ご都合主義的な匂いが無いではないのですけれども、ここまで続いてきたエチカとハロルドの物語がいよいよクライマックスに向けて大いに盛り上がっているのは、素直に面白く読ませていただきました。これは、残り1冊ないし2冊で完結、という感じなのでしょうか。もうちょっと続いてくれても、という気もしますが、でも、実際はこれくらいが程よいボリュームかもしれません。
紺野天龍の『魔法使いが多すぎる 名探偵倶楽部の童心』(講談社 講談社タイガ)は、以前に紹介した『神薙虚無最後の事件』(講談社)のシリーズ化が決定し『神薙虚無最後の事件 名探偵倶楽部の初陣』(同社 同文庫)として文庫化されたのに続いて刊行されたシリーズ第2作。この作品の続編と言われても、どういう感じにしてくるのかなと思った本作の公式の粗筋は、次のようなものでした。「人を不幸にしない名探偵を目指す大学生・志希が出会ったのは、自らを魔法使いと信じる女性だった。依頼された事件は、師匠の死。剣が宙を舞い首が落ちる事件で、獄炎使い(フレイム・マスター)も人形師も次々に犯行を自白するという異常事態を論理で解決せよ!『探偵たるもの、依頼人を信じ抜くのです!』魔法を信じる心に〈名探偵倶楽部〉の論理は届くのか。青春の日々が蘇る、やさしいミステリ。」……なる程、まぁ普通に考えて、「神薙~」で活躍した探偵と助手が新たな事件に取り組むという、こういう形にするしかないわけですけれども、「神薙~」の事件が印象深いものであるが故に、それを上回るインパクトが出せなければ、肩透かしのシリーズ化になってしまいます。その点で本作がどうだったのか。魔術師の、まるで某危機一髪のような形での死、そして自分こそが犯人であると次々と名乗り出る姉弟子達、という流れは、確かになかなか面白かったです。第1作を上回れたかというと微妙なところもありますが、今後のシリーズ継続に繋げるという意味では良い感じだったのではないでしょうか。毎回こういうふうに過去に起こった事件のちょっと特殊なシチュエーションを設定し、ミステリーの傑作にオマージュを捧げるような感じで、多重解決的な構成にしていく、ということになりそう。マニアには本格ミステリーとしては最終解決への納得度が足りないというような批判を受けもした前作ですが……。今作も、最終謎ときには「ふーん、そうなんだ」というのはあれども「えっ、そうなんだ!」というものは感じなかったので(熱心なミステリー者では無い私には何となくとしか言えないのですが)そういう批判が同様に当てはまりそうな気もするものの、娯楽作としての面白さを重視しつつミステリーを読んでいる身には、結構楽しく読ませてもらいました。
ちょっとエッチなライトコメディー作品で、何となくシリーズの1冊目と2冊目はこの「雑記」では紹介してこなかった、西条陽の『少女事案3 バクハツして時を駆ける夏目娘と、小五の娘を持つ高校生の夏目幸路』(小学館 ガガガ文庫)を読了。著者名は西条 陽(さいじょう よう)ではなく、西 条陽(にし じょうよう)と読むそうですが、そんな作品の裏表紙にある粗筋は、「クリスマス。『ぼかふ~!!』なんて悲鳴とともに夏目幸路の前に現れた小学五年生の名は、夏目ミント。夏目……夏目ぇ~!? なんでもミントは未来から(バクハツでタイムスリップする)能力でやってきたのだという。父である俺が死んでしまった未来から、俺と日本を救うために。今回の相手は『運命』そのもの。月子や白瀬さん、雪見や風町の力を得てもまだ足りない。運命を切り開く力は――『カワイイ』!? 時をかけ続ける『俺の娘』と高校生なのに小五の父・夏目、そして母親候補なヒロインたちが立ち向かう、ファミリー×ラブ×サスペンス!」というもの。これを見て、頭の軽そうな作品だな、と思われたかもしれません。それはあながち間違った直観ではないのですけれども、この3作目に関しては、時間モノのラノベとしてかなり好みな感じに仕上がっていたので、ここに紹介をしておきます。未来から娘が現れ訪れる危機を回避する為の歴史改変を試みる、というのは、そんなに珍しくない設定ですし、話の展開もこの手のものとしては非常にベタで目新しさは無いのですが、定番な流れを定番らしくしっかりと描いていて、面白かったです。第1巻や第2巻もそういうところがありましたが、この第3巻は、ライトSFとしてもなかなか秀逸な出来。しかし、ラストであんなことをしておいて、これでシリーズ第4弾も出るとなったら、どうするんだろう?
TVアニメが絶賛放送中の、宮下裕樹『宇宙人ムームー』第8巻(少年画報社 YKコミックス)。今回もいつも通りの家電薀蓄ライトコメディーで、安心して楽しく読ませていただきました。後半はサークル夏合宿で、桜子の故郷である北陸は金沢に行くことに。まぁ、場所が変わったとしても、彼らがやることは基本的に変わりが無いのですけれど……。このままどこまで連載が続くかは分かりませんが、このテイストを維持してくれるのであれば、最後までお付き合いさせていただく所存です。
オランダのシンフォニックメタルバンド、EPICA の新譜『ASPIRAL』を購入。今回も最高に盛り上がる良いアルバムだったのですが、彼等の音楽に私が親和性を感じるのは、アニソンでこういうサウンドを聴きまくってきているからというのも、あるかもしれませんね。というか、あるいはもしかして、アニソンとヨーロッパのシンフォニックメタル勢とは、相互に影響を及ぼしているかもしれませんし。まぁ、そんなわけで、「メタル」「ヨーロッパの(それも、オランダの)バンド」ということだけで EPICA を敬遠している人がいらっしゃるとしたら、それは非常にもったいないですよ、ということを、私としては声を大にして言いたいところです。普通に、めちゃくちゃ格好良いですから。特に、アニメファンにも是非、この辺りの音楽には触れてみてほしいなぁと、結構強めに思っていたりします。全11曲、61分と、収録時間がわりと長めの1枚なのですけれど、その長さを感じさせない、名盤です。
アニソンということだと、何やかんやでアニメ系のタイアップも多い、TK from 凛として時雨 の新譜『Whose Blue』も購入。相変わらずキレッキレのアレンジとボーカルスタイルで、かっ飛びまくっている1枚です。これに比べると、上記の EPICA はかなり「普通」のサウンドに感じられてしまいますね……。TK の脳内がどうなっているのかは、私にとって 凛として時雨 の初体験だった「Telecatic fake show」を知って以来、全く理解できないままですが、しかし文句なしに格好良いことは間違いありません。少しばかりワンパターンなところがあるのは否めないところですが、これだけのものを作ってくれているのであれば、問題にならないでしょう。
さだまさし の新譜、ソロ45枚目、グレープ/レーズンを含めれば自身50枚目となるメモリアルアルバム『生命の樹 ~Tree of Life~』を購入。全10曲と、収録楽曲数は、まぁ普通といえば普通なのですが、わりと短めの曲もおおいので、今作の総収録時間は約40分弱となっています。ただ、曲の長さと曲の良さとは比例したりしませんし、昔のLPはそもそもこれくらいのボリュームでアルバムがリリースされていたのですから、そんなに変なことでもないようにも思います。さて、もともと久し振りに さだまさし の新譜を(ほぼ)オンタイムで買おうと思ったのは、TV番組 EIGHT-JAM でさだまさし特集が行われ、そこでこのアルバムの簡単な紹介があったことがきっかけでした。つまり、それを観ていて「何だか良さげな感じだな」と感じたのです。さだまさし はかなりの数のアルバムを所有していますが、それでも50枚の全てというわけではありません。手元に無いものについては……どうしようかな。本作のような出来栄えであるのであれば、買ってみてもいいのですが。
コロナが落ち着いて、途中で中断となった2020年のツアーから4年振りに行われたコンサートの内容を収録したという、中島みゆきの『歌会 vol.1』を購入。1、ということは2や3に続いていくのか、という話にもなってくるのでしょうが、「歌会 vol.1」というのは今回のツアータイトルがそうなっていることから付いているもので、つまり、来年、再来年と彼女がツアーをやり続けない限りは、2や3は出ない、ということになります。というか、2020年の時点で「ラスト・ツアー」と銘打っていたはずだから、その辺り、中島みゆき としてはどう考えているのでしょう。ステージに2時間弱立って歌うというのは、年齢的にもキツくなってきているだろうというのは察せられますし。小さなライブハウスで、随時休憩を入れながらギター一本の弾き語りライブ、というのならばやれるかもしれませんけれども、彼女くらいのビッグネームになると、そういうのはむしろ難しいですよね(とはいえ、中島みゆき が弾き語りライブをやるというのであれば、それは是非観てみたい、聴いてみたいと思いますけれど)。まぁ、長くファンをやってきている身としては、本人が思うように、満足できる音楽活動を続けてくれれば、それで満足なのですが。








| 2025年5月24日(土) 続:アイコン化する「TOKYO」 |
1ヶ月前、4月19日の「雑記」で私は、実際のところがどうであるかとは全く関係なく、メディアによって醸成されたイメージとしての「東京」が多くの人の脳内で形成されているのではないか、と書きました。それは今や宗教めいたもののレベルに達しているかもしれず、そして私たちはそんなアイコンとしての「東京」を消費し、そこに描かれるものに憧れたりしているわけです。まぁ、そう書きながらも「これは極論かな」とか「さすがに妄想が入っているかな」と思わないでもなかったのですけれども、それでも、当たらずとも遠からず、程度の差はあっても、そういうところは実際にあるのではないか、と私が思っているのは事実です。だからって、虚像に憧れることは云々と何やら説教じみたことを書きたいわけではありません。だって、虚像だって偶像だって、それに憧れ目標とすることが、その人が成長していくことの糧になるのであれば、それは別に悪いことでは無いとも思いますしね。
ところで、アイコン化、偶像化ということが当てはまるのは「東京」だけれはない、とも私は感じています。どの街であれ、多くの人が思い描くイメージと実像との乖離というのは決して珍しいことではないでしょう。で、そんなことを思っていた時に、今年の「住みたい街ランキング」が、ふと目に入ってきました。ランキング自体の発表は2月末には行われていたのですけれども、例年特に関心も興味も無いからスルーしているのですけれども、本当にたまたま、目にしたという感じです。そこには、首都圏の第1位が7年連続で「横浜」だったと書かれてていました。生まれこそ都内ですが、育ったのは横浜北部のベッドタウンだった私としては、横浜市が暮らしやすいとか、住んでみたいと言われているのだとすれば、そこには一定の納得があるのですが、このランキグで言うところの「横浜」というのは、結局「みなとみらい」地区のことだったりするわけです。で、まぁ、これは2歳から30代まで横浜市民だった者の個人的見解ですが、「みなとみらい」って、そんな、住みやすいところでは無い気がしないでもありません。
もちろん、「住みやすい」「住みたい」の基準は人それぞれです。ただ、一般的には、通勤・通学の便利さ(要する時間)とか、買い物の便利さ(近くにコンビニやスーパーがあるか)とか、近隣に大きな医療機関があるかとか、そういうところで判断されるものだと私は思っているのですけれど、そこからすると、「みなとみらい」は……。この「住みたい街」ランキングで投票した人の選択基準が別のところにあるのか、それとも皆さんが想像するところの「横浜」すなわち「みなとみらい」のパブリックイメージがそんなに良いのか。いずれにしても、そこには現実と虚像との間の乖離があると、私には見えます。そういったイメージの拡散に「みなとみらい」の開発に係ったデベロッパーとか横浜市とかの広告・広報が利用されたとしたら、住みたい街第1位になったことで、それは戦略的に大成功だったということになるのでしょう。実像と離れたイメージとしての「横浜」の完成、すなわちアイコン化ですね。それはそれで需要と供給がマッチングしているようなところもあるのでしょうから別に構わないのですが、個人的には違和感がかなり大きくて、何だかなぁと思ってしまいます。
まぁ、私が今まで住んだりしていない街、「札幌」でも「仙台」でも「名古屋」でも「大阪」でも「福岡」でもいいですが、そこに対して私が抱いているイメージも、実際に現地在住の方からすると、違和感バリバリのちゃんちゃらおかしいものだったりするのでしょうけれど。イメージ戦略の虚像性、実際との乖離、アイコン化、メディアによるイメージ消費というようなことは、全国共通である、と。この辺りを学問的に調べてみるのも面白そうかも。民俗学とか文化人類学とか、そういうジャンルになるのかな……。書籍、論文などが複数出ていたら、どこかで時間があれば、ガッツリと収集して読んでみたいですね。
なお、これもよく言われることですが、実際に市民に対して「横浜に行きたい」等の発言を投げかけた場合、彼等が想像するのはJR横浜駅辺りであって、「みなとみらい」ではありません。だから、住みたい街ランク第1は「横浜」です、と言われると、余計に違和感があるのかもしれませんね。多くの市民の脳内では、おそらく、「横浜」「関内」「桜木町」「みなとみらい」「元町」「伊勢佐木町」などなど、全て別の場所として認識されていますので、食事や飲み会、観光、遊びなどで横浜地元民に予約や案内を頼む時は、「横浜で食事」とか「横浜を案内して」という言い方ではなく、できる限り具体的な目的地、「中華街で食事をしたい」「伊勢佐木町の飲み屋に行きたい」「みなとみらい辺りでお洒落に飲みたい」というような指定をした方が、変な行き違いが出なくていいかもしれません。余談ですけれど。
単著としては2冊目になる、十三不塔の『ラブ・アセンション』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)を読了しました。「軌道エレベーター上で開催される恋愛リアリティ番組、ラブ・アセンション。12名の個性豊かな美女たちが参加者として集められて、クエーサーと呼ばれるセレブ男性をめぐって奮闘する。セクションごとにデートを繰り返すなかで、クエーサーに選ばれて究極の愛を見つけるのは誰なのか?そして番組の裏側では、ある地球外生命体をめぐる実験が極秘で行われており――? 様々な人物の思惑が火花を散らすバラエティSF!」というのが、裏表紙の粗筋。デビュー作の『ヴィンダウス・エンジン』(同社 同文庫)は溢れるイメージの奔流を書いている十三不塔自身が制御できていない(制御しようとしていない?)感のある、若さ溢れる作品でしたが、その後に読んだ短編は非常に完成度の高い面白いものばかりで、これは次の長編にも期待できるかもと思っている中、昨年の11月に発売になった作品です。
閉鎖空間で運営される恋愛リアリティ・ショーにファースト・コンタクトものを絡めて、そこにロマンスで味付けをした物語は、『ヴィンダウス・エンジン』の時のような、どこまで大風呂敷が広げられて話が広がっていくのか分からないワイドスクリーン・バロック的な興奮はありませんけれど、様々な要素を上手くまとめ上げてミステリー的なストーリーに仕立て、エピローグまで持って行っていて、バランスがしっかりと取れているという印象でした。それでこじんまりとしてしまうようでは、(短編ならばともかくとして)長編としては展開のドライブ感がもうちょっと欲しいなということになってしまう可能性もあるのですが、幸い、それも無し。あとはまぁ、個人の好みの問題が残るだけかな、というくらいで、これは、なかなか良くできた作品だと思います。前述したように十三不塔さんは短編が良くて、さすがにそれを全てフォローはしきれていないから未読のものもあるはずなので、どこかで、それ等をまとめた短編集も出て欲しいですね。
知念実希人の『天久鷹央の推理ファイル 神話の密室【完全版】』(実業之日本社 実業之日本社文庫)は、原点に戻って主人公達の勤務する病院で起きる事件を扱ったりした、2編の中編からなる薄めの文庫となっています。その粗筋は「まるで神の魔法のような2つの『密室』事件。 アルコールが一滴もないはずの閉鎖病棟で泥酔を繰り返す、かつての人気作家。キックボクシングの王者決定戦、勝利の瞬間にリングで死亡したチャンピオン。かたや厳重の名警備の病院で、こなた千人以上の観客が見守る中で、それでも起きた奇妙な『密室』事件。摩訶不思議な2つの謎に対し、天才医師・天久鷹央がくだした『診断』とは? 書き下ろし掌編『後輩、朝霧明日香』収録。」というもので、バッカスとトールという、神話に出てくる2人の神が司るものをネタにしているところが共通点だから、サブタイトルも「神話の」となっているというわけですね。前者は北欧神話で後者がローマ神話と、そこに統一感はありませんが。大きな事件が発生して……という長編もいいですが、こういう短めのエピソードも、「天久鷹央の推理ファイル」シリーズには合っているように思います。素人考えかもしれませんが、定期的に、こういう短編集をラインナップに入れていくのも、目先が変わっていいのではないでしょうか(現時点でシリーズ既刊を半分くらいまでしか読み進めていないので、実は今後にそういう短編集が既に何冊か出ているのかもしれませんけれど)。
八目迷の『終わらない冬、壊れた夢の国』(小学館 ガガガ文庫)は「時と四季」シリーズの4冊目にして完結作。シリーズ、といっても、時間ネタのジュヴナイル的な青春SF作品であることを共通項としながらも、個々の作品は単独で成立していて相互に関連していたりはしないので、実のところ、どれから読み始めても構わない4つの作品が、「シリーズ」として括られていると言うのが適切かもしれません。とのあれ、そんな「冬」の裏表紙にある公式の粗筋は、「足を踏み入れた人間が次々と消えていく……そんな都市伝説が囁かれる老舗の遊園地『サニーパーク』に、竜崎カシオは高校の友人たちと訪れる。満喫した一日を終える頃、カシオは友人の一人である小練菜々に人目のない場所に連れられ、刃物で刺されてしまう。――カシオが目を覚ますと、サニーパークに入園した朝に時間が巻き戻っていた。混乱を極める彼の前に、一人の女子高生が現れる。彼女は、カシオがサニーパークから出られず同じ一日をループしているのだと告げる。そして、この現象から抜け出す唯一の方法は、誰かを殺すことだと。」というもの。これまでの3作品、デビュー作でありアニメ映画にもなった『夏へのトンネル、さよならの出口』は時間と引き換えに望むものが手に入るというタイムトンネル、2作目の『きのうの春で、君を待つ』は過去に飛んでの歴史改変、3作目の『琥珀の秋、0秒の旅』(いずれも、同社 同文庫)は時間停止した世界でのロードムービー的物語と、様々な形で「時間」を扱ってきたシリーズ、今回は同じ1日が延々と繰り返されるループものとなりました。何故、ループが起きたのか。どうして主人公がそれに巻き込まれたのか。ループの円環を断ち切る方法はあるのか。物語は、そういったことを軸にしつつ、そこに色々な要素を絡め展開していきます。これまでも決して明朗快活な物語とは言えないシリーズでしたが、ラストを飾る本作は、もしかしたら過去一番重い空気感のストーリーでした。まぁ、「冬」ですしね。ヒロインの設定がループに密接に絡んでいることや、細かいところの見せ方などは、重いテーマを扱った『ミモザの告白』全5巻(同社 同文庫)を書くことで得た経験値なども良い方向で貢献したのかもしれません。かなり面白かったので、彼が次に書く作品がどのようなものになるか、これは是非とも注目する必要があるでしょう。
そういえば、今月頭に「読む」に掲載した人間六度の『烙印の名はヒト』(早川書房)の第1章はこちらが初出だったっけというところから、すっかり積読になってしまっていた、日本SF作家クラブと早川書房がタッグを組んで毎年出している書き下ろしアンソロジーの第5弾は、『AIとSF 2』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)を読了。2024年11月に発売されたのを今になって読んでいることを責められると言い訳のしようも無いのですけれども、まぁ、全700ページ越えの分厚いアンソロジーですから、なかなか読み始めるきっかけがつかめなかったというのが、正直なところです。テーマとしては、2023年の第4弾に続いて、「AI」を題材としたのにどういう理由があるのかは確認していないのですけれども、前回で掲載しきれなかったとか、前回を読んで自分も、と作品を書いてきた会員がいたとかなのか、あるいは時期柄、「AI」と社会変革というものがますます旬になってきているとか、そういうことだったりするのかもしれませんね。ともあれ、今回収録されている11の作品の中から、特に面白かったものを、いつものように収録順に簡単に紹介していきたいと思います。
冒頭から200ページというなかなかのボリュームを突き付けてきた、長谷敏司の「竜を殺す」は、人生において自身が乗り越えるべき困難を「ドラゴン」と例えて、登場人物たちそれぞれがその「ドラゴン」に対峙する様を描く作品。タイトルを最初に目にした時にはファンタジー系の内容で、AI絡みの、例えばゲーム世界などを題材にしてくるタイプのSFなのかと思っていたのですが、実際に読み始めてみると、これはそれとは全然違うタイプの、AIが日常生活のあらゆるものをサポートしてくれるようになった社会での親子の物語、突然訪れた大事件に翻弄される家族の物語という、非常にオーソドックスな作品でした。もしかしたらAI要素を為しにしても成り立つかもしれないレベルです。とはいえ、本作がAI社会を描いていることにはやはり意味があって、近未来がこういう世の中になることは普通にあり得るだろうということ、そのような世の中での家族の姿のシミュレーションとして非常に面白かったです。想像していたものの100倍くらいヒューマニティー溢れる作品で、なる程、この『AIとSF 2』を読んだ人の多くが絶賛していたのも納得でした。
AIに自身の作品を勝手に学習素材として使われ、類似の作品が出力されることは死活問題であると訴えるクリエイターがいる一方で、AIを創作のアシストに使う小説家やイラストレーターも出てきているわけですが、茜灯里の「幸せなアポトーシス」は、そのようなAI活用が科学研究の分野にも進出してきたらどうなるだろうかというシミュレートした作品。過去のデータを分析しつつその上に新たな理論を走らせて成果を得ようというようなもの……それは研究に限らないでしょうが、そういうものについては特に、AIが人の居場所を奪っていくことというのは、確かにあり得るだろうなと思いました。とはいえ、そこで「人」が完全に排除されるのかどうかは分かりません。私の仕事している業界の例で言うならば、かつて週刊誌などでAIの進化が進めば真っ先に人が要らなくなる職種として紹介されたものの、実感かつ実態として、実際には「人」の存在が欠かせない部分というのが存在していて、そこに注力している事業者は普通に生き残っていく……どころか、その存在感、重要性は増していくのではないかとさえ感じられているところですし。そんなことを色々と考えさせられる作品として興味深く読みましたが、実は私が本作で好きなのは、背景に通奏的に流れている「ロマンス」の部分だったりもするのです。
科学研究ではなく、介護の世界に進出したAIの未来を創造したのが、揚羽はな の「看取りプロトコル」。介護・看護や老人福祉の世界にロボットが進出するというのは既に起きている事実ですし、AIが進化していけばそれ等のロボットが完全に自律的に稼働することになるだろうというのも想定できることです。本作は、そんな中でAI搭載の介護ロボットが、いかに人の死に向かい合うのかを描いていました。介護分野での人とAIとの望ましい在り方、関係性を提示した作品と言ってもいいのかもしれません。それは 揚羽はな という作家にとって望ましいということであって万人にとってもそうであるとは限らないだろう、という指摘もあるでしょうが、私はここで描かれたような形でのAIの進化は、悪くないなと感じました。
今回収録されている作品の中で他と大きく毛色が異なっているのが、海猫沢めろん の「月面における人間性回復運動の失敗」。AI技術が進んで日常生活のあらゆるところをサポートしてくれるようになった社会では、むしろAIにはできない堕落や自己破滅をすることこそが「人間性」の表れであるとされているのですが、少しでも前向きな者は皆、開発の最前線である火星に行ってしまっており、後方の月がまるで吹き溜まりのようになっている中、そんな風潮を煮詰めたようなタクシードライバーの男が、地球人類の存続可否を判定するべくやってきたオーバーロードとコンタクトするよいうのが、本作の導入。終始笑わせてもらった作品なのですけれど、AIの進化が極北まで行った先にあり得る人間社会の姿として、十分あり得る、むしろこんな感じになるのが当然の帰結なのではないかという気にさえなってしまうというところで、他の収録作同様、これもまたAIが私達の社会に入り込んだ未来を予測する、そういうテーマの下に書かれたものだと言えます。実は、何気に今回の収録作の中では、これが一番好きだったりします。
生成AIとクリエイターとの関係を扱った、塩崎ツトムの「ベニィ」も面白かったです。実際、本作で描かれているようなことは今の段階できちんとした法体系、指針を作っておかないと、これがフィクションではなくなってしまうわけですが、そういう状態が「良いもの」と呼べるかどうか。ここは人によって考え方は色々とあるだろうとは思います。とはいえ個人的には、生成AIを利用した創作、それをアシスタントとして利用するというのはアリだとしても、その先はやはり人の手によるものであってほしい、そこにその作者なりの個性が色濃く反映されていてほしいと思ってしまうのですけれど、こういうのってオールドスタイルなんでしょうね。まぁ、それで私があと年年間生きていられるのかということを考えれば、「オールドスタイル上等!」という風にも思ってしまうわけですが……。
マニアックで地味な作品だと思っていたら、そのマニアックさがむしろニッチな人気に結びついて、何だかんだで一定の固定ファンを掴んでいるらしい、鬼ノ仁の『一級建築士 矩子の設計思考』第4巻(日本文芸社 NIHCICBUN COMICS)。一般的な大ヒットとかアニメ化などのメディアミッスク等とは縁が遠いでしょうが、題材にしている業界の支持を受け、コミックス等のある程度の売上が見込める状態になっているのであれば、連載もネタが尽きるまでは続いてくれることでしょう。今回は、主人公が故郷である弘前の街を歩き回ってその建築的な見どころを紹介していくというのがメインの内容になっており、非常に面白かったです。弘前、言ってみたい街の1つなんですよね。現存天守もありますし。
JBがアフリカに移住して、いよいよシリーズのラストが近づいてきた、獣木野生の『パーム TASK Ⅸ』(新書館 ウィングスコミックス)。陰謀論的なニュアンスが漂うようになってからの本作には少々微妙な感もあるのですけれども、それでも、第6部「オールスタープロジェクト」までは間違いなく面白く、第7部の「愛でなく」も悪くなかったし、総じて好きなシリーズと言えるので、最後まであと少し、しっかりと付き合っていくつもりでいます。やはりここまで来たら、JBの最期は見届けないと。
ヤマザキコレの『魔法使いの嫁』第22巻と『魔法使いの嫁 断片集』第2巻(ブシロードワークス ブシロードコミックス)は、物語が竜を巡って動いていくであろうと思われる第3部の、新展開を見せた1冊と、アニメの円盤特典マンガ等を収めたスピンオフ集の2冊目。前者について、前巻ではヤマザキコレの悪いクセが出て画面が分かりにくいことになったりもしていましたが、今回はそんなこともなし。ここからの展開も面白くなりそうな予感をさせてくれるので、これはこの先の展開が楽しみな感じです。後者は、普通にサブエピソードとして面白く読ませてもらいました。一時は新刊を追いかけるのをやめるかどうしようかと迷った作品ですけれど、読み続けてきて良かったなぁと思います。








| 2025年5月17日(土) 「オタク」な私の製造工程(その6) |
先々週は、自宅からの通勤圏で就職を決め、行き帰りの途中のターミナル駅でCDショップやアニメショップ、大型書店に立ち寄っては趣味のものを購入する素晴らしき「オタク生活」が始まったと思ったら、わずか1年で他県の山の中にある工場に転勤、オタク的な物欲の点ではなかなかに禁欲的な状態になったことと、事務系の転職も見据えて簿記の通信教育を始めたことを書きました。そんな中で、想定外のところから状況の変化が訪れます。というのは、私が転職も視野に簿記を学んでいると言うことを(正月の集まりで)何となく話していた義理の叔父から、そちらの方向に興味があるのならば、自分のやっている事務所に来ないか、というお誘いがかかったのです。叔父夫妻には子供がいないので、これはもう明確に、後継ぎとなることをも期待されての勧誘と考えていいでしょう。一方で、叔父がやっている専門的資格については、私としては自分がそちらの道に行くとは全く考えておらず、かつ、その話を一度受け容れてしまえばそこからの進路変更は甚だ困難……というか、まず無理なことも見えています。だから、これをどうするべきかは、かなり悩みました。しかし、人生は一期一会ですし、こういうのは「縁」ですから、思い切って別職種かつ親族関係の個人事業所への転職を決めたわけです。
で、当然今までの会社の寮は出るわけですが、事務所の所在地が東京都の多摩地区であったので実家から通うのも少し無理があって、早急に、賃貸の部屋を決めなければなりません。まぁ、この辺りも書くと長いのですが、ともあれそうして私は中央線沿線に居を構え、吉祥寺(当時)の事務所に通勤するようになったわけです。吉祥寺といえば、サブカル系、アニメ系の趣味を持つ者にとっては、書店ありアニメショップありCDショップありライブハウスありで、いわば楽園のような街。人生というのは何がどう転がるかなんて分からないもので、結果的に、約5年の雌伏の期間を経て私のオタクライフは、一気に活性化することとなるのでした。もちろん、財布の限界というものがある以上は何でもかんでも買うことはできないから、そこに依然として一定の歯止めは存在していたのですけれども。なお、先月から書いているこの「『オタク』な私の製造工程」という一連のエントリーは、あくまでアニメ、漫画、ラノベやSF等の小説に関する振り返りで音楽面については基本的にノータッチでやっているのですが、この転職で私が一番嬉しかったのは、実は、これで頻繁にライブに行けるようになる、ということだったかもしれません。
それから20年と少し、事務所の場所は隣駅の三鷹に移転しましたし、結果的にきちんと(?)資格も取得できて、事業承継もさせていただいたので、状況は変化していっていますが、オタクライフという点で言えば、あの時の転職の決意が現時点では最後の、そして最大の分岐点だったと思います。今のところ生活に苦労せずに、好きな本やCDをそれなりに購入できるだけの収入も得られているので、幸運な人生を送れていると考えていいでしょう。さすがに不安だったり後悔だったりが全く無いというわけではありませんし、ここまで独り身出来てしまったのは若干計算違いですけれども、総じて満足すべき人生を送れていると思います。あとは、これがどのように締めくくられるか。そんな話を友人知人にすると、終活にはまだ早いと笑われますけれども、孤独死の可能性だって視野には入っている以上は、どうすれば周囲に迷惑をかけずに生きていけるか、それを考え出すのに早すぎるということは無いでしょう。ここまで集めた本やCDが私の死後にどうなるのか、ということは気にならないではなく、それ等が好きだという人に大切に引き継いでもらえればとは思うものの、基本、私が死んだ後のことだから……。今では入手困難なレアものもあったりしますけれど、一般的には人気が無かったりもするので、下手な古本屋等に出すと二束三文で買いたたかれたり、そのまま廃棄されたりしてしまいそうなのが気になりはしますけれど。
以上、(実は終活の流れの一環として)ここまでの私のオタク人生をざっくりと全6回で振り返ってみました。断片的には過去の「雑記」で書いたこともあることですが、それを一度時系列に沿ってまとめておきたいという意図はありましたけれども、所詮は自己満足な行為であることも承知していますので、もしここまで全て読んでお付き合頂いた方がいらっしゃったら、こんなものに突き合わせてしまって申し訳ないと同時に深く感謝いたします。プライベートに過ぎるので記述しなかったことも多々ありますが、ひとまず私個人としては書きたかったことは書けたかな、というところ。次は、音楽面での経歴も書いてみようかなぁ。さすがに、すぐに、というわけではないですけど。
書籍の形で短編がまとまることを熱望していた、天沢時生の『すべての原付の光』(早川書房)の帯にある宣伝文句は、「『ガチで半端ねえ機械なのさ』滋賀県近江八幡市の不良の取材が思わぬ結果へ繋がるワイドスクリーン・バロックの表題作、無限増殖する大型ディスカウントストアをめぐるサイバーパンク『ショッピング・エクスプロージョン』、第2回ゲンロンSF新人賞受賞作のディストピアSF『ラゴス生体都市』など、破壊力満点の奇想が炸裂するSF作品集!」というもの。この紹介に載っていない収録作品は2つ、日本SF作家クラブが編纂した文庫アンソロジー『ポストコロナのSF』(同社 ハヤカワ文庫JA)に収録されていた未来の辺境宇宙コロニーでヤクザが濡れタオルでシバきあう任侠移民SF「ドストピア」と、ちょっと幻想小説とか民族風というか伝奇風というかホラー風味のある「竜頭」になります。天沢時生という作家はサイバーパンク的なSFを志向しているのかどうか、これ1冊で判断するのは早計ですが、表題作である「すべての~」と「ショッピング~」そして「ドストピア」という前半3作品はどれも、ヤンキー・任侠的なものとサイバーパンクを融合させてアクセルを床ベタ踏みで加速しまくったような読み心地をしていて、読んでいると困惑と興奮とが互い違いに連続して浮かび上がってくる感覚に頭がクラクラしてきて、気が付けばその世界観にどっぷり浸って酔いしれていること間違いありません。ネットに公開されている水町綜との対談(https://virtualgorillaplus.com/interview/amasawa-mizumachi-2024/)では不良とパンクは、どちらもアウトサイダーという点で親和性が高いというようなことが話題になっていましたが、なる程、確かにそれはそうかもしれません。だいぶ前に読んだ作品で恐縮ですが、そういえば海猫沢めろん の『零式』(同社 同文庫)も、そういう感じでノリノリかつ疾走感溢れるポストアポカリプスなサイバーパンクSFでしたっけ。なお、この短編集を締めくくる「ラゴス生体都市」も、これはヤンキーやヤクザではなく、エロ、AVをフックにアフリカのナイジェリアを舞台にした物語で、ヤンキー的な文脈こそはないもののパンクの匂いを強く感じさせるものでした。短編集というのは作品ごとに、気に入る、気に入らないの差が出たりもするものですが、本作については5編全てがクオリティーの高いものになっていて、大いに楽しませてもらいました。天沢時生はこれが初の単著書籍。これから発表されていくであろう作品、そして果たして彼がどのような長編を書くのか、期待しています。
シリーズ10冊目となる、知念実希人の『天久鷹央の推理ファイル 魔弾の射手【完全版】』(実業之日本社 実業之日本社文庫)を読了。「見えない『魔弾』を放ったのは、誰か。 西東京市にある廃病院で、看護師が転落死した。不治の病を苦にした自殺と見做されたが、彼女の娘・時山由梨はそれを頑なに否定。母が一人で死ぬはずがないと訴える。天才医師・天久鷹央は由梨の依頼を受け、事件を調べ始めるが、そこに『不可視の魔弾』の謎が立ちはだかる……。現役医師の著者のみが描ける驚天動地のトリック。その犯人とは?書き下ろし掌編『幽霊と鴻ノ池』収録。」というのが、今回の粗筋です。『魔弾の射手』といえば何をおいてもウェーバーのオペラが真っ先に頭に浮かびますし、その次には『エロイカより愛をこめて』の外伝でエーベルバッハ少佐を主人公にしたコミックのタイトルですが、本作がそれに並び立てる地位になったかどうか……それは、実際に読んでみて皆さん自身で確かめていただきたいところですが、とりあえず言えるのは、なかなか面白かった、ということ。犯人の使ったトリックにちょっとレアな病気が絡んでくるのが、このシリーズの特徴であり読みどころなのですけれど、ミステリーとしての読者に対するフェアさ、解決編に至る前に必要な情報を全て読者に示していることというところを考えると、それはちょっとどうなのかな、という気もしないでもありません。まぁ、私はそんなに熱心なミステリーファンではなくて、この「雑記」で紹介している各種ミステリーも、謎解きを楽しむというよりもキャラクター小説の文脈で消化しているところがあるので、個人的には問題ないのですけれども。
今年の前半はいくつかのアンソロジー文庫を買っているのですが、他に読みたいものも多かったりした関係で、なかなかそれ等に手を出せずにいます(特に、結構な「鈍器」のアンソロジーも複数あったりするので)。そんな中、いつまでもこれではいかんなということで、まずは薄めのものを片付けていこうと、メディアワークス文庫から出た「神様」がテーマのアンソロジー『神様の本』(KADOKAWA メディアワークス文庫)を読了しました。ここに収録されているのは全部で6人の作家による6つの短編なのですが、面白いもので、微妙に題材が被ったりしていました。それが、ある意味で「旬」なネタだということなのかもしれません。以下、シリーズに絡んでいたり、面白かったりしたものを簡単に紹介します。
三上延の「ビブリア古書堂の事件手帖 ~約翰福音之傳~」は、北鎌倉の隠れキリシタンを題材にした1編。時代的には《栞子編》と《扉子編》の間、扉子がまだ生まれて間もない、一歳半の頃のエピソードになっています。いつもの世界でいつものキャラクターがいつものように物語を紡ぎだしているので、安定・安心して読めた作品だと言うことができるでしょう。
近江泉美の「深夜0時の司書見習い ~注文の多い図書館~」は、そのタイトルの通り宮沢賢治が題材の1編。メディアワークス文庫で2冊出ているシリーズの番外編的な扱い……になるのかな?内容的にはわりとオーソドックスで、どこかで見たような物語なのですけれども、出来は悪くありません。
もしかしたら本初収録作で一番楽しませてもらったのが、杉井光の「ハレルヤ出版編集部」です。これについては少しでも内容に触れるとネタバレになるので、タイトルを紹介するだけに留めておきますが、ある意味、禁じ手なネタかもしれませんね。バカバカしいと同時に、ちょっとした皮肉、批判精神も入っていて面白かったです。
浅葉なつ の「神様の御用人 ~雲隠~」も、いつものメンバーがいつもの感じでいつも通りのことをやっている掌編。何らかの店舗特典で配布されたものだと言われても信じてしまいそう……。なお、それは決してつまらなかったとか駄目だとかいう意味では無くて、きちんと面白かったのですけれど、驚きとか新鮮さとかは無かったな、と。ところで、『神様の御用人』シリーズについては第2部を書くというアナウンスがあってからちょっと経ちますけれど、それはどうなっているのでしょうか。あるいは、『神と王』シリーズの執筆に時間を割いてしまっていて、こちらには手が回らないということだったりするのかも。あちらはあちらで面白いから、だとすれば、痛し痒しというところですね。
発売をすっかり見落としていた、板垣巴留の『BEAST COMPLEX Ⅳ』(秋田書店 少年チャンピオンコミックス)を購入。6編の短編が収録された、『BEASTARS』(同社 同コミックス 全22巻)の番外編の4冊目ですね。巻末のおまけページで本人がコメントしているように、この作品はもう、すっかり板垣巴留のライフワークになっています。もともと『BEASTARS』から始まるこの一連の作品は容赦なくシビアなストーリー、現実社会の様々な差別問題や対立問題、憎悪とか優和とか、そういうものを、結構エログロなところも描写しまくりつつ寓話的に取り上げていっているわけですが、今回も、なかなか面白かったです。レゴシとハルのエピソードもあったりして、『BEASTARS』の読者も楽しめるようになっていますし、充実の1冊と言っていいでしょう。
amazarashi の『ゴースト』は、映像を伴うライブの為に書き下ろしたストーリーに沿った楽曲を集めたアルバム……という説明でいいのかな?amazarashi については、どのアルバム、どの楽曲を聴いても基本的には同じようなテイストであるということ、根っこの部分での差異が存在しないのではないかと思えるところが特徴であり、それはつまり、徹底的にワンパターンでマンネリであり、バラエティー性も無ければ発展性も無いということでもあるのですが、何故か、新しいアルバムが出るとなれば購入して聴きたくなるし、「特に好きな楽曲」とか「そこまででもない楽曲」という区分もあったりするのです。この辺りは考えてみればちょっと不思議なところで、理屈では拡大も縮小もしない永遠の再生産音楽だとすら思うのに、麻薬か何かのように、その魅力に取りつかれて離れられなくなってしまっています。理屈ではなく、感情・心で聴いている、ということなのでしょうか。だとすれば、それは音楽と聴き手との関係性としては、かなり素晴らしいことなのでは、とも。そんなわけで今回も新譜を購入したし、そしてじっくりと何度も聴き返していたりもします。今回も、ハマれるアルバムでした。
試しに買ってみたアルバムが想像を超えてぐっと良かったので、ヴァイオリニストの壷井彰久とギタリストの鬼怒無月の2人がやっているデュオ ERA の、それ以外のアルバムも購入。順に、ライブ録音だったという1stと3rd のスタジオ再録音盤である『Era :Re-Recording』、『Three Colors of the Sky : Re-Recording』、そして4thの『忘れられた舟』と5thの『Forest is Burning』です。ここまで聴いた2枚の内容から、何となくこのユニットはプログレ志向が強いものだと思っていたのですが、こうしてまとめて聴いてみると、それだけではなく、もっと広くて奥深い音楽性があるということを知ることができます。私の趣味的なところからいくと、やはりプログレ色の濃い楽曲が好物ではあるのですが、それ以外もクオリティーの高い良い曲が揃っているのが、良いですね。さすが、実力者2人のユニットです。更に良いのが、彼らのアルバムは一切のオーバーダビングを行わず、2人が2人だけで演奏している曲のみで構成されているというところです。ヴァイオリンもギターも表現力の高い楽器ですし、もともとテクニックの図抜けたミュージシャン達ですから、オーバーダビングが無いからといって、それで音が薄くなってしまったりはしていません。むしろ、しばしば音にとんでもない厚みを感じてしまうくらい。インディーズ作品で、ご本人の運営しているBASEのサイトとか、ディスクユニオン、ライブ会場での販売くらいしかしていないようなのですけれども、興味のある人は、是非、試しに何か1枚を買って Era の音楽を聴いてみてください。
3月にリリースされたサザンオールスターズのアルバム『THANK YOU SO MUCH』も購入。熱心なファンに怒られるかもしれませんが、サザンといえばメンバー全員がもうかなりの年齢ですし、ここ数年の訃報の流れからいっても、おそらく自分たちもどこまでこの面子でバンドを続けていられるか、ということが彼らの脳裏をよぎっていても個人的には全く驚きません。だからこその今回のアルバムタイトル、ここまで支えてきてくれたファンへの感謝を表明しているのかなと感じました。それだけに中身は大きな冒険は無しの、サザンとして非常にオーソドックスなものになっていたと思います。そこが逆に私としては少しつまらなかったのですが、まぁでも、ここまで活動を続けてきて高齢にもなっていて、それでもしかしたらレーベルの収支を背負っている状態かもしれないサザンが、手堅い作品をリリースするのは、それはそれである意味で当然ですよね。決して出来が悪いわけでは無いのですし。妙な要求をしている私の方が悪いのです。










| 2025年5月10日(土) フロイトの夢判断だとどうなるのかな……? |
あまり公言していない「ぱんたれい」運営マイルールの1つに、どんなものであれ、1年に1作品は「書く」に新作を掲載する、というものがあります。昨年は8月末という比較的早い時期に新作を公開していたのと、その次に作ろうと思っていたもののボリュームがそこまで重いものでは無かったこともあって、(昨年10月くらいには着手していましたし)2025年についてはかなり早いタイミングで新作を出せる見込みでした。で、実際に1月末には初稿ができていたのですけれど……自分が見た夢の中身を下敷きにしたその作品「#6DREAM」を、そのまま公開するのにちょっと躊躇いを感じたので、その時点では公開を一旦保留にすることにしたのでした。何故そういう感じになったのか、これは今でも「こういうわけだ」という確たる断定ができる話ではなくて、本当に、ただ何となくとしか言いようがありません。支離滅裂なところがあるのは、もともと夢を下敷きにしたのだから当たり前だし、出来栄えに不満は……無いとまでは言いませんがそれは私の実力不足の問題でどうしようもないことだし、インモラル過ぎたりするようなものでもないし、ということで、さてどうしたものかな、という状況だったわけです。
で、最終的な結論として、これ1つで新作公開というのが何だか嫌だというのならば、もう1つ新しいものを書いてしまえばいいのではないか、ということに。そんなわけで、今回の更新で「心象語」の中に2つの散文作品を公開しました。上に書いた「#6DREAM」と、「海と彼女は言った」です。後者を付け加えたことで何がどう変わったかと問われると、実際のところ何も変わってはいない気もするのですけれど、しょうもない(けれども自分としてはそれなりに気に入っている)ものが2つ並んだことで、その「しょうもなさ」が多少緩和されたというか、変質したというのは、あるかもしれません。あくまで「私の心情として」の話であって、客観的にはどちらもロクでもない作品な気もしますが。「心象語」というのは散文詩的なスタイルで、ややビターな物語を(可能であれば寓話的に)書こうというのが趣旨の連作なのですけれど、その芯になるところから外れ気味なものを最近は書いている気もしますね……。次回、「心象語」の8本目になる作品は、原点に戻る感じのものにしなければならないかも。まぁ、次に書くのはそれじゃない予定なのですけれども。
ともあれ、「書く」の更新です。仕事その他が色々と忙しくて、なかなか新作を書く時間も確保できにくいのがここ数年の傾向なのですが、実力その他の問題はさておいて、やはり何かしら作品を作るという行為は好きなので、今後も続けていく所存です。
昨年行われた第12回ハヤカワSFコンテストの審査員たちの選評を読んでからずっとかなり気になっていた、犬怪寅日子の『羊式人間模擬機』(早川書房)を読了。「男性が死の間際に『御羊』に変身する一族に仕える『わたくし』は、その肉を捌き血族に食べさせることを生業としている。ついに当代の大旦那様が御羊になった日、『わたくし』は儀式の準備を進めるが、一族の者たちは『御羊』に対して複雑な思いを抱いていた。かれらはなぜ、難題にもわたり血族の地区を食みつづけるのか。人間は/機械は、何のために存在するのかー―第12回ハヤカワSFコンテスト大賞を受賞した異色の幻想SF。」というのがその粗筋なのですが……なる程、これは審査員によって評価が大きく割れたというのも、頷けます。私としても、本作をどう評価するべきか、そしてどのようにここで紹介するべきか、かなり迷うところだったりします。というのも、私はこの作品に「物語」を感じられなかったのです。
作者には書きたいテーマがあって、それを余計なものは徹底的にそぎ落とす形で愚直にアウトプットしたのが、これなんだろうなとは思います。そして、全150ページ程の短めのボリュームの中にそれを凝縮した。だから、全編から「凄み」のようなものが滲み出ている、濃厚な力作であることは、間違いありません。その点では、読んで面白かった本、刺激を受けた本を掲載することにしている「読む」に採り上げてもおかしくなくらいです。ただ、おそらくテーマ的な部分は執拗に堀下げを行っているものの、全体を通じて「物語」と呼べるようなものは、ほぼ無い。そういう作品が存在しないわけではないですし、それに否定的なわけでもないつもりですけれども、本作については、それがどこまでもピンと来なかった感じで、私にとってはちょっと微妙な1冊となりました。執事的ポジションにいる語り手がやたらに丁寧な、そのうえで端々に違和感を覚えさせる口調なのは、後半になるにつれて事情が判明していく、一種の仕掛けなのですが、それが最後までしっくりこなかったのも理由としては大きいかもしれません。とはいえ、そういったところに、例えば審査員の神林長平が強く推したというのも分からなくはないだけの魅力があるのも、事実でしょう。私には刺さらなかったけれど……。なお、本作についてはSFというよりは幻想文学として扱うべきだという感想をネットで見ましたが、その意見には私も賛成です。
前回の第7巻発売が2021年2月の事だから、実に4年振りの続巻となった、オキシタケヒコの『筺底のエルピス8 ー我らの闘いー』(小学館 ガガガ文庫)。焦れったさでどうにかなりそうなくらいに待たされた本作の裏表紙の粗筋は「殺戮因果連鎖憑依体――。古来より『鬼』や『悪魔』と呼ばれる脅威と戦ってきた三つの組織は、月の知生体《一二〇》からの侵攻を一時的に封じた。依然続く危機的状況を打破する道は、白鬼の所在を隠匿しながら、時間切れまでに《一二〇》との和睦を果たすことのみ。各ゲート組織にて可能な限りの準備と再編が進み、かつての敵までもが戦力として集結するも――立ちはだかる圧倒的な絶望を前に、集った “我ら” はいかに戦い抜くのか。人類の存亡をかけた、影なる戦士たちの一大叙事詩。終焉に立ち向かう、一致団結の第8弾。」というもの。正直、実際にページを捲る前には、あんまりにも「待望の」1冊であるが故に、何を読んでも、内容がどんなものでも楽しんでしまいそうな感もあったのですが、そんな妙なことを考える必要はありませんでしたね。これは、間違いなく最高に面白いです。今回は全体の構想の中で最終第5章「絶望時空」の前半という位置づけになるらしいのですが、この段階では、まだそこまで「絶望」が前面に出てきてはいません。今巻は、これまで作中に出てきたサブキャラクター(と新たなキャラクター)が最終決戦に向けて何を考え、何をやっていたのかを描く、言ってみれば群像劇のような感じになっています。基本的な雰囲気は穏やかな日常系の様相を呈していながら、その裏では様々なことが進行していっています。果たして人類は《一二〇》との圧倒的な対峙を無事に行って、未来の存続を獲得することができるのか。一応最終巻という予定になっているらしい次の第9巻(個人的な予想では、なんとなく2分冊になりそうな気もしないでもありませんが)が、一体何年後の刊行になるのかは分かりませんが、人類が筺の底に最後に残された希望(エルピス)を掌中にできるラストであることを願って、首を長くして待つつもりです。
「謎の人体発火現象。陰陽師の呪いに、挑め。 安倍晴明、蘆屋道満……そんな平安時代の陰陽師に連なる存在として、複数の大学が調査を行っていた呪詛師・蘆屋炎蔵。だが、彼の墓を調べた研究者たちが相次いで体調を崩し、さらに翠明大学准教授が謎の焼死を遂げる。殺人か、呪いか。皆が疑心暗鬼に陥る中で、鷹央は事件に潜む『病』を看破するが、それは新たな呪いの始まりでしかなかった……。書き下ろし掌編『新しい相棒』収録。」という粗筋の、知念実希人の『天久鷹央の推理ファイル 火焔の凶器【完全版】』(実業之日本社 実業之日本社文庫)を読了。パッと目を引く派手な事件に対して医学的な理由を付けて解決していくというのが、このシリーズの特徴となってきている感がありますが、今回は、ファラオの呪い系の話に、人体発火が題材。登場する各キャラクターの役回りも安定していて、安心して読み進めていくことができる物語となっていました。これがシリーズ9冊目ということは、次からはいよいよ2桁の大台に乗るわけですけれど、現状はまだまだ、ワンパターン、マンネリの沼にはまることなく、面白く読ませてもらっています。
主人公2人のいちゃいちゃエピソードを堪能する1冊と見せておいて、最後にちょっと不穏さを感じさせた、宮沢伊織の『裏世界ピクニック10 あり得るすべての怪談』(早川書房 ハヤカワ文庫SF)。「〈山の牧場〉で民間軍事会社との訓練合宿を終えた、空魚と鳥子。しかし 潤巳るな が放った一言が、ふたりの関係にわだかまりを残し……? 膝枕をめぐる空魚の災難『裏膝枕って知ってる?』、認知科学者の小桜が開発した怪談メーカーが見せる光景と、閏間冴月の残したアーティファクトをめぐる『あり得るすべての怪談』、弾丸を確保するため裏世界を探検する『アンダーグラウンド・ピープル』を収録のSFホラー第10巻!」というのが裏表紙の粗筋で、ここで物語全体のクライマックスを持ってこようとしているという解釈もできなくもないだけに、ここから次の第11巻の展開は、ちょっと目が離せないかもしれません。
荒川弘の『黄泉のツガイ』第9巻(スクウェア・エニックス ガンガンコミックス)は……面白くなってきたのは間違いないのだけれども、まだイマイチ物語に乗り切れないんですよね。アクションは相変わらず迫力がありますし、味のある新キャラも出てきているのですが、全体として、こう、何というか微妙な感じが抜けません。もちろんこれは私個人の感想に過ぎないので、本作を読んで「最高に面白いぜ!」という人もいらっしゃるでしょうし(だからこそ、連載が続いているはず)、それを否定しようとも思っていないのですが。それでも作者に対する信頼はあるから、どこかでこのムズムズするのが逆転して最高な感じになってくれるだろうという期待でコミックスは買い続けているのですけれども。
ここからストーリーがグッと広がっていくのかな、という感じの、丸山薫の『司書正』第3巻(KADOKAWA HARTA COMIX)。架空の疑似中華王朝の後宮で繰り広げられる、陰謀に満ちた不穏な物語は、ここでクライマックスというには、まだ広げたままの風呂敷が幾つかあるから、それ等を有機的に繋げていく作業が多く残っているので、次の第4巻で完結するということはさすがに無いでしょう。連載の人気が極度に低かったりするのあんらば、話は別ですが。本作は結構メンタルを抉ってくるような展開が多いのですが、丸山薫の絵柄が基本的に柔らかいから、陰惨さは多少緩和されています。とはいえ、例えば『事件記者トトコ!』(KADOKAWA ビームコミックス 全4巻)のような明るく明快な作品ではないので、メンタルの調子のよい時に読むのをお勧めします。
同じく丸山薫の『図書室のキハラさん』(KADOKAWA)は、雑誌『ハルタ』の帯裏に連載されていたショートコミックで、そういうものであるが故に、連載期間の長さ(全40回)と作品の多さは比例せず、また、コミックスにまとめるということもしづらいという性格の作品でした。が、個人的にはかなり好きな作品でしたし、丸山薫のファンとしてはこれも1冊の書籍とならないものかとずっと思っていたのですけれども、それが4月についにコミックスとして発売されたのです。しかも、同人誌として発表された「キハラさんの一週間」、「キハラさんの夏休み」も同時収録で。もともとが帯裏という変形枠での連載だったので、この本も「B5判横」という少し特殊な判型になっていますが、それもまた、本作らしい。なお、当然、これにも帯が付いていて、そして帯が付いている以上は……。大満足の1冊でした。







| 2025年5月3日(土) 「オタク」な私の製造工程(その5) |
前回は大学の漫研に入ることで、ようやく私も「自分がそこに存在していい」コミュニティーを手に入れたということを書きました。所在の定まらぬ根無し草な状態、当時の世間からは決して肯定的には受け入れられていなかった「オタク」趣味の持ち主が、自宅以外の「自分の座席」をひとまず手に入れられたわけで、その事実の意義は個人的には非常に大きなものであったと、今振り返ってみれば実感させられます。周囲に徒なす。害を及ぼす、というようなことはしていなかったから、基本的には他者にとっては無害な存在の私で、特に差別とか迫害を加えられた覚えもありませんけれども、己の足をどこに置くか、置けるのか、学内におけるポジションをサークル活動という場が与えてくれた、手に入れることができた。しかし、いつまでも大学に在学しているわけにはいきません。もちろん必要な単位が足りなければ大学は卒業できませんし、学費さえなんとかできるのであれば、最終的に放校処分になるまで最大で8年間、学生で居続けることはできます。とはいえ、そんな親の脛をかじり続けることは、さすがに私にはできませんでしたし、そもそも両親の側からも、4年で卒業できなかったとしたら5年目以降の学費は負担しないので自分で何とかしろということは入学時に言われていました。つまり、否応なく、卒業はやってきたのです。
何度も書いているように、当時は「オタク」的趣味はまだまだ日陰者で、差別対象でした。なので、就職をして会社勤めを始めてしまうと大学時代のように自らの趣味をオープンにはできません。それが負担と言えば負担ではありますが、とはいえ、社会人になって給与を得られるようになれば、趣味に投下できる資金も少しは増えるわけで、マイナスなことばかりがあるわけではありません。問題はむしろ、就職先を首尾よく獲得できるかどうかにありました。というのも、私が就職活動をした当時はいわゆる就職氷河期の初期の頃。その後に比べれば、そこそこの大学を出たという事実があれば(贅沢さえ言わなければ)就職先が全く見つからないという状況にまではなっていなかった分、遥かにマシでしたけれども、誰しもが思うような職に就けたわけではなく、私の同期や友人関係でも、不本意な就職をした者の割合はかなり高かったです。私もかなり苦労をして、就職活動自体は2月くらいから始めたものの、最終的に就職先が決まったのは、8月も終わろうかという時期でした。が、まぁ、いずれにしてもそれで学生時代と決別する準備は整ったわけです。
就職して1年間は自宅から通える事業所だったので、バスと電車と徒歩とで通勤していました。途中ターミナル駅での乗り換えもあって、そこには大きな書店もアニメイトもあったから、私の「オタク」趣味はそこで満たされましたし、片道時間だけでも若干長めな通勤でしたけれども、その時間は読書に充てていたりしたので、大きな問題ではありません。むしろ漫研時代のように「オタク」趣味を大っぴらにできないのがストレスだったかもしれません。就職したのは何も知らずに飛び込んだ業界だったので仕事を覚えるのに一生懸命だった1年が過ぎ、そこでまた私に環境の変化が訪れます。そこの事務系職員が辞めてしまったという会社の都合で、100キロほど離れた他県の山の中の工場の受発注&加工指示の部署に転勤となったのです。当然、自宅から通うのは不可能だったので、工場事務所の上の階にある寮に入ることになりました。何と、通勤時間はわずか1分です。「職住接近」どころの話ではありません。寮には同じ工場の同僚が5人ほど一緒に住んでいて、相部屋ではなく個室でしたけれども食堂や風呂トイレは共有でしたし、まぁ、率直に言ってプライバシーがそこまで守られる環境では無いわけです。一応、アニメだったりCDだったりは、ヘッドホンをして視聴していましたが。
同僚はいい人が多くて、仕事終わりに飲み会(私はアルコールが駄目なので食べる専門&運転手役でしたが)に誘ってもらったり、寮の食堂でマージャンを教えてもらったりと、なかなか悪くない日々を送ってはいたのですけれど、工場のあるのが千葉の山の奥だったこともあって、「オタク」趣味を満たす買い物には非常に不便なのは否めません。おおっぴらに寮に通販を配達してもらうのは、この頃はまだ「オタク」は日陰者であったので憚られましたし、そういう意味で、「オタク」としての私はここで再び抑圧の中に置かれることになったのでした。また、会社員としての将来についても、このままだと一生この工場で勤務することになるかもしれないという危機感(もともと数年で本社に戻すという約束で異動したのが反故にされそうになっていた)もあったので、転職なりキャリアアップなりを考えて、この時期に私は、通信教育で簿記の勉強を始めています。そのことが、私の人生に大きな転機を呼び込むことになるとは、当初は全く想像もしていませんでした。
先々週紹介の第1巻に続き読んだ駒居未鳥の『アマルガム・ハウンド 捜査局刑事部特捜班』第2巻(KADOKAWA 電撃文庫)の粗筋は、「平和祈念式典で起きた事件を解決し、無事正式なパートナーとなった捜査官のテオと兵器の少女・イレブン。事後処理に追われる日々のなか、特別捜査官の下に『人体復元』を謳う怪しげな医療法人の存在が報告される。アマルガムの関与を疑ったテオたちは捜査の末、ターゲットが潜伏すると思われる豪華客船に潜入するが、事態は水面下で大きく動き出して――『あなたの役に立てるのであれば、それ以上のことはないわ』 捜査官と兵器の少女が凶悪犯罪に挑むクライム・サスペンス、第2弾!!」というもの。物語としては基本となる世界観とキャラ配置が終わったところで、ここから様々なエピソードを展開できる状態になったと言える段階なのですが、残念ながら、シリーズは第3巻には続かず、ここで終わり。面白いか面白くないかで言えば前者ではあったものの、もうちょっとストーリーテリングに奥行きが欲しかった第1巻、第2巻でしたし、イレブンに万能の変身能力があるという、少しこれはやり過ぎではないかと思われるくらいの能力を付与したにも関わらずそれを物語に生かし切れていなかったりもしたので、そういう「浅さ」がマイナスに働いてしまった、かなぁ。それでもどこかに「本作ならでは」と言えるものがあれば少しは違ったかもしれませんが、ここだけの特徴と呼べる程のものは、残念ながら感じられませんでした。完結第3部がカクヨム上で公開されているらしいので、一応、そちらも時間のある時に目を通してみようと考えてます。
正調のラノベ系スペースオペラのシリーズ第2作、榮織タスクの『銀河放浪ふたり旅 ep.2 宇宙ウナギ出没注意!』(KADOKAWA 電撃文庫)の粗筋は「惑星を喰らう宇宙ウナギの進行を阻止せよ!? 滅亡しかけの地球を離れ、人類最後の宇宙旅行――と突き進んでいたら、銀河超文明『連邦』と遭遇し、結果的に地球人を救うことになった男・カイトと相棒の機械知性・エモーション。二人の次なるミッションは、惑星を喰らう “宇宙ウナギ” の進行阻止!希少生物を保護したい『公社』と、惑星を守りたい『連邦』のどちらも超巨大すぎる道の生命体に手を焼く中――。『初めまして、僕はカイト』《――やあ、小さな異質なる方。初めまして。》 誰も成しえなかった宇宙ウナギとのコンタクトに成功し、友人に!? 未知との遭遇盛りだくさんのバディ・スペースジャーニー、第二弾!」というもの。第1巻の時から、最近はこういうのを見ないよなとつくづく思わされていた、逃げも隠れもしないスペオペです。しかも、登場するキャラが魅力的で、かつ面白いのですから、もう、最高であるとしか言えません。この痛快さを是非皆さんも味わってほしいので、もし書店で本作をみかけたら、迷わず購入して読んでみることをお勧めいたします。
人間六度の『烙印の名はヒト』(早川書房)を読了したのは先月の半ばのことだったのですが、そこから、ちょっとこれはきちんとした感想を書かなければと思っているうちに、半月余りが経過してしまいました。そんな本作の粗筋は、「介護施設で〈介護肢(ケアボット)〉として働くヒト型アンドロイド(ウエイツ)のラブは、ある日入居者のカーラ・ロデリック博士に依頼され、彼女を絞殺した。そして彼女は記憶が曖昧なまま訴追され、準一級殺人の罪で無期懲役の判決をくだされる。だが、ウエイツの思考は人を害するようにデザインされていないはずだった。なぜ殺人が起こったのか?人権を持たないウエイツが、なぜ “法で裁かれた” のか? 汚名を返上するために、“自らが人間でないこと” を証明すべく逃亡したラブは、ロボット排斥論者(ラダイト)との死闘や友人〈介護肢〉マーシーとの確執を経て、ヒトとAIの究極の関係性にたどり着く。 “介護(ケア)” の視点から人工意識の存在意義を指し示す、AIアクション思弁SFの極北!」となっています。本作は、ラブの物語を通して、フィクションの中に「ヒトになりたいAIが多すぎる(作者のXへの投稿より)」問題に1つの回答を示しています。それに納得するか、反発するかは読者次第ですが、私は「なる程確かにそういう面はあるよな」と感じ、納得したということは、書いておきます。そんな、非常に思索的で内向的なテーマを扱いながらも、あくまで本作はエンターテインメントであることに徹しているのも好印象。おかげで、500ページにもなろうかという厚さを一気に読み切ってしまいました。人間六度はこれまでにも魅力的な物語を何作か送り出してきていますが、間違いなく本作はここまでの最高傑作であり、1つの到達点であると言っていいでしょう。これは、「読む」に採り上げないわけにはいきません。本作の内容に関することというよりは、これおを読んで私がどう感じたのかが中心になった気もしますが、今回の更新で「読む」への掲載を行っていますので、よろしかったら、リンク先をご覧ください。
前巻を読んで以来、続きが出るといいなと思っていた、和ケ原聡の『エルフの渡辺』第2巻(KADOKAWA 電撃文庫)。「渡辺風花はエルフである。 悩める高校生・大木行人が姿隠しの魔法を破ったことで、呪われしエルフの使命――『魔王討伐』に再び向き合うことになってしまった。思いつめた表情の “エルフの渡辺” に気を揉む大木であったが、風花は突然『お泊りしたい』と言いはじめ……? 『……ま、魔王討伐に、必要なことだから!』 そんなわけあるか!謎多き少女の真意とは――。エルフな君と過ごす日常系ファンタジー、お互いに向き合う第2弾!」というのが、その裏表紙の粗筋ですが、内容的には新たなキャラが登場しつつ、状況が少し転がりだすという、まぁ、シリーズ化された2作目としては定番な流れになっています。すぐに「魔王」とか「世界の危機」とかを入れてしまうのは、あるいは作者の手クセかもしれませんが、それで作品のテイストがどうこうなっているわけでもないから、現時点ではあまり気にならないという感じ。この先も、本作についてはそっちにあまり舵を切らないで、あくまで日常的なコメディーで済ませて欲しい気がしないでもありません。あくまでここまでの2冊を読んだ時点での感想ですけれど。
3月発売、久し振りのコミックスとなった、阿久井真の『青のオーケストラ』第12巻(小学館 裏少年サンデーコミックス)。私はアニメ化を機に原作を購入した口であり、その時にはこの「雑記」に感想を掲載することはしていなかったので、今回が初の紹介ということになりますが、まぁ、本作の面白さについてはここで改めて書くまでもなく、皆さんの方がよくご存じかもしれません。おそらく次の第13巻では主人公と父親との直接的対峙が起こるのでしょうが、それがどのような影響を及ぼすことになるのか……次の巻はここまで待たずに出ることになるそうですし、アニメの第2期も今年はあるので、楽しみが増えました。
1月から3月まで放送されていたTVアニメもなかなかに好評だった、上山道郎の『悪役令嬢転生おじさん』第8巻(少年画報社 YKコミックス)を購入。アニメはひとまずの終了となりましたが、原作の方はまだまだ続くということで、この第8巻ではかなり大きな展開になっています。もとより主人公である グレイス・オーヴェルヌ/屯田林憲三郎 の暮らす世界が、どうやら単純にゲームそのものと同一ではなさそうだということはこれまでも何となく示唆されていましたけれども、ではたまたま類似しているだけの異世界なのかというと、そういうわけでもなさそうな出来事が、この第8巻のラストで発生したのです。これについてファンタジー的なものであれSF的なものであれ、一応の筋が通る説明・設定が用意されているのかどうかは分かりませんけれども、少し停滞していた物語が再び面白くなってきたという感じです。
佐原ミズの『ハネチンとブッキーのお子様診療録』第3巻(コアミックス ゼノンコミックス)を購入。シングルファーザーとパンキッシュな小児科医との交流などを描く本作ですが、題材的にどこかで描かなければならなかったとも考えられる、子供の発達検査についてのエピソードが何といっても今回は印象に残りました。私は独り者で子育ての経験がないので本作に対して「共感」というスタンスで接することは出来ないのですけれど、それでも十分楽しめるというか、面白く読ませてもらいました。






