
2025年9月~12月
[9月の雑記/10月の雑記/11月の雑記]
[一覧に戻る]
[今まで日々雑記で採り上げた読了本の一覧(その1/その2/その3)]

| 2025年12月27日(土) 充実度、高し |
今回の更新を以て、2025年の「雑記」は終わります。毎月の最終更新時には Top写真 を更新するのがこの「ぱんたれい」のお約束であり、それは年末であろうとも何も変わりませんから、恒例に則り、新しい画像への差替えを行いました。また、例年1月は寺社仏閣関係の写真を使うというのもちょっとしたマイルールにしていますので、今回もそういうモノを選んでみています。これがどこを撮影したものなのかというのは、例によって次回更新時に「あーかいぶ」にて書かせていただきますが、ここは明治になってから創建された比較的新しい神社で、ただ御祭神と創建された場所の由来もあって、結構なパワースポットとして知られているらしいです。
さて、今回は今年最後の「雑記」なわけですから、ざっと2025年の総括でもしておきましょう。それには、まず今年の頭に掲げたテーマを再確認する必要があります。
プライベートについて年始に打ち出したのは「健康を保つ」ということでした。軽度の高血圧等で定期的に病院に通って薬をもらったりしてはいますけれども、これについては、まずまず達成できているのではないかと思います。体重を70キロ台まで落とすことと腰回りの余分な脂肪をなくしていくことは道途上というか、体重は5キロは減っていますが目標達成にはまだまだ。ただ、後述する仕事の方の状況変化のおかげもあって、今年の後半くらいから身体のコンディションはかなり良くなっています。あまり急に体重その他を変動させるのは却って良くないだろうから、こんな感じであと1~2年で木業の達成を目指す感じでしょうか。
仕事面での大きな課題は、「働き方改革」でした。その為にDX等を推進して業務の効率化をするとか、手順を見直すとか、従業員の増員といったことを進めていこうということを書きました。これについては、ソフトのクラウドへの切替その他でDXが多少進んだものの手順見直しはほぼ手付かずで、ただ有難いことにベテラン職員を1名春に採用できたこともあって、私の過剰労働は少し改善されたかなというところ。まぁ、こういった辺りも来年以降も継続して進めていかなければならない事項と言えるでしょう。特に事務所業務の合理化については、先代からだとかれこれ30年は続いているアレコレを変更していくことなので、時間も手間も否応なくかかってしまいますから。
以上、2025年の目標とその現状を改めて確認してみましたけれど、こうして振り返ると、悪い1年ではない……というか、比較的良い1年だったと言っていいんじゃないかと感じます。読書とかCD鑑賞では良い本、CDに結構出会えましたし、一時期のように毎月ライブハウスに行くようなことはできていないものの、ライブ・コンサートにも少しずつ通いだしていますし。残りの人生がどれくらいかは分かりませんが、60歳前後で亡くなってしまう著名人の訃報等も多い昨今、元気なうちに充実した毎日を送りたいですしね、どうせ生きるなら。
今年は私の好むジャンルで結構色々な本が出て、それ自体はすごく嬉しいことなのですけれども、おかげで大分積読にしてしまった神林長平の『フォマルハウトの三つの燭台〈倭篇〉』(講談社 講談社文庫)を、ようやく読みました。「知能家電管理士である『ぼく』の仕事は、家電製品たちの仲を取り持つこと。きょうトースターが死んだ。自殺かもしれない。困り果てた『ぼく』と、友人で生来の自由人・太田林林蔵の前に現れたのは、角の生えた愛らしい兎。それは〈フォマルハウトの使い〉だという。日本SF界の巨匠が放つ想像力迸る野心作。」というのが裏表紙にある粗筋ですが、実際にはこれは、全部で3つあるエピソードのうちの、第1番目のものの内容。内容的には2番目のエピソード、3番目のエピソードと段階を踏んでどんどんと深みに入り込んでいきます。冒頭から饒舌というか冗長というかの語りで入り、ゆるい会話劇として展開していくところは最高に神林長平らしいなと思ったのですが、このクセの強さは読みにくさにも通じるものであり、実際、440ページあまりの物語の半分辺りまでは私も微妙に「読みづらいな」と思いつつページをめくっていました。まぁ、久し振りに読んだ神林作品だから、というのもあるかとは思いますが。一方で、文体に個性があるというのは悪いことではなく、本作についても神林節が目に馴染んできてからは、逆に「まぁでも神林長平はこうでなくては」ということも思ったりも。で、肝心の内容ですが……。虚実入り乱れるというか、幻惑的というか、野心作・意欲作であるのは間違いないのでしょうけれども、これ、読んでいて途中で投げ出す人も多いかもしれませんね。AIとシンギュラリティー、人間とAI、意識の所在、認識と実在とか、そんなことを考えるきっかけになるでしょうし、2016年に書かれた本作は生成AIがどんどん進化している今の時代にむしろ読まれるべきかもとも思うのですが、うーん、このクセの強さは、他人にはちょっと勧めにくいかも。つまらなかったわけではないけれど、手放しで面白かったとも言いにくいです。
京都を舞台にした大学生たちの青春譚、洲央の『京のたわけの神頼み 京都学生単位戦記』(小学館 ガガガ文庫)を読了。裏表紙の粗筋は「『これは京都で一番くだらない争いだよ』。単位に餓えるダメ大学生・不明門新は、謎めいた美人の先輩・墨染桜花と神社で出会う。そして、居合わせた同回生・笹屋町御蔭と共に気が付けば、大学生たちのバトルロワイヤル “単位争奪戦” に参加することになっていた! 十人に一人が学生の街・京都にて、愚かな単位の餓鬼たちは、今宵も全力で神頼み、戦いの後は酒場に繰り出し、飲めや歌えの大騒ぎ。名所を巡って、歴史を知って、勝てずに悩んで、デートして……青春の浪費を肯定する、たわけ者たちの祝祭的モラトリアム、ここに開幕!」となっていて、先人が数多く書いてきた京都を舞台とした、腐れ大学生モノの系譜に連なる作品であることがうかがえます。そのうえで、実際に読んでみると、ドタバタなノリよりもむしろ恋愛要素込みの青春小説としての印象が強く残りました。大きな仕掛けである「単位争奪戦」について、単位玉の奪い合いの描写が今一つ分かりにくいというか、何がどうなっているのかイメージしにくいというのはマイナス要素でしたが、全体的な読後感は爽やかで良好。あちこちに色々なパロディーを盛り込んでいるのだけれども、それをやるならば、ヒロインの桜花がアニメ好きであるというような描写があっても良かったかなという気も。サブヒロインの扱いが少し雑なのも難点ですが、基本的にかなり面白かったです。こういう大学生活、私は送れなかったなぁ……。まぁ、私の大学生活も、しっかり充実していましたし、恋人はできなかったけれども大事な友人は作れたし、非常に楽しいものではあったのですが。
何となく手に取って買ってみたらなかなか面白かったのが、福田和代の『空に咲く恋』(文藝春秋 文春文庫)。公式の粗筋は、「花火屋の実家を飛び出し、放浪の旅の末、新潟・山古志村に移り住んだ女性アレルギーのヘタレ男子・由紀。ある日、花火店の跡取り娘ぼたんと出会う。自信のない自分とは違う、勝気な彼女に段々と惹かれていき――。花火師は目指すライバル同士の恋のゆくえは?逆風に負けず、恋に仕事に全力投球!夏を彩る青春恋愛ストーリー。」となっています。つまりは、お仕事小説であり、自分に自信のない青年の成長物語であり、恋愛小説でもあるという、ちょっと欲張りな構造の作品と言っていいでしょう。展開も含め、色々なところが非常にベタ極まりないのですが、それを決して長いとは言えないボリュームで過不足なくかつ丁寧にまとめているので、安心して最後まで楽しくページをめくらせてもらうことができました。余談ですが、花火師の物語というとちょっと前にも美奈川護の『ギンカムロ』(集英社 集英社文庫)を読みましたが、何らかのトラウマ等を負った若者と花火師モノというのは相性がいいのでしょうか、どちらも似た路線だった気がします。
シリーズ2冊目の短編集である、餅月望の『ティアムーン帝国物語 断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー 短編集』Ⅱ(TOブックス)。「『「続・女帝ミーアの箴言集」の草稿が、ついに完成しました』『ふむ、わたくしが確認しますわ』(クソめがねには、任せておけませんわ…!) 女帝になったミーアは、ルードヴィッヒが纏めた原稿を読み進める。美辞麗句に赤字を入れつつも、ページをめくるたびに蘇るのは、若き日の思い出――。知られざるエピソード満載の短編集、大人気につき第2弾が発売!第10~16巻特典短編や舞台&ドラマCD特典短編など、単行本未収録の短編計23本!望月望による描き下ろし閑話を多数収録!」というのが裏表紙の作品紹介。本筋には関わってこない、新刊の店舗特典等の為に書かれたSSをまとめた1冊なわけですが、最近はこういうのをきちんと本にまとめてくれるので、凄く助かっています。さすがにそれ等全てを集めるのは困難なわけですし。まさか本編を読まずにこちらに手を出す人はいないだろうという前提で、様々な登場キャラのちょっとした楽しいエピソードを読めて、ファンとしては素直に嬉しいのです。
長かった銀夜祭編がやっと終わる、白浜鴎の『とんがり帽子のアトリエ』第15巻(講談社 モーニングKC)。ここで「やっと」と言ってしまう辺りに私の本音が出ているのですが、ここで描かれたことが無駄になったり冗長な蛇足になったりするのか、それとも今後の展開にとって重要な、捨てる部分の何一つないくらいの重さを帯びるのか、それはまだ分かりません。おそらく本作全体の構成上もかなり重要なエピソードになるのだろうということは予想ができるものの、現時点では、1つのエピソードに随分かかったなという気持ちの方が強い、かなぁ。つばあり帽の思惑とか、人と魔法の力関係とか、キーフリー先生の隠していたこととか、今後の展開に大きく関わるであろう変化もあった第15巻。次のエピソードがどういうものになるのか、ここはかなり大事なところでしょう。
高校時代の美術部仲間とやることになったグループ展で、主人公がプロ作家を目指すことについての自覚を深める、山口つばさ の『ブルーピリオド』第18巻(講談社 アフタヌーンKC)。もちろんこれはアートの世界の物語ですけれども、「創作をする」ということを多少なりとも経験してきたような人にとっては、かなり心に刺さる内容だったかもしれません。私程度でもそうなのだから、プロを目指している/目指したことがある、あるいはアマチュアでの作品発表を続けている、というような人には、なおさら。
今一つ人気が出ず、コミックス第1巻の売上もそこまでではなかったのか、第2巻での終了となってしまったヤマモトマナブの『嘘から出た真琴』第2巻(少年画報社 YKコミックス)を購入。「嘘つき高校生・新倉健介が《嘘》から生み出してしまった《嘘》の彼女・風晴真琴と、健介と両思いの八重樫幸香の奇妙な三角関係が続く波乱万丈の学生生活であったが、ネット動画サイト『人類滅亡チャンネル』による《嘘》の流布により、本当の《人類滅亡》の危機が訪れる……その時、健介たちは!? ヤマモトマナブが贈るファンタジーコメディ完結の第2巻!!」というのが、裏表紙の粗筋です。私もこの「雑記」で第1巻の感想を書かなかったので、「どの面下げて」という話ではあるのですが……実は、結構好きな作品だったので打ち切りはちょっと残念です。それでも、編集部の尽力もあって物語は綺麗に幕を下ろせる形で完結を迎えられたのは不幸中の幸い。作品としての彩りを深めるべく想定されていた複数の日常系のエピソードが描かれない形での締めくくりとなりましたが、その分、物語としてはコンパクトに、濃密にまとまったと言えるのかもしれません。それが作品にとって良いことだったのかどうかは、描かれなかったエピソードを読んでいない以上コメントしにくいところですが、世に出たこの第2巻を読む限りでは、状況下でベストな終わり方を迎えられたとは言えそうです。
最近のマイトレンドである、大人買い&プログレ熱によるアルバムの一気購入、本年の最後となるのが、BIG BIG TRAIN の既存のアルバム(EP含む)16枚購入。在庫が無いことで一部手に入らないものもありましたが、これで BIG BIG TRAIN については概ねコレクション的に一通り揃ったことになるわけです。まぁ、我ながら、16枚を一気に買っているのはどうかと思うところもありますが……。なお、具体的なアルバム名も一応列記しておくと、リリース順に、『English Boy Wonders』、『Bard』、『Gathering Speed』、『The Different Machine』、『The Underfall Yard』、『Far Skies Deep Time』、『English Electric Part One』、『Englich Electric Part Two』、『WASSAIL』、『Folklore』、『Grimspound』、『The Scond Brightest Star』、『Grand Tour』、『Common Ground』、『Welcome To The Planet』、そしてライブ盤の『ARE WE NEARLY THERE YET? -LIVE AROUND THE WORLD-』となります。ここまでまとめて買って立て続けに聴いていると、脳内が BIG BIG TRAIN のプログレに染まってきてしまうのですが、音楽的に好きだからこその大人買いなわけで、まぁ、そういう日があってもいいですよね。メロディアスなプログレにどっぷりと浸って過ごすことができて、個人的にはなかなか至福の時間となりました。傍から見た場合にどう思われるかは、ともかくとして。
森口博子の『Your Flower ~歌の花束を~』は40周年のアニバーサリーアルバムということで、これまでの彼女のヒット曲を手がけた作家が再集結して新曲を提供するという、まさしくお祝いムードに満ちた新譜になります。年齢的にもそんなに派手な曲はやらないというのもあるだろうし、彼女の場合は圧倒的な歌唱力と美しい歌声を堪能するのが正しいファンとしての在り方というのもあって、収録されている曲はどちらかというと「聴かせる」タイプのものが多いという印象です。その分、アルバムとしてのインパクトはやや弱めですが、じっくりと味わっていける、噛めば噛むほど味が出るスルメ的な佳作になっているのではないでしょうか。
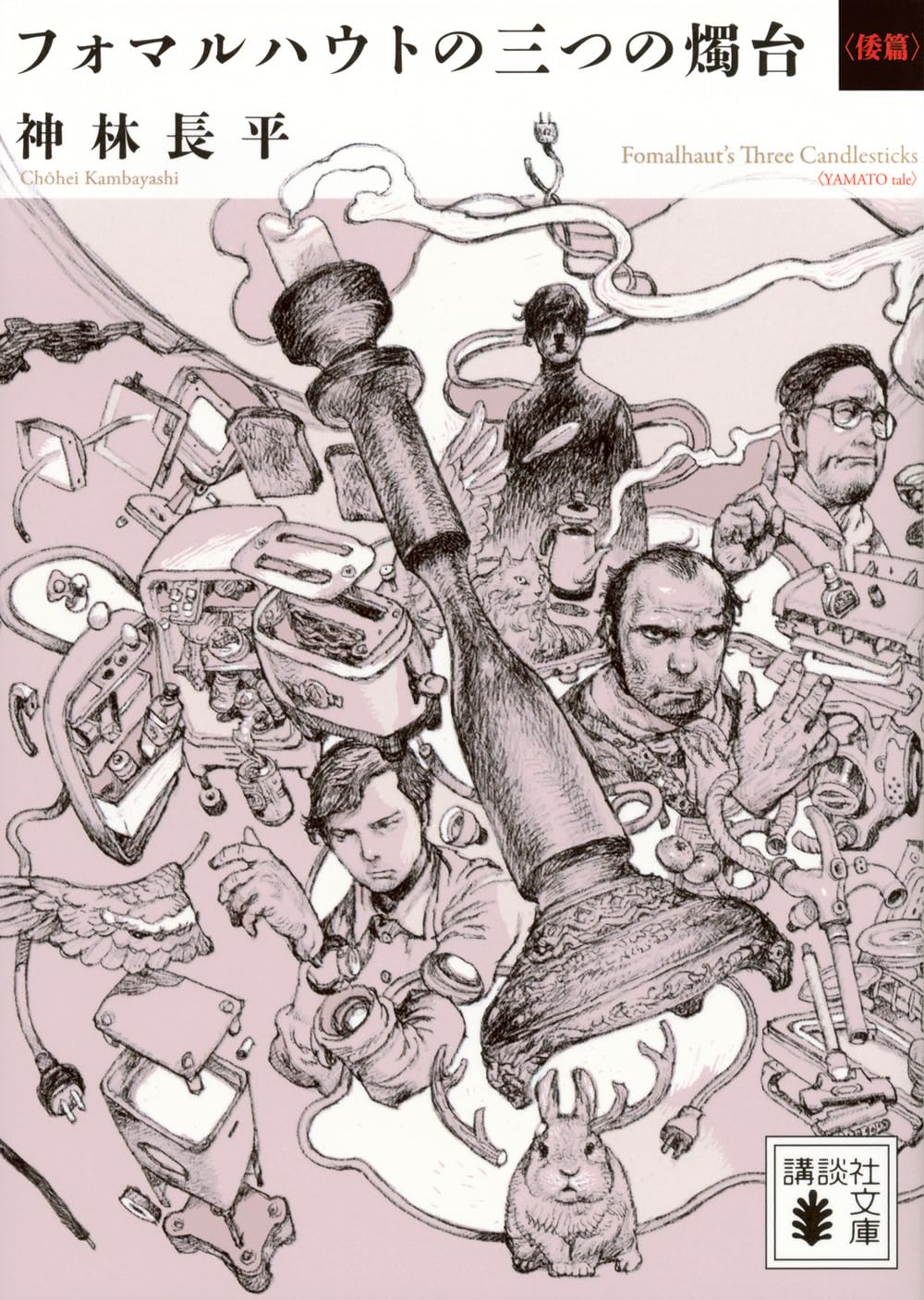





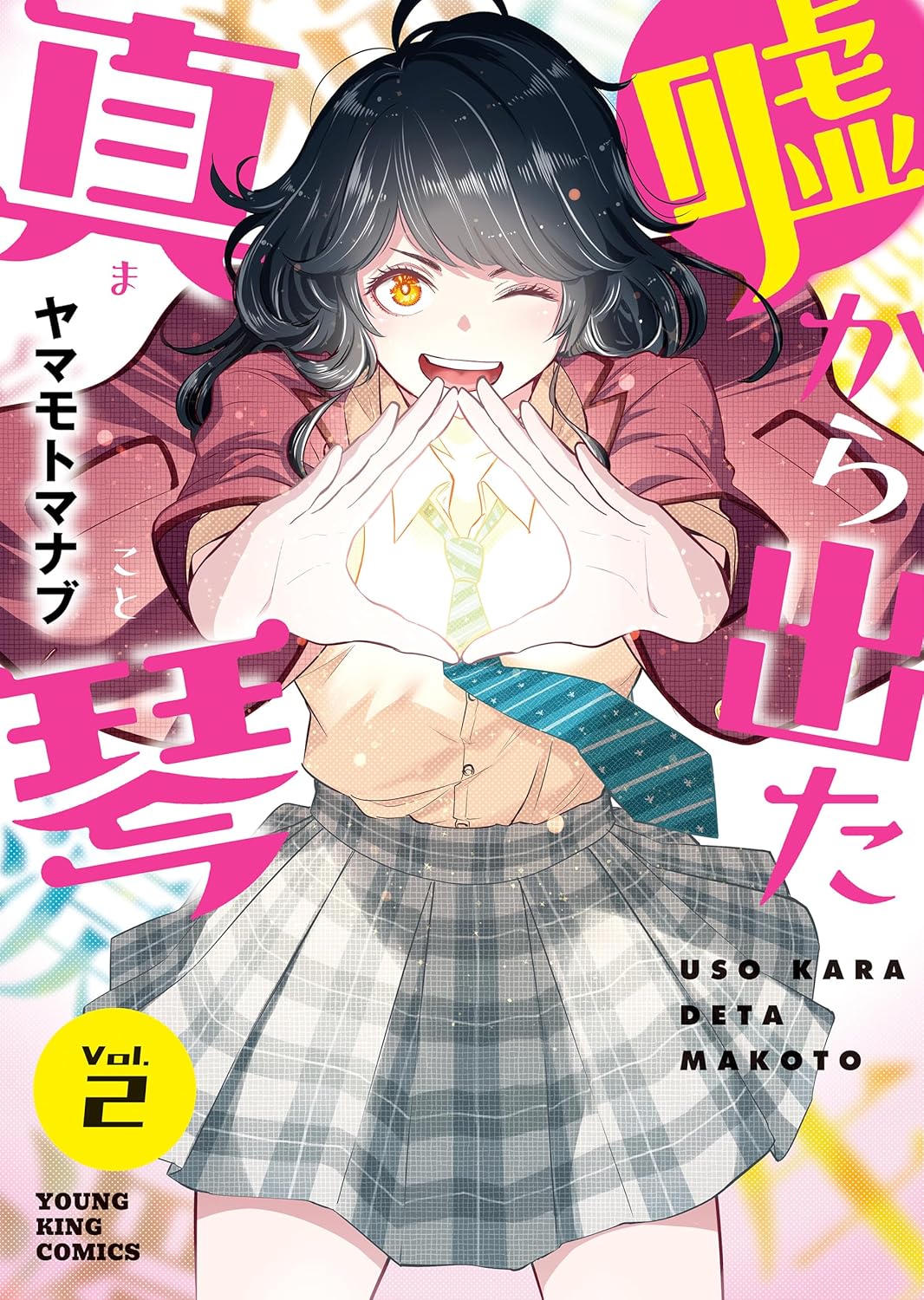
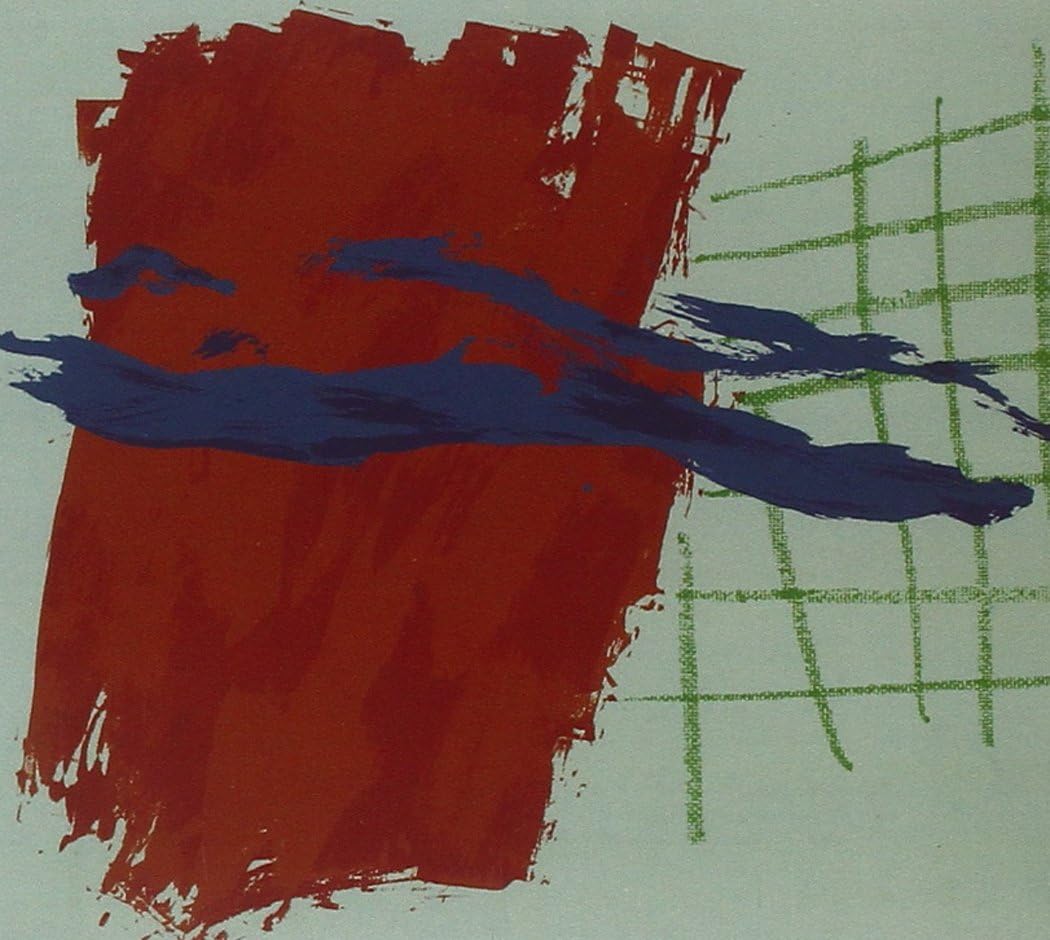



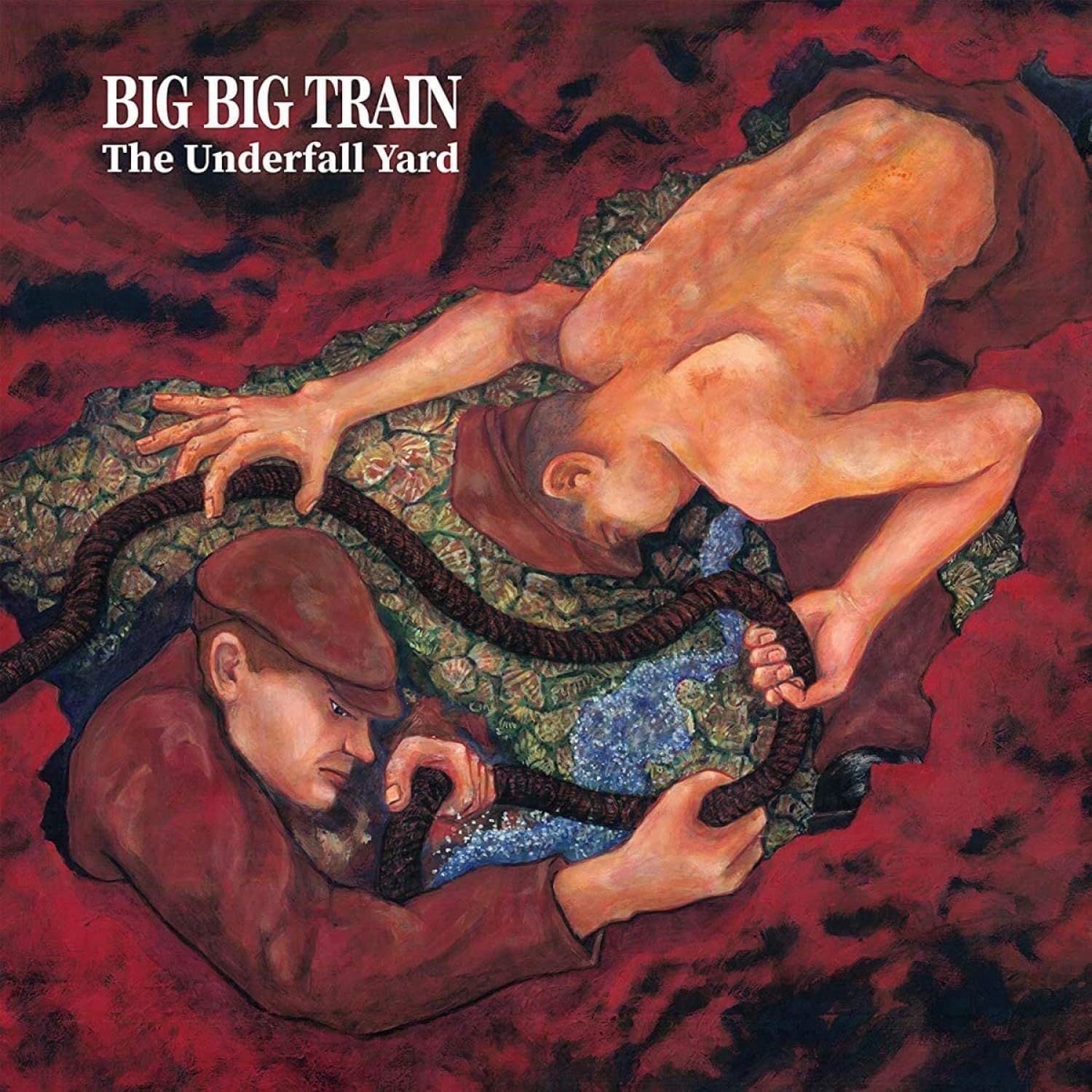


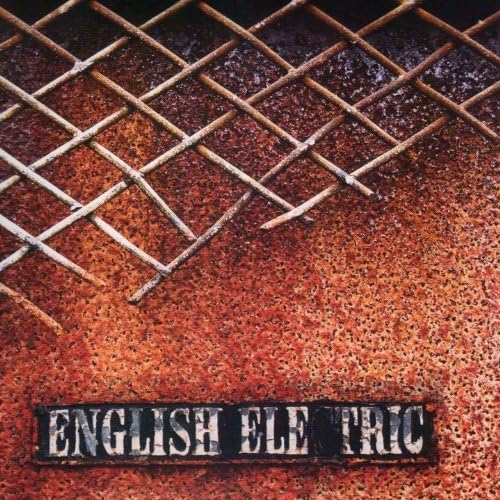









| 2025年12月20日(土) 続:優遇と自尊心 |
11月22日の「雑記」に書いたことの続き、というか、延長上の話なのですが、クオーター制に対する世間の意見をリサーチしている時に、「Quality じゃなくて Quantity」 という発言を目にしました。確か、イベント時等で男子トイレには列が出来ていないのに女子トイレには常に長い列ができているよね、という話から、様々な施設での男子トイレと女子トイレの数の違い、広さの違い等に関して出てきたものだったと記憶しています。その施設がどのような層をターゲットにしたものなのかでそもそも事情が大きく異なるとは思いますが、概ね、広く一般が利用するようなところでは男子トイレも女子トイレもほぼ同じくらいの面積を割り当てられているだろうということが前提になりますが……。だとして、男子トイレには個室の大便器だけでなく横に並んで設置された小便用の便器があるのに対し、女子トイレには個室の方しかないから、便器の数に圧倒的な差が出ることになってしまうというのが、この発言の背景になります。一説によれば女性の方が男性よりもトイレの1人当たり所要時間が2.5倍だということで、その結果として女性用トイレの回転率が男性用と比べて悪いというのもあるのでしょうが、それはそれとして、そもそもの便器数の話については、確かにその通りの事実なので否定するようなことでもありません。それに、小用でトイレに入る時にどこまで服を脱がなければならないか等の肉体構造の違い考えれば、利用時間に差が出ること自体は納得できます。とはいえ、2.5倍というのは、さすがにそれだけのせいではない気もしてきます。そうなってくると、(別に私オリジナルの「気付き」ではなくて、世のあちこちで言われていることですが)トイレの使い方そのものに男女差があるのではないか、ということに当然なりますよね。
トイレの鏡で化粧直しをしたりする分だけ女性は時間がかかるという説については、個室の利用時間の長さとイコールではないだろうから話半分以下で扱うとして、嘘か本当か、女性は個室の中でスマホをいじっていて、その分だけ時間が長くなるんだ、なんて話も聞きます。仮にそれが本当であるならば、便器の数だけ揃えればいいという単純な話ではなくなります。長い行列の解消が最終目標だとして、不必要に個室を長く使うことを排除するには、トイレ内は一切のネットを遮断するということも併せてやる必要性が出てくるかもしれません(案外、それは副次的に盗撮カメラの設置防止にもなるかも)。そこまでやって、トイレでは基本的に排泄行為以外のことは最小限しかやらないという環境を作ってからでなければ、「平等」云々ということを本当の意味で数値的には測れないでしょう。その「平等」に、そうまでして追求する価値があるかどうかは、また別問題として。
あれこれ書いていますけれども、男女平等を社会の様々なところでできるだけ達成するということ自体には私は賛成のスタンスです。その過程で女性側にプラスになる傾斜が付けられがちなことについても、身体的な差がある以上はバランスを取る意味である程度の配慮はして良いとも思っています。ですが、一方でそういう風潮に甘えて(図に乗って、という言い方でもいいかもしれません)過剰な配慮、男性への逆差別になるようなレベルのことまで要求する一部の(声の大きな)政治家や思想家には、私は否定的です。そういう逆差別的な方向で優遇し、それでやっと「平等」が達成されるのだとすることって、昭和以前の女性を有効戦力と見做さない「お嬢さん」扱いと構造的には同等じゃないでしょうか。要するに、下駄をはかさないと駄目な存在だと言っているに等しくなるわけですから。むしろ甚だしく屈辱的なこと、許容しがたいことなのではないかと、私などは思うのですけれど。私がかつて色々と調べて「共感すべきところも多いな」と思ったウーマンリブやフェミニズムは、そういうことを毛嫌いしていたはずですなのですが。
同じようにとんでもなく屈辱的な措置だろうと思う事例というと、例えばホストに貢ぐ為に犯罪行為をした、自己破産をしたというような女性に対して法的救済を等という動きが挙げられるでしょう。これって、私には判断能力がありません、だから(法的)責任能力もありません、と言っているのと同じですよね?それで返す刀で役員や議会の議長その他の重職ポジションに女性枠を作れとおっしゃられても、そんな、判断能力も責任能力もない人を重職や公的職務には就かせられない、という話になってしまうわけですが、本当にあなた方はそれでいいんですか?ちなみに現在の民法では成人年齢は18歳です。そして(条文などに明記されているわけではないようですが)一般に、刑事責任能力は14歳以上から、民事上の責任能力は過去の裁判事例などから12歳以上に認められるとされています。つまり、上記の法的救済論を言い換えるならば、女性は何歳になっても12歳未満の精神性しか持っていないと主張しているということになるのでは?そういうことではなく、悪い男に騙された被害者救済の観点だというのならば、全ての詐欺事件の被害者に対して同じような救済を求めるのが筋ですし、そこまで行かずとも最低でもキャバ嬢にハマって持てる金銭の全てを貢いだり、頂き女子のような疑似恋愛を利用して男性から金銭等を巻き上げようという女性に入れ込んで破産状態になった男性にも、同様の法的な救済が無ければなりません。それが、「平等」ということですよね。
斜線堂有紀の『詐欺師は天使の顔をして』(講談社 講談社タイガ)の粗筋は「一世を風靡したカリスマ霊能力者・子規冴昼が疾走して三年。ともに霊能力詐欺を働いた要に突然連絡が入る。冴昼はなぜか超能力者しかいない街にいて、殺人の罪を着せられているというのだ、容疑は “非能力者にしか動機がない” 殺人。『頑張って無実を証明しないと、大事な俺が死んじゃうよ』彼はそう笑った。冴昼の麗しい笑顔に苛立ちを覚えつつ、要は調査に乗り出すが――。」というもので、要するに現実世界とは異なる様々な異世界で起きた殺人を巡る、特殊ミステリーの1つと言っていいでしょう。こういう作品の場合は探偵役の設定とか、トリックとかがキモになってくるわけですけれども、そこは「講談社タイガ」という、ちょっと年齢を重ねたラノベ読者・ティーンズ文庫読者を対象にしたレーベルらしく、いかにもキャラクター小説ライクなものとなっています。特に、例えばこれは同様のポジションにあるメディアワークス文庫などもそうなのですけれども、レーベル創設当時から年数を重ねるにつれて段々と純然たる男性読者向け作品が減っていく傾向にある(と私は感じているのですが)中で、女性読者の存在を強く意識したもの、つまり少々BL的な香りの漂うものになっているところが、特徴といえば特徴になるでしょうか。とはいえ、それはそれで他にも類似の作品はあるので、物珍しさはそこまででもありません。結局のところ、謎解きとしての痛快さがどれくらいのものか、誰もが超能力を使えるという世界で起きた殺人の真相がどういうものなのか、そこにどれだけ面白さを感じられるかが勝負所となってきます。その点で本作は、まずまず面白かったと言ってよく、どうせならば詐欺師設定をもっと生かし切れれば更に良かったろうにというところが残念ではありますが、満足のいく読書体験をさせてもらいました。いっそシリーズ化とかされてくれてもいいのにと私としては感じますが、本作が2020年1月に出てからここまで音沙汰がないということは、そこまでセールスは良くなかった、のかも。
第19回小学館ライトノベル大賞の優秀賞を受賞した、塗田一帆の『1/nのワトソン』(小学館 ガガガ文庫)。受賞後の改稿を経て一旦は決まった発売日が、予定されていたイラストレーターが問題を起こした為に延期、結局イラストの担当を変更して11月に刊行されることになったという、ちょっといわくのある作品。その粗筋は「探偵系Vtuber『ほむるちゃん』。彼女のもとには視聴者からの一風変わった依頼が舞い込んでくる。それを解決するのもまた視聴者であり、1万人の『ワトソン』たちが “正解” を目指して競い合う。エンジニア男子・啓×Vtuberオタク女子・ひかりの幼馴染コンビが、インターネットを、ゲームの世界を、メタバースを、そしてリアルを駆け抜ける――。なんでも有りなアンチミステリ・インターネットバトル、ここに開幕!」というもので、早川書房から出した『鈴波アミを待っています』に続いてVtuberモノということですが、その辺は、著者の活動を調べてみると「なる程、Vtuber文化に対する思い入れがかなり強いのだな」と頷けます。最優秀「ワトソン」の座を争うライバルとの白熱し手に汗握るような競争などがもっとあると、より私の好みだったかもとは思いますが……。まぁ、作者自身が「アンチミステリー」であると宣言している作品で、人間関係とか、ネット・AI時代に起こり得るトラブル、技術の可能性と同時に潜む危うさとか、そういうところをエンターテインメントなラノベに落とし込んで描くことが本作の裏テーマだったりしたのだとすれば、謎解きの部分には実はそんなに重きは置かずに書かれたのであろうことは納得できますね。もちろん、それは私の勘違いである可能性も否定できませんが。結構面白く読めた、佳作です。
同じく、第19回小学館ライトノベル大賞の優秀賞を受賞した、宮下愚弟の『名前のない英雄』(小学館 ガガガ文庫)も読了。邪を祓う英雄が活躍するその前、英雄が戦う前段階に力を尽くし命を落とした無名の者たちを描くというコンセプトで書かれたという本作の粗筋は「凶暴な怪物『邪族』と人類が戦いつづける混迷の時代。辺境の山奥で、不治の病を抱えた妹と二人暮らしをする少年がいた。貧窮する生活のなか、少年は〈勇者の剣〉探しの道案内に手を挙げる。報酬は妹の治療。しかし――「あなたには死相が視える。任務についてくれば命を落とすでしょうね」〈勇者の剣〉を探す特務分隊のひとり、〈魔眼〉の少女から死の予言を告げられる。それでも少年は同行を決意する。全ては妹のために。特務分隊の任務は、行方不明の〈勇者の剣〉を探し出し、前線の勇者へ届けること。残る時間は、あと数日。いまも、勇者は手元の剣を次々と使いつぶしながら『邪族』に立ち向かっている。道案内だったはずの仕事は、捜索の手助けを経て、ついには狙われた〈勇者の剣〉を抱えての逃亡劇へと変わり――ただの村人だったはずの少年は『名前のない英雄』となる。命を懸けて“希望”を届けろ。勇者でなくとも、世界を救うために。これは歴史には残らない、英雄たちの物語。」というもの。ストーリーラインは敢えて王道かつシンプルなものにして、キャラクターの生き様に焦点を合わせて語るようにしたということで、斬新さ等は確かに無いものの、オーソドックスならではの良さがありました。
「スライム倒して300年~」シリーズは現時点では追いかけていないので、かなり久し振りに単著の書籍を読むことになった、森田季節の『異世界エルフと京大生』(星海社 星海社FICTIONS)。発売日は昨年の7月であり、私としてもその時点で買っていたのですけれど、何だかんだで実際に読むのはこのタイミングになってしまいました。個人的に、彼の尖った単巻作品は結構好きだったので、これはどうかなと期待感を持って読み始めた本作の粗筋は、「小説家志望の京都大学二回生・真中英勝は、南禅寺裏手の山道を散歩していたところ気を失ったエルフと遭遇――!?神官のアスライナと名乗ったエルフは、なぜ異世界転移をしたのか心当たりがない……。真中くんは路頭に迷う彼女――アスラさんを見捨てられず、異世界に帰還する方法を見つけるまでの仮宿として聖護院のワンルームの同棲生活をスタートすることに!京大生&異世界エルフの、ほのぼの京都ライフが開幕!」というもの。例えば『ともだち同盟』(角川書店)や『ウタカイ 異能短歌遊戯』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)といった過去作のような尖り具合はあまりなくて、どちらかといえば角の取れたまろやかな作風で、京都のパワースポット紹介的なところがあるのは、『てらめぐりぶ?』(白好出版)に近い、と言えなくもないかも。こういう作品、個人的には結構好きなのですが、毒にも薬にもならない感があるから、セールス的にはどうなのかな……。設定に新鮮味もあまりありませんし。
先々週の第1巻に引き続き読んだ理不尽な孫の手 の『オーク英雄物語 忖度列伝』第2巻(KADOKAWA ファンタジア文庫)の裏表紙の粗筋は、「『大切なもの』を捨てる旅に出たオークの英雄バッシュ。次なる華米候補を求め辿り着いたエルフの国で、相棒のフェアリー・ゼルから衝撃の事実を告げれる――。 『今、エルフの国では異種族との結婚がブームらしいっす!』 千載一遇の好機をモノにしようとするバッシュだが……。金が必要と分かり、ゾンビ狩りをして金を稼ぐことに。 『俺はまた、お前に会いに来る』『私に会いに……だと!?』 そして選ばれた花嫁候補のサンダーソニア。しかしバッシュは彼女が、かつての戦争で自分が倒した大英雄であることを知らず……。WEB上で屈指の人気を誇るヒロイン本格参戦!」というもの。ヒューマンの次はエルフ、というわけで、今回も嫁探し、脱童貞を目的にオークの英雄の珍道中が繰り広げられるていきます。とりあえず、こういう形で各種族から嫁候補が出てくるというのが当面の流れとして、どこまでバラエティー性を持たせられるかという問題がありますけれど、そこはそれ、各種族の特徴と絡めてやっていけば、ひとまず一巡するまでは、この路線で引っ張ろうと思えば行けそうですが……まぁ、どこかでさすがに別路線に転じるのでしょう。それで物語がどうなっていくのか、これはなかなか楽しみです。
柴堂恭子の『辺境警備前史 ~銀のイリュージオ~』第1巻(秋田書店 BONITA COMICS)は、さすがに主人公というわけではないものの、まだ中央で活躍している頃の美形な隊長さんことサウル・カダフが登場する作品。「活気のある炭鉱町で暮らす少年クリスと少女リュナ。慎ましいけれど、幸せな毎日を送る二人だったが、突然リュナは閃光とともに姿を消してしまう。同時にリュナの母も村からいなくなってしまい…。」というのが裏表紙にある粗筋なのですが、ここからどのように『辺境警備』(KADOKAWA あすかコミックスDX 全6巻)に繋げていくのか、あるいは作品世界が一緒でサウル・カダフが出てくるだけで、ストーリー上は直接的な繋がりは無いのか。それは第2巻以降を読んでみなければ分からないところです。
ノリにノッてきている、市東亮子の『やじきた異世界道中記』第4巻(秋田書店 PRINCESS COMICS)。魔族国側の事情も語られましたし、人間側のうさん臭さも増していて、さて、ここから物語はどのように転がっていくのか。やじさん と きたさん は今巻で合流していますが、ここに雪也たちも合流すると、さすがに悪だくみ側に勝ち目は無さそう、かな。ある種、俺TUEEE系の展開ではあるのですけれども、本編からの流れとか、そもそも「やじきた」の場合は やじさん と きたさん が無双状態に活躍することが読んでいる側の快感になっているわけだから、むしろそうでなければならないとも言えます。まだ物語は序盤を抜けたくらいの感じなので、この作品が全何巻になるのかは何となく想像するくらいしかできませんけれど、いずれにせよ、最後までバッチリ楽しませてもらえそう。
2025年は大人買いの年、と決めたわけでもないのですけれども、ここのところ、これまで手元にしていなかった音源を一気に購入するということが増えています。まぁ、これはおそらく色々なストレスの蓄積のせいだろうと自分では分析しているのですが、分析をしたからといってそれで購入を止めているわけではないという辺りに、我ながら「業」のようなものを感じないでもありません。で、そんな前振りで始まる今回、購入を報告するのは、サカナクション。彼等の(配信モノ以外の)オリジナルアルバム7枚を、一機購入いたしました。発売順に並べると、『GO TO THE FUTURE』、『NIGHT FISHING』、『シンシロ』、『kukUUiki』、『DocumentaLy』、『sakanaction』、『834.194』となりますね。エレクトロポップ、テクノポップ、ニューウェイブという辺りのジャンルになるのでしょうか(それだけでもない気もしますが)。個人的には、これまでサカナクションといえば「新宝島」が代表曲で音響に拘っているというイメージが強くて、悪い曲ではないけれども私の好みからするとちょっと外れるかな、と思っていました。が、昨年から今年にかけて放送されたアニメ『チ。―地球の運動について―』のOPだった「怪獣」が御多分に洩れず私のツボにもハマったので、これは一度、先入観を捨てて彼等の音楽と向かい合わなければならないかと思った次第。結果、抱いていたイメージが外れだったわけではないけれど、これは思っていた以上に奥の深いバンドだぞ、と今は感じています。これからゆっくりじっくり、揃えた音源を聴き込んでいって、私にとってのサカナクションの位置づけを定義しなおしていかなければならないでしょう。
鈴木博文の4枚組ライブアルバム『Fou FEVER』を購入。これは鈴木博文 with カーネーションとして開催された「Wan-Gan King Live 2017」と、鈴木博文単独名義の『Wan-Gan King Koki Live 2024』という、それぞれ2枚組のライブアルバムをセットにして4枚組として発売するというもの。値段が8,800円と、決してお安くは無いのがネックといえばネックですが、収録時間も多いし、内容的にも実に良いライブ音源になっていますから、1枚当たり2,200円と考えれば、むしろお買い得かも?鈴木博文の音楽、特にソロでやっている音楽は万人受けするようなものとは少々違うので、誰にでもお勧めとまでは言えないところはありますが、このライブ盤は、ファンなら必携、絶対に買うべきものですね。















| 2025年12月13日(土) 2025年の10冊と10枚 |
毎年12月の半ばになるとお約束企画としてやっている、雑誌などでもよくある「今年の〇〇ベスト10」を、今年もいつものようにやろうと思います。対象となるのは昨年の同企画終了から先週までの間にこの「雑記」で紹介してきた本やCDで、それぞれ10ずつを選んでいます。なお、これは別にこの期間中に新たに発売されたものを対象としたのではなくて、あくまでその期間に「雑記」で紹介した、つまり私がこの1年で新たに読んだり聴いたりしたものからのセレクトであることと、順位付けが目的では無いので、10冊(10枚)を選んではいますが、特にその中でのランキングは行っていません。以下に選んだ本とCDのリストを掲載していますが、それは当初の紹介日の順番をなぞっているのであって、面白さの順位とか、そういうものとは無関係です。
この企画……お遊びは2004年からやっていますので、つまりもう20年以上続けていることになりますね。始めた当初はこんなに継続するとは思っていなかった、というか、そもそもこの「ぱんたれい」そのものをここまで長く続けるとは思っていなかったので、何だか不思議な気分にもなります。どうせならば、このまま25年、30年と、やれるところまでやるつもりですが、要は出たとこ勝負ですね。そんなわけで、2025年のセレクト、まずは書籍の方から始めたいと思います。
<2025年の10冊>
・ 四季 大雅 『クラスで浮いてる宇良々川さん』(2025/1/25)
・ 陸 秋槎 『喪服の似合う少女』(2025/2/15)
・ 人間 六度 『烙印の名はヒト』(2025/5/3)
・ 天沢 時生 『すべての原付の光』(2025/5/17)
・ 十三 不塔 『ラブ・アセンション』(2025/5/24)
・ 藤井 太洋 『まるで渡り鳥のように 藤井太洋SF短編集』(2025/7/19)
・ 長谷 敏司 『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』(2025/8/23)
・ 大武 栄一 『ニュー忍者ロード』上下巻(2025/9/13)
・ 立川 浦々 『ミドルノートにさよなら』(2025/10/4)
・ 飛鳥部 勝則 『堕天使拷問刑』(2025/11/29)
いつもの面々に、若干の新規が加わったという感じですね。SF系が多いのは私の趣味がそちらにあるからなので、ご照射ください。どれも自身を持って皆さんにお勧めできるものばかりだと思っていますので、リンク先の個々の感想を読んで興味を抱かれた方は、是非、購入してご一読の程を。今回、惜しいところで選外としたのは、宮西建礼の『銀河風帆走』(2025/1/11)、カスガの『コミケへの聖歌』(2025/3/29)、大倉崇裕の『怪獣殺人捜査 殲滅特区の静寂』(2025/4/5)、逢坂冬馬の『ブレイクショットの軌跡』(2025/7/26)、新馬場新の『歌はそこに遺された』(2025/9/6)、知念実希人の『機械仕掛けの太陽』(2025/11/22)の6冊。つまり2025年の読書歴も、非常に豊作だった、ということですね。コミックをセレクト対象に入れていない状態で、これですから。
続けて、2025年の10枚を。CDは、新譜ももちろん購入しているのですが、大人買いで一気に揃えるケースが多いので、色々と手に入れて色々と聴いたなぁという感覚があるわりに、選ぶのはそんなに迷わずに終わりました。一応、1ミュージシャンで複数選ぶというのは、NGにしていますので。それでは、リストをご覧ください。
<2025年の10枚>
・ THE CURE 『Songs Of A Lost World』(2025/1/4)
・ BUCK-TICK 『スブロサ SUBUROSA』(2025/1/25)
・ Perfume 『ネビュラロマンス 前篇』(2025/2/8)
・ ERA SPECIAL 『Gleams』(2025/3/22)
・ EPICA 『ASPIRAL』(2025/5/31)
・ 金属恵比須 『虚無回廊』(2025/7/26)
・ PINK FLOYD 『The Division Bell』(2025/8/9)
・ THE ROOSTERZ 『KAMINARI』(2025/9/6)
・ EMERSON, LAKE & PARMER 『BLACK MOON』(2025/9/19)
・ 核 P-MODEL 『Unzip』(2025/11/15)
次点、というのとはちょっと違いますが、Perfume については10月18日に紹介した『ネビュラロマンス 後篇』も良いアルバムでしたし、両方を併せて1つの作品、という考えも成り立つでしょう。また、大人買いしたミュージシャンの中には、このリストに含めるか否かを迷ったものも幾つかあったのですが、それは一気に購入した複数のアルバムをまとめて評価、というようなところがあったものですから、今回はリスト掲載を見送らせてもらいました。今後、新譜が出れば……って、さすがにもう新譜の出る見込みがないようなミュージシャンが多かったりするのですが、まぁ、そこはそれ。
というわけで、2025年は大体こんな感じで本を読み、CDを聴いて過ごしてきました。ここ数年は読書と音楽鑑賞という趣味のジャンルで非常に充実した日々を送れているのがとても有難く、できれば来年以降もこれが継続していけばいいなと思っています。本については、「ぱんたれい」運営開始以前に買ったことで「雑記」に未掲載なものの個人的に好きな作品を、再読して掲載していこうと昨年くらいから思っていつつも、なかなかそれが進んでいない実情もあるから、その辺りの改善も、1つ大きなテーマになりますね。










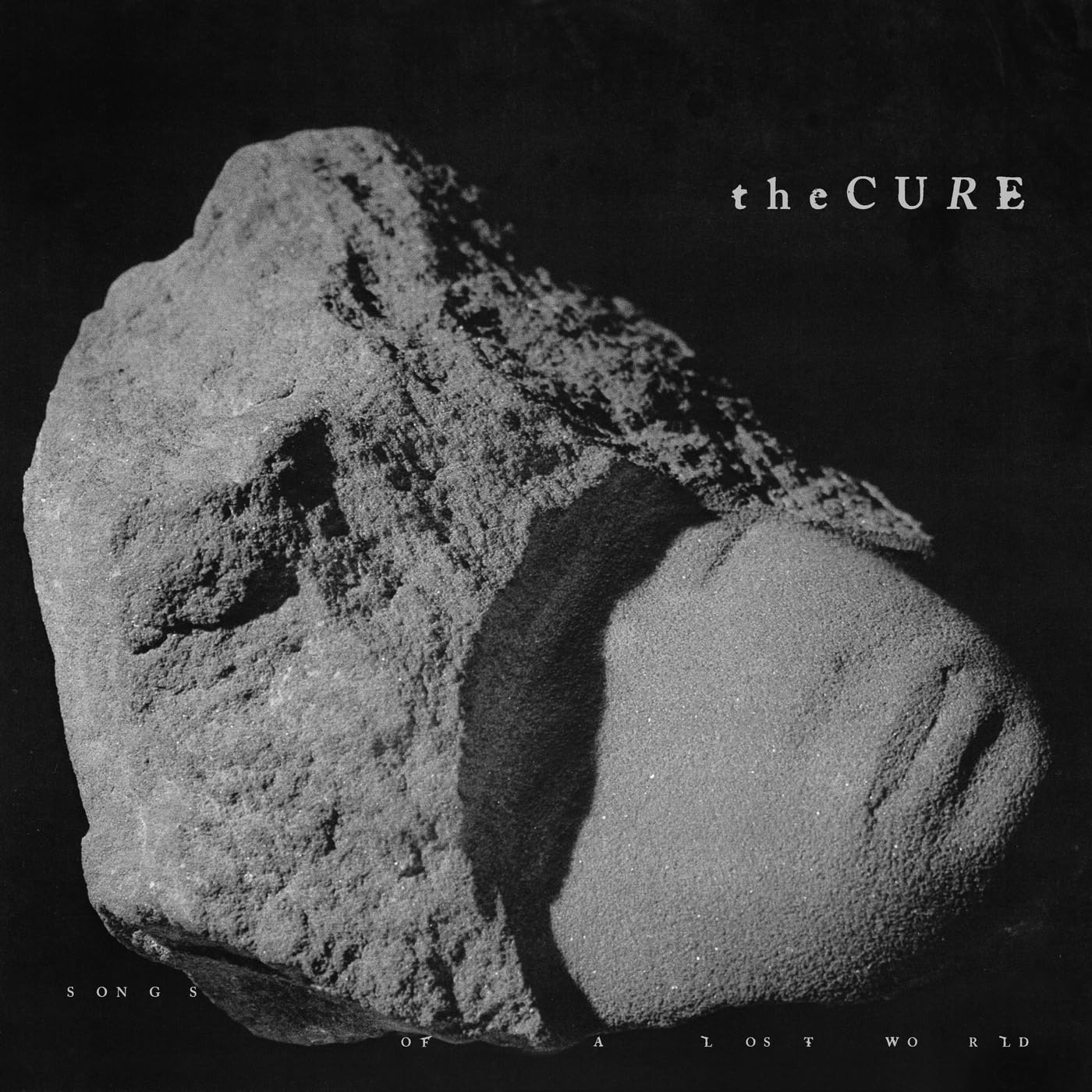









| 2025年12月7日(日) can't live without MUSIC(その6) |
前回の「その5」までで、私が幼少期にどういう音楽に触れていて、そこからどんな感じで聴く音楽が変わって来たか、幅を広げてきたか、ということについては、概ね書き終わったと思っています。そこで、今回はここまでの記載で漏れていた辺りを簡単に書いて、一連の文章の締めとさせていただきます。
前回までにほとんど触れずにきたジャンルが、クラシックです。「その1」の時に書いたように、もともと父がクラシック好きで、それで家にはクラシックのLPがそれなりに多い枚数存在していましたから、小さい頃からクラシックには親しんできましたし、例えば音楽の授業で聴く名曲についてはほとんどが耳に馴染んでいたものだったりしました。といって、自分自身がクラシックのCDを買ったりしたかというと、「その5」で書いた大学時代~就職してすぐくらいのところだと、ほぼほぼ、私自身のコレクションにクラシックCDを加えるようなことはしていませんでした。それは、そこまで手を出し始めると収拾がつかなくなって、資金をどれくらい要しなければならないか分からないという事情があってのことでした。そこが多少解禁されたのは、多分30歳になるくらいで、要するに、ロック・ポップスで欲しいものをある程度揃えたことと、資金繰りに多少の余裕が出てきたのがその時期だったことによります。それでも、クラシックを本格的に買い始めると、同じ曲であっても、指揮者違い、オケ違い、録音時期違い、という感じでバリエーションを揃えていくことになって、結果的にコレクション枚数が万単位になっていくことになるのが目に見えている(実際、クラシック好きな大学時代の友人2名はそんな感じでコレクションを有しています)から、かなり厳密に購入対象を絞って、クラシックCDは買っています。ただ、これ等については、趣旨には合わないかなと思って「聴く」には掲載していません。
同じく「聴く」に掲載していないものでいうと、ドラマCDも少しは持っています。とはいえ、これは少なくて、所有しているのは、片手で足りるとまではいかないものの、30枚は行かないくらいだと思います。私が好んで聴くのはあくまで「音楽」であって、音声のみの「劇」にはそこまで興味が無い、と言うことはできるかもしれません。その辺りを真面目に考えてみたことはこれまで無かったし、ここからも特にそれをやろうとは思っていませんが。また、落語のCDなんかは、買ってみると面白いかもと思いつつも、現状は手を出していません。ジャズは有名どころのベストをちょっと持っているのと、ほんの数枚、気に入ったミュージシャンの有名アルバムを持っているくらいかなぁ。これも、本格的に揃えだすと収拾がつかないのが分かり切っているので、敢えて自制しています。なおジャズについては、ほんの一部、「聴く」に掲載しているのもありますね。そこの基準は、何となく買ってみたビッグネームの廉価版CDではなく、明確に「この人のコレが欲しい」という意志のもとに入手したものであれば、載せている感じです。
「聴く」に掲載されているけれど前回までにあまり触れてこなかった各種サントラ盤は、実写映画・ドラマのものも若干ありますが、アニメを中心に、自分が好きな作曲家の物だったり、放送を観ていて「これはいいな!」と思ったものを買っています。アニメに関しては作品により、キャラソンのシングルやアルバムも買っているものも、ありますね。ここで、サントラ系で好きな作曲家で「聴く」に単独の項目を設けている人と、好きになるきっかけとなった作品を挙げてみましょう。五十音順で、梶浦由記は『Noir』のサントラ、川井憲次は『紅い眼鏡』のサントラ、菅野よう子は『天空のエスカフローネ』で、澤野弘之が『アルドノア・ゼロ』、そして久石譲が『風の谷のナウシカ』のサントラとなります(久石譲について言えば、とどめとなったのは『アリオン』のイメージアルバムですが)。なお、単独項目を設けなかった作曲家、サントラでも、好きなもの、折に触れて何度も聴き直しているものはたくさんあります。基本的には、作曲家の名前で買っているわけではなく、アニメなどを観ていて音楽が気に入ったから買っているわけですから、作曲を担当した人の名前をリスト化したら、結構な数になるのではないかな?
そんなこんなで、レンタルで借りてきてコピーしたものも含めれば、なかなか壮観な量のCDを所有しているので、中には、10年単位で長いこと再生していないようなものも存在します。アパート暮らしの時代と、今のマンションに引っ越してしばらくの頃は、所有しているCDを全てカラーボックスやストッカー等に並べていたわけではなく、半分以上は段ボールに入れて積んでいたのですが、そうなると、仕舞い込んでいるものはなかなか聴かないことになってしまいます。それも何だかなという気持ちもあったので、昨年夏くらいにストッカーの買い増しをして、所有する全てのCDを表に配列しました。それ以降、ちょこちょことコレクションの聴き返しをし始めていて、年内くらいには、一応、一通り回転できるかなと思っています。久しぶりに聴いてかなり新鮮に感じたCDも結構あったりして、それが楽しかったり。コレクション拡大のペースをそろそろ落とすべきではないのかということは、現時点ではたまに考えることもあるかな、という程度なので、しばらくは今のように、年間にそれなりの量のCDを買う生活が続きそうです。
ゆっくりと再読を進めていた「ランサム・サーガ」も、いよいよ最終12作目となりました。アーサー・ランサムの『シロクマ号となぞの鳥』上下巻(岩波書房 岩波少年文庫)の上巻裏表紙にある粗筋は「帆船シロクマ号で公開中に、スコットランド近海の小さな入り江に停泊したキャプテン・フリントと子どもたち。見知らぬ土地を探検するうちに、ディックがそのあたりにいないはずの鳥を発見しますが……」というもの。子どもたちとキャプテン・フリントが、タチの悪いたまご収集家、現地に住んでいるゲール人たちの2者を相手に繰り広げる冒険譚というわけで、いつものように心ワクワクする物語を楽しませてくれます。子どもたちやキャプテン・フリントの言動に若干イラっとするところが無くもないのですが、そこはまぁ、それ。昔はそれは別に気にならなかったのになと思うと、加齢とともに私も頭が固くなってきているのかもしれない……だとすれば、それはあんまり嬉しくないかな。シリーズ最終巻だからといって何か特別なことがあるのではなく、ランサムとしては次回作も書くつもりで下書きを始めてもいたらしいのですが、残念ながらそれが形になる前に彼は亡くなってしまいました。8月の頭からおよそ4ヶ月くらいかけてきた今回の再読ですが、おそらくは30年以上ぶりに読み返したランサムの世界は、やはり非常に魅力的であり、今でも多くのファンがいるというのも頷けるものでした。本当に熱心な方々と比べられると全然大したことはありませんが、私も一応、ランサムファンの片隅にいさせていただいていますし、こうして少年文庫という手に入りやすい形でシリーズ新訳版が出たことは、非常に喜ばしいことだと思っています。
かなり長いこと積読にしてしまっていた、神野オキナの『伏龍警視・臣大介』(小学館 小学館文庫)を読了。「神奈川県警監理官の臣大介警視は火災現場で偶然刺殺体を発見した。被害者は有名経済文化人・新堀兵衛の『金庫番』井上幸治だった。時を同じくして突然死した捜査一課長の後任として、大介は現場の指揮に当たる羽目に。捜査が難航する中、警視庁捜査二課第二係を率いる奥瀬真紀から電話が入る。真紀によれば、『新堀が投資に失敗した損失分を、井上が地上げで取り戻そうとしていた節がある』という。地元の反社会的勢力と揉めた末に殺害されたのか?捜査線上に半グレグループの頭・又喜星一郎が浮かび上がり……予想外の真相に辿り着き、たじろぐ大介は――。」という粗筋からも分かるように、これはかなりガチな警察小説です。神野オキナといえば私にとってはどうしても『あそびにいくヨ!』シリーズ(KADOKAWA MF文庫J 全20巻)の作者というイメージが強いのですが、まぁ、『カミカゼの邦』(徳間書店 徳間文庫)というエロスやバイオレンス溢れるハードな傑作も書いているわけですし、最近はこちらの方に軸足を移しているというのは、知っていたのですが。
さて、本作については、ジャンルとして現代の警察小説であり、大掛かりなテロとか国際謀略とか政治的陰謀とか、そういうものは登場しません。あくまで、戦後の沖縄の置かれている状況を物語に反映させて、そこに人間的な感情、悲哀といったものを絡めてきた作品という印象です。地に足の着いた、現実味のある警察小説に徹しようとしているのであろうと感じられる分、物語的なダイナミクスやカタルシスには欠けるところがあるのが、エンタメとしてはどうなのかという気もしますが……。こういう作品で、リアリティーラインをどこに引くのかというのは、どういう作品にしたいのかを反映する話であり、作者としてはおそらく、本作を、エンタメに徹した小説にしようとして書いたかというわけではないでしょうから、まぁ、これは私の好みの問題ですね。よりフィクション味の強そうな作品でシリーズになったもの(全5巻)もあるので、次は、それも読んでみようかな?
シリーズ7冊目となる、城平京の『虚構推理 忍法虚構推理』(講談社 講談社タイガ)を読了。「WEBに投稿された小説『真九郎忍法料理帖』を見つけた琴子は、作家が六花ではないかと疑う。理由は、九郎がモデルにされているから。しかし六花には覚えはなく――。誰が、何のために。リアルタイムで更新される小説を武器に、虚構と推理が連鎖する!(『忍法虚構推理』)。不死の九郎と知恵の神である琴子。二人の道行きにひとつの答えが出る。シリーズ随一の傑作ついに刊行!」というのが今回の粗筋。収録されているのは表題作の他、「廃墟に出会う」と「まるで昔話のような」の2つのエピソード。この2つは既にコミカライズが完了していて、一方の表題作は今まさに『月刊少年マガジン』でコミカライズが連載中です。相変わらずの安定した面白さで楽しませてくれるのですが、今回はラストに大きな動きが発生します。シリーズ通しての最大の懸念がこれで本当に解決されるのかどうか、読者がその内容を受け入れられるかどうか、というのはあるかもしれませんけれど、私としては「そう来たか」と納得させられた次第。ちょっと強引さも感じましたけれど、ここは「虚構推理」の「虚構」たるところですよね。コミカライズ版の存在がライトコメディー感を本作にもたらしているのでついつい忘れがちですが、そもそもこれ、世の不条理を強く内包したシリーズでしたっけ……。これを、コミカライズ版がどのように描くのか、そこはなかなかの見ものになるかもしれません。
ハマカズシの『姉の彼女にキスをした』(小学館 ガガガ文庫)の粗筋は「姉の詩織がつれてきた大学の友人・浅倉薫。自由奔放で、謎めいた空気を持つ大人の女性――高校生の恭平は恋に落ちていた。でもある日、恭平は詩織の部屋でキスをする二人を目撃してしまう。薫は詩織の友人ではなく『彼女』だった。二人の関係を受け容れられず、やり場のない感情に苦しむ恭平。そんなとき、薫は恭平に語り掛ける。『弟くんは、私とキスしたい?』踏み込んではいけないと知りながらも、押さえきれない感情に身を委ねたとき、普通ではいられない恋が動き出す――歪な三角ラブストーリー。」というもの。ちょっとインモラルで登場キャラが精神的にゴリゴリと削られていくような恋愛もの、ひところはラノベであまり見かけなくなっていましたが、最近は結構多いですよね。その手の作品刊行の主たる舞台の1つとなっているガガガ文庫が出す新作で、このタイトルですから、結構な覚悟とワクワクを持って読み始めたのですが……そういう観点から言うと、現段階ではまだソフトな感じの物語です。各所に色々と仕込まれている火種はあるので、それが今後火を噴くか噴かないかというところで作品のイメージは大分変るでしょうが、さて、本作はどちらの方向に向かっていくか。もちろんそれを確かめるには第2巻、第3巻と続巻が出て行ってくれないといけないわけですが、この感じだと、第1巻の段階ではまだ助走を始めたところで、ここからもっとグチャグチャでドロドロしたものにもなっていけそうで、個人的には、何気にそちらの方向性を期待してしまっていたりも。
『無職転生』シリーズ(KADOKAWA MFブックス)が面白いのだから、同著者の他の作品だって読んでみなければならないだろうとずっと思っていたのですが、他に積読本も多いしと若干足踏みしていたのですけれど、ようやく重い腰を上げて、理不尽な孫の手 の『オーク英雄物語 忖度列伝』第1巻(KADOKAWA ファンタジア文庫)を読了しました。「十二の種族を巻き込んだヴァストニア大陸の戦争で、ありとあらゆる敵を打ち倒し、『英雄』の称号が与えられた最強の戦士バッシュ。全オークから尊敬と信頼を集めるバッシュだが、実は大きな秘密を抱えていた。『はあ、憧れるよな。いったい今まで、何人の女を抱いて孕ませてきたんだろうな……』(……ゼロだよ)そう、『童貞』だった。種族の誇りと名誉を守るため、そして『童貞』を捨てるため、オークの英雄は嫁探しの旅に出る。『どうやらヒューマンの常識では、いきなり性行為を持ちかけても同意は得られんらしいな』これは真の英雄へと至る漢の物語。」というのが粗筋です。つまり、「オークはエルフの森を焼く」し「女騎士を捕まえたらレイプする」というテンプレートを逆手に取った作品なわけですが、まぁ、そのこと自体は別に珍しいものでは無くなっていますよね。主人公の目的が「嫁探し」なところが、周囲の誤解と忖度とでいつの間にか不埒な同族を成敗する世直しの旅になっているというところが笑いどころです。かなり面白かったので、これは、第2巻以降も読むのが楽しみになってきました。
石塚真一の『BLUE GIANT MOMENTUM』第6巻(小学館 ビッグ コミックス スペシャル)は、主人公の参加したインターナショナル・ジャズ・コンペティション決勝戦の顛末を描く1冊。結果がどうなるのかは、まぁそこはマンガですのでご想像の通りになるわけですけれども、分かり切った展開だとしても、こうして収まるべきところにきっちりと収まってくれて、痒い所に手が届くようなストーリーライン、悪くは無いですよね。主人公が真に世界的プレイヤーになれるのかはここからが正念場、賞は取ったもののその後はパッとしないというパターンも現実には存在するわけですが、エンタメ、娯楽作品としてさすがにそれは無いとしても、次の第7巻が楽しみです。
良くも悪くもいつも通りな大武政夫作品である、『J⇔M』第6巻(KADOKAWA HARTA COMIX)。いつものノリでいつものような話が展開されていくわけですけれども、マンネリと言ってしまえばそれまでながら、でも相変わらず面白いので問題はありません。あとは、これをいつまで私が楽しんでいられるか、どこかで飽きが来るのではないか、というところが懸念されますが、案外このまま、定番的なノリとして受け入れ続ける、楽しみ続けることになりそうな気もします。つまり、何となく波長が合っているということなのでしょうね、これはきっと。
オカルトバトルから時間モノ、並行世界モノSFの様相を呈してきている、田中靖規の『ゴーストフィクサーズ』第6巻(同社 ジャンプコミックス)。伝奇系の作品も好きな私ですが、それよりもさらに好きなのは時間モノSF。つまり、本作はかなり私のツボにハマる展開を見せているということになります。コミックス単位で読んでいるとストーリーにやや分かりにくいところが出てくるのは欠点かもしれないのですけれど、これはある程度コミックスを貯めてから(あるいは完結してから)まとめ読みしてみないと最終的にどうこうは言えないところかも。細切れにしないで最初から最後までを一気通貫で読むことで物語の印象ってかなり変わったりしますから。まぁ、いずれにしても、ここからの展開がかなり楽しみになってきたと言えそうです。









| 2025年11月29日(土) カワラバト……かな? |
11月最後の更新ですから、いつものように Top写真 を更新しました。1年を締めくくると同時に新年を迎える準備をする12月には、翌年が良い年になることを祈念して富士山の写っている写真を使う、というのがこの「ぱんたれい」における何となくのルールとなっています。とはいえそれに従っていない年も普通にありますので、これは絶対に、というようなものではないのですが。では今年はどうなのかというと、既にご確認されている方もいらっしゃるでしょうが、ルールに則って、富士山の写真を選んでみています。海を挟んだ奥に浮かんでいる富士山よりも、手前のハトとか岩にむしろフォーカスが当たっているような画像ですけれども、単純に富士山を中心に入れたものは今までに何枚も使っていますし、そういうのばかりだと変わり映えもしなくて面白くないですよね。なお、鳥がこういう形でフレームに入ってくるというのは、例えば2012年6月に使った写真のように過去にもあるのですが、こういう構図にしようということを狙って自分で鳥を用意していったというようなことは当然無いわけで、これは全くの偶然の産物。そのわりには上手くハマったなと我ながら思いますし、こういうのがあるから、街歩き&スナップ撮影は面白いですよね。
で、今回のこの画像の撮影場所なのですが……これは、こういう時にいつもそうしているように、細かいことは来月末、Top写真 を次の物に変えた際に、過去の Top写真 の記録である「あーかいぶ」にて書かせていただく予定ですので、ここでは特に触れないでおきます。海越しに、こんな感じで富士山が見えて、こういう岩があるところと言えば……ということで察しがつく方もいらっしゃるでしょうけれど。「ぱんたれい」で定期的に富士山の写真を使うか、と決めたのは大体10年くらい前のことでした。そこから2~3年で幾つかの撮影スポットを回ったことがあって、今回のは、その時に撮影したものになります。というか、毎年の12月に使っている富士山の写真は大体その時期に撮影したものだったりします。ネタ切れにはまだならないのでもう数年は全然大丈夫なのですけれども、今年の冬辺りにまた、どこか数か所に撮りに行ってもいいかもしれませんね。定番の撮影スポットはある程度行ってしまっているから、ちょっと変化球的なところ他で、良さげなところのピックアップを始めようかな。
いよいよディックとドロシアのDきょうだいが自分の船を持つ、「ランサム・サーガ」の11作目、アーサー・ランサムの『スカラブ号の夏休み』上下巻(岩波書房 岩波少年文庫)。ウォーカー兄妹はまだ合流していませんが、とりあれずナンシィとペギィのブラケット姉妹のアマゾン号と、出来立てのスカラブ号とで夏休みを楽しもうと思っていたところに、第2作『ツバメの谷』上下巻(同社 同文庫)で存在感を発揮していた大おばさんがブラケット家に来襲、ブラケット夫妻とキャプテン・フリントが不在の中、ナンシィたちが考えていた予定はあっけなく白紙に……というのが、今回の粗筋です。古き良きビクトリア的秩序を重んじる大おばさんのことは、これまでは煙たいだけの厄介者という印象で語られていましたし、実際今作でもそれは基本的なスタンスとして変わっていないのですけれど、久し振りに読んで思ったのは、大おばさん、そんなに酷い人じゃないですね。年齢なりの頭の固さはありますけれど。そんな発見もありつつ、読み終えた『スカラブ号の夏休み』。「ランサム・サーガ」は残り1つ。早速、読み始めることにしましょう。
900ページを越える厚さが見た目にインパクト大である、飛鳥部勝則の『堕天使拷問刑』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)を読了。「魔術崇拝者の祖父が密室で怪死した。中学生の如月タクマはさらに、ある一族の女たちが祖父の召喚した悪魔により斬首されていたという噂を知る。やがてタクマは転校先で『おまえツキモノイリだろ』と謎の罵倒を浴びせられる。タクマは『月へ行きたい』とつぶやく少女。江留美麗に不思議と心慰められるが、斬首事件が再び……純愛と推理が融合するボーイミーツガール・ミステリ。」という粗筋の作品で、要はいわゆる「因習村」ジャンルの作品なわけですが、横溝正史のようなガチガチのミステリー、トリックや動機などが作り込まれた本格派ミステリーというより、アンチ・ミステリーの傑作として名高い中井英夫の『虚無への供物』(講談社 講談社文庫 上下巻)のような空気感を、個人的には感じました。エグさでいうと中西鼎の『さようなら、私たちに優しくなかった、すべての人々』(小学館 ガガガ文庫)には及ばないのですが、独特の雰囲気を上手く醸し出せていて、かなり刺激的で面白かったです。「読む」にもう少し長い感想を、掲載させていただきました。
7月に紹介した『恋に至る病』(KADOKAWA メディアワークス文庫)のスピンオフ短編集である、斜線堂有紀の『病に至る恋』(同社 同文庫)を読了。「150人以上の被害者を出した自殺教唆ゲーム『青い蝶(ブルーモルフォ)』の主催者である女子高生の寄河景。彼女がなぜここに至ったのか。その片鱗が垣間見える幼少期を描いた『病巣の繭』。ゲームに囚われた少年少女を描く『病に至る恋』。景と宮嶺望のデートを描いた『どこにでもある一日の話』。もし自分の異常性に気付いた景が小学校に通うのをやめていたら?運命の残酷さを描く『バタフライエフェクト・シンドローム』。 これは、愛がもたらす悲劇の連鎖――病に至るまでの恋の物語。」というのが粗筋なのですが……。いやぁ、元々の作品が作品だけに想像がついてはいましたが、見事なまでに気が滅入るタイプの短編が並んでいます。フィクションはフィクションとして良くも悪くも割り切って、登場人物に共感したり事故を投影してみたりというようなことは一切やらない(できない)私なのですけれども、それはそれとして、本作は読んでいても、あまり面白いというようなことを感じませんでした。『恋に至る病』の方はかなり楽しめたのになぁと思ったりもしたのですが、これはきっと、ブルーモルフォを、景と望を巡る物語がどういう経緯を辿ってどういう結末を迎えることになるのかを知った上で、ここに収録された4つのエピソードを読んでいるから、というのがあるのでしょう。「これは本編では語られなかったけれど、描かれるべきだったエピソードだ」と思えるものもなかったし、申し訳ないけれど個人的には微妙な1冊で、せっかく完成度のあった『恋に至る病』をむしろ損ねることになるような蛇足のスピンオフと感じました。
展開がゆっくり過ぎて若干苛つくことが無いとは言い切れなくなってきた、三河ごーすと の『義妹生活』第15巻(KADOKAWA MF文庫J)。まぁ、2人の感情をきっちりと丁寧に、かつ双方の視点から描いていこうという作品コンセプトについては嫌いでは無いし、そこが本作の良い所でもあるので、ここはなかなか難しいと言えます。そんな本作の今回の粗筋は「初めての夜を迎えた悠太と沙季。初体験は二人の関係を大きく変えてしまうのか、それとも何も変わらないのか。その答えは、これから二人が人生を歩みながら作っていくのだろう。大学生活が本格的に始まり、新しい友人と付き合い、新しい職場で働き、新しい日常を過ごす。生活時間のズレは小さな隙間を生んで、時間とともにゆっくりと拡がっていく。二人は自分の人生を生きながらも、綻びを縫い合わせるように歩み寄り――初体験、SNS、仕事での失敗、学外での出会い、パパ活の話題、運転免許の取得、二人の思い出の記録。互いの人生を生きる “兄妹” が、距離を越えて共に歩む恋愛生活小説、第15弾。」というもの。こうしてみると、今巻では結構な変化が2人に起きていることが分かるのですが、それでもあまり大した動きが無いような読後感になってしまうのは、描写が淡々としているからなのか……。何かイベントめいたことがあっても、そこに主人公2人がそこまで深入りしなければ作中描写としてはわりとサラッと流されてしまうのが、良くも悪くもそういう感触を生んでいるのでしょう。初体験の辺りも(そういう方向性の作品では無いのでそれは当然そうでしょうが)ネチっこい描写は無く、あっさりと記述されるだけだったりしますしね。だから、盛り上がるべきところで今一つ盛り上がらない感があって、読んでいてそこがちょっとひっかかるのかも。読み物として面白いことは確かなのですけれど。
石川雅之の『もやしもん+』第1巻(講談社 アフタヌーンKC)については、こうしてコミックスを購入し一読した今でも、「なぜ、今になって『もやしもん』なのか?」という疑問は一向に解消されないままなのですが……。しかし、10年余りが過ぎてあの面々にこうして再び会えたこと、そして絵柄も物語のテイストも全く変わらず、当時そのままの延長線上で読ませてくれたことにほっとしたのは、間違いがありません。つまり、面白かったし、楽しかった、ということです。昔の作品を引っ張り出して続編を書くということは、当時のファンを読者としてある程度想定できるという点ではプラスになるかもしれませんが、ちょっとした絵柄の違いやキャラの言動の違い、テーマの違いなどで逆に炎上を呼んでしまう、ファンに叩かれることになる恐れも大きいという意味ではマイナスな要素も無視できないわけですけれど、本作については……現時点ではまだ、判断保留、かなぁ。
高橋葉介の『夢幻紳士 猟奇篇』(早川書房)を購入。夢幻紳士の新作というと、最近は魔実也氏や魔実也様や魔実也さんが多かったですが、今回は久し振りの魔実也くん登場です。ただし、マミではありません。アッコとのコンビとか、猫おばさ……もとい、猫夫人との掛け合いが好きなのですが、さすがに冒険活劇篇の続きは難しいですよね。「キ〇ガイ博士とその助手」テーマのマンガを描きたいけれども、そのままではさすがに連載の許可が出ないだろうから夢幻魔実也を絡めることにした、という経緯があとがきに書かれていましたが、それで少年探偵夢幻魔実也が読めるのであれば、どんどんその手のネタを描いてほしいくらいです。これぞ高橋葉介、という感じの不謹慎で悪趣味なスラプスティック・コメディー。第2話の扉で「良い子は読んじゃいけない漫画だよぉ」と魔実也自身が言っていますが、いやいや、個人的には「良い子」ほどこういう漫画を読んでおくべきだと思いますよ……。もちろん、魔実也くんは今回も助走しまくっているので、そちらが好きな人も大満足。非常に面白かったです。
2025年におけるマイムーブメントとなっている大人買いの……第何弾になるのかは分かりませんが、ともあれ、昨年から依然として維持されているプログレ熱と相まって、今回は P.F.M. (Premiata Forneria Marconi)のアルバムを6枚、具体的には『Photos of Ghosts』、『The World Became the World』、『Chocolate Kings』、『Jet Lag』の4枚のボックスセットと、『Dracula Opera Rock』、『Emotional Tattoos』を購入しました。このうち、『Dracula Opera Rock』は、自作のロックオペラ「Dracula」用に作った楽曲を自分たちが歌ったアルバムがまずあって、そこに収録しなかったインスト曲も含めて、しっかりとキャスティングをした形で2枚組化して再リリースしたもの、という位置づけのようです。初期のアルバムと最近のものを買って、その間にリリースされたものは買っていないのかと思われるかもしれませんが、これは、とりあえずすぐに手に入りやすいところの購入を優先したが故とご理解ください。で、早速聴き倒しているのですが、やはり、こういうメロディアスなタイプのプログレは好みです。最近の人気バンドの中には、わりとプログレ的なアレンジや曲展開をポップスに混ぜ込むミュージシャンも多いから、その辺りを聴いている人には、実はこの辺りの洋楽プログレは親和性が高いのではないかな……。まぁ、なかなか接点も無いでしょうから、そこが残念なところなのですけれど。
こちらはプログレではないのですが、菅田将暉の出したアルバムのうちで未所有だった3枚(うち、1枚はミニアルバム)、『COLLAGE』、『QUIET JOURNEY』、『SPIN』も購入しています。彼の音楽活動については、時々「これはなかなか」という曲があるものの、基本的にはそこまでではないという感じだったのですが、現時点での最新作である『SPIN』を聴いて思ったのは、結構いい方向に変化してきているのではないか、ということでした。「いい方向」というのが偉そうであれば、「私の好みの方向」と言い換えてもいいかもしれません。ここで具体的に〇〇に似ているというようなことを書くのはやめておきますが、問題点としてはオリジナリティーというところでやや欠けているかもしれないですし、ちょっと地味めなのですけれども、こういうの好きなんですよね。

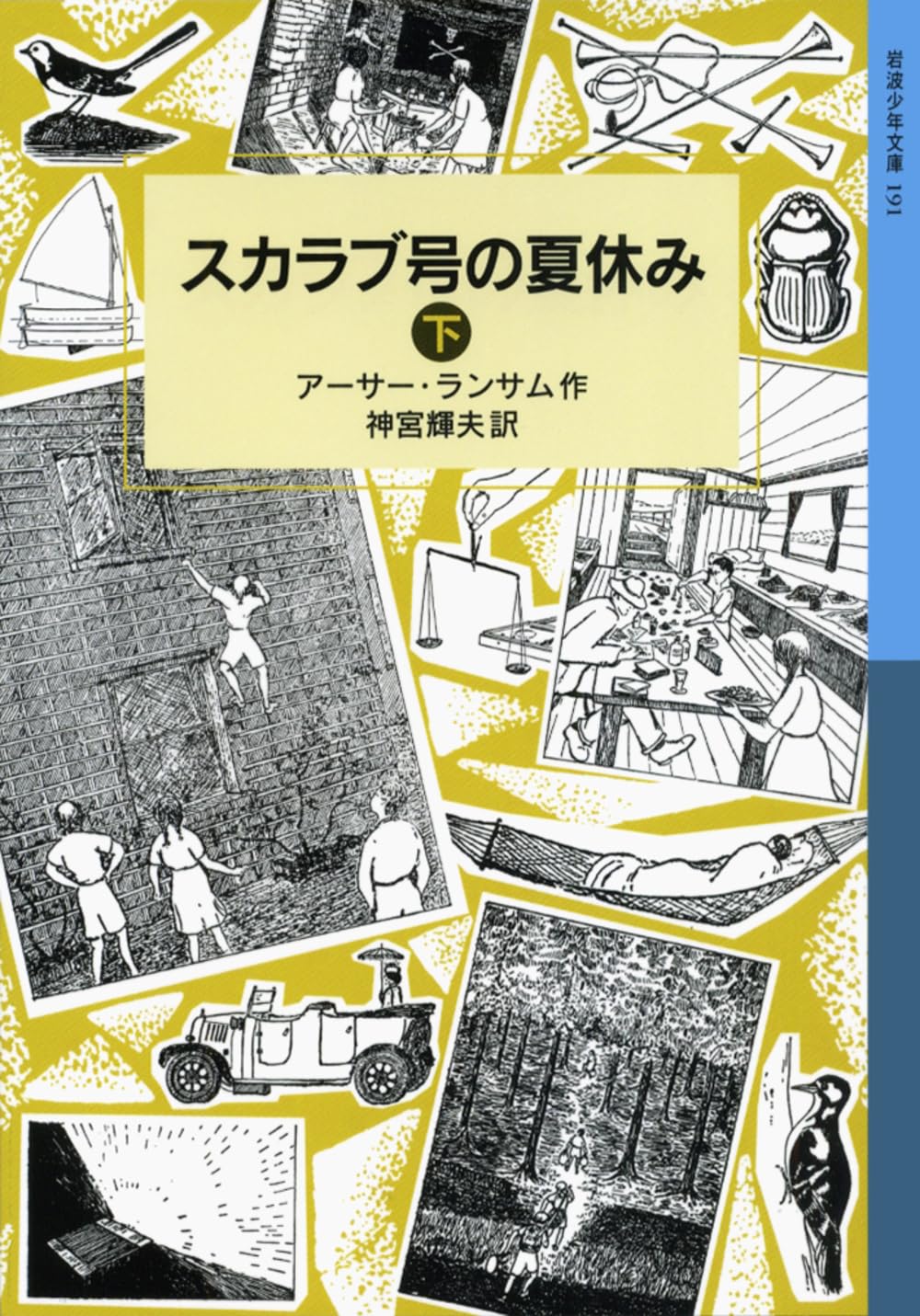







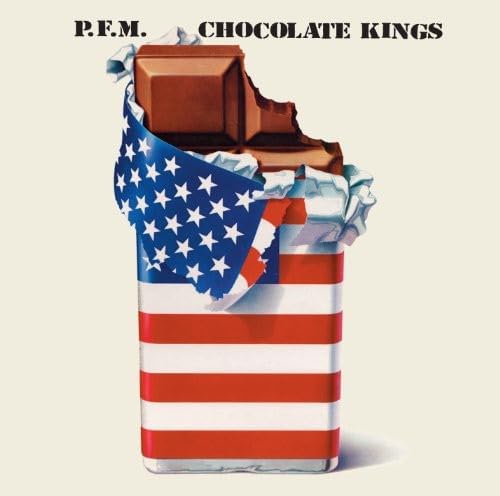
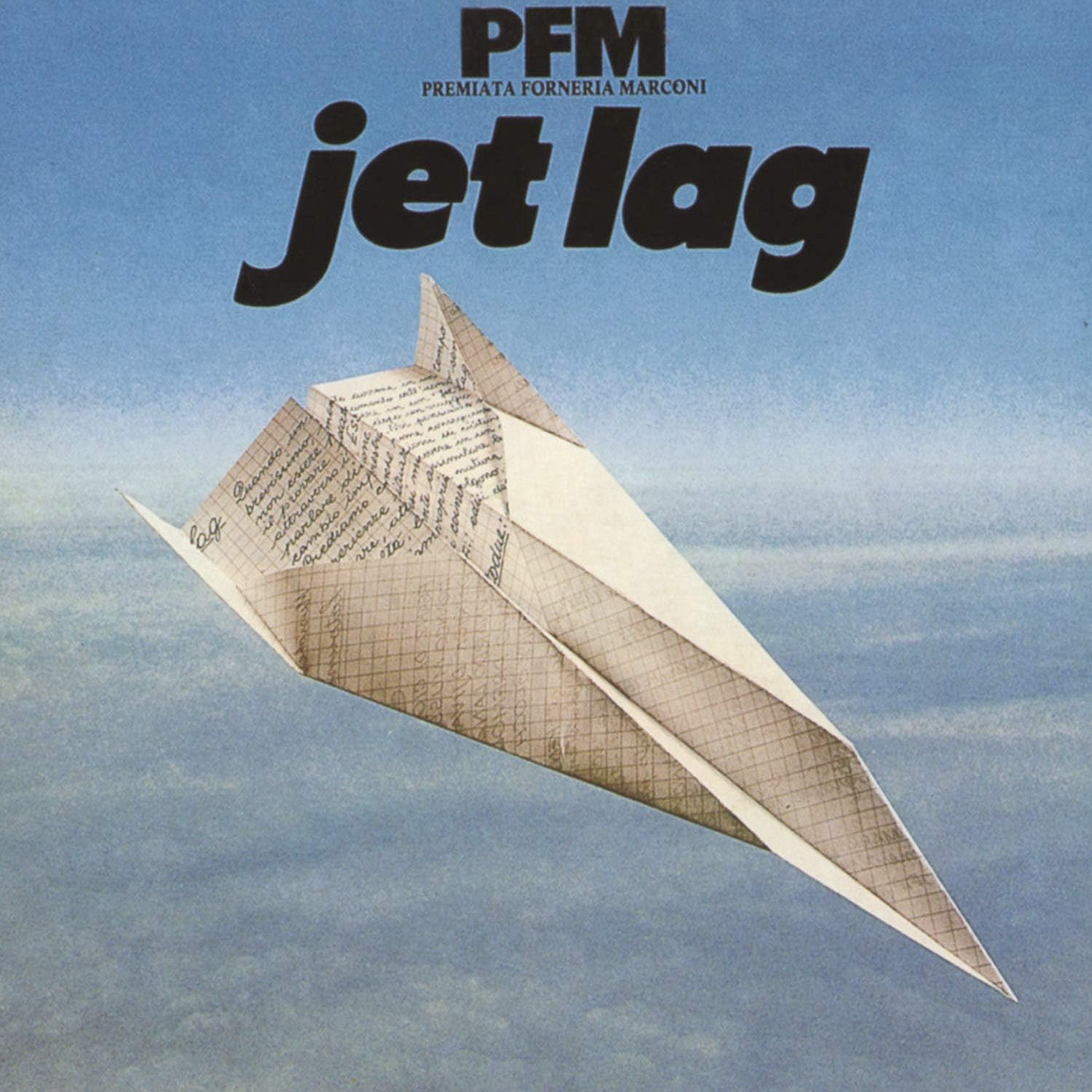





| 2025年11月22日(土) 優遇と自尊心 |
11月もまもなく終わりますから、大学、高校、専門学校などの受験本番も、段々と近付いてきています。受験生の皆さんは勉強も追い込みの時期で、無事に志望校に合格できるように最後まで全力を尽くすべく頑張っていると思います。今回の「雑記」がそんな状況に水を差すような内容かもしれないのがいかにも申し訳ないのですが、しかし考えてみれば、受験生がこんな趣味だけで運営している個人ホームページの、こんなところを読むこともないだろうから、あまり気にしなくてもいいのかも……?
大学に絞っていうと、ここのところ「海外の学生の特別枠・支援金」とか「多様性、LGBTQ対応」とか「女子大の共学化」とか「一部大学の新規募集受付停止」とか、経営的なことやら思想信条的なことやらでニュースを騒がすことがちょこちょこと起きている印象があります。大学の自治とか学問の自由というような非常に重要な権利がありますし、もちろん余程の違法行為でもなければ大学が自主的に行う施策に対しては最大限の尊重がされるべきです。とはいえ、中には「それってどうなんだろうか?」と首をかしげてしまうようなものもあるわけで、例えば、私にとっては、7月にも「雑記」内で別件でちょっと触れたクオーター制がそれに当たります。大学入試でこれが騒がれることになった背景には、一部の大学で入試での得点が基準をクリアーしているにも関わらず、学生の男女比を一定範囲内に調整する為に優秀な女子受験生を落とし、それよりも得点の低かった男子受験生を合格するという歪みが生じていたことがありました。そこから、受験時の男女差別を撤廃するのに、いっそのこと女子学生をこれだけの人数合格させなければいけないという「枠」を作って強制的に一定数の女性を合格させるようにする制度、クオーター制というシステムの導入が声高に叫ばれるようになって、実際に一部の大学では導入が始まったりもしているのが現状ですよね。
実際、学力が基準に達しているのに女性だからという理由で合格にされなかったのは私もどうかと思っていましたが、学力が基準に達していないのに女性だというだけで合格するというのもどうかと思います。例えば、旧:東京工業大学(現:東京科学大学)の女性枠創設について、「つまり女生徒の接点が無い若き工学系研究者の卵に将来の配偶者候補を供給するという枠か」という声がSNS等で出たことについて、クオーター制を作れと主張していた活動家の皆さんはどう感じたのでしょう。学力が基準にどの程度達していなかったのか、不足していたのかによって状況は変わると思いますが、仮にその差が結構あった場合に、それでもクオーター制で下駄をはかせるような形で合格になったとして、それって本人がひどく苦労することにならないですかね……?その苦労も自身の成長の糧ととらえてポジティブシンキングで行ける人ならば問題は無いかもしれないけれど、メンタルをやられてしまう人も出てしまいそうです。会社役員とか議員などでもこのクオーター制の導入を、と主張する人もいますが、能力があるのに差別されている人についての救済は当然必要なものの、地位に足るだけの能力を持たなくても数合わせだけで女性を登用するのは……。ただ、例えば現実世界の議員が、地方であれ国であれ、全て人より秀でた能力を持っているのか、と言われると、そんなことは無いよね、というのも否定できないのですけど。
結局、それが男性についてのことであれ女性についてのことであれ、身の丈に合わないようなおかしな特別扱いをされること、要求することは、そうして特別扱いされることになるあなたの尊厳を損ねることにならないか、それはあなたが自身に抱くプライド的に許容できることなのか、というところに、私の疑問は帰結します。なぜならば、私がその立場にあるとしたら、ちょっとそれは勘弁してほしいな、と思うに違いないからです。そんなのはどうでもよくて、自分は特別扱いによって得られるものをこそ重んじているのだ、とおっしゃるのであれば、それも尊重されるべき1つの考え方ではありますが、私は(軽蔑するとまでは言いませんけど)そういうのは好きではありません。何だかんだ言っておいて、最終的には個人の好悪の話か、と思われるかもしれませんが、まぁ、この「雑記」はもともと開設当時から、様々なことをネタにして私が自分の思っていることを吐き出す場でもあるので、そこはご了承ください。
8月に紹介した作品のシリーズ2冊目である、小森収の『明智卿死人を起す』(東京創元社 創元推理文庫)を読了しました。今回の粗筋は「帝の新たな命により、堺を訪れた明智卿と安倍天晴。堺には商人組合の納屋衆があり、大店では上級陰陽師を抱えているが、そのひとりで熟練の陰陽師・土御門が行方不明となったのだ。かたや京では、若い娘と老人の骸が相次いで盗まれていた。堺と京の奇怪な事件は、やがて思わぬ場所で交錯する。魔術の発達した世界での不可能犯罪に、名探偵と陰陽師が挑む本格ミステリシリーズ!」というもので、第1作と同様に駄洒落気味の小ネタを大量に含みつつ、架空の日本を舞台にした謎解きが行われています。今回のエピソードは、謎解き部分はなかなか興味深く面白かったのですが、その終わり方にはちょっとばかりスッキリしないものが残りました。それが次回作に繋がるものなのかどうかは、構想上は存在しているという第3作「明智卿西へ」が刊行されれば分かるのでしょうか。前作は独特の雰囲気があって非常に面白かったですから、この第2作にも大いに期待していたのですが、その期待は裏切られなかったと思います。これについて、小ネタを入れ過ぎだとか、ふざけ過ぎだ、という批判もあるかもしれませんが、それがあっての良い応え、読み心地ですよね。
「『我は人間に其(その)存在の意義を教へむとす。即ちそは超人なり、人間の黒き雲より來る雷光なり。』「ツァラトゥストラ」フリイドリッヒ・ニイチェ(生田長江譚/新潮社) 二十年前、『超人』という光を目指し、孤独と虚無に満ちた引きこもり生活の中で、妄想と哲学を武器に闘った。中年を迎えた著者は再びその旅路を歩み始める。老い、貧困、そして現実の荒野を越え、真の『超人』として生きるとは何か? 中年男性よ、君たちはどこへゆく。僕のゆく道は『超人ロード』だ!」という、おそらくそれを読んだだけではどういう作品なのかさっぱり分からないであろう作品紹介で、著者の近影がそのまま表紙になっている、滝本竜彦の『超人計画インフィニティ』(集英社)を読了。この「雑記」で感想を書いていないのですが、前作……というと少し語弊があるかもしれませんけれども、一応、本作とも関係のある過去作品『超人計画』(KADOKAWA 角川文庫)が小説風エッセイだったとすれば、こちらはエッセイ風小説になっています。その系統には、古川日出夫の『ボディ・アンド・ソウル』(河出書房 河出文庫)や宮内悠介の『偶然の聖地』(講談社 講談社文庫)等、過去に「読む」に採り上げてきた傑作・名作があるわけですけれども、本作は、さすがにそこまでのものとは言えないのですが、しかしなかなかの面白さ。滝本竜彦という人物の、この鬱屈したところを「楽しめる」には、その読者がある程度は健全な精神の持ち主でなければならないかもしれませんが。
現役の医師である作者の手による、2019年の秋から2022年春までの新型コロナと医療従事者が題材の小説、知念実希人の『機械仕掛けの太陽』(文藝春秋 文春文庫)を読了。裏表紙の粗筋は「大学病院でコロナ病棟の担当者に任命されたシングルマザーの医師・椎名梓。同じく病院の看護師・硲瑠璃子は恋人と同棲中だが、独身ゆえにコロナ病棟勤務を命じられる。そして七十歳を超え持病もありながら地域の患者を救うためコロナに立ち向かう町医者の長峰邦昭。戦場と化した医療現場の2年半のリアルを描く感動の物語。」となっていて、つまり総合病院の医師と看護師、街の診療所の院長の3人を主人公に据えて、この3名と感染症との戦いを描いているわけです。これがどこまで現実をトレースしてリアルなものなのかというのは、この戦いの内側にいたわけではない私には確たる判断はできないのですけれども、ここで変な作りごとを入れても仕方が無いですし、キャラクターとその家族の物語としてはフィクションであっても、コロナと医師・看護師の闘いの様相については、現実がまさにそうであったことを描写しているものと思います。
これまで、コロナ禍の中の医療従事者の皆さんがどのような感じであったのかは、様々な記事だったりネット上の体験記だったりで、ある程度の知識は持っていましたが、やはり、こうして実際にそれを良く知る人が、誰にも読みやすい物語の形式で文字に残してくれるというのは、あの時期の事を後世に残していく為にも、大いに意味があるように思います。現在の私たちはコロナと否応なく共生していくことになっているわけですが、今後どのような変異株が再び私たちに対して猛威を振るうかもしれず、あるいはコロナでは無い新たなるウィルスが襲い掛かってくるかもしれず、そのような時に私たちがどのように振る舞っていくべきかを判断するのに、本作はその一助となりそうです。基本的な公衆衛生知識を持つことの必要性、それを実行する予防意識の徹底の意義、誤った情報に左右されずに科学的でしっかりとした裏付けのある情報を信じる事の重要性など、こうして列記すると当たり前ですが、Withコロナに慣れてしまうとついつい忘れてしまったり疎かになったりしてしまいがちなことを、改めて再確認した1冊でした。
裕夢の『千歳くんはラムネ瓶のなか』第9.5巻(小学館 ガガガ文庫)は、シリーズ2冊目となるサブキャラ短編集。「『んなところにしゃがんでるとパンツ見えるぞ、女子高生』『おじさんくさいですよ、男子高校生』芦葉高校三年、岩波蔵之介。芦葉高校二年、美咲渚。ふたりの青春が、交わる。濃密なボリュームで描かれるかつての青、そして、今。本編級サイドストーリー第2幕!」というのが裏表紙の粗筋ですが、これまでシリーズを読んできた読者へのサービスな1冊と言っていいでしょう。発売時期的にTVアニメの放送開始に合わせた刊行であることは明らかなところ、併せての効果を狙ったはずのアニメの方が色々と、ちょっと、ナニなことになっているのが気になるところです。ポエミックな地の文と、時にちょっと迂遠な会話、そして表面に出さずに押し隠される登場キャラたちの本音が織りなす物語が本作の良い所として、その性質的に映像化には不向きなのではないかという懸念を抱いていたのですが、それが的中、ということにはならなえければいいなと案じています。どうしてもアニメにするに際してカットされる部分も多いですし、行間を余白として自分のペースで楽しむことも映像だとできないから、丁寧な語りと行間を楽しみつつ小説で読むべき作品だと思うんですよね、『千歳くんはラムネ瓶のなか』って。が、アニメのことは本題では無いので9.5巻の話に戻りましょう。とはいえ、書けることもそうそう無いのですが、本作については、ベタな流れでなストーリーではあるものの、それだけに押さえるべきツボをしっかりと押さえた良いエピソードとなっていたと感じました。読み始めてしばらくは、ポエムな描写が若干キツかったりもするのですが……「これでこそこのシリーズである」とすぐに馴染んできますし、そうなってしまえばそこで描かれる人間模様、感情の動きをじっくりと味わうのみです。今巻は、これまで作中で印象的な役を割り当てられていた2人のオトナ、主人公達の理解者である教師たちの高校時代に焦点を当てた内容で、ここまでシリーズを読んできた身として大いに楽しませてもらいました。普通に佳作だと思います。
結構硬質な作品だった『月とライカと吸血鬼』(小学館 ガガガ文庫 本編全7巻+外伝1冊)の印象が強かったので、今回はそれと比べればかなりライトなものを書いたな、と思ったのが、牧野圭祐の『遥か遠くのスターライト』(KADOKAWA 電撃文庫)。「私たちの宇宙計画、始めます。 地球に巨大な宇宙船が不時着。ウサ耳しっぽなモフモ星人が日本にやってきて、はや30年。銀髪の少女、ルーフェニッピカンニュ・ファーミィ(通称ルー)は、どこか寂しそうに地球で暮らしていた。そんな『ぼっち』な彼女に気づいた高1少女、花宮陽奈乃は『手作り宇宙船』で、遥か彼方にあるルーの故郷に手紙を届けることを思いつく。もちろん技術も予算もゼロ……でも情熱は無限大!科学に詳しい大北宙理、頼れる生徒会長の御船真帆に声をかけ、少女たちだけの宇宙開発『コードネーム:マカロン』が始まる!涙も笑顔を一緒に分け合いながら、今日もまた少女たちは星を目指す。これはきっと宇宙に届く、私たちだけの物語。」という粗筋の非常にポップなラノベらしいラノベで、作風の温度差にちょっとびっくりしました。が、面白いか面白くないかで言えば、まぁこれは前者かな。何か1つくらい「お、これは!」というフックになるものがあっても良かったかなという気もしますけれども、作者曰く、本作は「読んでいて楽しいライトなきらら系SF」ということなので、つまりこの「ゆるふわ」なテイストこそが最初からの狙いというわけだから、そこに文句を言うのは間違っていますね、きっと。
いよいよ世界ジュニアオーケストラコンクールが開幕する、阿久井真の『青のオーケストラ』第13巻(小学館 裏少年サンデーコミックス)。会場として設定されたのは、池袋の東京芸術劇場ですね。つい先日、東京都交響楽団の創立60周年記念シペシャル公演「すぎやまこういちの交響宇宙」で「カンタータ・オルビス」や「交響曲イデオン」を生で聴いた興奮の記憶があまりに鮮明で、内部構造の1つ1つを克明に思い出せるだけに、かなりの臨場感をもって読ませていただきました。それを狙ったわけでも何らかのタイアップがあったわけでもありませんけれど、結果的には最高のタイミングで読むことになったと言えるでしょう。内容的には、ライバルとなるであろう奏者、国が取り上げられた後にいよいよ日本の演奏で、手堅いけれども地味目な第一楽章が終わり、いざ第2楽章、というところまでが描かれています。仕込みは十分で、これから始まるクライマックスをどうぞご覧ください、という感じであり、これは、次の第14巻が非常に楽しみになってきます。
これまでは屯田林憲三郎の人格の影で檻の中に閉じこもっていたグレイスの魂がそこからいよいよ出てくるという流れになった、上山道郎の『悪役令嬢転生おじさん』第9巻(少年画報社 YKコミックス)。世界の謎的なものも前巻くらいから提示され始めていますし、クライマックスが近付いてきているのか……というと、今の段階ではそこまでの盛り上がりを仕込んでいるわけでもないような気もするんですよね。変に迷走するようなことにならなければいいなと危惧しつつ、現時点では相変わらず面白いので、今回の第9巻もバッチリ、楽しませてもらいました。
山地ひでのり の『ソアラと魔物の家』第6巻(小学館 サンデーうぇぶり少年サンデーコミックス)は、過去編を終えてまた通常の感じに戻って来たかなという1冊。今回も面白く読ませてもらいましたが……流れとしては、ここで一旦テンションを元に戻して、ということなのでしょうけれども、当然、過去編で開示された事実がある以上はそのまま素直に序盤の感じに戻るわけではありません。つまりポイントになるのはここから物語をどういう方向に持っていくのか、どこを着地点と設定するのかということになりそう。それ次第で作品の完成度は大きく左右されるでしょうから、実は次の第7巻以降2冊くらいが本作にとっては結構な勝負何処理になる気がします。
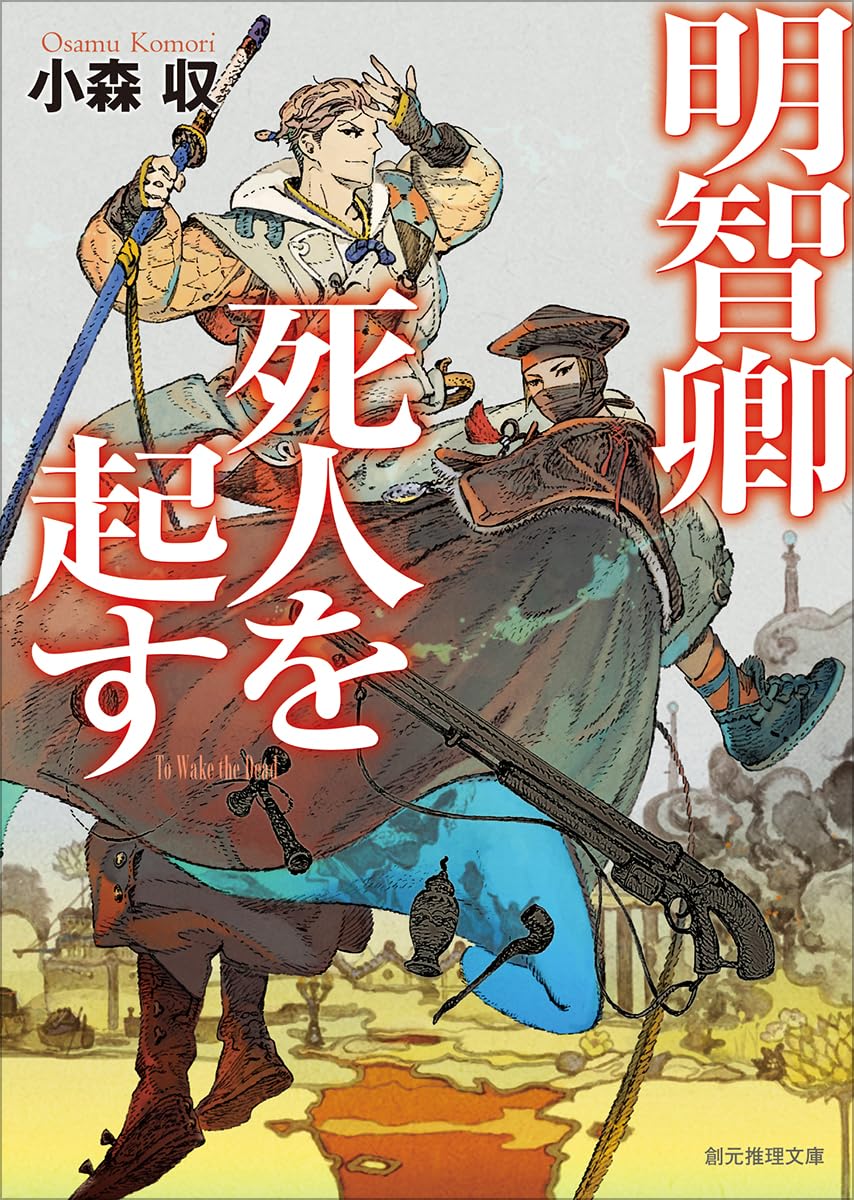







| 2025年11月15日(土) 130/80 |
ちょっと前のことなのですけれども、日本高血圧学会が2025年7月25日に、高血圧であると判断された患者の、投薬等による降圧の目標値とされるものについて変更し、新たな治療指針である「高血圧管理・治療ガイドライン」を発表したというニュースがありました。何を隠そう……って、別にとりたてて隠そうとしてきたわけでもありませんが、かくいう私自身、数年前に健康診断時に高血圧気味であると診断されて(非常に弱いレベルのものであるとはいえ)降圧剤を処方されている身なので、ここについてあまり偉そうにどうこう書くのもいかがなものかと言われてしまうかもしれないのですが、自身の目標の1つでもある、90歳・100歳までの健康維持ということを考えても、これは無視するわけにはいかない話です。
で、この指針なのですが、従来は75歳以上の人と75歳未満の人とで大きく2分して、それぞれに数値を設定していたのですが、今回の変更ではその区分を撤廃し、75歳以上の目標値を75歳未満と同数値に統一、「上(収縮期)140未満、下(拡張期)90未満」だったものを「上(収縮期)を130未満、下(拡張期)を80未満」としています。ちなみにこの数値は診療所などで計測した場合のもので、それぞれの自宅で計測する家庭での測定値であれば、それぞれ5マイナスして「上は125未満、下は75未満」を目標値とするという内容となっているとのこと。なお、ここで変更になるのはあくまでも降圧投薬の目標値なのであって、血圧がどうなれば「高血圧」とされるのかという判断基準、数値的なボーダーについては、「上が140以上あるいは下が90以上」というもので変わってはいません。私も一時期、このボーダー超えになった時があって、だからこそ定期的に病院に行って薬を処方してもらっています。
高血圧を放置することで様々な病気の原因となってしまうのは間違いないというから、国民の健康を促進するという意味でもガイドライン変更は意味がある、ということなのでしょうが、ただ、血圧の下げ過ぎはむしろ心疾患の可能性を高めるという説もあるらしいんですよね。誰もがそうだというわけではなくてその人がどういう症状で降圧剤を服用しているかで、過降圧リスクの大きさは結構変わるとも聞きますし、いずれにせよ、その辺りが実際どうなのかは素人が簡単にどうこう判断できないですけれど。1つ言えるのは、過去の薬害その他の事例からすると、学会や厚労省、WHO等が言っていることだからといっても100%信じられるとは限らないということでしょう。けれども、最初から全面的に疑ってかかるのも、それはそれで間違っている気もします。となれば、専門家ならぬ身では自分で調べるていくのにも無理がある以上は、ここは、気軽に相談できて信頼できる医師を見つけ、その医師との間に良い関係性を構築していくことが、大きなポイントになる、のかな?
それに、そうやってかかりつけの先生を作っておくと、実際に何かがあった時に、大きな病院への紹介状を書いてもらえるというメリットもあります。医者に通うというのは時間も診療費もかかるものですが、予防医療的なことを一切していないところから大病をする場合のリスクを考えれば、一定の期間ごとに定期的に医院へ通うのは悪いことではないのかも。そこでコミュニケーションをしっかりと取っておくことは、健康維持に役立つでしょう。とはいえ、ひところ話題になったりもした、(そういう人が本当にいるかどうかはともかくとして)何も必然性・必要性が無いのに居場所や話し相手を求めて老人会の集会代わりに病院に通う老人にも、なりたくないのですけれど。
全部で12あるエピソードの中で、ストーリーに他にない特殊性のある、「ランサム・サーガ」の10作目、アーサー・ランサムの『女海賊の島』上下巻(岩波書房 岩波少年文庫)を読了。「舞台は中国。世界一周の航海中、思わぬ事故で船が炎上した子どもたちとキャプテン・フリントは、海賊が支配する島にたどりつきます。泣く子もだまると恐れられる女が遺族、ミスィー・リーの意外な正体とは……。」という上巻の粗筋でお判りいただけるように本作はツバメ号のウォーカー兄妹(ブリジットを除く4名)とアマゾン号のブラケット姉妹、そしてキャプテン・フリントの7名が世界一周帆走の旅をしている中、中国で出会うことになる冒険を描いているという点で、シリーズ中ピカイチの個性を放っているエピソードです。規律に厳しい親の元で育っているウォーカー兄妹が、どれだけ月日を要するか分からない世界一周航海に出ることを許可されると思いにくいということを、子どもの時分にこのエピソードを初めて読んだ時から私は思っていて、だからこの話は、作品世界の中で本当にあったことというよりは、例えばDきょうだいのドロシア辺りが7人をモデルにして書いた作中フィクションの小説なのではないかとも感じたりしています。ストーリーそのものは結構面白いのですが、実に久し振りに今回読み返してみたところ、6人の子どもたちだけでなく、彼等を引率している身としてもっと分別と冷静さを持っているべきキャプテン・フリントまでもが、かなり無責任で考え無しな言動をしているのに、ちょとうんざりしてしまったりも。児童文学としては、こういう展開でいいかもしれませんが……個人的には、こういう態度を取るキャラクターは、あまり好きではないんですよね……。なので、私の中ではこの『女海賊の島』は作中世界でのリアルな出来事ではなく、ドロシアの書いたフィクションだということで確定させておくことにします。そう思って読んでいる分には、前述の点もそこまで気にはなりませんから。
有川ひろ の『イマジン?』(幻冬舎 幻冬舎文庫)の粗筋は、「『朝五時。渋谷、宮益坂上』。その9文字が、良井良助の人生を劇的に変えた。飛び込んだのは映像業界。物語と現実を繋げる魔法の世界にして、ありとあらゆる困難が押し寄せるシビアな現場。だがそこにいたのは、どんなトラブルも無理難題も、情熱×想像力で解決するプロフェッショナル達だった!有川ひろ が紡ぐ、底抜けにパワフルなお仕事小説。」というもの。映像制作会社という、何となくどんな仕事なのかは知っているものの詳細となるとよく知らない仕事を題材にしていて、そのネタ選びは 有川ひろ 自身のアイディアなのか編集サイドの手動なのかは分からないながら、いいところを突いてきたな、という感じ。大体の場合において恋愛モノの要素が絡んでくるのも、有川ひろ らしさですが、本作はそこはそんなに甘めではありません。収録されている5つのエピソードを「ふむふむなるほどね」と思いながら読み進めていて、まぁ、それなりに楽しませてももらったのですけれど、娯楽作品として考えると最終エピソードの読後感がちょっと苦いものになっています。他にスッキリした後味のものもあるのだから、各エピソードの並び順をいじれば、全体として爽快な気分でページを閉じられたであろうに、そういうことにはなっていないわけですね。それくらいのことは、キャリアの長い 有川ひろ であれば先刻承知のはずだから、敢えてこういう並びにして、ああいった展開を持ってきたと考えるべきだとすれば……もしかしたら彼女が過去に自作の映像化で似たような体験をしていて、その時の不満、鬱憤をここで開陳したのかな、と邪推してしまったりもします。
もともとは『神酒クリニックで乾杯を』というシリーズ名で角川文庫から発売されていたものを、天久鷹央の兄が出てきているからという理由で、「天久鷹央の推理ファイル」シリーズがアニメ化されると同時にタイトルを変えて実業之日本社からの出し直しがされた「天久翼の読心カルテ」シリーズ第2弾、知念実希人の『天久翼の読心カルテ 淡雪の記憶』(実業之日本社 実業之日本社文庫)を読了。裏表紙の粗筋は「爆破事件の鍵は、記憶を失った美女。 茅場町を皮切りに都内で多発する連続ビル爆破事件。人々がテロに新刊する中、天久翼を含めた神酒クリニックの六人は、ある電話をきっかけに記憶を失った美女『赤羽』とである。過去を失い、翼でも心が読めない謎の女性。だが、彼女こそがテロの鍵を握る人物で……。記憶と事件が結びつく時、驚きの真実が明らかに!現役医師によるハードボイルド医療ミステリー第2弾。」となっていますが、このシリーズについてはあまり強く「医療」部分を押し出すのもどうなのかな、という気はします。確かに、探偵役を務めるのは医療関係者ですし、その医療知識や技術が解決に貢献しているとも言えますが……実際は「医療」がさほどのカギにはなっていないように私としては感じているからです。それはそれとして普通に面白い作品であるのに、あまり「医療」推しをしてしまうと、それを期待して本作を読んだ人が肩透かしをされて不平不満を述べることになってしまわないかという心配も。作品タイトルも、この内容で「天久翼」主体の題名というのは違和感がありますしね……。そうしたい、そうしなければいけない、という事情は分からなくもありませんけれど。
各所で話題になっている、詠井晴佳の『きみからうまれる』(小学館 ガガガ文庫)の粗筋は「『誰よりも会いたかったです、みきとくん』幼い頃にお別れした名前も知らない初恋の少女が、高校生になった僕の目の前に現れた。彼女――鈴代憬と再会し、会えなかった過去を、新しい現在で埋めていく二人。『わたしが全部、みきとくんの理想を叶えてあげる』繰り返される憬との “見当違い” な倒錯の時間は、みきとの失った初恋と欲求を満たしていく。でも、憬はある秘密を抱えていた。すっかり甘い時間の深みにはまった頃、それを知ったみきとが進む未来は――。過去も、現在も、未来も、きみの理想で塗り替える初恋リメイクストーリー。」というもの。うーむ、これはなかなかに刺激的です。ネグレクト、ヤングケアラー、共依存、嘘と洗脳などなど、かなり攻めた内容となっていて、しかも展開が結構エゲつない。「きみからうまれる」って、そういう意味ですか……。
この尖り具合、個人的には「ガガガ文庫らしい」なと思っているところで、こうなると、(著者の過去作はあまりきちんと読んでいないので偏見や思い込みであるのは承知の上で)どちらかというと “おなみだちょうだい系統” の作品を得意にしている人なのかな、と思っていた私の認識を改める必要がありそう。メンタルの壊れたヒロインは定期的にラノベ新作に出てきますが、つまり一定のニーズがあるという解釈をしてもいいのでしょうか。個人的には、こういうヒロインを可愛いとは思わないのですけれど……。まぁ、「可愛くて魅力的なヒロインが出てくる」ことだけがラノベの(小説の)面白さというわけではないでしね。第2巻の発売も待ち遠しい1冊でした。
ゆうきまさみ の『新九郎、奔る!』第21巻小学館 BIG SPIRITS COMICS SPECIAL)を読了。伊豆の国盗りを決意しつつも、戦力と大義名分が足りないのですぐに決行できるわけでもない。そんな状況で色々と手を打ちながら状況を整えていく新九郎が今巻では描かれています。アクションの前段階である仕込みであり基本的には地道かつ地味な部分なのですが、それを退屈させずに緊迫感を持って描いて魅せるのは、さすが、ゆうきまさみ。本当に面白い、傑作マンガです。
平沢進のユニット 核P-MODEL の『Unzip』を購入。平沢印のテクノポップをこれでもかと浴びせかけられる全10曲で、聴いていて実に心地よかったです。ジャケットは、P-MODEL のデビューアルバムである『IN A MODEL ROOM』を単色にしたようなデザインなわけですけれど、そこに何らかの意図があるかどうか……無いということはないだろうとは思うものの、ではどういう狙いが、というのは分かりません。「始まり」と「終わり」というようなニュアンスでは無いといいなぁ。
谷山浩子の『フェニックスで弾き語り ~初セルフカバー曲集2~』は、彼女が他者に提供した楽曲(歌詞のみのものと、曲のみのもの、そして作詞作曲をしているものの3種類あり)から9曲、自身の音楽劇に作った曲のセルフカバー1曲の、全10曲。ホールでピアノ弾き語りで録音し、そこに佐藤研二のベースや石井AQのトラック等を合わせて制作されたものということなのですが、普通にスタジオ録音のアルバムとして違和感なく聴ける仕上がりとなっていますただ、基本が弾き語りですので、全体的に派手さのない落ち着いた感じの1枚に仕上がっていました。谷山浩子らしい暗さ、谷山浩子らしい重さはほぼ無く、それ以外の谷山浩子、リリカルな谷山浩子をしっかりと堪能できる1枚でした。
凛として時雨の『Lost God of SASORI』は4曲(+リミックス1曲)収録の、EP。いつも通りと言ってしまえばそれまでな彼等の音楽が繰り広げられているのですが……。それをワンパターンと批判することも可能とはいえ、ここまで唯一無二の「凛として時雨な」音楽世界を構築されていると、つまりこういう音楽をやっているのは彼らが 凛として時雨 だからであり、このメンバーが集まって音楽をやるならば必然的な帰結であるのだから問題は無い、という結論に至ります。もちろん、技巧の高低が音楽としての優劣とイコールなわけではないのは言うまでもありませんが、凛として時雨 のメンバーが創り出す音楽は、相変わらずのハイテクニックとハイテンションに満ち満ちていて心の底から堪能できますし、なにより、格好良いことは正義ですしね。
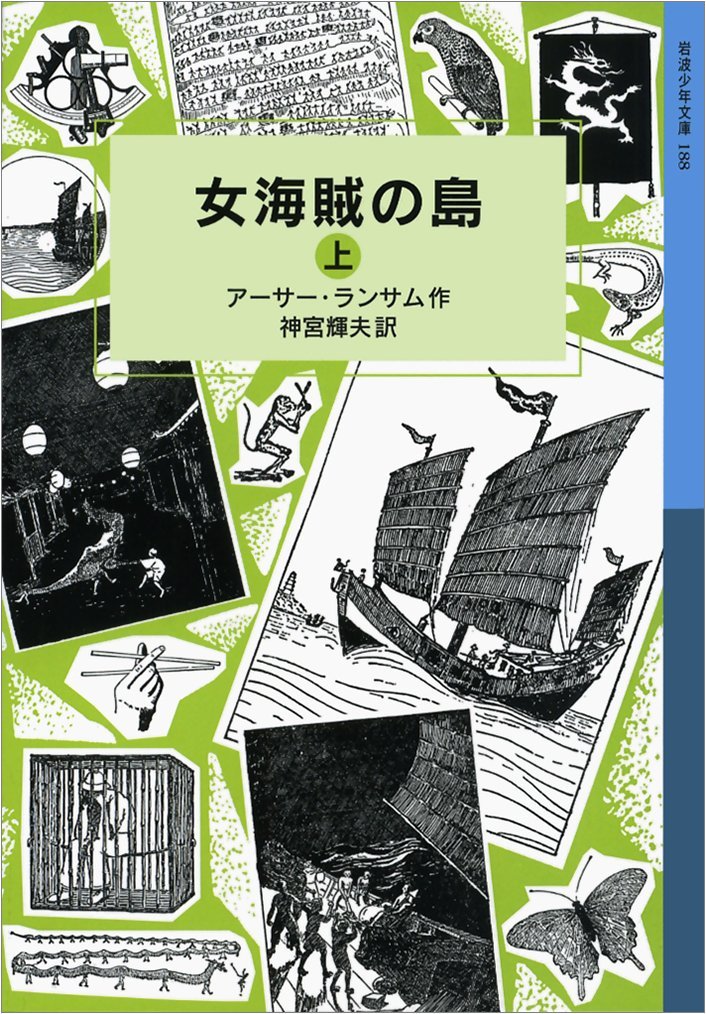
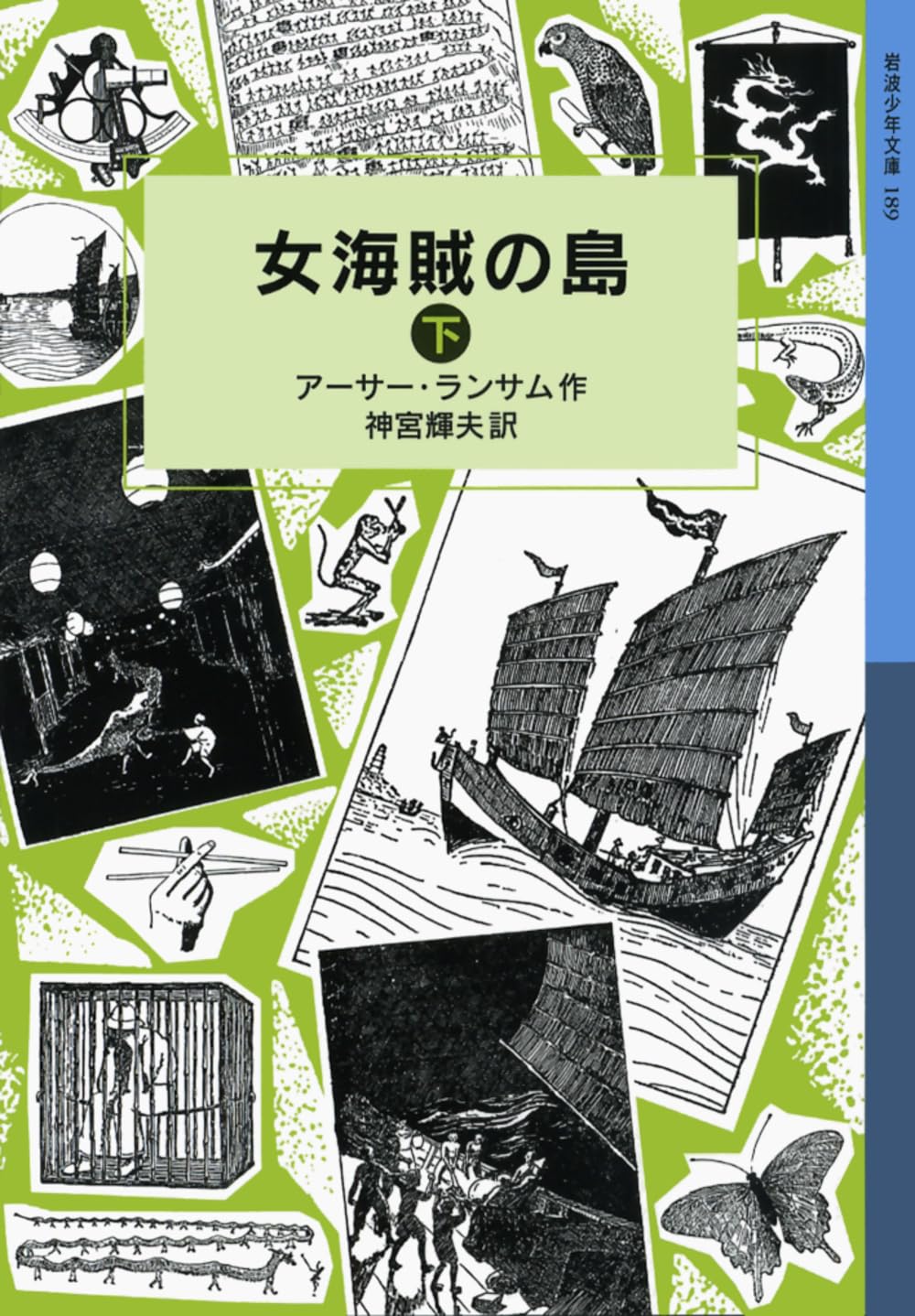



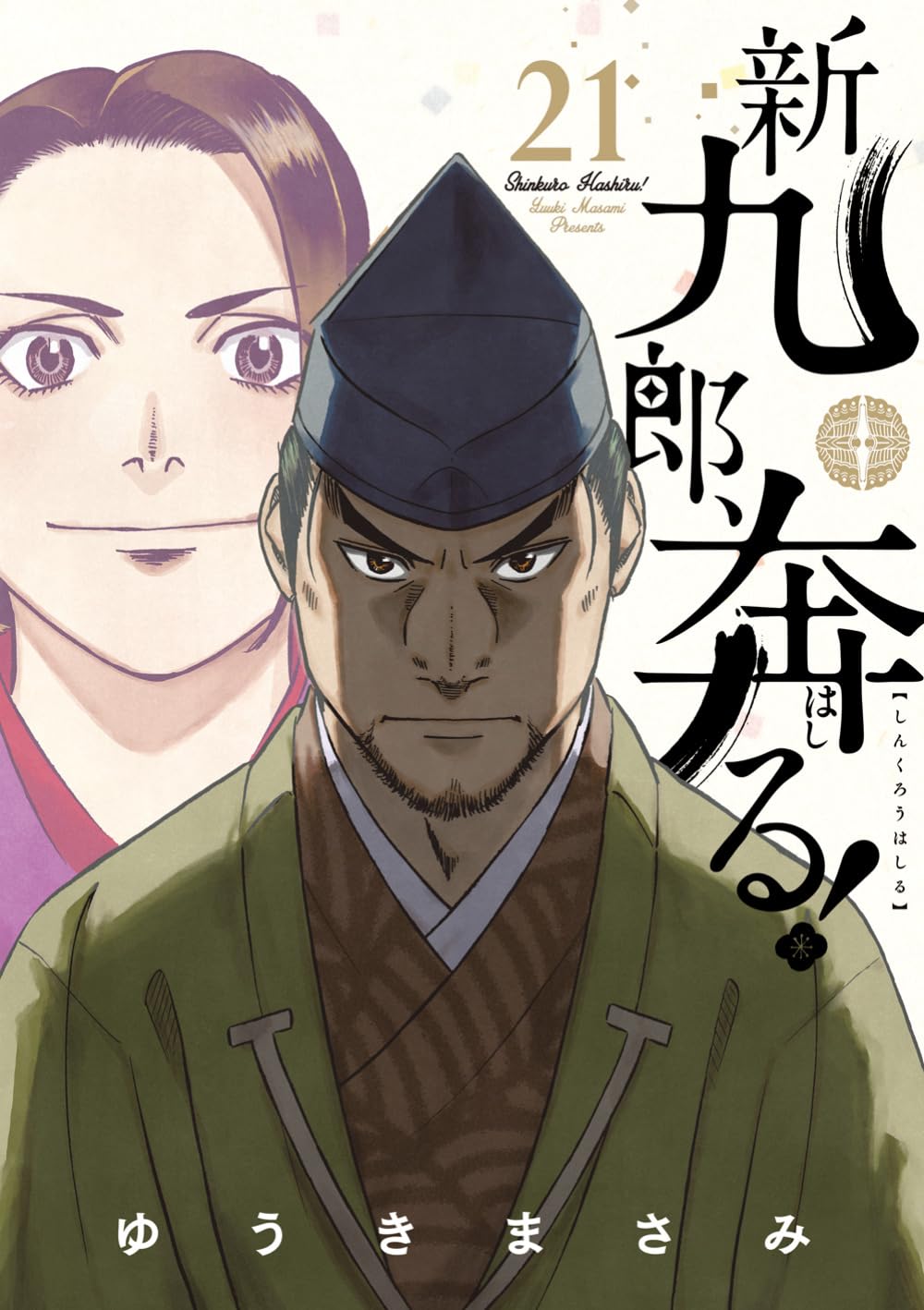



| 2025年11月8日(土) can't live without MUSIC(その5) |
いきなり何の話から始まるのかと思われるかもしれませんが、我が家の方針の一つとして、大学生になったら小遣いは貰えない、というものがありました。大学の入学金、学費、教科書代、通学費用、普段着購入費用等は出してくれるのですが、その先、本やCDを買ったり、友人と遊んだりする費用、つまりいわゆる遊興費については自分でバイトなどをして稼げ、ということです。ですので、大学進学をしたからといって私の懐事情が急に裕福になって、それまでであれば買えなかったCDを買いまくったというようなことはありません。それでもバイトで稼いだ中から、厳選した好きなCDを買うくらいの予算は回せましたし、大学生協で注文すればCDが割引価格になるというのもあって、例えば前回名前を挙げた MOONRIDERS のアルバムとか、松岡英明のアルバム、YAPOOSのアルバムなんかは、この時期に買い揃えていったと思います。また、引き続き視聴していた音楽番組で大学時代に存在を知ったミュージシャンとしては、デビュー曲「愛してくれなかった人達へ」がミュージックトマトジャパン(だったかと思います)でマンスリー曲に選ばれた 服部祐美子 とか、アルバム『ワタツミ・ヤマツミ』収録の「もののけと遊ぶ庭」のMVが強烈な印象を残した SOUL FLOWER UNION とかが挙げられます。
大学時代にはそれ以外だと、早稲田大学に通う友人が、フォークソング部でライブをやるからということで遊びに行った大学祭の日に、ゴスペラーズのステージを観ていたり、自分の大学の学祭でゲストにやってきた LEE SANG EUN(イ・サン・ウン)のライブを聴いてその場で当時の最新アルバムの『Gongmudohaga ~公無渡河歌~』を物販で購入したり、同学部の友人から THE ALFEE の『ARCADIA』を借りて「こりゃ格好いいな」と唸り「そういえば『星空のディスタンス』とか好きだったな」と思い出したり、次姉に頼まれて THE SMITH のアルバムを大学生協に一気注文したりしています。そうやって何枚ものCDを買っているうちに大学生協の職員にも顔を覚えられて、しまいには「今度は何を買うの?」と声を掛けられたり。もともとコレクター気質のある私でしたが、それが業として逃れ得ないレベルにまでなったのが、この時期だったのかなぁと今になれば思います。つまり、自分自身の意思で自由に使える時間が増えたことや友人関係の広がりその他の影響で愛聴する音楽の範囲が広がるのと同時に、少しずつ手元にCD等の音源を集め始めた時期だ、ということですね。
なお、自宅から大学への通学には結構時間がかかる環境だったので、買ったものとレンタルしたものと、CDの音源をカセットテープに落として、ウォークマンで聴きながら通う毎日という、どっぷりと音楽に浸かった生活を送っていた(この時点ではまだまだ私が自分で所有しているカセットの数は限定的であったとはいえ)というこの時の状況が、私の人生に与えた影響は非常に大きいものでした。具体的には、この頃から私の日常に対して、「音楽」が切っても切り離せないものとなっていったのです。もちろんこれ以前から、音楽は好きでした。歌うのも好き、聴くのも好きで、小さい頃は電車の中で大声でアニメソングを歌ったりして、母に怒られたりしていたものです。だからまぁ、なるようになったというか、「三つ子の魂百まで」を実証したというか、それで今に至るまでその状況から抜け切れていないというか……、むしろそうであってこそ私だと開き直っている、そんな風に認識しているところ辺りに、私の禄でも無い側面が出ているかもしれません。
で、そんな大学時代のバイト代だけではさすがに買えなかった、買うのを控えてレンタルで済ませていたようなCDを改めて手元にする、フォローするミュージシャンの数を更に色々と増やしてCDを買っていく、というような、この「ぱんたれい」の「聴く」にあるように、コレクションが際限なく拡充されていくようなことになっていくのは、就職をしてからになります。大学生時代は、さすがにそこまでバイトに時間を割けなかったので、予算の都合から、欲しいCDを厳選しての購入活動となっていました。飲み会で2次会に行くカラオケ対策で演歌の音源を幾つか買ってみたり、好きな曲についてはやっぱり欲しいよなというわけでクラシックのCDも買ったり、というようなことも、就職して給与をもらえるようになってからやったことです。概ね、一度好きになったミュージシャンについてはその後も新作のフォローをし続けているので、購入対象は減るどころか増えるばかり(思想的・行動的にちょっとどうなんだろうかと思うミュージシャンもいましたが、それと音楽とは別物だと切り離して考えるようにしています)。その頃からは同時に本も大量に購入していますから、どれだけそこに資金を投下したんだとよく呆れられますが、酒・タバコ・ギャンブルには手を出さなかったこともあって、趣味の世界に使う余裕は、結構ありました。そのおかげで、今の私の家には、それ1つでおおよそ1,000枚は収納できるCDストッカーが複数存在し、かつ、それにみっちりとCDがしまい込まれている状態になっています。個人的な満足度は非常に高いのですが、傍から見るとさすがにどうかしていると思われるかもしれません。でも、いいんです。私自身はそれに納得していて、かつ、それ等は全て自己資金で、法に触れることなく手にしているのですから。
「ランサム・サーガ」の9作目、アーサー・ランサムの『六人の探偵たち』上下巻(岩波書房 岩波少年文庫)の上巻にある粗筋は、「ノーフォークの湖沼地方で、船がつぎつぎに流される事件が発生。ジョー、ビル、ピートらオオバンクラブの仲間たちに疑いがかけられます。ディックとドロシアは探偵団を結成して、事態に立ち向かいますが……。」というもの。ノーフォーク、そしてオオバンクラブということで、ツバメ号のウォーカー兄妹も、アマゾン号のブラケット姉妹も登場しません。主役として活躍するのはオオバンクラブの中でも、デサンドグローリ号の3名で、ディックとドロシアのDきょうだいは、ポジション的には助演のサブキャラというような扱いになっています。今回はシリーズでは唯一の犯人探しモノで、まぁ誰が犯人かというのはわりと早々に分かってしまうのですけれども、謎解きでどうこうというような作品では無いから、そこは問題ありません。子供らの “冒険” が生き生きと描かれているのが魅力なシリーズですから、それが本作のようにきっちりと行われていれば、それだけでもう十分以上に楽しめます。シリーズは残り3エピソード。このまま一気に読んでいきます。
日本の昔話・民話を元ネタにしたミステリーがまずあって、その派生として西洋童話からネタを引っ張ってきたというライトミステリーの第2弾である、青柳碧人の『赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。』(双葉社 双葉文庫)を読了しました。「大ヒット作『赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。』の第2弾が登場!――おじさんにクッキーとワインを届ける途中、赤ずきんはピノキオの右腕を拾いました。実はピノキオ、体をばらばらにされていて、赤ずきんはそれらを集めるたびに出ます。ところが、殺しの犯人として逮捕されてしまったのです。 ピノキオのほか、親指姫や白雪姫、笛吹き男に三匹の子豚など、世界の童話の主人公がいろいろな事件に登場する驚き連続の連作ミステリ!」というのがその粗筋で、今回はピノキオを道化的なポジションに据えて、全4編のエピソードが展開されています。童話の持つ残酷性を保持しているところが面白いところでもある一連の作品ですが、今回も、まずまず面白く読ませてもらいました。個人的には、赤ずきんのキメセリフ、「あなたの犯罪計画は、どうしてそんなに杜撰なの?」がちょっと気に入っています。
佐伯さんの『お隣の天子様にいつの間にか駄目人間にされていた件』第11.5巻(SBクリエイティブ GA文庫)の粗筋は、「自堕落な独り暮らし生活を送っていた高校生の藤宮周と、“天使様” とあだ名される学校一の美少女、椎名真昼。かけがえのない毎日を共に過ごすなか、お隣さんの関係から、お互いに生涯を捧げたいと思える相手へとなった二人。愛しい人ができて初めて知る気持ちや、思いがけず救われる言葉。周と真昼が出会い変わっていく世界で、何気ない日々の宝物を綴った描き下ろし短編集。」というもの。前巻のラストに不穏な引きをしておいて短編集か、というのは気にならないではありませんが、あとがきにおいて作者は、それは重々承知の上で、作中で主人公たちの学年が変わる前に短編集を挟んでおきたかったのだと説明しています。その気持ちは分からないでは無いし、基本的に主人公たちがまったりとイチャイチャするのを楽しむ作品なわけだから、第12巻が少しお預けを喰らったところで、そんなにダメージはないかも。
永瀬さらさ の『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中』(KADOKAWA ビーンズ文庫)のスピンオフ外伝、『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中 プラティ大陸正史』(KASOKAWA)を読了。本編あってのスピンオフなので、書籍名にどこか暢気さを漂わせている本作の、帯に印刷された粗筋は「『愛してくれる竜妃なんかいない』 プラティ大陸を分かつラーヴェ帝国とクレイトス王国。二国間で火種が燻る中、即位した竜帝ハディス。彼の支えは誰にも見えない竜神だけ。歴史の因果、出生の秘密、度重なる裏切りとすれ違いの果てに彼が選んだ道は粛清だった――。ジルの家族や仲間、ハディスのきょうだいたちが死にゆく中で思い願ったこととは……?ジルが竜妃にならなかった本当の歴史。地図や大陸史も収録した待望の一冊! 『一人残らず殺せ』 さあ、世界終焉へ……」というもの。要は、本編主人公のジルがタイムリープをして人生をやり直す前の、「元々はこうであった」歴史を描いた1冊なわけですけれども、率直に言って、これがハードかつエゲつない。まぁ、そうやって世界の破綻、崩壊が竜帝ハディスによってもたらされ、自身も破滅することが分かっているジルが、それを回避しようとしつつ竜帝とイチャイチャするというのが本編なわけで、その回避&イチャイチャを除いたら、残るのは救いの無いシリアスでヘヴィーなストーリーだけになるというのは、当然の帰結なわけですけれど。
さて、そんな本作ですが、そのような内容だからでしょう、本編と同じフォーマットであるビーンズ文庫からの発売ではなく、ソフトカバー単行本の形を獲ったというのは良く理解できる話です。本編読者に気が付かれないかもしれない、手に取ってもらえないかもしれない可能性はありつつも、きちんと差別化をしたというわけですね。雪乃紗衣の「彩雲国物語」シリーズの外伝『骸骨を乞う』と同じ流れですが、そういえばあれも本編はビーンズ文庫でしたね(今は角川文庫版も出ていますけれど)。気になるのは「きょうだい」という表記で、作品内容のシビアさに対して、これだと何だか気が抜けるというか、ミスマッチというか、作品の雰囲気に相応しくない感じがしてならないこと。兄も姉も弟も妹もいるから、「兄弟」「兄妹」「姉妹」「姉弟」といったような表記ができない。さりとて毎回「兄弟姉妹」と書くのもわずらわしい。ならばということで「きょうだい」という表記を採用したのだろうな、というのは分かりますが、せっかく硬質な雰囲気を濃く纏っている作品なのに、もったいないなぁと思ってしまった次第です。あと、タイトルに「やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中」という本編シリーズ名を付したのも、作品の雰囲気的には違和感があるのですが、これは本編あっての外伝だということからすればやむを得ないかな。物語の重層化に大いに貢献する外伝で、面白く読ませていただきました。
物語がクライマックスに入ってきたのかなという、岩原裕二の『クレバデス 魔獣の王と赤子と屍の勇者』第10巻(KADOKAWA MFコミックス アライブ+シリーズ)。作品世界の根本的な設定、謎が明かされはじめてきていて、話のスケールがさらにグッと広がってきました。ここから少し世界のなぞ解明的なところの話が入って、それで怒涛の畳み込みのような流れでしょうか。どうせならばこの2倍でも3倍でも続いてくれてもいいくらいの作品ですが、それをやると変に冗長になってむしろつまらなくなってしまいそうですし、ここで思いっきり盛り上げて一気に大団円へ、というのが作品にとって最適、かなぁ。
羽海野チカ の『3月のライオン』第18巻(白水社 YOUNG ANIMAL COMICS)は、1冊ほぼ丸々が島田さんの話。表紙も小雪舞う夜の聖橋(お茶の水)の上で湯島聖堂方向を見ている島田さんですし。まぁ、作者にも読者にも愛されているキャラですしね、島田さん。そして巻末のあとがきによれば、本作は次の第19巻で完結(予定)とのこと。正直、本作については、どういう終わり方をすれば「大団円」と感じられるのかが今一つ想像つかないところもあるのですが、例えば あかりさん が誰と交際・結婚をするのかが解決したり、零がタイトルを獲ったり、あるいは高校を卒業したりというところに、これまでの描かれてきた様々な人生模様と作品全体のテーマを絡めれば、良い感じにまとまる、のかな……。作者の体力気力的な要素もあって、ここから完結までは物語をギュッと詰め込んで一気に進めていくことになるような感じなのですが、変に駆け足感が出て忙しなかったり消化不良だったりという感じにならなければいいな、とは思います。
2クールで放送されたTVアニメは知る人ぞ知るという感じになってしまいましたが、出来は決して悪くなかったのでもうちょっと宣伝が成されていればと惜しい気持ちにもなってしまった、宮下裕樹の『宇宙人ムームー』第9巻(少年画報社 YKコミックス)。アニメは第7巻の途中までで、連載の方は現在アニメ最終回以降の物語が進行中なわけですけれども、今回の第9巻は、また、なかなかに派手な展開となっています。派手な展開、バトル展開も、日常のゆるい家電薀蓄話も、どちらもこの作品の大きな魅力ですが、ここでこんなに盛り上げて、本当のラストではどうするのかという心配も出てきます。案外、このままラストに突入していくのかもしれませんけれど。
ヤマザキコレの『魔法使いの嫁』第23巻(ブシロードワークス ブシロードコミックス)は、ここから先の大きな展開を前にして各キャラクターの深掘りをしつつ色々と仕込んでいるのかな、という内容。完全なるサブエピソードというのではなく、今後に向けての準備という感じですね。なので、この先どうなっていくのか、これをどう展開させていくのかを予想してみるのも一興で、結構楽しみながら読ませていただきました。




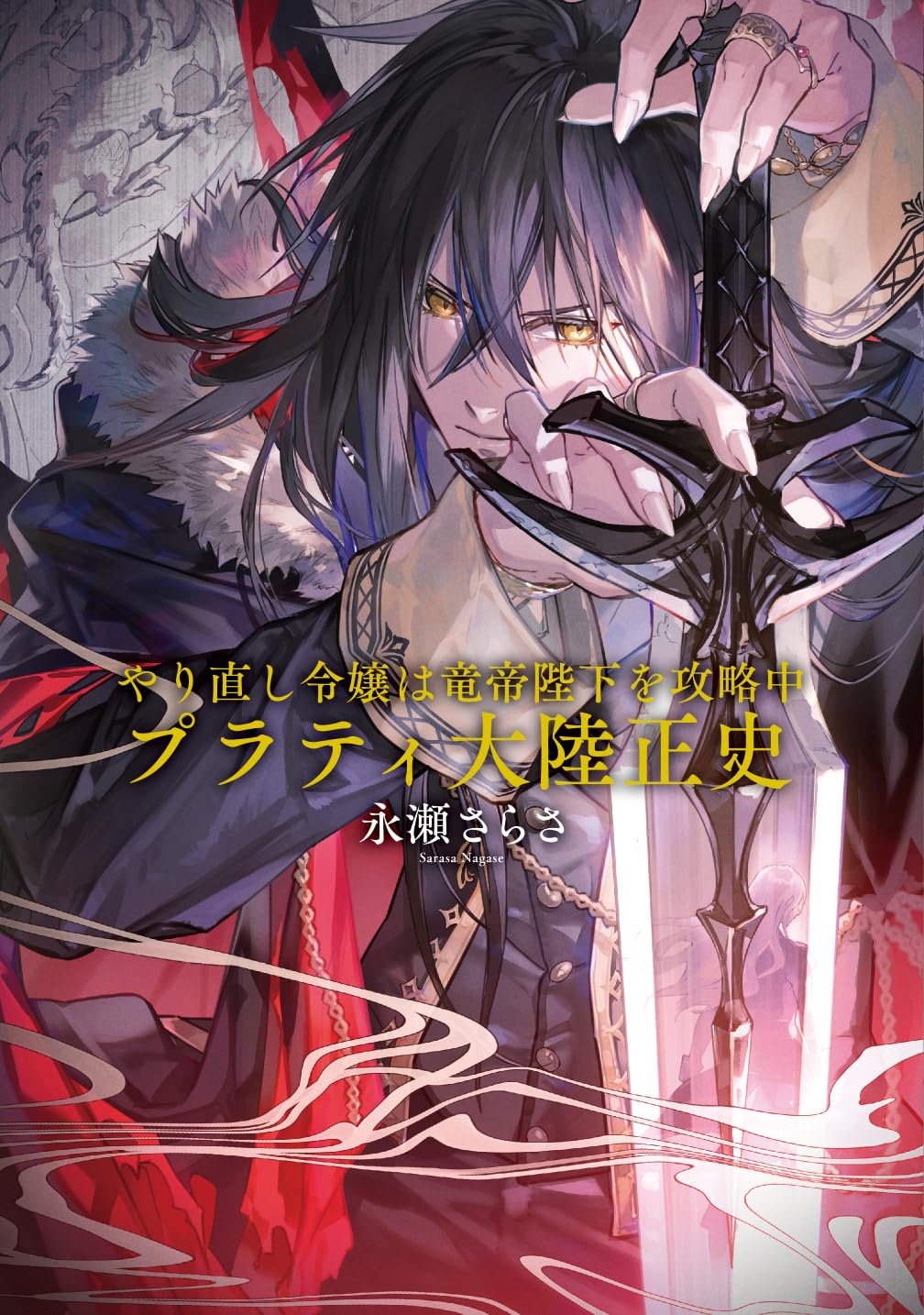




| 2025年10月31日(金) 植物学と書道と |
毎週土曜日に更新するのがこの「ぱんたれい」の基本スタンスのところ、諸事情で1日更新を早くしたというイレギュラーですが、今回が10月最後の「雑記」更新ですから、恒例に則って Top写真 を変更しました。先月に続いて秋っぽい画像をということで、今回は秋の花を撮影したものを選択。以前にもこういう花をアップで撮影したものを何回か使ったことがありますが、その際にも書いたように、私は植物の名前には全く詳しくありません。人は興味の無いものに対してはそんなに知識欲が湧かないものですけれども、確かに私、「全く」とまでいくとさすがに言い過ぎですが、植物に関して、それがどういう名前で、どういう花を咲かせて、学術上どういう分類に属するのか、というようなことには関心が乏しいかもしれません。とはいえ、それで済ませてしまうのもちょっとアレですから、少しネット検索をして調べてみました。多分、今回のこの画像に写っているのは、ヒユ科ケイトウ属の植物、鶏頭(ケイトウ)だろうと思われます。しっかりと確定までしているわけではありませんけれども、見た目などの特徴から、ほぼ間違いないと思います。
こういうことを書くと、普通は、植物の名前くらいまではともかくとして、科や属まで記憶していたりはしないものだろう、という指摘を受けたりします。それは確かにそうでしょう。が、私の場合はそもそも家庭環境が(そういう意味では)普通では無かったという特殊事情があります。というのも、私の母方の祖父が植物に関しては専門家で、その影響から母も植物には非常に詳しく、2023年前半の朝ドラ『らんまん』のモデルになった牧野富太郎が出した日本植物図鑑が実家の本棚にずらりと並んでいるというような中で育ってきているのです。そういうことであれば私もその流れで、少なくとも一般の人より少し上くらいのレベルでは植物に詳しくなりそうなものなのですが、実際は、一般と同じくらいか、下手をしたらそれ以下のレベルで、植物に関する知識がありませんし、当然、判別をすることもできません。
親が知っていれば/できれば、子供もそうなるというわけではないよ、ということの良い例になるかもしれませんね。同じように、父の趣味の1つに書道があって、中国の古人の名筆の拓本を集めた大判本が全集で本棚に並んでいて、それを見本に字を書いていた父は達筆なのですけれど……。私はというと、結婚式の芳名帳や、ご祝儀袋や香典袋などに筆ペンで署名をしようという時に、あまりに字が下手クソなので毎回絶望感に襲われている始末。達筆とまで行かなくてもいいのですが、筆である程度(せめて、人に笑われないで済むくらいの、バランスの取れた普通のレベルで)綺麗な字が書けたらこんな恥ずかしい気持ちにはならずに済むのにとは思うものの、今から習字教室などに通う気にもなれず(というか、大人も入れるような習字教室が通える範囲にあるかどうかも分からず)燻っている現状は、客観的に見て、ちょっと情けないですよね。これは、適切な書道教室の所在を調べて思い切って入会すべきなのかもしれません。忙しさを言い訳にせずに、そこに通う為の時間は無理やりにでも捻出して。
前作『海へ出るつもりじゃなかった』の直後から話が始まる、「ランサム・サーガ」の8作目、アーサー・ランサムの『ひみつの海』上下巻(岩波書房 岩波少年文庫)。実は今回の再読をするにあたって、全部で12あるランサム・サーガ作品のうち、どういう内容だったのかを漠然とでも思い浮かべられなかったのが、これでした。もちろん読み始めてしまえば「そういえば、こういう内容だった」とすぐに思い出したのですけれども、そういう、私にとって少々印象の薄かった本作の上巻裏表紙にある粗筋は「船の赤ちゃん、ブリジットも加わり、浮き沈みする秘密の島々の探検に乗り出した子どもたち。白地図に調査した場所を一つ一つ描き込んでいきます。ところが、そこは地元の部族、ウナギ族のなわばりで……。」というもの。これはイギリス国内での話ですので、ここで言う「部族」というのはもちろん、現地に住んでいる新たなる子どもたちということになります。今回のポイントになるのは「未開の地の冒険」「地図の作成」という要素で、もちろん本当に未開の地なわけでは無くて、ウォーカー兄妹にとって初めての地だからそこを未開の地であると見做して楽しもうということなわけですけれど、今回もしっかりと楽しませてもらいました。それに、いよいよブリジットがメンバーに加わってきたのも新鮮でしたしね。
今野天龍の『幽世の薬剤師 鬼の花婿』(新潮社 新潮文庫nex)は、第2部になってからナンバリングが表題につかなくなったので分かりにくいのですが、シリーズ10冊目という、2桁の大台に乗ったある種メモリアルな1冊。それが表紙からだと分からない、途中からシリーズの読者になった人はどういう順番で買い進めていけばいいのかに迷いかねない、という点から、私としては最近のこういう、シリーズものなのに巻数を表紙に載せないという風潮には否定的なのですけれども……。まぁ、それはそれとしてそんな今作の裏表紙の粗筋は「天子として命じる。薬剤師・空洞淵霧瑚は、鬼の王族の婿となれ――。異世界『幽世』で暮らす空洞淵がある日、目覚めるとそこは鬼の国だった。牢獄に入れられた上、一族にかけられた『呪い』を解け、と命じられる薬師。しかも、依頼を達成できない場合は鬼の王女と結婚することに……。難局を乗り切り、綺翠の元へと帰れるのか。現役薬剤師が描く異世界×医療×和風ファンタジー!」というもの。いつものような設定でいつものような展開のいつものような物語が綴られているわけですけれども、それがこのシリーズの面白さでもありますし、食傷気味になる程に続いているわけでもないので、特に問題は無し。第2部の敵役のことも徐々に明らかになりつつありますし、霧瑚と綺翠の関係も大きく進展するしで、楽しく読ませてもらいました。
「天久鷹央の推理ファイル」シリーズのアニメ化を受けてでしょう、鷹央の兄が出ている知念実希人の別シリーズがタイトル等を改めて加筆修正され『天久翼の読心カルテ 神酒クリニックで乾杯を』(実業之日本社 実業之日本社文庫)として今年頭に出版されました。「神酒クリニック。院長である神酒章一郎のもとに集ったのは、六人の天才たち。その中には、天久鷹央の兄、精神科医・天久翼の姿もあったーー。とある資産家から息子殺害の犯人探しを依頼された翼たちは、事件が想像以上の『闇』を孕んでいることに気づく。違法賭博。誘拐。殺人。複雑に絡み合う謎の真相は?現役医師による、もう1つの代表シリーズ。ハードボイルド医療ミステリー!」というのが粗筋なのですが、もともと「天久翼」という人物にそこまでフォーカスしたわけでもない作品を「天久翼の読心カルテ」とリタイトルするというのには、ちょっと違和感が無いわけではなりません。また、作品のテイストが両作品ではちょっと異なるので、兄妹シリーズのように扱うのはどうかのかなという気が……。セールスを考えた宣伝戦略としては、これで正解だよなとも思いますけれど。中身は、各キャラの能力がさすがに盛り過ぎなのではと思われる点を差し引けば、かなり面白くて、なかなか楽しんで読ませてもらいました。2019年にはドラマにもなっているんでしたっけ?本作には続編も出ているので、そちらも読まなければなりませんね。
約半年前の発売時に購入して積読化していた『筋肉少女帯小説化計画』(KADOKAWA)は、筋肉少女帯の楽曲を題材とする6編の書き下ろし小説を集めた1冊。収録作は順に、辻村深月の「中二病の神ドロシー」、柴田勝家の「十光年先のボクへ」、滝本竜彦の「日光行わたらせ渓谷鐵道」、空木春宵の「ディオネア・フューチャー」、和嶋慎治の「福耳の子供」、大槻ケンヂの「香奈、頭をよくしてあげよう」となっています。特定の音楽やら画やらから着想を得て小説を書く、というのはそこまで珍しいことではなく、プロの作品の中にもしばしば見受けられますし、私自身も「書く」に掲載している幾つかの作品はそんな感じで作っていたりします。小説にするに際して、元々の曲や画のテイストをどこまで残すのかは作品それぞれ、書き手それぞれでしょうが、こういうのは元ネタを知っていると「1粒で2度美味しい」感じにもなりますよね。私は筋肉少女帯についてはアルバムを揃えているくらい好きですので、まさしくその状態で、大いに楽しませてもらいました。
筋肉少女帯、大槻ケンヂの作る曲がどういうものなのかをご存じの方はこの作品集があの雰囲気を再現できているのかどうかが不安になるかもしれませんけれど、ご安心ください。大槻ケンヂ自身の手による作品、人間椅子の和嶋慎治の作品はもちろん、それ以外の4編も含めた全てが、まさしくこれそ筋少だ、というような濃い仕上がりになっています。柴田勝家と滝本竜彦、空木春宵と大槻ケンヂの4作品が個人的なお気に入りですが、他の2作品も決して悪いわけではなく、むしろ素晴らしい出来だと言っていいでしょう。つまり、この企画モノは(セールス的にどうであったかは分かりませんが内容的には)大成功であり、6編の傑作の集合体なのです。全体的にかなりロマンチックなところも含め、素晴らしい1冊でした。
幸村誠の『ヴィンランド・サガ』第29巻(講談社 アフタヌーンKC)は2005年4月の連載開始(当初は『週刊少年マガジン』で、同年12月からは『月刊アフタヌーン』で)から20年を経て、堂々の完結。トルフィン・カルルセヴニのヴィンランド入植が失敗に終わることは史実で確定しており、だから本作もハッピーエンドと行かないことは最初から分かっていました。無理やりハッピーな終わり方をさせるならば、入植して、麦が実って収穫が出来た辺りで終わらせるような感じでしょう。それで、モノローグで最終的に入植が失敗に終わることに言及するという。ただ、それではトルフィンの、ここまで描かれてきた『ヴィンランド・サガ』という物語の終わり方としてはそれでは相応しくない。やはり、王道楽土を思い描いて海を渡ってきたヴィンランドでも、人は戦いを忘れることが出来なかったこと、殺し合いの果てに夢が挫折すること、それでもトルフィンは前を向いて次の世代へと希望を繋ぐこと、そしてノルドの民とウーヌゥ人(ネイティブアメリカン)との間の融和の種子はキョロ&ニスカやブルムクに僅かながらも芽吹いていることを描いての完結。良い物語でした。私が改めて言うまでもないでしょうが、日本のマンガ史に間違いなく残る傑作です。
angela の新譜、『Answer』を購入。相変わらずのタイアップの多さに、人気の高さがうかがえます。『宇宙のステルヴィア』のOP「明日へのbrilliant road」を始めてみた時にシングル購入を決意し、彼らのファンになってから、まもなく四半世紀。それだけの間ファンとして追いかけてきたことを思うと何だか感慨深いものがあります。今回のアルバムについては、特に凄いということもないけれども、悪いということも当然無くて、いつもの angela が展開されているなぁという感じです。彼らの新譜に対する私のもともとの期待値が高いのは自覚していますが、そのうえでこう感じるということは、一般的にはなかなかハイレベルなアルバムだということになるかもしれませんけれども、まぁ、そこはそれ。
麻枝准×やなぎなぎ の『Love Song from the Water』はスマホゲームの『ヘブンバーンズレッド』に使用された楽曲を集めたという企画アルバム。内容はいかにも麻枝准らしい13曲で、良い意味でも悪い意味でもワンパターンなのは否めないのですけれど、基本的にクオリティーが高いのでほとんど飽きたりすることなく聴くことができました。なかなか良質なアルバムだと思います。同じようなテイストで何枚も聴くような感じでは無いかもという気もするのですが……11月末には2ndが出るので、そちらも買ってみるつもりです。どこまで存分に楽しめるかは分からないのですが、この1枚目の出来がいいだけに、期待はしています。
山崎まさよし のベスト盤『山崎見聞録 30TH ANNIVERSARY ALL THE BEST』は、そのタイトルの通り彼のデビュー30周年を記念して発売された、3枚組。30年といっても寡作な彼のことですから、その年数だけ活動している日本のミュージシャンにしては発表してきた作品はそんなに多くありません(欧米のミュージシャンだと、山崎まさよし より少ないくらいの人も珍しくありませんが)。そんな中から選ばれた全31曲+ボーナストラック2曲ですが、これまで彼の音楽をまとめて聴いたことがなかったというような人には、入門的にもお薦めな内容になっているかもしれません。……私がマイベストを選ぶと多分こうはならないですけれども、一般的には、こういうラインナップですよね。ライブの件で炎上もあったりしましたが、音楽的には間違いなくかなり良いものをやっているので、3,500円程度でこれが買えるというのはお得ですし、興味があるならば、是非。









| 2025年10月25日(金) 再配達の日時指定 |
以前に7月19日の「雑記」で国土交通省が通販等の配達に関して「置き配」を標準的な方法として制度化することを検討しているという話について、疑問を呈しました。それと若干関係してくることですが、実は最近、私は Amazon で何かを購入するのを控えていたりします。というのも、ちょっと前から Amazon で発注した商品を配達しに来る業者の質が、どう考えても著しく悪くなっているからです。かつての Amazon はヤマト運輸や佐川急便、日本郵便等の大手配達業者と提携契約を結んでいて、そういった会社か、せいぜいそこの下請けの地域の事業者が配達にきていたのですが……、今でもそれ等の会社との提携が完全に解消されたというわけではないのでしょうけれども、私の住んでいる地域では少なくとも大手事業者による戸別配送は無くなっていて、個人事業の軽貨物配送事業者が回っているようです。
そこでちょっと調べてみたところ、これは「Amazon Flex (Amazon フレックス)というシステムの模様。具体的には、小規模運送の個人事業主(黒ナンバーの軽貨物車を所有している人に限ります)に対して、Amazon が直接的に配送業務を委託していくという内容で、よくあるその手の契約と違うのは、事業者の側で働きたい日時を自由に選んで設定ができるということらしいです。そういう形態なので、名前も「Flex」となっているのでしょう。サラリーマンが副業などでやることもできるでしょうし、そうでなくても、事業者の側にとってみれば、自分にとって無理のない形で働くことができるという点で、いわゆる「働き方改革」の考え方にも沿う悪くないシステムだと言うことができそうです。
ただ、実際にその荷物を受け取る商品発注者の側からするとどうなんだろうか、というのが、今回私の言いたいことになります。もちろん、小規模個人事業者がスポット的にアマゾンの仕事を受けて配達をする、そのドライバーの全てに問題があると言いたいわけではありません。むしろ、しっかりとした仕事をしている人の方が多いのだろうなと(期待的には)思っています。しかし私の住んでいる地域を担当することになったドライバーについては、何だかなぁと言わざるを得ないところがあったというのは否めない事実です。最初の配達が私の不在時(平日の日中だったので出勤して仕事をしていました)だったのは、時間指定をしていなかった私も悪いのでいいのですけれど、そこで不在通知を入れて再配達日時を指定させるのではなく、Amazon の注文情報上も、スマホにアプリ経由で届いたメッセージでも、後ほど再配達で訪問します、となっていたんですね。ということは、当日の夜に再配達で来てくれるのかなと思うのが普通でしょう。そこで仕事を定時で打ち切って早めに帰宅し着荷を待っていたところ、その日は空振り。「どういうことだ?」と思っていたら、翌日の日中でまた不在通知が入っていて、そこでも「後ほど再配達」としていながらもその日も再訪は無し。翌日も同じ。翌々日は不在通知すら入っていない(つまり、配達に来もしない)。あくまでも日中(それも午前中)にしか配達しない、ユーザーからの日時指定は絶対にさせない、自分の好きな日時に配達させてもらう、というスタンスが露骨に透けて見えていますよね。これが1回の注文だけでなく、複数回続いたので、さすがに我慢の限界となった私はアマゾンのカスタマーセンターにクレームを入れると同時に、配達未了だった注文についてはその時点で把握できたもの全てをキャンセルしました。
ネット通販の配送・受取の現行システムにそもそも問題の根っこがあるということは、7月の雑記に書いたとおりですが、それはそれとして、このドライバーの行動もどうかなとは思ったので、(それ以上アマゾンやドライバーを不必要に責めることはしたくなかったし)余計なトラブルやストレスを作らない為にはアマゾンでの買い物を控えることにするしかないと考えたわけです。要は、他に購入経路があるのであれば、多少の運送費が発生するとしても、そちらで買うことにした方がはるかにいいと考えざるを得ない、ということ。それで現状は様子を見ているところなのですが、結局のところ、配送業界全体でドライバー不足とか報酬の妥当性とか再配達発生の抑止とか、そういう対応がきっちりとなされないと、こういうことは解決には至らないんだろうなと思います。そしてその手段として「置き配」をというのはマズいのではないか、ということと、ならばどういうやり方があり得ると私が考えているのか、というようなことは、7月の雑記で確認していただければ。
その時に書かなかったことを追記しておくと、9月半ばに出てきた、国交省がオートロックマンションで配送業者が「置き配」をできるようにパスキーを与えることも検討しているとかいう話もあります。今回書いたように、Amazon のような大手であっても現実の配送業者の質が低下している中でそれをやるということは、窃盗だけでなくストーカー犯罪等をも助長することになる未来しか見えないのですけれど……。だって、軽貨物業の個人事業主として大手の下請けなどに入れば、オートロックマンションに入り放題になるということですよね、これって。配送業を隠れ蓑として利用しようという輩が出てくる恐れが否定できない、というか、その可能性はかなり高くなりそうです。私程度がすぐに思いつくこんなことが国交省のお役人には分からないのか、そんなことは警察の領分だからどうでもいいと思っているのか、それともその両方なのか。
かなり長くなったので今回はこれくらいで終わらせますが、とりあえず、かなり前に予約を入れていて初回特典等の絡みでキャンセル不可だった商品が発売になったことで、随分久し振りにアマゾンの荷物を受け取った(今回はパッケージも小さく、ポストへの投函で配達は完結しています)ことで当時のストレスを思い出してしまったものですから、ここに少し、Amazon Flex への不満を吐き出してガス抜きをしておかないと、と、読んでいて気持ちの良い文章とはならないことを承知で、グダグダと愚痴をこぼさせていただきました。まぁ、そんなことを言いながらも、この「雑記」の末尾には Amazon のアフィリエイトを設定しているのですが、これは紹介している書籍の書影・CDのジャケットを(著作権的にクリアな方法で)画像で表示した方が、ここをお読みいただいている貴重な読者の皆さんがイメージしやすいだろうというところで載せているものとなっています。つまりアフィリエイト収入を目当てにしているものではありませんし、当然、Amazon で買ってほしいというような意図は全くないので、お許しいただけると……。私の住んでいるところとは別の地域を担当しているドライバーは、逆にちゃんとしているかもしれないですし。
「ランサム・サーガ」の中でも1,2を争うくらいに私が好きな7作目、アーサー・ランサムの『海へ出るつもりじゃなかった』上下巻(岩波書房 岩波少年文庫)を読了。「河口の町ビン・ミルにやってきたツバメ号の乗組員たちは、ゴブリン号をあやつる青年ジムと知り合い、いっしょに川をくだることに。ところがジムがいない間に、船は錨を失い、河口から外海に流されてしまいます。」というのが上巻の粗筋になるのですが、このエピソードは、冒険モノとして非常に優れたものだと私としては思っています。「ランサム・サーガ」について今更ネタバレでもなかろうということでもう少し書いてしまうと、ツバメ号のクルーであるウォーカー兄妹は、ジムのいないゴブリン号の錨をアクシデントとミスで失い、嵐の中、自分たちがどこにいるかも不明瞭なままに海を航海することになるのです。果たして、荒れる海に揉まれる船を彼等はしっかりと操って、無事に母校であるビン・ミルに戻ることができるのか、というのが、本作のストーリーになります。
ベテランの船乗りもいない中、兄妹4人という子供だけでの外海航海、しかも悪天候という厳しいコンディションでの冒険です。これでワクワクしない方が難しいというものでしょう。少年少女の冒険モノとして正統派です。今作はメンバーをウォーカー家の4人に絞っていることも、良い方向に働いています。それによって視点が変に分散することなく、また、ジョン、スーザン、ティティ、ロジャそれぞれのキャラクター性が際立ってくることにもなっていて、特に、ジョンが非常に頼りになるのがいいですね。これまでのシリーズでも長男としてのポジションでの言動を見せていましたが、本当の危機に際して長子としての自覚が強くなったというか、真の頼りがいが出てきたというか。いきなり本作から読むのではなく、できればシリーズを読み進めていって欲しいところながら、最悪、いきなりこれを読むのでも十分楽しめるかもしれない、それくらい面白い作品です。
猿渡かざみ の『殺し屋JKとハンバーガー』(KADOKAWA 電撃文庫)は、単巻作品なのであろう、なかなか攻めた作品。その粗筋は「おしゃべりJKの素顔は無敵の殺し屋コンビ!?『やっぱり育ちの良さってのは笑い方に出ると思うね!』『急になんですか、チドリさん』『てかそういえば私、チドリの笑顔ってまだ見たことないかも』『人は楽しくなければ笑いませんから』『……ああっ、あっ!? ノンデリ発言! まるで私と駄弁ってる時間が楽しくないみたいだろ! おいツバメ、スマイルよこせ!』『しょうもな……ほらチドリさん、早くこの人たちを片付けますよ』 これは二人で無駄話して、しょっちゅうけんかして。もちろんきちんと仕事もこなして――最後にはハンバーガーを食べる、そんな彼女たちのお話。殺し屋としても女子高生としても無敵な彼女たちの青春の一幕。」というものなのですが、この、あっけらかんと人を殺していくインモラルさ……最近こういう悪品も増えてきているような気がします。それが必ずしも悪いというわけではなくて、一頃多かった、殺人をしてしまうことに対して思い悩むとか、逆にそれが当たり前だと洗脳されていて疑問にも思わないとか、そういうシリアスだったり重かったりするような作りではなくて、「殺し屋」であるということそのものは特に何がどうということもない、それこそ「ケーキ屋やファミレスでバイトしている」と大差ないようなレベルのこと、違いといえばそれが小遣い稼ぎのバイトではなくて生活の糧を稼ぐための手段であるという点くらい、というようなテイストの作品が増えてきたかなぁという印象があるということです。もちろん、昔からそういう作品が存在していたのも間違いないところ、一時期はそこに上記のようなヘヴィーさをまとわせることが多かったのが、また傾向が変わってきたのかな、と。実際、本作の主軸は少女たちが不器用ながら友情を築いていく様を描いていくことにあるのかなと思われるところ、そうであれば別に彼女らが殺し屋家業に従事していなくたって、それこそケーキ屋やファミレスが舞台でもいいのではないかと言ってしまうことだって、できるわけです。が、まぁ、もしそのようにした場合には、本作の読み心地は随分と異なるものになっていたでしょうけれど。
ニテーロンの『転生程度で胸の穴は埋まらない』第3巻(KADOKAWA 電撃文庫)を読了。金(黄)、赤ときて、今度は青のヒロインが登場する今巻の粗筋は、「亡国の竜姫を救う鍵は、白い孤独と黄金で――? テルネリカともメルミナとも仲を深めたコノエが再開したのは、超越者(アデクト)の同期である竜人の姫巫女フォニア。何事にもクールで無感動な彼女はコノエを国にスカウトするため、ハーレムを用意してきた!? 『……これから、よろしく? 旦那様?』 竜人の国(アーキノルカ)は新人の超越者に、毎回とある依頼をしていた。かつて国を滅ぼしかけた、無限再生の権能を持つ魔王の討伐。教官すら滅ぼせない邪悪を封印するため、この国はある運命を背負っていて……。『ねえ、コノエ。――私たち、きっと正反対ね』 キーとなるのは、テルネリカのコノエへの想い――!? 持たざる超越者たちの運命が重なる、本格異世界転生譚第3弾!」というもの。第1巻で感じた「主人公の人間性回復の物語」要素はほとんど感じないくらいまで薄れていますし、展開的には感を重ねるごとに1人ずつヒロインが増えていくという、ラノベによくあるハーレム展開で目新しさ云々というより食傷気味な感の方が大きいのですが……。しかし、そういうところを差し引いて、エンターテインメントなラノベファンタジーとして単純に評価するなら、これがかなり面白い作品であることは間違いありません。ここから更にヒロインをむやみに増やしていくようになるなら、それはどうかと思いますが、とりあえず次の第4巻を楽しみに待たせていただきたいと思います。
野中春樹の『嫉妬探偵の蛇谷さん』第3巻(小学館 ガガガ文庫)は、収まるところに収まるべきものが収まった堂々のシリーズ完結巻。その粗筋は「『私はずっと、嫉妬しないで済む相手を探していたわ』そう僕に語る蛇谷カンナの目には、もう嫉妬の色はない。いま僕の隣にいるのは、探偵としてはあまりにポンコツになってしまったけれど、僕に行為を向けてくれて、からかいつつも近づいてきてくれる、ただの綺麗な先輩――まるで、理想の彼女みたいな。 だからこそ、僕は決めなければならない。蛇谷カンナとの……『嫉妬探偵』との生き方を。『嫉妬』なんて、なくてもいいものかもしれないけれど。それでも、僕が好きな先輩は――。嫉妬を失った『嫉妬探偵』の、学園青春 “探偵” 物語。」というもので、終わってみて思うのは、これは蛇谷カンナというヒロインの魅力をとことんまで書き綴っていく作品であったな、ということ。出てくる女性キャラが軒並みピーキーで面倒くさかったりウザかったりするのは作者の性癖なのかどうかは分かりませんが、それが故にヒロインが相対的に可愛く見えるというところは、あるいはあったかもしれません。そこは冷静に判断しなければならないと思うのですが……。それにしても魅力的だな、蛇谷カンナ。実際に自分のそばに彼女のような人がいたとした場合に惹かれるものを感じられるかどうかは不明ですが、シリーズ中では最強です。全3冊とコンパクトなシリーズとなりましたが、最初から最後まで大いに楽しませていただきました。作者の今後の作品にも注目して行きたいと思います。
「ダンジョン編」の後始末が続く、おがきちか の『Landreaall』第44巻(一迅社 ZERO-SUM COMICS)。今回のエピソードを経て、DXとディア、そしてファラオンの気持ちに変化が生じる……かな?これを受けて何がどう動いていくのか、最終的な帰着点は皆さんご想像の通り、という感じになるのでしょうけれども、そこまでの過程はこれからまだまだ楽しませてもらえそう。しかしこうなるとこの作品、全部で何巻になりそうなのかが分からなくなってきますね。面白から別にそれはどうでもいいじゃないかと言ってしまえばそれまでですし、コンパクトにまとめる云々というようなことが語られる作品では既になくなっているのですから、人気があって続けられるだけ続けばいいのかなとも。
ちょっと興味があった 小菊路よう(こきくじよう) の『ヴォカライズ』第1巻と第2巻(KADOKAWA シリウスKC)を購入。低い声がコンプレックスになっている女子高生が、聞こえる音に味を感じるという共感覚の持ち主の男子高校生と出会い、アカペラグループを結成するというストーリーで、物語の構造はかなりベタなのですけれども、そのベタさが心地よくて、この第2巻までのところはかなり良い感じです。このままベタな流れで行くとしたら、次はもう1人女子メンバーを入れるような流れになるのかな……?ここから先の展開がどうなるか、結構化けて更に面白くなるかもという気もしますし、第3巻以降は発売日に買っていこうと思います。
アニメ2期も好評だった、龍幸伸の『ダンダダン』第21巻(集英社 ジャンプコミックス)。ストーリー展開にややマンネリ化というかワンパターン化を感じないでもないとはいえ、画の方は相変わらず圧倒的ですし、物語も決してつまらないわけではありません。むやみやたらに引き延ばしを図られているようだったら勘弁ですが、現時点ではまだそんな感じではありませんしね。とはいえ、そろそろちょっとした動きがストーリーに欲しいというのも否めないところではあります。まぁ、才能のあるマンガ家ですし、編集も優秀そうなので、そこは安心していても大丈夫、かな。
主人公たちのさらに下の世代にスポットが当たる前半、祖父の若き挫折を描く中盤、主人公たちの成長エピソードである後半、そしてややオールスターキャスト的なラストエピソードと、なかなかの充実っぷりを読ませてくれる、namo の『クプルムの花嫁』第7巻(KADOKAWA HARTA COMIX)。地味ですけれども、槌起銅器の若き職人たちの奮闘を描く良作です。前巻の感想の時にも書いたように、本作について私は当初、地味なだけにコミックス2~3冊くらいで終わってしまうかなとも思っていたのですが、やはり面白い作品を面白いと思って読んでくれる人はきっちりと存在しているということなのでしょう。気が付けばコミックスも7冊目で、かつ、連載はまだまだ続きそうです。こういう良いマンガがしっかりと評価されるのは、素晴らしいことだと思います。










| 2025年10月18日(金) Work と Life のバランス |
高市早苗さんが自民党総裁就任演説において「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります。」と述べたことについて、色々と揚げ足取りのごとき報道やコメントが湧いて出ている状態でしたよね。私自身は、あれはあくまで高地早苗という政治家個人の意思表明だし、そういう心構えで取り組んでいくという宣言だろうから、普通にアリだろうと思っています。というか、内外に緊急課題が山積されている状況下において、保守だろうがリベラルだろうが共産主義だろうが、それくらいの覚悟の無い人に国の代表にはなってほしくないなというのが本音かもしれません。公明党の連立離脱騒ぎがあって首相指名がどうなるのか各メディアを騒がせていますが、自民党の総裁になったということはこの国の総理大臣になるということと(あの時点では)同義なのであり、日本国民全員の生活・生命を負うのが総理大臣である以上、最低限の姿勢として、その程度はやってくれよ、と。とはいえ、本当に不眠不休レベルで全てを仕事に捧げて身体を壊されても困るので、そこは適宜休憩等を入れてくれとも思いますが、それくらいは私などに言われなくとも高市さん自身がよく分かられていることでしょう。
ところで、この発言に対するリアクションの中で、Xに投稿された、政治家でも経営者でも名を挙げている人は大体ワークライフバランスを鑑みずに自己の業務・責務に全力を投下しているものだ、という趣旨のポストがありました。私の知っている範囲でも、成功をしている人というのは確かに、生活の時間的な中心や軸を「ワーク」に置いていて、その中に上手く「ライフ」を組み込んでいる、忙しく働く中に生活の潤いやゆとりを上手く入れ込んでいるという人が多い印象があります。ゆうきまさみ の『究極超人あ~る』の中で、主人公である あ~る の光画部の先輩である鳥坂先輩が「人生には息抜きというものが必要だぞ。」と嘯くのに対して、後輩で後に光画部に入る(当時野球部入部予定だった)曲垣が「あんたたちは、息抜きの合間に人生やってるんだろう!!」とリアクションしていましたが、それで行くと、社会的・経済的に成功者と呼ばれるような人たちは「ワークのあいまにライフをやってる」のかもしれません。それを「不幸だな」「自分は嫌だな」と思う人はその道を選ばなければいいだけのことで、そこでワークとライフとでどういう時間の割き方をしていくかについて、どちらか好きな方、自分に向いていると思われる働き方を選べるのが、「多様性」というやつですよね。ワークに偏り過ぎて心身に不調をきたすのはNGですが……そこの自己管理ができない人は、それはそれで成功はできなさそうな気もします。
結局、日々の生活に余裕や潤いがあって、人生を経済的不安無く謳歌しているように見える「成功者」というのは、第一のパターンが、今まさに「ワーク」を全力で楽しみつつその中に上手く「ライフ」を入れ込む適切な「バランス」を確立できていて、「ワークのあいまにライフをやる」ことが好調に回せている人で、第二のパターンが、有能な後継者を育てられたことである程度の仕事を任せられる段階に至って第一パターンを脱してプライベートの時間をより多めに確保できるようになった人、第三のパターンが世襲等で御輿として担ぎ上げられているだけの人、という辺りに概ね集約されてしまうのかもしれませんね。つまり、もともと経済的に潤っているどこぞのボンボンでもない限りは、経済的・社会的に成功している人は、ほとんどの場合は一般的なワークライフバランスを逸脱した生活を多かれ少なかれ送っている(もしくは送ってきた)からこそ、その地位にいるのだ、ということになります。例えばちょっと見た感じでは、ゴルフだ会食だ飲み会だと遊び惚けているように思えるとしても、それも仕事上の欠かすべからざる付き合いだったりして、つまらない顔をしてメンバーになっても仕方がないし周囲を不快な気持ちにさせるだけだから(場合によって自己暗示をしてでも)積極的に楽しんでいくスタンスで参加するようにしていたりするものです。
なお、「ワーク」と「ライフ」の「バランス」について、一般的な指標、労働者・一般市民に対して(生活保護ではありませんが)「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する為の指針はあってしかるべき、雇用側、資本側に労働や健康を搾取されるような過剰労働等は制限されるべきだと私も考えています。しかし、成果を掴むために自ら望んで「ワーク」に偏重しようという決意とアクションそれ自体は、特に一定の役職や地位以上にある人に対しては、やり過ぎのないよう慎重に観察しつつ見守る姿勢を示してもいいんじゃないか、とも思うのです。現状が成功していると呼べるかどうかというのはともかくとして、ちょっと前から個人事業主として従業員を雇用している私も、従業員はなるべく定時で帰宅させながら自分自身は帰宅後の夜とか土日とかも仕事をして、そのあいまに息抜きや趣味のことや旅行といったものをねじ込んでいくスタイルで日々を送っています。これは、自分がやっている仕事が好きだし職種的な社会的意義も感じているからこそこういうこともできるわけですけども、それで最近になってようやく、その最適なバランスというか、こんな感じにやるのが一番いいかなと思えるものが分かってきて、仕事重視は変わらないながら少しメンタルには余裕が出てきています。
そんな実体験もあって、指導的、管理的、経営的立場にいる者が、身を粉にして働くことを「悪」であると断じて非難する流れには、私は違和感を覚えてしまうんですよね。重ねて書きますが、自分はそういう働き方は嫌だ、やりたくない、不幸だと思う、という人に強制しようとか私の言い分に賛同してもらおうとかいうことは、微塵も思っていません。ただ、そういう考えで、自らそういった働き方を選ぶ人もいるし、それはそれで尊重すべきだし、そういう人がいるからこそ社会が回っているようなところもあるんだよ、ということを言っておきたい。今回は、そういう「雑記」でした。
ロイス・マクマスター・ビジョルドの『魔術師ペンリックと暗殺者』(東京創元社 創元推理文庫)は〈五神教シリーズ〉のうち、庶子神教団の楽師(魔導士)ペンリックを主人公としたシリーズの4冊目。裏表紙の粗筋は「愛する妻と娘とオルバスで暮らすペンリックの平和な日日は妻の兄アリセイディア将軍に暗殺者が差し向けられたことで、もろくも崩れ去った。"魔”による暗殺は阻止したが、ペンリックは否応なく故郷の政争に巻き込まれ……。長編『ササロンの暗殺者』に、遺体安置所の死体が動き出した事件にペンリックが駆り出される短編『影の結び目』を併録。ヒューゴー賞受賞シリーズ第四弾。」というもの。このシリーズは描写が丁寧なのでページ数のわりに要約してしまうと内容はそこまでのボリュームではないのですが、むしろその丁寧さと、そして会話の面白さとが魅力であり、今回もそれをすっかり堪能できて、楽しく読ませてもらいました。やはり、ペンリックとデズデモーナは良いコンビですね。
浅葉なつ の『神様の御用人 見習い』(KADOKAWA メディアワークス文庫)は、全10巻+外伝1冊で完結した作品の、主人公を変更しての新シリーズ開幕の1冊になります。「神様たちの御用を聞いて回る人間――御用人。その御用人を代々輩出する神社に生まれた桜士朗は、幼いころから自分も御用人になりたいと望んでいたが、未だに任命されず焦燥感を抱いていた。そして迎えた17歳の誕生日。直談判を受けた大国主神は、『御用人見習い』として神様のお手伝いをするという提案をするが……猫捜し?改名したい!?漬物の神って!?!?神様オタクの桜士朗と、保護者枠の白狼・青藍。新たな御用人(※見習い)コンビが西へ東へ駆け回る!」というのが粗筋なのですが、新シリーズというわりに読んだ感じにあまり目新しさがないのは、従来のファンを離さないという目的だと考えればプラスですけれども、だったらわざわざ主人公を変えて新シリーズにすることも無かったのではないかとも思ってしまいます。一応、この新シリーズの主役の桜士朗は全シリーズの主役である良彦とは性格等に明確に違いもありますし、もっと違った読み応えになっても良さそうなものに思えるのですが、実際には、ほぼほぼ変更なしという印象です。それでいいのか、という疑問はあるのですけれど……まぁ、新シリーズ2冊目以降が今後も刊行されて、それを読んでいけば、その辺のもやもやも解消されていくのかもしれません。
大森望が巻末の解説で「この十年に読んだ日本の冒険小説ではまちがいなく最高峰」と絶賛している、冲方丁の『アクティベイター』(集英社 集英社文庫)を読了。まぁこういう解説の文章はある程度差し引いて捉えておくべきだよなと思いつつも、結構期待しながら読んだ本作の裏表紙の粗筋は「羽田空港に突如、核兵器を積んだ中国の新型爆撃機が飛来した。警察庁の鶴来は女性パイロットを事情聴取しようとするが、護送中に何者かに拉致されてしまう。鶴来の義兄で警備員の真丈は囚われた彼女を救出し、逃亡の手助けを決意する。彼女の身柄をめぐり、中国の工作員、ロシアの暗殺者、アメリカの情報将校、韓国の追撃手、日本の各省庁の思惑が交錯する中、鶴来と真丈は東京中を奔走する!」というもの。1976年のミグ25事件(ペレンコ中尉亡命事件)を下敷きにしつつ、今の時代の国際情勢、政治状況を反映させたエンターテインメントとして、冲方丁がその持てる力を最大限注ぎ込んで完成させた一大アクション小説です。途中からページを捲る手が止まらなくなる、かなり面白い作品でした。
同じように現代の国際情勢を舞台にした危機を描いた作品は他にも多々ありますし、この「雑記」でも複数紹介してきましたが、今作の特徴としては、終始展開が抑制された感じのあるものになっている印象があることでしょうか。もちろん、ストーリーをなぞっていくと、「いやいや、これは全然抑制されていないのではないか?」と思えるようなところも幾つもあるのですが、全体としてそういう雰囲気があるのは、冲方丁がそういう路線になるような意識をしながら執筆をしたからなのでしょうね。フィクションはフィクションとして、娯楽に徹するところは娯楽に徹して、それでいながら、あくまで現実の延長上にある物語として描こうという狙いでもあったのかな……。その分、例えば、作品を通じて冲方丁が訴えたいことは似ているように思える、SFとして思い切り大胆なことや派手な展開を繰り広げた「シュピーゲル」シリーズ(KADOKAWA スニーカー文庫/富士見ファンタジア文庫 全13巻)辺りと比べると、カタルシスには欠ける感はあるかもしれません。ラノベレーベルからラノベ読者向けに出た、カリカチュアライズされた描写も色々と盛り込んだ作品と、一般向けを狙った作品とを比較するのも、無茶かもしれませんが。
雲雀湯の『愛とか恋とか、くだらない。』第3巻(小学館 ガガガ文庫)を読了。裏表紙の粗筋は「期末テストが終わり、もうすぐ夏休みがやってくる。そんなある日の休み時間、いつものように奏音や涼香たち一年生が、祐真の教室に押しかけて来ていた。そこへ菊司の『皆で夏祭りに行かない?』との提案に思わず歓声を上げるクラスメイト。黒髪にイメチェンした奏音に下心を露わにする男子たちと、それを適当にあしらう奏音の姿を見て、苦笑する祐真。だが、その時――『僕はどちらかといえば、彼女より涼香ちゃんと仲良くなりたいな』菊司の聞き逃せない呟きに、祐真の心はざわつく。そして、生涯忘れられない夏休みが幕を開ける。」となっていて、作者によるとこの巻までで内容的には「最初の着地点」を迎えたのだそうです。だからといってシリーズが完結になるのかというと、そういうわけでも無い、のかな?まだ続きそうな感もありますし。第2巻を読んだ時に思ったよりもさらに「普通の物語」になってきた印象は強いのですが、ストーリーの面白さは増しているように思います。キャラの個性付けがちょっと上手く行ってなくて一部判別の付きにくいところがあったとか、対比構造の妙みたいなものが今回は少な目だったなとか、そういう不満はありますが、致命傷にはなっていませんし、もし今後もシリーズが続くのであれば、それは楽しみです。
野上武志の『はるかリセット』第22巻(秋田書店 チャンピオンREDコミックス)を購入。今回のキモは台湾の阿里山森林鉄道と金門島への旅行でしょうか。未だ実現に至っていませんけれど、台湾旅行はいつか行ってみたいと思っているんですよね……。まぁ、「いつか行ってみたい」という括りにしてしまうと、他にもリストに入っている場所が大量に存在するのですが。さすがに生きているうちにその全てを回るのは、無理だろうと思われるので、こうしてマンガだったり小説だったりアニメだったりドキュメンタリー番組だったりを読んだり観たりすることが、その代償行為になったりもするわけです。それでもなるべく多くの場所に、心身が元気なうちに旅行したいとは考えています。現状は、国内で小旅行をし始めているところですが、台湾は近いからまだしも、欧米などはさすがに体力的にキツくなりつつあるかも。
水野栄多作画、宮澤伊織原作の『裏世界ピクニック』第15巻(スクウェアエニックス ガンガンコミックス)は、今回も安定の面白さ。そういえばラブホ女子会って一時期かなり話題になっていたよなぁと思いつつ読んでいたのですが、あれって、今でも普通に行われている、んですよね?私はいい年をしたおっさんなのでその辺りはあまり分からないのですが、通常の利用形態の1つとして定着したから、もうニュースバリューだったりバラエティーで取り上げるネタとしての旬さが無くなっているというだけで。ともあれ、コミカライズは鳥子と空魚の関係が段々と変化していくところが描かれていく辺りで、現在第10巻まで発売されている原作でいうと第5巻の部分。この頃から百合系の作品が得だしたのだったかどうか……もうちょっと前からそうなってきていた気もしますが、いずれにしても、本作もその流れに乗って人気が出て行ったのは、間違いないかも。これからさらに面白くなっていくことは原作で確認済みですから、コミカライズの続きも楽しみです。
最近は以前ほど積極的にアニメのサントラを買っていないのですが、2025年夏クールの『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』については、放送を視聴していて「これは、良い曲だな」と思えたものがいくつかあったので、ならばとサントラ盤を購入。全体的にはオーソドックスな、手堅く作られたサントラという感じで、思いっきりクラシック寄りの曲とかもあって、手堅い出来栄えになっていました。それにしても、私があまり買わなくなったからというわけではないでしょうが、最近はこういうサントラ盤が発売されることも昔と比べると少なくなっているような気がします。Blu-ray や DVD の初回特典に付けるというものもあったりしますが、それすらも無いものも少なくないような……。日本は欧米に比べるとまだまだCDというメディアが普通に生き残っているところが特異であるというような話もありますが、それでも全体的な市場規模はサブスク配信等に押されて一時期に比べると減っているようですし、あるいは、アニメファンの消費活動とサントラCD購入という行為とが、今一つマッチングしなくなってきているのでしょうか。本作のような良作のサントラ盤がそれでリリースされなくなってしまうようだと、それはもったいない気もしますね。時代の変化と言ってしまえば、それまでとはいえ。
ハードロック・ヘヴィメタルのレジェンドドラマー、COZY POWELL のベスト盤である『THE BEST OF COZY POWELL』を購入したのは、まぁわざわざ書かずとも察している方も多いかもしれませんが、高市早苗衆議院議員の自民党総裁就任に伴って、かつて大学時代などにアマチュアロックバンドのドラマーをやっていたこと、DEEP PURPLE や JUDAS PRIEST、BLACK SABBATH といったグループが好きだったこと、ドラムの練習は COZY POWELL の「OVER THE TOP」でやったこと等を話しているインタビュー動画をネットで見て、そういえば彼の音源は持っていなかったなと思ったから。いわば、総裁就任祝いでもあり、ミーハーなリアクションでもあり、という感じかも。で、とりあえず3枚のソロアルバムから16曲をセレクトしたこのベスト盤を購入。全てがインスト曲なので、歌が入っていないとちょっと、という人には向かないかもしれませんけれど、これは個人的に好きなラインの音楽で、かなり気に入りました。しばらくヘビロテ状態になるかも。
昨年に Oasis が再結成されたのは本当に驚きの事件で、いったいいつまで続く者かと疑心暗鬼でみているうちに、とうとう来週末には東京ドームでの来日公演が2daysで行われるわけですけれど、争奪戦に参加する気になれなかったのと値段も高いのとで、私は今回のチケット購入は見送りました(結局また空中分解で再解散してしまってライブが実施されない可能性も高そうと思ってもいましたし)。そんな Oasisi のギャラガー兄弟の兄であるノエルが2009年に Oasis を解散させた後にソロで行ったユニット……というかプロジェクト、NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS の『WHAT A LIFE! LIVE AT CASINO DE PARIS 2011』は、2011年にパリで行われたライブを収めたライブ盤。1枚目のアルバムをリリースしてのツアーで、Oasis 時代のナンバーも演奏された全20曲2枚組となっています。何で今このタイミングでこれがリリースされるのかはちょっと分からないところがありますけれども、しかしライブ盤としてかなり出来も良いから、ここは素直に感謝、ですね。
2026年から活動を「コールドスリープ」させることを発表した Perfume の、おそらくは活動凍結前の最終アルバムになるであろう『ネビュラロマンス 後篇』を購入。昨年発売の『~前篇』とセットになるコンセプトアルバムですが、あるいはこれが彼女等のラストアルバムとなる可能性も(そうなってほしくは無いけれど)否定はできないわけですよね。シングル「ポリリズム」をラジオだか何かで聴いて、なかなか良さげなテクノポップアイドルが出てきたなと思ったのが2007年ですから、かれこれ20年。まぁそれは確かに、一度インターバルを空けて休みたくもなるかもしれないなと思うので、凍結自体には否定的な気持ちはありません。できるだけ早く活動を再開して欲しいという気持ちが無いと言えば嘘になりますが、これは当人たちの気持ちの問題ですから……彼女等自身が「一番いい」と思える方向、選択肢を選んでくれれば、それが何よりです。そんな区切りのアルバムである本作は、昨年の『前篇』に続き、もう「最高」としか言えない素晴らしい出来栄えでした。ここに来て Perfume に黄金時代が再来するのではないかと『前篇』を聴いた時には思ったものですが、今回の『後篇』もそれを上回りこそすれ劣りはしない1枚。それだけのものを置き土産としてリリースして活動凍結というのも、なかなか格好良いですね。痺れるなぁ。




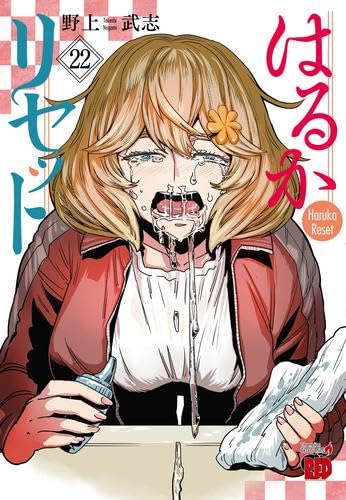





| 2025年10月11日(金) 盛大なる勘違いか、あるいは他に目的が |
ここ数年、環境保護、動物愛護、平和活動・戦争反対活動などの主張を訴える団体の、抗議活動・主張活動に関して行き過ぎ、やり過ぎ、暴挙がひどく目につくようになってきていますよね。9月にレースの最終結果とそれに対する私の簡単な感想を書いた、スペイン開催の自転車ロードレース大会、ブエルタ・ア・エスパーニャでも、私には過剰と感じられる抗議活動がレースを阻害し、選手に怪我を負わせたということがありました。もちろん誰にだって、そしてどのような内容であっても、思想信条の自由は常に尊重されなければならないし、それを主張することの権利は保証されてしかるべきだと私も考えています。綺麗事ばかりをお題目にしていても社会は変わっていかないという側面だって、あるでしょう。そのことは否定しません。ただ、一体誰に向けて、何をやりたくてしている抗議活動なのかが分からない……というか、表面に見えているものとは異なる意図、異なる目的でやっているのではないかと疑いたくなるものが、ちょっと多くなってきてはいないかということも、ひどく気になっているのです。
私自身はこの手の政治活動や抗議活動をやったことがないので、実際にそこに従事されている人にしてみれば「違う、そうじゃない」と言いたくなるようだと申し訳ないのですけれども、基本、ああいう活動は、自分たちの掲げる思想・主張を世間に対して訴えて共感を呼ぶもしくは支持を得るために行っているというのが建前なんですよね?つまり、もともとそういった活動をサポートしている支持層の内部であれこれ述べているだけでは目的が達成できないから、現状よりも更に幅広げた支持を求め訴えていく為に、いわば広報をするべくデモ等をする。そして、多くの人の注目を集め、TV中継もあるようなイベント等はその恰好の場になる。真の動機が本当にそこにあるのかはともかくとして、一応、そういう行為の持つ意味合いとしては理解できますが、そこでイベントの進行そのものを妨げたり、そのイベントの出演者、出場者などに危害が加わるような行動に出たりするのは、それは違うでしょう。そのようなアクションが他者から理解され、支持されるとは思えません。まして、美術館にて高価な美術品を損壊する行為に至っては、全くの意味不明です。
一方で、そういった行為に快哉を叫び、もてはやす人々がいるのも事実。それは行為者のそもそもの支持者たちと重なるように見え、それ以外の人々にドン引きされているのだとすれば、主張への共感を呼び支持層の拡大を得ようということとは正反対の効果を獲得しているわけで、それは環境保護なり動物愛護なり戦闘行為の中止なり、団体・グループとしての根幹目標としていることの達成にはマイナス以外のなにものでもないでしょう。これが、自分達はそういう行為に拍手喝采をするから、自分たち以外もそうであるに違いないという思い込み、視野狭窄、勘違いから出ているのであれば、笑えないし愚かだということになるわけですが。いわゆる「エコーチェンバー」の内部でちやほやされて自己肯定感や顕示欲が満たされ、そんな自分に酔いしれる……。非生産的ですし、そういうのは仲間内の内部だけで完結するところでやってもらって、他者を巻き込まないようにしてほしいものです。
あるいは、実際は「支持者たちにウケの良い行動をする」ことそのものが目的であり、そこで訴える主張はどうでもいいのではないか。それをすることで寄付金、物品等の提供を受ける事こそが目的なのではないか。実のところは掲げている理想や目的はそのようにして金品を集める為に便利だから使っているだけのダミーなのではないか。そんなふうにも見えてしまうのは、(ここで個別の名前をあげつらうことはしませんが)そうとしか思えない・見えない活動、生活をしている活動家が、現実に存在しているから。Aさんがそうだからといって、Bさんもまたそうであるとは言えないことは重々承知していますし、もしかしたら悪意ある邪推なのかもしれませんけれど、そういうスタイルのビジネスなのだと考えれば色々と腑に落ちてしまうのは、どうしようもない。これが正解なのでしょうか。それはそれで、とんでもなくしょうもない……。
「ランサム・サーガ」の6作目、アーサー・ランサムの『ツバメ号の伝書バト』上下巻(岩波書房 岩波少年文庫)の上巻の粗筋は、「猛暑の夏、ツバメ号、アマゾン号の乗組員とDきょうだいは、高原で金鉱をさがすことに。伝書バトで連絡をとりあい、ますます活動範囲を広げます。ところがあやしげな『つぶれソフト』が行く先々にあらわれます。」というもの。今回はセーリングではなく、高原で採掘者を真似して行うキャンプが題材です。いつものメンバーが勢ぞろいして楽しい時間を過ごしているのですが、Dきょうだいが加わっれ人数が増えた分、やや散漫になったところがある、と言えなくもないかも。とはいえ、子供たちだけでのワクワクする冒険譚として相変わらず今回も非常に面白く読める良質な作品であることは変わらないのですけれど。ランサム・サーガもこれで折り返し点。引き続き、ペースを保ちつつ、一気に読み進めていこうと思っています。
いよいよ最終章が開幕となった、安里アサトの『86 ―エイティシックス― EP.14 ペイント・イット・ブラック』(KADOKAWA 電撃文庫)。「全戦線の同時崩壊により、前線の兵は征路を〈レギオン〉に、退路を人の悪意に鎖された。その在り様は “第86区” と呼ばれた戦場と何一つ変わらなかった。事態を察知したシンたち機動打撃群は、首都に “軟禁” されているレーナたちの支援でリュストカマー基地に防衛戦を構築。かつての轍は踏むまいと奮戦を続ける。無理に笑って。飲み下せない感情に歯を食いしばって。希望を、灯して……しかし〈レギオン〉の魔の手がシンに及んだことで、彼らはかつてない危機を迎え――! Ep14『ペイント・イット・ブラック』 “悪意で塗りつぶされていく戦場で、俺たちが戦うべき真の敵を見定める――”」というのが今回の粗筋で、人間盗聴器、人間爆弾と、人間サイドにおける互いの信頼関係を破壊する戦略の帰結として、かつての共和国時代の捨て駒扱いを受けるようになる主人公達に残されたのは、〈レギオン〉の侵攻を唯一停止できる大君主作戦だけ。そんな中、〈レギオン〉を指揮するノウ・フェイスの正体が遂に判明します。そして、最後はいよいよ彼女が旗印として起つ、という流れで、以下次巻。せっかくここまでハイクオリティーに物語を紡いできたのですから、刊行を急ぐあまりに作者として不満足な半端な作品を出されるのは勘弁してほしいですが、第15巻、続きが気になって仕方が無いので、来春くらいには出てくれると嬉しいです。
先々週紹介の第4巻に引き続き読んだ、樽見京一郎の『オルクセン王国史 野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか』第5巻(一二三書房 Saga Forest)の公式の粗筋は、「オークを魔種族を擁する連合国家オルクセンと、エルフたちの国エルフィンドの因縁の戦いは、いよいよ激化していた。ネニング平原での会戦は苛烈を極めて……もはや戦を決するのは、鉄と血の量だけだ。《平和なエルフの国を、野蛮なオークが焼き尽くす》という『異世界ファンタジーあるある』の常識を覆した異世界戦記第5弾!」となっています。主な購買ターゲットをどこに設定しているのかを考えれば、こういう書き方になるのも分かりますけれど、前回第4巻の感想でも書いたように、本作の場合は、よくあるラノベの「異世界ファンタジー」の枠で語るべきものでは無いですよね。架空の戦争を描いた戦記モノ、戦争モノとして捉えるべきです。実際、そういう目で読むようにせずに、キャラクター小説を読む時の感じでページを捲っていると、キャラの存在感が薄くてひたすら散文的なつまらない作品と言う印象になってしまうかもしれません。しかし、とある架空の戦争の記録、輜重であり戦略であり、1つの戦争がどのように展開し、どれだけの血が大地に吸われて行っているのかということをじっくりと追っていく作品であると意識して読んでいくと、これは相当に面白い作品です。今巻で描かれているのはおそらくこの戦争の大局を決定づけた最重要の戦いでしょうから、そうすると本編は折り返し点を過ぎたくらいだと考えてもいい、のでしょうか?
前作がなかなかに衝撃的な終わり方を迎えたシリーズの2冊目である、摩耶雄嵩の『化石少女と七つの冒険』(徳間書房 徳間文庫)を読了。今回の粗筋は、「京都の名門高校の裏手には一本の巨木がある。カップルの聖地とされるそこに、生徒の遺体が三つ……。学園の事件あるところ、化石オタクのお嬢様探偵・神舞まりあ、あり。まりあ率いる弱小古生物部に突如加わった怪しい一年生。迷探偵にワトソン役を押しつけられてきた男子部員が抱え込んだ黒い秘密。はたまた新たな高校生探偵まで登場。いかがわしさマックスの果てに茫然自失の結末が!」というもの。前作は、上流階級の子が通う学園を舞台にした高校生探偵モノという枠組から、いわゆる日常の謎系の青春ミステリーかと思って手を出したところがあったのですが、実際はそんなことはなくて、バンバン人死にが出る(殺人事件が発生する)江戸川コナンもびっくりの殺人事件頻発学園を舞台にした、ややインモラルな、捻ったミステリーでした。その続編となる本作。どういう味付けをしてくるのかと興味津々で読み始めさせていただきました。
……なる程、こう来ましたか。相変わらずのインモラルさというか、探偵役である 神舞まりあ 以外の主要登場人物が軒並み〇〇〇だというのは、どうなんでしょうね。そこが本作の面白さであるところは否定できないのですが、といって、これを「面白い」と言ってしまっていいのかどうかは、少し躊躇ってしまいます。まぁ、あくまでフィクションなので、そんなに目くじらを立てるものでは無いといってしまえば、それまでなのですけれども。読み終わったところで何ともモヤモヤした気分になるというか、スッキリしないというか、「嫌ミス」というほどではないにしても、読書に爽やかな読後感を求めるような人には絶対に向いていない作品なのは間違いありませんので、本作に手を出すか否かは慎重な検討をして決めるようにしてください。なお、本作はここからさらにシリーズ3冊目に続くのか、というような内容になっていたのですが、しかし、これで まりあ は高校を卒業をしてしまいますよね。大学生になったら続けられないというような設定の作品では無いから、特に問題にはならないかもしれませんが、ワトソン役との日常的な接点は減るでしょうから、もしも第3巻が出るのであれば、そこをどう処理してくるか、興味深いところです。
7~9月に放送されていたTVアニメの出来が非常に良かったので、雑誌連載で読んでいるからとコミックス購入を見送っていた、渋谷圭一郎の『瑠璃の宝石』第1巻~第7巻(KADOKAWA HARTA COMIX)とムック本である『瑠璃の宝石 公式図鑑 鉱物のススメ』(同社 同コミックス)と、『瑠璃の宝石』の前に作者が連載して他作品が復刻された『大科学少女』上下巻(同社 同コミックス)を大人買い。原作の絵柄はアニメよりもずっと地味ですけれども、内容の面白さは一緒。こういう薀蓄ネタを楽しく読ませる作品が長期連載になっていて、アニメ化され、かつ、そのアニメも好評だったというのは、日本のマンガ・アニメ文化が捨てたものでは無いということの表れの1つであり、それはとても良いことだなと思っています。鉱物趣味に目覚めてフィールドワークに出る人や、鉱物標本を購入する人が増えているかどうかは分かりませんが、少なくとも、これまでほとんど鉱物に興味が無かった人が関心を抱いたくらいのことは、結構多く発生していそうです。何といっても、それだけの面白さ、魅力のある作品ですから。アニメ化で原作の読者も増えたでしょうから、連載もまだまだ続いてくれる、かな……。そして、『鉱物のススメ』の方は、キャラクター紹介やゲストイラスト等もありますが、メインは作中に登場した様々な好物をカラー写真入りで解説するという、まさしく「図鑑」な内容で読み応え抜群で、この手のムック本の中ではかなり良質なもの。作品ファンならば、必携でしょう。
藤田麻貴の『彼の世の獣が見る夢は』第2巻(秋田書店 PRINCESS COMICS)を購入。デビュー時からのファンだしマイナーなマンガ家だしということで応援の意思も込めてコミックスを購入し続けている藤田麻貴ですが、正直、最近の数作は「ちょっとこれはどうかな」と思わせられるような、どこかで読んだことがあるようなものが多かったのは否めませんでした。が、最新作であるところの本作は、少なくともここまでのところは、という限定は依然として付きますけれども、かなり良い感じです。パターン化された展開を感じるところが残っているのは否めないけれども、本作ならではなところも無くはないし、何よりストーリーが良い。内容的にも全4~5巻くらいのボリュームかもしれませんが、しっかりと楽しませてもらえそう。
















| 2025年10月4日(金) can't live without MUSIC(その4) |
前回は、高校に入る辺りをきっかけに、それまでLPを買う・レンタル屋で借りてカセットに録音をする、というような形式で音楽を聴いていたのが、生活の中にCDは入るようになってきたところまでを書きました。ちょうどこの時期に我が家にもCDプレイヤーがやってきたのがきっかけですが、それで、私が人生で初めて買ったCDは、1988年にリリースされた、さだまさし の13枚目のソロアルバムである『風待ち通りの人々』でした。少ない小遣いのやり繰りの中で何故これの購入を決めたのか、それは、小学生時代に出会って以来ちょこちょこと彼の音楽に触れていたこと、そして何よりこのくらいから彼がパーソナリティーをしている深夜ラジオ「さだまさしのセイ!ヤング」を聴き始めていたことも大きかったかも。
なお、2枚目に買ったCDが何だったかは覚えていないのですけれども、大学に入ってバイトをするようになるまでは財布事情は寂しいままだったので、この時期でもやはり、自分で買うというよりはレンタルで借りてきてカセットにダビングするということがほとんどでした。そのレンタルも、そんなにしょっちゅうは行けなくて、月に1回、2~3枚借りるくらいがせいぜいだったかなぁ。あと、長姉がこの頃には THE CURE や DURAN DURAN や ECHO & THE BUNNYMEN 等の洋楽から若干邦楽ロックに意識が向きだしていて、それで、TVKの番組ライブトマトか何かで演奏を観た BUCK-TICK にハマって、彼等のアルバムを買ったりしたので、それを貸してもらったり。兄はこの頃、PANTA とか ROOSTERS(Z) 辺りを聴いていて、次姉は……何を聴いていたっけかな。時期的には 泉谷しげる 辺りかもしれません。
兄姉が複数いて、それぞれの音楽の好みに差異があると、こうして色々なタイプのものを聴くことが出来るのですが、こういう形で育ってきたことが、今の私が幅広な音楽的趣味を有していることを作る、決定的なきっかけだったのかなと、今は思っています。もちろん、兄や姉が聴いているもの全てを肯定的に受け入れていたわけでは無くて、これは自分の趣味には合わないな、と思っていたものも、それ等の中には存在します。それで喧嘩をしたりとか、そういうようなことは無かったのですが、多分お互いに、「何だ、つまんないモノを聴いてるな」くらいのことは感じていたことでしょう。年齢的にも、自分の好みこそが絶対的に正しい、自分の好きなものこそが真実に格好良いものだ、という承認欲求の裏返しのような歪んだ自己肯定感を時期ですし。中二病とまでは言いませんけれども、多かれ少なかれ、中坊って、そんなところがありますよね。
で、姉や兄がそういう音楽を聴いている中、私はというと、さだまさし からの流れで 南こうせつ や 谷山浩子(彼女の音楽を最初に教えてくれたのは長姉でした) 等を聴きつつ、やはり TVK の音楽番組、MUSIC TOMATO や MUSIC TOMATO JAPAN を観て音楽的な知見を広げていました。洋楽方面では姉兄の影響が強い中、邦楽の腕は少し独自性も出てきていた私が、この頃に知って好きになったのが、松岡英明 であり、YAPOOS(戸川純)であり、そして MOONRIDERS でした(もっともそれを知るきっかけは兄や姉に教えられたというものが多いのですが)。多分ですけれど、この時期に私の音楽的な嗜好は決定づけられた気がします。つまり、中島みゆき のブルースやニューミュージックを根底にしつつプログレの洗礼を受け、そしてニューウェーブやニューロマンティック、テクノといったものに頭までどっぷりと浸ったわけです。まぁ、大学に入学してバイトを始めるまで、さらに言うならば就職して給与をもらうようになるまでは、浸っていても自分の手元にCD等の音源を入手するということができなかったので、そんなに一気にコレクションが増えたりはしなかったのですけれど。
そして、1年の浪人生活を経て、いよいよ私の音楽歴は大学時代に突入します。
「ランサム・サーガ」の5作目、アーサー・ランサムの『オオバンクラブ物語』上下巻(岩波書房 岩波少年文庫)を読了。今回は前作で新登場した「Dきょうだい」ことディックとドロシアをメインにしたエピソードで、その上巻の裏表紙にある粗筋は「ディックとドロシアは、水郷ノーフォークで、地元の少年トムと知り合い、念願のセーリングを学ぼうと、胸をおどらせます。ところがトムが、オオバンの巣を守るために、好き放題の観光客たちと対立して……。」というもの。物語の舞台をいつもの湖水地方からノーフォークの湖沼地方に移し、メンバーも少し変えて、湖沼地方の水路をセイリングするちょっとした航海が描かれていて、エンターテインメントとしても大型クルーザーをレンタルしてマナー無視で乗り回している観光客との対立がスリリングさを物語にもたらしていますし、ランサム・サーガの中でも好きなエピソードの1つです。かつて読んでいたハードカバーの「アーサー・ランサム全集」ではタイトルが『オオバンクラブの無法者』だったのを、この少年文庫版では改題していますが、まぁ確かに、無法者なのはオオバンクラブのメンバーではありませんから、これは変えるのが正解なきがします。小さい頃に何度も読み返していることからかつてのタイトルに馴染みがあるので、若干の違和感はありますけれども。
デビュー作である『公務員、中田忍の悪徳』(小学館 ガガガ文庫 全8巻)を、本編に入れなかったエピソードを小学館及びガガガ文庫編集部の許可のもとに作者自らが同人誌として発売した超公式的非公式同人誌2冊を含む10冊で完結させた立川浦々の、同作に続く新作である『ミドルノートにさよなら』(小学館 ガガガ文庫)を読了。これは最初から単巻作品として書かれていてシリーズになるようなものではないのですが、長く続くことだけが正義なわけではもちろんなく、内容的には非常に濃いものになっていました。そんな本作の裏表紙の粗筋は、「主よ。これは、誰がための試練なのですかーー。勝ち気で誰よりも “女の子であること” に真摯な少女、九重彩音。気弱だけど少し意固地な少女、桜庭真白。ふたりは、ミッション系中高一貫校、清葉女学院の片隅で密かに想いを育んでいた。彩音は真白の声を、真白は彩音の香りを、一番に愛していた。ふたりの世界にはふたりしかいなかった、他の誰もいらなかった。ある日、真白が倒れた。医者から告げられる無慈悲は【突発性性転換現象】。真白は遠からず、生物学的な男性に変わる。ここから二人の世界は変わる。その純愛さえも、歪む。」というもの。率直に言ってかなり良い作品であり、ちょっとこれは「読む」に採り上げる必要があるかなと感じましたから、そのようにしました。これまでに発表した2作品ともがこのレベルで面白いとなると、必然的に次の3作目への期待も高まってきますね。
裕夢の『千歳くんはラムネ瓶のなか Days of Endless Summer』(小学館 ガガガ文庫)は、シリーズ2冊目の販促SS集。といっても、第一弾は特装版特典だったので、単独書籍としてはこれが1冊目とも言えるのですが。「学祭が終わった翌日。俺たち応援団の中心メンバーは蛸九に足を向ける。いわゆる学祭の打ち上げってやつだ――。『それではみなさん、かんぱーい!!』夏が終わり、飽きが終わる。それでも、俺たちの軌跡はいつまでもここにある。5~9巻までの特典SS、コミックスSS、さらには9巻後の書き下ろし短篇『長く短い祭りのあと』を収録。何度も読み返したくなる、夏めく日々の記憶。」というのが裏表紙の粗筋なのですけれども、こういうSS集の総合粗筋なんて(決して悪い意味ではなく)あって無いようなものですよね。独立エピソードとしてどうこうというのではなく、純粋にファンサービスとして存在すると考えられるわけで、そういう意味ではあまり深く考えず、ちょっとした読み物として楽しむのが正解でしょう。
第8部の1冊目となる、餅月望の『ティアムーン帝国物語 断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー』第18巻(TOブックス)。「生徒会選挙が近付く春。ガヌドス港湾国での厳しい戦いを終え、冬休みをのんびーり過ごしたミーアは、悠々と学園へ帰還した。気がかりなのは、ラフィーナからのお誘いだ。入学してくる司教伯ルシーナの息子・リオネルが、生徒会長になるのを絶対に阻止して欲しいという。ところが、『ルードヴィッヒの日記帳』によると、ミーアが彼を制して会長になれば、ベルが生まれて来なくなる!?不穏すぎる未来を追い払うべく、繰り出し戦略とは――?『この選挙(しょうぶ)、勝たせて頂きますわ!』元ポンコツ姫が運命に抗う、一世一代の歴史改変ファンタジー第八部開幕!」というのが裏表紙の粗筋です。ストーリーとしてはこれ1冊でひとまず区切りがついているようにも見えますが、サブタイトルはあくまで「第八部 第二次司教帝選挙 ~女神肖像画の謎を追え~Ⅰ」となっているので、ここから更に「女神肖像画」を巡って物語が展開していくということなのでしょう。刊行ペースを考えると年内にもう1冊は出るはずですが、巻末の発売予定だと次は短編集の2冊目で、第8部の続きは来年春とのこと。楽しみに待たせていただきます。
修学旅行のラストと文化祭を描く、高松美咲の『スキップとローファー』第12巻(講談社 アフタヌーンKC)。特筆すべきは、志摩くんの過去、りりか を巻き込んだという事件の流れが明らかになったこと。何か誤解のようなものがあるのだろう、実際には彼は悪くは無いのだろう、ということは皆が予想していたことですが、なる程、こういうことがあったのかと納得させられました。そして主人公である みつみ と志摩の関係に更なる動きが。個人的に、島崎藤村の使い方が非常にいいなぁと思いました。アニメ第2期楽しみにしています。
買わなくてもいいかなぁと思っていた、Ado が今年4月に出したベスト盤、その名も『Adoのベストアルバム』を、半年たった今になって結局購入しました。デビュー5年といったところで、現時点で彼女はオリジナルアルバム2枚と企画モノ1枚、カバーアルバム1枚しかリリースしていないのだから、そのような段階で全40曲の2枚組ベストアルバムを出すと言われていも、それは本当に「ベスト」と呼べるのか、単にここまで発表してきた楽曲をまとめただけなのではないか、ならば(既発売のアルバムは全部持っている以上)それをわざわざ入手する意味があるのか、というのが疑問だったのです。契約上「期間中に〇枚のアルバムをリリースしなければならない」という事情があるとか、ある程度のスパンで新譜を出して収益を出したいという考えがレーベルにあるとか、まぁ理由は色々と考えられますが……。で、最近のこういう商品で嫌らしいのが、「ベスト」を名乗りながら、新曲を数曲入れてくるんですよね。そうやって既存のアルバムを持っている層にも買わせようとしているのが露骨過ぎて、正直、気に入らないやり口です。そういうことがあって当初は購入を見送った本作をこのタイミングで買ったのは、単なる気まぐれで、それ以上の理由はありません。オリジナルアルバム未収録の「エルフ」は好きな曲ですが、現時点では音源を手元にしたいとまでは思っていませんでしたし。若干のワンパターンさはあるのですが、まぁ、概して良いベストアルバムです、これ単体で考えれば。既存のアルバムに入っていない曲がなんやかんやで10曲ほどあるし、値段的にもそれ等が入ったオリジナルアルバムの値段と思えなくもないとはいえ、「ベスト」と名乗っている以上は、上記の理由から私はあまり評価しませんけれども。
2023年2月14日に亡くなった moonriders の岡田徹 を追悼する意味を込めて、仲間達が作ったアルバムが、サエキけんぞう&CTO-LAB. featuring 白井良明 の『岡田徹 forever』。内容的には彼の作った楽曲をカバーするというものであり、そうするとどうしても原曲のイメージが先に立ってしまって余程のカバーでないと格落ちするものに思えてしまうのですが、本作の場合は根っこにあるのが故人へのリスペクトであり、追悼なので、落ち着いた感じで聴かせていただきました。
昨年12月末での音楽活動からの完全引退を宣言したRURUTIA の、メジャーレーベルとの契約が終了した後のインディーズ時代にリリースしてきた楽曲から、本人が16曲を選び出したベスト盤、『烙影 -The Song for 2005~2025-』を購入。2月15日に紹介した『SIX of CUPS』はメジャー時代のベスト盤でしたから、それと今回のこれとを購入すれば、一応、彼女のキャリアを一応ひととおり網羅することになる、のかな……。どちらも彼女の楽曲の美しいメロディーラインやアレンジ、そしてウィスパーボイスの歌声を堪能できるので、個人的には多くの人に是非お勧めしたいベスト盤となっています。









| 2025年9月27日(金) 公園(in the park) |
今回が9月最終更新になりますので、Top写真 を変更しました。やや気が早いかもしれませんけれど、まぁ立秋もとっくに過ぎていますし10月と言えば基本的には秋といっていいよねということで、秋に撮影した、秋っぽいものを今回は選んでみています。とはいえ、露骨に紅葉を使うのもアレなので、そこは一応避けてみたつもりです。仕事が忙しくなってからはそんな時間もなかなか確保できないでいますけれども、本来私は、天気の良い休日などにちょっと公園に出かけて行って、そこで文庫でも読みながら1日呆けているのが結構好きです。なお、当然ですがこの場合の公園は町中にある小さな公園というのではなく、一定以上の大きさがあって、家族連れがボールで遊べるような広場やら日本庭園やらがあったりする、広域公園に該当するようなもののことです。今回の写真はそんな公園で撮影したもので、ここは中をゆっくりと散歩しているだけでも1日使えるような広さで、入場もタダでは無いのですが、時間に余裕があった頃はちょっとした気分転換でふらりと行ったりもしていました(この写真も、その頃に撮影したものになります)。
ちなみに、「公園」は法的にはどう定義されているのかとしらべてみたら、そもそも「公園」とは大きく「営造物公園」と「地域制公園」に分かれ、前者は都市公園法、後者は自然公園法で規定されているのだそう。後者は国立公園や国定公園、都道府県立自然公園など、「優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的(自然公園法第1条)」として作られるものということで、私が今回言いたい「公園」というよりは、まさしく「国立公園」に代表されるような自然環境保護的なニュアンスのものなのでここでは除外するとします。後者では「『都市公園』とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含む」とされていて、細かくは、国の営造物公園である国民公園(皇居外苑や新宿御苑など)と都市公園(国営公園など)、地方公共団体の営造物公園である「都市公園(街区公園や近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広域公園など)」と「その他の公園(特定地区公園(カントリーパーク)など」に区分できるようです。なお、これはあくまでもざっくり調べただけなので、間違っていたら申し訳ありません。
さて、ではこの写真の公園は、というと……「国の営造物公園である都市公園」に該当しそう。都市公園法には、都市公園が備えるべき要素も色々と規定されているのですけれども、それもクリアしているように思えますし。まぁ、ここでその定義づけ等や行政上の分類が分かったからといって、それで何がどうなるというわけでもないのですが、少なくとも個人的な知識欲等は満たせたかな。
帯にあった「究極のバッドエンド」「慟哭の学園百合×猟奇ホラーサスペンス」という宣伝文句に惹かれて3月に買ってあった、東崎惟子の『美澄真白の正なる殺人』(新潮社 新潮文庫nex)。粗筋は「あなたを守るためならば私は“正しい罪”を犯す 私たちは、どこで間違ったのだろう。天主堂と聖歌の町で、『正義の味方』を目指す女子高生の美澄真白は、八年ぶりに再会した親友・紫音と楽しい日々を過ごしていた。紫音の抱える闇に気づくまでは――。事故死したはずの母親、虐待と思しきいくつもの痣……。聖なる夜、大切なものを守るため、痛々しいほど真っ白な少女が犯す、完全に正しい罪の炎。衝撃のラストが心を穿つサスペンス。」というもので、さぞや鬱々たる物語を読ませてくれるのだろうという期待を抱かせるものとなっていました。で、満を持して今回それを読んだのですけれど……うーん、ちょっと色々と中途半端かなぁ。学園モノとしても百合モノとしても猟奇モノとしてもホラーとしてもサスペンスとしても、もっと突き詰めることができただろうという気がします。周囲のキャラを生かし切れていないところも多々ありますし、ならば主人公とヒロイン2人の物語というところだけに焦点を合わせていくのかというと、そうとも言い切れないし。題材としては悪くないだけに、いかにも惜しいなと感じました。中西鼎の『さようなら、私たちに優しくなかった、すべての人々』(小学館 ガガガ文庫)を読んで以来、こういう作品を読む時の基準が同作になってしまっているので、どうしても採点が辛くなっているところはあるかもしれませんけれど。
「三年生になって受験生スイッチが入っ写った佐藤さん。睡眠時間も削る猛勉強で両親も心配するなか……ある事情で知人の飼い犬を預かることに。犬を飼うのが小さい頃からの夢だった佐藤さんは一気にテンション爆上がり! しかし、実際にやってきたポメラニアンの『シュガー』は、人間不信な暴れん坊だった。勉強の息抜きどころか、シュガーに振り回されてへろへろになる佐藤家一同。なだめてもすかしても全然懐いてくれないその姿は、まるで以前の『塩対応の佐藤さん』を見る様で――糖度120%の甘々青春ラブコメ、新展開の第11巻!」という粗筋の、猿渡かざみ の『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』第11巻(小学館 ガガガ文庫)を読了。煽り文句として「新展開」と言っていますが、実際にはそこまで目新しい何かがあるとか、新キャラが登場するとか、そういうことはなくて、ブリッジ的な日常回という印象があります。そんな中でこの第11巻は、いつものように甘々なエピソードが展開されるお約束通りの内容で目新しさ的なものは無いのですけれども、その分、安定した面白さで読ませてくれたというところでしょうか。とはいえマンネリ気味なのは否めないですから、次の第12巻には本当の意味での「新展開」があってもいいかな、とも。
前巻から、これはそういうことなのかなと感じていましたが、いよいよもって、これはいわゆるラノベやキャラクター小説の文脈にある作品では無いな、と思った、樽見京一郎の『オルクセン王国史 野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか』第4巻(一二三書房 Saga Forest)。「長きにわたる怨讐を晴らすため、魔種族連合オルクセン軍は一丸となり、エルフたちとの戦いに身を投じる。そしてついに、エルフィンド軍最強と名高いダリエンド・マルリアン率いる一群がオルクセン軍の前に現れた。この可憐な少女のような外見をしたマルリアン大将こそ、さきの戦いでオルクセン王国の先王を討った敵将その人であった……。大人気シリーズ、待望の第4弾!」というのが今回の粗筋です。確かに、ここに書かれているような、なかなか立ちまくっている新キャラも出てくるのですけれど、それもあくまで戦争の一局面に出てくる登場人物という扱いで、あまり踏み込んだ描写や扱いはせずに、どこか引いた感じで描いていきます。一応、表紙にもあるように主人公はアンファングリア旅団長のディネルースであり、オルクセン国王のグスタフのはずですが、その2人の出番が全体の何%なのかという話ですね。といってキャラクター描写と同等、いや、それ以上のボリュームと情熱を注ぎこまれて描写されているのが戦況であり戦術理論でありというところから、群像劇になっているとも言い切れません。これは、戦争記録としての「戦記」であると考えるべきなのかも、もちろん、架空の戦争の、という注釈は当然に付されるわけですが。超絶に面白いのは間違いないですし、この作品がここからどういうように完結まで語られていくのか、これはなかなか興味深いことになってきました。
上記『美澄真白の正なる殺人』の感想中に言及した中西鼎の新作は、表紙のイラストから既に不穏な空気が充満している『サクチシノニエ 異端の儀式』(小学館 ガガガ文庫)です。帯には「ようこそ、知と肉片にまみれた佐口漸(さくちし)村へ この村に住む人々は、誰もが凄惨な死を迎える。」という惹句、そして裏表紙の粗筋が「高校生にして天涯孤独の身となった川上縫は、児童養護施設に入るため佐口漸(さくちし)村にやって来る。そこで彼は、何度も夢で見た少女『芽璃』と出会う。夢が侵食してきたかのような現実に当惑する縫に、芽璃はかつて佐口漸村で起きた事件について語る。この村ではこれまでに三件の怪死事件が起きていた。第一の事件は四つのでき死体が蝋化し ”連結” されて発見されたというもので、第二、第三の事件は、それよりも凄惨なものだった。そしてこの残酷な事件は、今年も起きるのだと芽璃は予言した。この日から、縫の日常は狂気に呑み込まれていく。」となっているという、もう、読み始める前の時点で全方位から「覚悟をしてページを捲るように」という警告が突き付けられてくるような作品なのですけれども、中身も、その予感を裏切らないものとなっていました。破滅に向かって転がり落ちていく物語はメンタルが元気な時に読むべきなので、これから本作を手に取ってみようという方はご注意を。合理性とか科学的根拠とかそういうものをすっ飛ばしたこの作品について作者がXにポストしていわく、これは「殺人、オカルト、因習村、狂気、少女、ボーイミーツガール」の物語である、と。……まさしく。「そういうオチに持っていくか」というラストまで、できるだけ情報なく読み進めていただきたいので敢えてこれ以上触れませんが、ガガガらしい非常に尖った作品でした。
最近、リアリティーラインを大きく逸脱し始めた感があって、それはどうなんだろうかと思っていた曽田正人の『め組の大吾 救国のオレンジ』第11巻(講談社 講談社コミックスデラックス 月刊少年マガジン)ですが、その傾向に少し補正がかかってきたというか、ストーリーが若干リアル寄りに戻ってきた感じはする……かな?無印時代から無茶な事件に無茶な活躍が多い作品ですけれども、だからといって行き過ぎは、さすがに、ねえ。これくらいのレベルで進めていってくれるのであれば、まだ本作を追う意味もあると思っています。
園芸高校の宇宙農業科を舞台に、とある事情で宇宙飛行士の夢を断念することになり、母校で実習助手をすることになった相良青星と、宇宙農業科に通いながら宇宙飛行士になることを夢見る広田千留の2人が主人公の笹乃さい の『ブループランター』第1巻(小学館 ゲッサン少年サンデーコミックス)を購入。宇宙農業というのはつまり、宇宙ステーションなどに滞在している宇宙飛行士が食べる宇宙食として、現地で(つまり宇宙で)野菜などを栽培することを指します。それを研究・実験する学科ということですね。わりとニッチな題材ですが、読み心地は作者の前作の『味噌汁でカンパイ』(同社 同コミックス 全14巻)と同じく、のんびりほんわかとしたラブコメという感じ。これは、個人的にかなりツボです。なお、前作については、この「雑記」で紹介するのをすっかり忘れてしまっていましたが、これも非常に良質で面白いラブコメですので、気になる方は是非。
コンプレックスを抱えた若き小説家たちを描く竹屋まり子 の『あくたの死に際』第4巻(小学館 裏少年サンデーコミックス)。一難去ってまた一難という感じで、主人公には次々と災難が降りかかってきますが、まぁそれはそうでなければドラマが成立しないというか、マンガとしてエンターテインメントにならないというところがあるので、不自然さは言うだけ野暮というものですよね。徹底したリアリティーのある方向を目指しているというよりは、あくまでも娯楽性の方に軸足があるので、キツい展開ばかりではありますが、ある意味で安心して読んでいられるところは、あるかもしれません。とはいえ、いつまでもこの感じでグルグルと同じようなことを繰り返していても仕方ないのも事実であり、このある種のループからどう抜け出していくかが、この先の展開のポイントになるのかも。それには主人公が小説家としてある程度名が通るようにならなければいけないかもしれませんが、そうなると『あくたの死に際』という物語はそこで完結となる気もします。ベタなのは(主人公が目標としている)芥川賞を受賞して終わり、というものですが、私ごときのこの雑な予想が当たるのか否か、第5巻以降を楽しみにしたいと思います。







| 2025年9月19日(金) ヴィンゲゴー、ピーダスン、ヴァイン、リッチテッロ |
2025年の自転車ロードレースで最後のグラン・ツールである、ブエルタ・ア・エスパーニャが最終日である先週末日曜日の14日(日本時間でいうと15日早朝)に3週間の日程の全てを完了しました。……これまでこの「雑記」でグラン・ツールの結果を紹介する時には、大体ここに「無事に」「最終日ゴールの街に」「ゴールした」という前置きをしているのですが、今回のブエルタについては、ちょっとそうとは言い切れない部分が残念ながら大きかったと思っています(とんでもない大クラッシュがあって負傷リタイアを余儀なくされる選手が大量に発生したとか、噴火や大雨や地震といった天災が襲い掛かってきたとか、そういうことではありません)。
では、今年のブエルタでは何が起きたのか。それは今大会に参加・招待されたチームに、その答えがあります。ブエルタはUCIワールドツアーの大会ですので、当然、現在登録されているワールドチーム18チームが、まず出場義務を課されています。そしてそれ以外に、主催者招待枠が5つあり、ここにはワールドチームからはランクが1つ落ちるUCIプロチームから、地元スペインのチーム他、ブエルタの主催者によって選抜・招待されたチームが参戦してくることになります。で、この中に、イスラエル籍のチーム、イスラエル・プレミアテックが含まれていた。これを、イスラエルはガザ攻撃を即時停止しネタニエフ首相などを戦争犯罪及び人道に対する犯罪で裁くべきであると訴える親パレスチナの活動家らが問題視しました。
チームスタッフにどれくらいイスラエル人がいるのかまでは確認していないのですが、イスラエル・プレミアテックというチームのオーナーの1人が元軍人でかなり熱心なイスラエル支持者であり、そしてネタニヤフ率いるイスラエルがガザで虐殺とも言えるような行為をしているのは事実です。だから彼等は、パレスチナの旗を掲げながら反イスラエルの主張を訴える。抗議活動をすることそれ自体は彼等の権利ですから、沿道からそれをやっているのであれば、別に構わないのです。パレスチナへのイスラエルの攻撃は即時に停止すべきだと思っているという点では私も同じですし、戦闘行為・虐殺の停止を求め訴えることは、むしろ、ある種の推奨をされてしかるべきことかもしれません。けれども彼等が問題なのは、沿道でプラカードを掲げたりするだけでなく、コース上にまで出てきて道を封鎖し、レースの運営そのものの妨害をしたことにあります。それで、飛び出しに反応して落車した選手がリタイアすることになってしまったり、ゴール前に活動家が集まっていて危険だからとステージが短縮されたり、最後は、最終日マドリードでの周回コース上に抗議集団が溢れかえって、その日のステージそのものがキャンセルされることになってしまう……。そんなことが起きてしまったのが、今回のブエルタでした。
選手たちが熱い戦いを繰り広げている中、あまりに無粋ですし、何よりも非常に危険な行為です。場合によっては、選手生命が失われるような大事故にも繋がりかねません。イスラエル・プレミアテックのチームをレースから排除すべきであるとブエルタ主催者に訴えるならばともかく、直接的にレースを妨害するというのは、さすがに何か違いやしませんか。ネット上には、ロシアのウクライナ侵攻時にロシア籍のチームがUCIによりレースから排除された例を挙げて、UCIやブエルタ側の対応に問題があるのであって活動家の行為もやむ無し、とする声もあります。だからといってこのような危険行為、妨害行為(幸いにも選手は巻き込まれずに済んだけれども、あるステージではコース上の登りに倒木を転がしていたりもしたようです)が許されるかというと、私はそうは思えません。抗議は結構、チームがレースから排除されるべきという見解は理解できる、されど主張のやり方がおかしい。選手の身体に危害が加えられるような行為は、テロ行為と変わらない。私はそう思います。こういうことを書くと非難されるかもしれませんが、それって、イスラエスのネタニヤフ政権がガザに対してやっていることと、本質的には変わらないのでは?
これはUCIがきちんと対応すべき事案、UCI主導でイスラエル・プレミアテックをブエルタから撤退させることの是非も含めて、主導権を持って積極的に対処すべきことだったのではないでしょうか。それが無かったのは、まぁ理由は色々と想像できますがそれは邪推だからここには書かないとしても、UCIという組織が、選手の安全と生命を護る競技団体としては機能しきれていないことを全世界に明確に示してしまったようにも思えます。それが今回、このような最悪の前例・成功事例を作り出してしまった。ネタニエフ政権への抗議活動に限らず、今後、競技にも出場チームや出場者にも一切関係ない内容のものまで様々な大会・レースで同様の事態が発生することが懸念されます。そんな予想は当たらない方がいいのですが……。
そんなわけで、憤りと、残念だという思いと、その他諸々の複雑な感情に襲われながらの幕引きとなってしまったのが、2025年のブエルタ・ア・エスパーニャでした。この話は近日もう少し掘り下げようと思っていますが、今回はこれくらいにしておいて、いつものように各賞の獲得者を(抗議活動の影響には触れずに)簡単に紹介していくことにします。
総合優勝の赤いジャージ、マイヨ・ロホを手にしたのは、チーム ヴィスマ・リース ア バイク のヨナス・ヴィンゲゴー。UAEチームエミレーツ・XRGのタデイ・ポガチャルを打ち破るべく出場したツール・ド・フランスでは残念ながら勝利を掴むことができなかった彼ですが、ならばこちらは、と挑んだブエルタでは見事に総合優勝をしてみせたわけで、改めて、世界最高峰の選手たちの中でも抜きんでた実力を持つことを証明して見せてくれました。なお、彼はこれがブエルタの初優勝とのこと。これはちょっと意外でしたが、考えてみればあれだけ様々な勝利を手にしているポガチャルだって、ブエルタはまだ優勝していないですし、そんなものなのかもしれません。ちなみにヴィンゲゴーはジロ・デ・イタリアも優勝したことが無いのですけれども、そちらには来年か再来年辺りに挑戦したりするのでしょうか……?
ゴール等で得られるポイントを争うポイント賞の緑色のジャージ、マイヨ・ベルデは、リドル・トレックのマッズ・ピーダスンが獲りました。山岳ばかりのブエルタではスプリンターが活躍できる余地は多くないのですけれども、ピーダスンは登りもかなりこなせるので、平坦ステージ以外でも逃げに乗って中間スプリントポイントを獲得していくなどの努力が実を結んだ形ですが、ピーダスンは今年のジロでもポイント賞を獲っているので、今まさに油に乗りまくっていると言っていいでしょう。
山岳賞の獲得者が着る白地に青水玉のジャージ、マイヨ・ルナレス。アスーレスは、UAEチームエミレーツ・XRGのジェイ・ヴァイン。上記の内容とも被るのですが、山頂ゴールも多いブエルタでは総合争いの勝者が山岳も持っていくことが少なくない中、ヴァインは様々なステージで確実に山岳ポイントを積み上げていく形で、総合慧選手の追随を交わし切ってこの名誉を手にしました。総合系の絶対的な強者がいるレースでは、このようにしてこまめなポイント獲得をしていかないと、特別賞で存在感を出していくことは難しいかもしれませんね。
ヤングライダー賞の白いジャージ、マイヨ・ブランコは、抗議活動の攻撃対象となっていたチーム、イスラエル・プレミアテックのアメリカ人ライダー、マシュー・リッチテッロ。彼が今後、ヴィンゲゴーやポガチャルと渡り合えるような選手になれるかどうかはまだ分からないところもありますけれども、期待はできるかなと思っています。その為には本人の努力も当然ながら、チームからのサポートも必要となるわけで、その辺りも含めて彼の今後を注視していくつもり。
以上、2025年のブエルタ・ア・エスパーニャの結果でした。
グラン・ツールに限らず、今後は今回のような抗議活動に対処し、場合によっては警察だけではなくて軍隊を使ってでも排除をすることが必要になっていくかもしれません(そんな自転車ロードレース中継は見たくありませんが)。ならばイスラエル籍のチームなど最初から出場させなければいい、という人もいるかもしれませんが、それに賛同するかどうかはともかく、前述のように、この手の抗議活動をする団体は、何も彼等だけに限らないことも忘れてはいけません。確かに今回のブエルタで起きたのはイスラエル問題を起因とする問題でしたけれど、環境問題その他、過激な活動をするグループは他にもいます。レースの支障ない運行と選手の安全を確保する為に沿道の全てに警備員を一切の隙なく配置することは、警備負担とその費用を考えてもできないでしょうから、そうなると、これからは、町から町へと走っていくオープンなラインレースはできなくなるかもしれません。あまり広くない、一定のエリアを観客を制限した形もしくは完全に観客をシャットアウトした閉鎖した形で行う周回コース(周回レースもそれはそれで、面白くないわけではありませんが)だけになってしまうと、自転車ロードレースの魅力の1つが失われてしまいます。そんなことにはならずにいてほしいのですけれども……。
シリーズの中で唯一、冬のエピソードである「ランサム・サーガ」の4作目、アーサー・ランサムの『長い冬休み』上下巻(岩波書房 岩波少年文庫)を読了。今回はツバメ号の4人とアマゾン号の2人に加えて、新たなメンバー、ディックとドロシアの「Dきょうだい」がメンバーに加わって、いつものように舟で帆走をしたりできない「冬」の休暇で彼等に訪れた冒険を描いています。前作『ヤマネコ号の冒険』が少しばかり無理のある、フィクション味の強めなエピソードだったのに対し、今回は再び湖水地方を舞台にしたストーリーとなっています。湖面全体が凍るような寒い冬に、南北に細長い湖の北端「北極点」を目指す子供たちの冒険譚。前作も前作で非常に面白いのですが、やはり「ランサム・サーガ」といえば本作のようなタイプの物語だよな、と思っています。
昨年11月に紹介した作品の2作目である、逆井卓馬の『この青春に、別解はない。 ―デルタとガンマの理学部ノート2―』(KADOKAWA 電撃文庫)を読了。今回の粗筋は「『GWに調査してみようよ……科学的に!』 生物部に入った出田たち四人が発見した、五〇年前の怪しげな報告書。かつての部員たちが『天狗の怪異』とされる現象を科学的に調査したというレポートからは、なぜか肝心の結論部分が抜け落ちていた。まるで後輩たちに向けて、通気を調べろと訴えるかのように。失われた真相を確かめるべく、連休を利用して実地調査を敢行する四人。森を探索し、夜の神社を歩き回り、宝物殿に伝わるミイラさえも観察しながら、伝説を科学的に検証する二泊三日の合宿が始まった。『こんな調査がしてみたかったんだ。同い年の、同じ趣味の人たちと』それは紛れもなく理系の青春だった。しかし怪異の真実を追う中で見えてきたのは、彼らの日常を壊しかねない不穏な秘密で――?」というもので、大きく、天狗祭にまつわる謎を解く前半と、そこから更なる謎解きへと繋がっていく後半の、2部構成のような形になっているエピソードと言っていいでしょう。シリーズ2作目だから、というのはあるにせよ、冒頭に各キャラの紹介的なところを入れておいた方が(本文でなく、登場キャラクター紹介ページ的なものでも可)いいのではないか、とちょっと気になったのは横に置いておくとして、ラノベレーベルにしては謎解き要素部分にかなり比重を割いていて、わりと創元推理文庫の青春ミステリーを読んでいるような感覚があった1冊でした。個人的にはそれは別に悪いこととは思っていなくて、そもそも東京創元社の青春ミステリーは結構好きで読んでいますし、特にだから何だということもないのですが、電撃文庫で出すならば「青春」なところをもう少しくらいプッシュしてもいいかもしれない、とは思いました。わりと大きな不満点は、キャラの造形を深めるような描写が少ないので、どうしても薄っぺらく感じられる時があったところでしょうか。もうちょっと、キャラは立たせた方が読者を楽しませられるかと思います。ストーリー自体は、結構面白いのに、そこで損をしている印象。
新御三家が活躍していたような時代の昭和の芸能界を舞台にした、村山由佳の『星屑』(幻冬舎 幻冬舎文庫)。その粗筋は「大手芸能事務所『鳳プロ』のマネージャーながら雑用ばかりだった桐絵は、博多のライブハウスで歌う少女・ミチルにほれ込み、上京させる。鳳プロでは専務の娘・真由のデビューが決まっており、ミチルには芽はないはずだったが、彼女の情熱と歌声は周囲を動かしてゆく。妨害、挫折、出生の秘密、スキャンダル……その果てに少女たちが見るものは――。」というもので、ああ、これはあの人がモデルだな、というようなキャラも出てきたりして、当時の芸能シーンを知っているとニヤニヤさせられたりもするのですが、それは余談。本作のメインとなるのは互いに対照的な2人の少女が、最初は反発しあいながらもやがて相手を唯一無二の相棒とする関係になっていく姿です。つまり、オーソドックスな成長物語、青春小説となっているのです。同時に、そんな2人を見守る大人たちの姿も描かれていて、かつ、彼女らの出生のまつわる秘密もストーリーのアクセントとして効いてくるという感じ。時代設定が昭和ということもあってか、全体的に斬新さとか目立つ特異性とかはなくて、オーソドックスな題材を、オーソドックスな調理法で、どこまでも丁寧に優しく料理した作品という印象です。その、しっかりとしたストーリーテリングが本作の魅力であり、500ページを超えるボリュームながら、一度読み始めたらそのまま一気に読み切らせるだけの吸引力にもなっていたのではないでしょうか。とても面白かったです。これは、あれですね。本作を原作にしたアニメとか、良いものができそう。良いものを読ませていただきました。
少しストーリーが整理されてきているとはいえ、まだ作者が本作で何をやりたいのか、どういう物語にしたいのかが分かりにくいということが完全に解消されたとは言い難い、藤本タツキの『チェンソーマン』第22巻(集英社 ジャンプコミックス)。今回のラストは「こう来たか」という感じでしたし、そこで「星条旗よ永遠なれ」の歌詞を引用するところが切れ味がいいなというところでもあったのですけれど、それでも、全体的な方向性は不明瞭なまま。後になってから「そういうことだったのか!」と膝を打てるようなことになればいいとは、思っていて、だからコミックスも買い続けてはいますが、キツいなぁ。
EMERSON, LAKE & PARMER が1992年にリリースしたアルバム『BLACK MOON』を買おうと思ったのは、ここに J-Sports が自転車ロードレースの中継中に使用している楽曲「CHANGING STATES」の音源を手元にしたいと思ったから。これがキース・エマーソン(Keith Emerson)とグレッグ・レイク(Greg Lake)がそれぞれソロアルバムのリリースを考えていたものの、レコード会社側としてはELPの再結成を望んでいたことから、最終的にこの再結成アルバムを作るに至ったものであるといった背景は全く知らずに入手しています。当時の評判は決して高いものでは無く、今もそれはあまり変わっていないらしいのですけれど、個人的にはここに収録されている楽曲はかなり好きです。そもそも、プログレ好きな私ではありますが、いわゆるELP的なものとしてイメージされる楽曲に対しては、嫌いではないけれども少々微妙なところがありました。だからこそ今回も、「CHANGING STATES」は欲しいけれども、全ての未所有アルバムを大人買いで揃えてみようとまでは思わなかったわけなのですが……。しかし、そんな経緯で買ったこの『BLACK MOON』が想定外に良かったとなると、久し振りに以前から所有しているアルバムを今度じっくりと聴き返してみる必要がありそうです。その結果として、大人買いに走ることになるか否かは、まだ分かりませんが。
HOWARD JONES が出した3枚目のピアノ・アルバム『PIANO COMPOSED SPIRIO』は、前2作が即興性も高めに録音したものだったのに対し、コロナ禍の外出禁止期間中にじっくりと制作をした10曲を収録したもの。彼のゴリゴリしたピアノが好きな私としてはこれまでの2枚もかなり好きだったのですけれど、確かに、しっかりと作り込まれたという今作は、さらに私の嗜好に合致していて、これは買って大正解でした。インストアルバムなので歌はありませんし、シンセポップなミュージシャンとしての彼しかイメージに無い人がそれを期待して本作を買うと肩透かしを喰らうかもですが、純粋に出来の良いアルバムですから、試しにちょっと買ってみてもらったりすると、昔からのファンの1人としては嬉しいです。
3rdアルバムまでを購入してきて少々飽きも来ていたので、彼女等の音源についてはこれでもういいかな、と思ったりもしていた BABYMETAL の4thアルバム『METAL FORTH』ですが、そんなわけで当初は購入の予定がなかったものの、Billboard でトップ10に入ったと聞いては、お祝いの意味も込めてこれを買ってみないわけにはいきません。……そんなわけで、発売から1ヶ月半くらいが経過してからの入手となったのですけれど、これは、結構良いのでは?今回は10曲中7曲で他のミュージシャンとのコラボをやっているのですが、それが多少の新鮮さをもたらすという形で良い方向に働いた、と考えていいのかもしれません。とはいえ基本的なラインが変わったというわけではないので、私が抱いていた若干の食傷気味感覚を完全に払拭するまでには至っていないのですけれど。なので、今後も彼女等の新譜を追い続けるかは、申し訳ないけれども現段階では未定です。








| 2025年9月13日(土) can't live without MUSIC(その3) |
前回のラストに The Beatles 主演の『A Hard Day’s Night(ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!)』のリバイバル上映を観に行ったことを書きましたが、これが、何歳の時のことだったのかということは明確には覚えていません。確か、だいぶ前にちょっと調べた時には、1982年にデビュー20周年を記念して行われたものだったということだったはずなので、であれば『銀河鉄道999』のLPを手にしたのとほぼ同年ということになりますね。ともあれ、これを観たことをきっかけとして、私の中に The Beatles への興味……というか、ロックへの興味というか、ともあれそういう感情が湧いてきたのです。これは、私個人の音楽史としてはかなり大きな転換点で、そこから「誕生日プレゼント」「クリスマスプレゼント」「お年玉」という流れで、その全てを投下して私は彼等のアルバムのLPを揃えました。先にも書いたように、この頃の小遣いだと何も使わずにひたすら貯めたところで年に1枚か2枚LPが買えればいいところだったわけですから、これはかなり思い切った支出だったなと、今でも思います。どちらかといえば「ロック」的なものには否定的な(当時の)母がこれを認めたというのも、そういえば何故なのかよく分かりません。本人がその辺を覚えているかどうかは分かりませんが、今度、聴いてみようかな?
この辺りから私自身も洋楽への興味が出てくると同時に、長姉や兄がそれぞれに洋楽を聴きだしたりもしていて、私の音楽生活はここで一旦そちらの方向に舵を切ることになります。この辺で記憶に強く残っているのは、長姉が好きだった DURAN DURAN の「Save A Prayer」の、スリランカで撮影したというMVでしょうか。TVK等の放送していたMTV番組で試聴をしたこのMV、今になって見直しても当時ほどのインパクトは受けないのですけれど、あの頃は、このオリエンタルな映像と、楽曲の美しさにすっかり撃たれてしまったのです。ちなみにこの曲もシングルがリリースされたのは1982年。ということは、これまで全く意識してきませんでしたが、1982年というのは私の人生の中で非常に重要な位置を占める年だということになりますね。世界初のCD発売も、確かこの年でしたっけ。
そこからしばらくは、父が相変わらず新譜を買っている 中島みゆき の他は、THE BEATLES のLPを聴きつつTVでその時にリリースされた、ヒットしていた洋楽を聴く、という時期が続きます。中学に入る頃には、兄がレンタル屋から借りてきた洋楽ロックのLPを私もカセットにダビングさせてもらって、それを聴いて幅を広げたりもしています。で、この頃の兄というのがまたひねくれていて、彼が借りてくるのは当時の流行のロックというわけではなく、それよりも前、1960年代後半~1970年代半ばまでの、プログレッシブロックのものでした。そこで私は KING CRIMSON の『In The Court of Crimosn King』(邦題:クリムゾンキングの宮殿)とか PINK FLOYD の『The Dark Side of the Moon』(邦題:狂気)といった名盤を教え込まれて、プログレにも染まっていったのです。一方で、中島みゆき は相変わらず聴いていましたし、友人関係だとオフコースのファンとか浜田省吾のファンもいました。で、浜省はピンと来ませんでしたがオフコースについては私も「これ、結構いいな」と思ったりもしていたから、さすがに洋楽一辺倒というわけではなかったことになりますね。レンタル屋で、友人の家で流れていたことから興味を持っていた さだまさし のアルバムを何枚か借りたりもしていましたし。
そして、そんな日々を送っていた私は、1988年、ちょうど高校に進学した辺りに、人生で初めてのCDを買うことになります。なお、これは The Beatles のアルバムを揃えた次に買ったものというわけではありません。その間に私はアニメのサントラLPを何枚か買っていましたから。具体的には、『蒼き流星SPTレイズナー』のサントラ3枚とか、『王立宇宙軍 オネアミスの翼』のサントラとか、そういう辺りです。……そういえば、「レイズナー」のサントラはCDでは手に入れていないから、もうずっと聴き返していません。高騰している中古価格で買おうとまでは思いませんが、何らかの形で復刻でもされたら、その時は入手しようかな。
第19回小学館ライトノベル大賞のガガガ賞受賞作、えるぼー の『炒飯大脱獄』(小学館 ガガガ文庫)を読了しました。「サイレンが鳴り、監視塔のサーチライトが脱獄者を追う――。ここは上海の沖合にある孤島に設立された【上海炒飯大学】。通称 “炒飯の監獄” 。解放条件は、一年で千皿を積み上げること。『やってられるか脱獄だ!』日本からの拉致入学者・柳葉蒼音の前に立ちはだかるのは、世俗を断つ【断獄壁】、鎮座する巨塊【豪鋼門】、登るほどに険しさを増す【三飯塔】。蒼音は、メモ魔のカンフー使い、最速の臆病者、気分屋のしゃべり魔、三人の少女と共に立ち向かう!『わたしの脱獄、舐めんなよっ!』。前代未聞の炒飯プリズン・ブレイクここに開幕!」というのが裏表紙の粗筋ですが、応募総数1,142作品の頂点(といっても、最上位の「大賞」は該当作なしだったようですが)にこういう奇天烈方向に尖ったものを選んでくるところがいかにもガガガ文庫らしいですし、それでこそという感じがします。で、本作なのですけれども、上記の粗筋だけだとまるでネタに走ったドタバタコメディーのような印象を持たせつつ、実際に読んでみると割とオーソドックスな成長モノになっていることに気が付かされます。中盤がやや駆け足ですが、それは単巻で完結するような作品であるのが前提となる新人賞応募作ですから、やむを得ないところでもあるでしょう。それよりも、エンタメとしての面白さ、全体的なノリの良さと、多少の無茶は勢いで突破する痛快さ爽快さが素晴らしく、実に面白く読ませていただきました。ラストのオチまで含めて娯楽作品として筋が通っていて、これは多くの人にお勧めできる一作と言えます。
評判の良さから読んでみた上巻が思った以上に面白かったのでこれは期待ができそうだぞと思っていた、大武栄一の『ニュー忍者ロード』下巻(小学館 ガガガ文庫)を読了。「永い間、主を持てぬまま常に最新の研鑽を続けてきた “上州大魔縁流” の当代・連城大弥は、憧れの生徒会長、姫氏原すみれ の未来を護るための戦いを開始し、史上最強の剣豪・上泉伊勢守信綱にまさかの勝利を納めた。絶望的な今を切り開くための旅に出た二人を、沼田城址で一族の最終結論と称される尾張柳生新陰流の柳生連也が、日本の中心・渋川四ツ角交差点で天然理心流の沖田総司が待ち受ける。そして旅の果てに立ち塞がったのは、“二刀流の大剣豪” ……!超常の力により蘇った古の剣豪VS現代忍者(高校生)の死闘、ここに完結!」というのが裏表紙の粗筋で、群馬県を舞台にして、現代に蘇った柳生連也、沖田総司、宮本武蔵を相手にして、日の目を見ずとも代々研鑽を磨いてきた忍者の当代である高校生が、あこがれの姫を護るために死闘を繰り広げる物語を、たっぷりと堪能させていただきました。青春と忍術と剣士と恋愛と伝奇と。アクションエンタメとしてかなり上質で、こういう作品がラノベレーベルから出るということに、かつてのソノラマ文庫的なものを感じて(ソノラマ文庫、夢枕獏の『キマイラ・吼』シリーズとか菊地秀行の『吸血鬼ハンター“D”』シリーズや『トレジャー・ハンター』シリーズを刊行していましたよね)、何だか嬉しくなってしまいました。本作でデビューした作者の大武栄一には、これからもこういう伝奇調の痛快アクション作品を書いて大活躍していってもらいたいです。
恩田陸の『蜜蜂と遠雷』上下巻(幻冬舎 幻冬舎文庫)と、スピンオフ短編集の『祝祭と予感』(同社 同文庫)を、今更ながらに読了。評判の高さも知っていましたし、題材的にも好きなものなので読んだら気に入るだろうなというのは予想がついていたのですが、でもまぁこれって要するに 一色まこと の『ピアノの森』(講談社 モーニングKC 全26巻)の焼き直しだよなという意識もあって、何となく読むのを後回しにしてしまっていたのです。が、特にこれと云ったきっかけは無かったものの、さすがにそろそろちゃんと読まなければならないなと思って、このタイミングで遂に満を持してページを捲りだすこととなりました。そんな『蜜蜂と遠雷』の、上巻の粗筋は次のようなもの。「近年その覇者が音楽界の弔辞となる芳ヶ江国際ピアノコンクール。自宅に楽器を持たない少年・風間塵16歳。かつて天才少女としてデビューしながら突然の母の死以来、弾けなくなった栄伝亜夜20歳。楽器店勤務のサラリーマン・高島明石28歳。完璧な技術と音楽性の優勝候補マサル19歳。天才たちによる、競争(コンペティション)という名の自らとの叩き。その火蓋が切られた。」要するに、国内で開催されるピアノコンクールを舞台にして、様々なコンテスタント(参加者)の人生を描き出す群像劇なわけですね。一方で、ちょっと強引な解釈をするならば、コンクールというのはある種の閉鎖空間、疑似的な密室のようなものであり、そこに個々に尖った能力を持つスペシャリスト達が集ってたった1つの優勝者の座を争うという点を捉えれば、多重解決(推理合戦)ミステリのような側面もありそうです。特に本作の場合は、物語の根幹となる部分に、今までのコンテスト出場経験などが無いままに亡くなった世界的ピアニストの推薦だけで出場してきた謎の少年ピアニストの存在と、何故彼を世界的大家が推薦してきたのか、推薦に添えられていた大家からのメッセージはどういう意味・意図があってのものなのかという「謎」が絡んでいるから、余計にミステリー味を感じるのかもしれません。加えて、多重解決モノは私にとっては結構な好物であることや、もともと音楽モノの作品が好きであることもあって、大いに面白く読ませてもらいました。
ビジュアルの無い小説で音楽、特にクラシックを描こうとすると、どうしてもポエミックになってしまいがちなところがあるでしょうが、そこは恩田陸の筆力もあり、気恥ずかしさとかをあまり感じさせることなく、むしろ個々のコンテスタントの演奏の個性がその描写により際立つような感じで読むことができました。なるほど、これは良い作品です。ただ、読み進めている間にしばしば、『ピアノの森』が想起させられてしまうのはどうしても否めませんでしたけれど。恩田陸がピアノコンテストを題材にした小説を執筆すると決めたのが2006年で、連載は2009年から2016年までで同年に書籍化。一方の『ピアノの森』は、1998年に連載開始で中断を挟みながら2015年に完結しています。タイミング的には重なっている部分もありますし、内容に似ている部分もあるのは否定できないところですが、これをパクりというのはさすがに邪推のし過ぎかも。全く影響を受けていないか、と言われると、それはさすがに多少はね、とは思いますが。しかしこうなると、久し振りに『ピアノの森』も読み返したくなりますね……。それで「読む」に掲載するとか。ちょっと真面目に検討してみることにしましょう。
作中で明言はされていませんが家庭環境の歪みから社会に馴染めず、自らの意思で選択しつつもどこか流されるように傭兵になった主人公が、居場所を見つけるまでを描いた(と私が感じた)物語である三河ごーすと の『姉妹傭兵』(KADOKAWA MF文庫J)を読了。裏表紙の粗筋は「伊澄凛子、十七歳。職業は――新人傭兵。バイト感覚で民間軍事会社に応募した私はベテラン傭兵の水崎渚さんと共に異国の紛争地帯に放り込まれた。土地勘もなく言葉も文化も異なる地で、銃の撃ち方や携帯糧食の開け方、他人との距離の取り方まで、私は全てを水崎さんに教わり、"この場所で生きる” ことを学んでいく――。私たちは戦争の本筋に関わらないし、歴史を変える使命だってない。戦場の片隅で与えられた任務をこなし、食事を分け合い、オフの日には渋谷でパフェを食べながら、ただただ今日を生き延びていく。これは世界のどこかにあるかもしれない日常の一幕。血縁ではないけれど互いを信じあう私たちの――姉妹生活小説。」というもの。モラルだインモラルだ命の価値だというような話はこういう作品を語る時に評価基準に持ち出すべきでは無いので横に置いておくとして、戦場を舞台にした日常系物語というノリな本作ですが、正規軍ではなく民間軍事会社の傭兵、武力衝突の最前線ではなく、前線ではあるけれども主要戦場ではない(戦略的重要性の低い)場所を舞台としているからこそ、それが成り立つわけですよね。ウクライナ、ガザ、イラク等々、個人的に戦争・戦場がリアリティーを持って身近なものと感じらえている昨今、こういう作品への微妙な感覚があるのは否めないのですが、面白く読ませていただきました。単発作品でシリーズ化は前提となっていないということですが、これで続編といっても何を書くかというのは難しいところもあるだろうし、ここで終わっておくのが綺麗だ、というのはあるかも。
2024年10月から2025年3月にかけてNHKで放送された全25話のアニメも好評だった、魚豊の『チ。-地球の運動について-』全8巻(小学館 ビッグコミックス)を読了。もともと連載が開始されコミックス第1巻が出た辺りでかなり話題になっていることは知っていて、題材的にも興味はあったのですが、絵柄が私の苦手なタイプだったのでちょっと敬遠していた作品です。が、アニメ版の出来があんまりにも良かったものですから、これはやはりきちんと全巻を購入して読まなければならないかと思ったのです。それで、最終回の放送とほぼ同時に買っていたのですが、やはり絵柄が苦手なことには変わりなく、結局実際に読むまでにこうして半年が経過してしまいました。まぁ、「読みたいと思った時が読むべき時」というのが私のモットーの1つでもあるので、そのこと自体は良しとしましょう。で、肝心の『チ。』ですが、こうしてきちんと読んでみると、第1巻ではかなりアレだった画も、最終話の時には大分上手くなっていて、当初程の苦手感は無くなってきているかも。物語の面白さ、テーマの深さは敢えて言うまでもないでしょう。そして改めて思うのは、この物語の主人公は、実はノヴァクだったのだなということ(あくまでも個人的な感想です)。反論・異論はもちろんあるでしょうが、私にとってはそうであった、と。「知」の探求が世界と人に何をもたらすのか。作品の提示した結論はやや楽観論な気もしますけれど、こういうところで希望を語れなくてどうするのか、ということですよね。やはり、これは傑作です。
およそ1年振りの新刊となる、つくしあきひと の『メイドインアビス』第14巻(竹書房 BAMBOO COMICS)。現在はWebでの不定期連載となっている本作ですが、特に明記されているわけではないけれども、コミックスの刊行がおよそ1年ごとになるような感じで、新話がネット公開されていくというようなペースになっている本作ですが、物語はいよいよ核心に迫りつつあるようで、しかし解明されなければならない謎はどんどん増えていっています。一部のコマで読みにくさがあるのは否定できないですが、それは本作、つくしあきひと の個性と言えなくもなく、またそれがあることで作品の魅力が損なわれるところまでは行っていないので、(できれば改善されればいいとは個人的に思いますが)とりあえず問題は無いでしょう。それよりも物語の魅力が大きく上回っています。彼等の旅の行き着く先がどうなるのか、目を離すことができません。

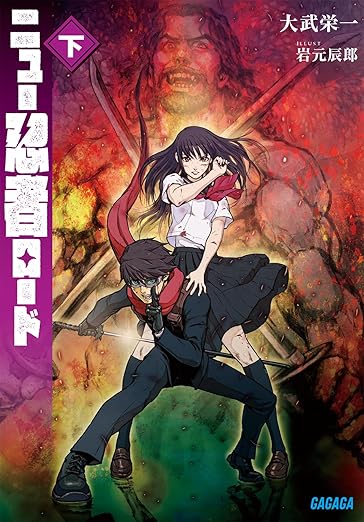
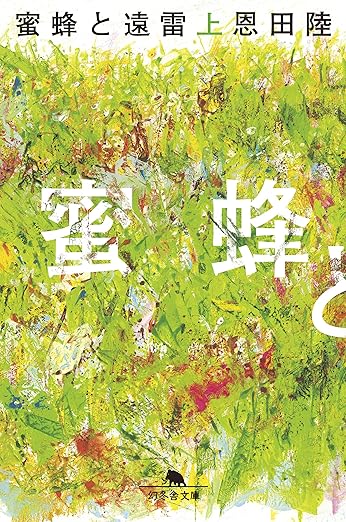












| 2025年9月6日(土) なんだかなぁ |
尾田栄一郎『ONEPIECE』のルフィーが言ったものであるという誤った認識が広まっていることでも有名な、西公平『ツギハギ漂流作家』における吉備真備の「何が嫌いかより何が好きかで自分を語れよ!」というセリフがありますよね。自分を語る為のツールとなり得る「好きなもの」であれば、それはつまり相当に好きということだから、ジャンルはともあれ「推し活」と言っても差し支えないのかもしれません。推しを作ることが人生を豊かにするというのはよく言われることで、それは実際確かなことだと私も思いますけれども、だからといって推しに依存しすぎるのは良くない、自らのアイデンティティーの最大の拠り所を推し活動そのものに置く、あるいは推し活動だけが自らのアイデンティティーの拠って立つところである、というような「推し活動」への過剰なのめり込みは、それはそれで非常に危険でもありますよね。「推し」が自分にとっての背骨、唯一無二の存在証明になってしまうと、それに対して少しでも否定的なことを言われると、まるで自分の存在自体が否定されたかのように感じて、強い拒否感と自己防衛からの攻撃性を発揮することになる……。そんなことは無い、悪意のある思い込みだ、と言われるかもしれませんけれども、実際のところ世の中にはそんな事例は腐るほど存在しているじゃないですか。
分かりやすい最近の事例でいえば、7月末に横浜の山下埠頭で行われた、Mrs. GREEN APPLE の 2days 野外ライブが挙げられるでしょう。強風などの自然要因もあったという話はありますが、ライブでの音量が大きかったことで周辺住民のみならず、川崎や大田区の住民からも、室内まで重低音が聞こえてきて不快であるというクレームが数多く発せられたことに対し、一部のファンが過剰な反応を示したという、アレです。10周年記念というメモリアルだったこともあってスタッフ含め全体に気合が入りすぎたかとか、会場設計を間違えたとか、そういう指摘もありましたが、どうやら Mrs. GREEN APPLE サイドが一方的に悪いということでも無さそうな状況ですし、私は別に彼等を責めたいわけではないので、そこが誤解しないでいただきたいのですが……。以後の話は、同じような内容を過去にこの「雑記」でも何回か書いた記憶があるのですけれども、こういったことがあった際のファン側の過剰な反応について、この Mrs. GREEN APPLE の件で改めて、10年以上前から何も変わっていないどころかここ数年でむしろ悪化しているのではないかとすら思えてしまったので、改めてまた触れさせていただきます。
まず大前提として、野外ライブで騒音に対するクレームが発生したからと言って、そのクレームは基本的に、あなたの好きなミュージシャンその人(達)を否定しているわけでは無いし、あなた自身を否定しているわけでもありません。そしてそのクレームを発してきた人は、あなたの敵でもありません。まぁ、中には本当に Mrs. GREEN APPLE が嫌いだったり、何でもいいから人の楽しむことにはケチをつけたいというようなクレーマーがいるかもしれませんが、ほとんどの人が、そういう意味で苦情を出したわけではないはずです。
また、忘れてはいけないもう一つのこととして、世の中の全ての人があなたと同じ価値観を持っているわけではない、という事実があります。あなたが好きなものを他の人も好きだとは限らないし、価値観や好みは多種多様であって基本的にはそこに優劣はありません。あなたにとって Mrs. GREEN APPLE というグループとその音楽がどんなに素晴らしくても他の人もそう感じているとは限りませんし、仮にあなたが「こんなに良いのに、それが分からないとはもったいない」というように憤っているとしても、それは Mrs. GREEN APPLE を高く評価するあなたが正しくて、そうではない他の人が間違っている、ということを意味するわけではありません。これは金子みすゞ の「みんなちがって、みんないい」が当てはまるような話なのであり、さらに言えば、そもそも正しいとか間違っているという基準で判定すること自体がおかしいということからすれば「みんなちがって、どうでもいい」と評するのが最適です。
しかし実際に目につくのは、ちょっとばかり自分の気に入らないことを言っている、自分が楽しんだものにケチをつけるようなことを書いている意見を目にしたからといって、即座に牙を剥いて噛みつきにかかり、自分の好きなもの、「推し」を理解できない相手の方がおかしいとばかりに人格や人間性を否定するような言動までする声。それは、傍から見ていて非常にみっともないものです。無論、それは一部の人に過ぎず、ほとんどのファンは冷静に批判の声を受け止めている、はず。ただ、目立つのは、批判者に対してむやみに攻撃を仕掛ける人ばかり。声の大きい者が(少数にも関わらず)目立っているだけだと言ってしまえばそれまでですが、だから仕方がないのだとこれをスルーするのではなく、ファンコミュニティー内部で何らかの対応をしておかないと、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」的に、こういうファンがいるということ、そしてそれを許容してしまうということは、Mrs. GREEN APPLE というグループとその事務所もタチが悪いなと思われてしまうことを招きかねないのでは?初動でミスしてこれを放置していると、プロ野球やJリーグが悪質なファンを無期限追放にするように、永久追放までしろとは言いませんが、ディズニーランドやサマーソニックでのやらかしも報じられたりする中、公式がファンのそういう言動を一般にも目に入る形(例えばTVや新聞、ネットに大々的に広告をうつとか)で大々的に諫めるような、ある程度の厳しい処置をするくらいにならないと、評判を回復できなくなるのではないかということが危惧されます。
必要なのは、人間の好みは千差万別で隙も嫌いも人それぞれなこと、その違いを尊重し、受け容れ、むやみな干渉や攻撃はしないこと。寛容の精神ですね。ここを見失っている……というか、もともとそういう精神を持ち合わせていない人が増えているのではないか、しかもその割合がどんどん高くなっているのではないか、そういうことを私は危惧しています。今回は Mrs. GREEN APPLE の件がきっかけでこんな「雑記」を書いていますけれど、他にも、個別に挙げることはしませんけれども、旧ジャニーズのタレント絡みの問題でも幾つか似たようなことを目にしましたし、その他にも色々と……。ちょっと、みんな、どのようなジャンルのことでもまずは冷静な対応をとること、自己を客観視する視点を身につけるような訓練が必要なのかもしれません。これって、「推し活」に限らず、趣味の世界に限らず、仕事でも政治参加でも他の様々なことでも該当する、重要なことですし。
一定のペースは保とうとしつつも、ゆっくりと、気が向いたタイミングで読み進め始めている「ランサム・サーガ」の3作目、アーサー・ランサムの『ヤマネコ号の冒険』上下巻(岩波書房 岩波少年文庫)を読了。「老水夫ピーター・ダックと、帆船ヤマネコ号で船出したツバメ号、アマゾン号の乗組員たち。初めて味わう海での航海は、不安と喜びでいっぱい。ところがぶきみな海賊、ブラック・ジェイクがつきまとい……。」というのが上巻の裏表紙にある粗筋で、これまでの2作品が湖沼地帯だったのに対し、今回は大西洋を舞台にした物語が展開されています。それも、その範囲はかなり広く。一方でストーリーはこれまでに比べるとフィクション味が強くなっているというか、リアリティーの面では少し弱くなっている感があります。その分、「冒険モノ」としての側面がちょっと増しているのも確かですし、シリーズを続けていくにあたって「こういうのもアリだろうか」というチャレンジもあるのかもしれません。実際、このエピソードは面白くて私も昔から好きだったりしますし、もしこれが本当にアーサー・ランサムにとって若干の挑戦をしてみたエピソードだとしたら、それは成功したと言っていいのではないでしょうか。
ざっと粗筋を観た時点では、『沈没船で眠りたい』(双葉社)の延長でAI社会における「人であることの意味」を問うような作品なのかなと思って読みはじめた、新馬場新の『歌はそこに遺された』(徳間書店)。その粗筋は、「『私と一緒に、ストーリーを作ろう。君が歌うからこそ意味がある理由を作ろう』 新進女性シンガー、荒井海鈴が殺された。彼女の遺作『人魚』は、死をきっかけに大ヒットする。生成AIの楽曲が隆盛の時代に、生身の人間の作った曲がここまでハズるのは異例だった。『あれを作ったのは、AI』と嘯く、海鈴殺害の容疑者・備藤龍彦の言動に違和感を覚えた東京地検公判検事の堂崎千也は、独自調査の一環で、彼女が所属していた事務所を訪ねる。社長の椎名栄弥は、一般的な芸能事務所の顔とは別に、レッスン提供を主体とした怪しげなビジネスに手を染めているようだった……。 『沈没船で眠りたい』で読書界を唸らせた気鋭が贈る、今世紀最もエモーショナルな、近未来法廷ミステリーの誕生!」というものなのですが、実際に読んだ本作は、想像していた通りだったところと、そうではなかったところが半々だったという感じでした。そんなわけで、事前予想とはやや異なっていましたけれども、これは失望したとかつまらなかったとかいうことではなく、むしろ「そうきたか!」という楽しさで面白く読ませてもらいました。人工知能の進化が人の仕事を奪うことへの言及があるの両作品ともに同じですけれども、この『歌はそこに遺された』の場合は軸足がそこではなく、むしろ別のところに置かれているストーリーだと感じられます(具体的なことは、ネタバレを回避する為に書けないのですが)。小説は必ずしもその書かれた時代を反映するものでは無いですけれども、生成AIや(ネタバレできない)〇〇といったことが題材になっている本作については時代性も結構高く、その意味でも興味深い作品と言えます。新馬場新、ここにきて筆が乗りに乗り出している感がありますね。
戦争が始まったことで一気にミリタリー小説の色合いが濃くなってきた、樽見京一郎の『オルクセン王国史 野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか』第3巻(一二三書房 Saga Forest)。その粗筋は「魔種族統一国家オルクセンの王グスタフは、オークらしからぬ穏やかで理知的な名君と名高い。それは彼が特殊な事情を抱えてこの世界に生まれてきたためであった。グスタフ王は故郷を追われ臣民となったダークエルフの美女ディネルースと心を通わせ、ついにエルフたちの国エルフィンドに宣戦布告する。奇襲ともいえる神速の開戦により、戦いはオルクセン軍の圧倒的有利で進むかに思われたが……。重厚にして胸アツ!空前絶後の異世界軍事ファンタジー、待望の第3弾!」というものです。ミリタリー色が強くなったことで読みにくさが増しているという印象もあって、そこはどうかなとは思うものの、かなり面白かったので、内容的なところにはまずまず満足しているのですが……。文章に、助詞の使い方等で「これは間違いなのでは?」と思ってしまうところがちょこちょこと見られたところはマイナス要素と言えるでしょう。これは、敢えてそういう書き方をしている、それが樽見京一郎という小説家の文体の個性である、と考えてわざと訂正しないままにしているというのでなければ、校正担当者、編集者にもっときちんと仕事をしてほしいところ、かな。あと、一部に致命的な誤字脱字がありました。人間のやることだからミスを完全に根絶するのは難しいというのは分かっていますが、それにしてもこれはちょっと多すぎではないかという気がします。物語そのものには、上記のようにとりたてて不満はないし、むしろかなりの良作だと思っているのですけれど。
青柳碧人の「ヤンキー、ミステリと出会う ~俺とあいつと、さしすせそ」、秋木真の「将棋部、無実を証明せよ」、相沢沙呼の「屋上の雪融け」、似鳥鶏の「学生時代の母の原稿」の4編が収録されたアンソロジー文庫、『ブラックボックス、誰が解く? 君に綴る4つの謎』(KADOKAWA 角川文庫)を読了。これがおそらく初読になる秋木真を除けば私がフォローしている作家ばかりという、非常にお得感の大きなこの1冊の裏表紙の紹介文は、次のようになっています。曰く、「世の中にはたくさんの本がある。でも、多すぎて何から読めば良いのかわからない。そんな悩みを持つあなたへ、ジャンルに特化したアンソロジーをお届けします。本作のテーマは〈ミステリ〉。人気作家4名が、フーダニット、ハウダニット、ホワイダニット、そして叙述トリックと『ミステリのお約束』をそれぞれ取り入れた極上短編を書き下ろし!各話扉に書かれた “どう読めば面白いか?” のガイドと共に楽しむ、満足度100%の謎解き小説。」。こういうのの宣伝文句は大袈裟になりがちですから、そこは話半分くらいに受け取っておくべきですが、それはそれとしても、これがミステリーの初心者に向けて「謎解きとひとことで言ってもそのジャンル内は更にこんな感じで分類されるし、それぞれがそれぞれに知的刺激があって面白いものなのですよ」ということを紹介する為に作られたアンソロジーで、そして内容的にはその目的はまずまず成功していると言っても良いのではないかということは、確かなことかもしれません、特に、青柳碧人の作品と相沢沙呼の作品が面白かったです。相沢沙呼は城塚翡翠シリーズのドラマ化に絡んで誹謗中傷じみた攻撃を受けて以来、小説の発表が途絶えていましたが、これがかなり久し振りの新作ということに。彼の書くミステリーは好きなので、これをリハビリとして、また様々な小説を出すようになってくれれば嬉しいのですが、打たれ弱い繊細なメンタルの持ち主なのは承知しているので、無理は言えない……かな。
「何で今?」と思われるかもしれませんが、何となく1枚目のソロアルバム『宮本、独歩。』をかなり久し振りに聴き直した結果、これは2枚目のソロも買ってみなければなるまいと感じたことにより、宮本浩次の『縦横無尽』を購入しました。アルバムとしての気に入り具合としては『宮本、独歩。』の方が上でしたし、「冬の花」を超えるナンバーがあったかというと微妙なところもありますが、しかし全体的にはかなり素晴らしい内容でした。宮本浩次というミュージシャンの音楽に対する姿勢、全力で音楽に向かい合っているところが今作にも強く打ち出されていて、そういうのが聴きたくて本作を購入した私としては大満足の1枚だったと言っていいでしょう。なお、彼のカバーアルバムについては特に買おうとも思っていなかったのですが、本作収録の「春なのに」を聴くとちょっと迷いが出てきてしまいますね……。うーん、どうしようかな。
2025年の個人的ムーブメントになっている感もある、CDの大人買いですが、今回はプログレ系では無くロックで以前からどうしようかと思っていたものをということで、ROOSTERZ(ROOSTERS)のオリジナルアルバムを4枚、リリース順に言うと『DIS』、『φ PHY』、『NEON BOY』、『KAMINARI』そしてライブ盤の『FOUR PIECES LIVE』を購入。概ね、大江慎也脱退後のものが多いですし、初期のものは買っていないのですが、これはまぁ、個人的な好みの結果というか、初期の ROOSTERS が嫌いなわけでは決してないけれど、自分が手元に置きたいのはどれかと言うとこれになるかな、というところです。所有リストに載っていないのに何でそんなことが言えるのかというと、そもそも ROOSTERZ(S)については私の兄がファンなので彼がアルバムを一通り所有していて、私もそれを学生時代にカセットに録音して聴いていたからそれぞれどういうアルバムで何が収録されているかというようなことは知っていたというのが、その答えになるでしょうか。で、初期の楽曲で好きなものは、以前に購入していたベスト盤で概ね揃っているので、今回はひとまず買わずともいいかな、という判断をさせていただきました。初期 ROOSTERS が大好きだという方には申し訳ありません。ともあれ、今回買ったものについては、もともと好きなアルバムや、欲しい曲が入っているアルバムだったので、楽しく聴かせてもらっています。色々と、「学生時代にこれをあんなことがあったなぁ」というようなことも記憶に甦ってきたりして、それはほっこりするものだけでなく羞恥心に悶えまくるようなものもあったりするのですが、過去は過去で今から何をどうできるわけもないし、それも含めて思い出、です。










